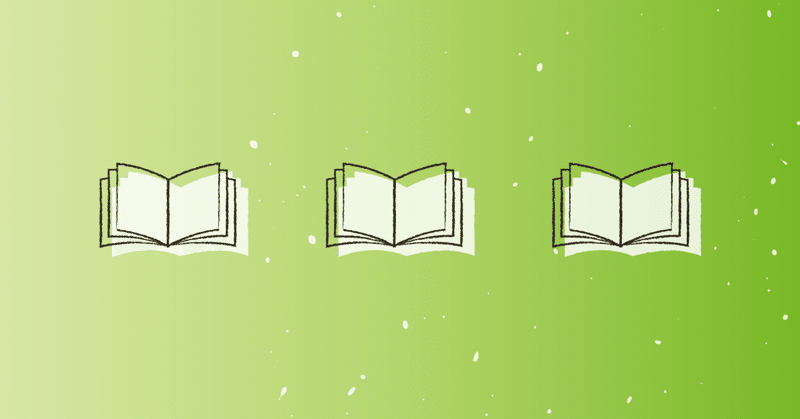
横溝正史『七つの仮面』を読む
今回は紹介するのは『七つの仮面』という作品。
角川書店から出版されている金田一耕助ファイルでは14巻目にあたります。
収録されているのは代表作の「七つの仮面」のほか「猫館」、「雌蛭」、「日時計の中の女」、「猟奇の始末書」、「蝙蝠男」、「薔薇の別荘」の7作品。どれも名探偵金田一耕助シリーズの中期から後期にかけて短編作品です。
金田一耕助といえば、『八つ墓村』や『犬神家の一族』といった地方を舞台にした作品が有名です。その多くは初期の作品で、作者の横溝正史が戦時中に岡山県に疎開していた時に着想を得たものと言われています。
その後の金田一シリーズは舞台を東京に移し、都会で起こる奇怪で不思議な事件を扱っています。そのため、この本の作品は東京を主な舞台としています。
後期の短編集の傑作
さて、この『七つの仮面』という短編集ですが、なかなかの粒ぞろい。物語においての人間関係の複雑さ、数奇な運命、横溝作品特有の怪しい雰囲気と、金田一耕助の憎めないキャラクターがいい味を出しています。
なかでも私が好きなのは代表作の「七つの仮面」。
物語の主人公である美沙の独白という形式で物語が進む一人称小説です。美沙は学園内では聖女と謳われた類まれな美少女でしたが、山内りん子という醜女と恋に堕ちることから彼女の運命は変わっていきます。
特に横溝先生は女性目線の一人称小説が上手な印象です。
執筆時は50代であったにもかかわらず、物事をとらえる視点や動機など一貫して女性目線で作品を書いていることに驚かされます。
一人称小説っていいよね
私は横溝作品のなかで、こうした一人称小説が好きです。
あまり多くはないのですが、有名なものであれば『八つ墓村』。この小説は事件後に寺田辰弥が書いた手記という設定で物語が展開されます。そのほかに『本陣殺人事件』に収録されている「車井戸はなぜ軋る」は手紙をもとに物語が展開する構成になっています。
横溝先生の文章は抒情的で、特に一人称小説では書き手に感情移入しやすく読みやすい印象があります。また、一人ならではの表現方法もあり、聖女から娼婦へと堕ちた美沙が、淡々と自身の物語の顛末を語る「七つの仮面」は独特の怪しさが満ちています。
あと、一人称小説では金田一耕助の登場が控えめになっており、後半の絶妙なタイミングで登場するところも特徴。複雑な人間関係で行き詰まった物語に颯爽と登場する名探偵、心なしか気持ちがホッとする瞬間です。
今後も時折、金田一耕助シリーズの紹介をしていこうと思います。
ナタデココをこよなく愛する旅のひと。
