
#08 【戦前|幼少時代】自慢の”高良山”と”筑後川”の話
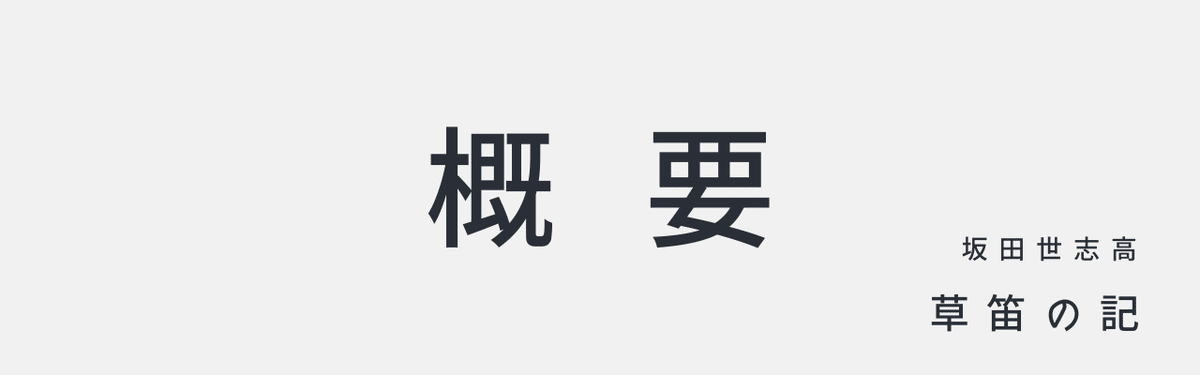
舞台
(福岡県)久留米
人物
主人公 :花山 三吉
家族構成:父、母、七人兄弟(五男二女)
三吉は四男坊
題名
草笛の記
物語
戦中 戦後 青春のおぼえがき

第一章 幼少時代
(一)大家族に育つ
(二)父母のこと
仕事ひとすじの父
父、良木への思いひとしお
大家族を支えた母
自然に恵まれた母の実家
(三)雄大な筑後の山河
長兄、ふるさとの四季を描く
故郷の象徴、高良山と筑後川 ★
第一章 幼少時代
(三)雄大な筑後の山河
故郷の象徴、高良山と筑後川
市の東方には、屏風のように高低がなくて、まっすぐに連なった耳納山脈が走っている。山脈は、正しく天地を二分して、南から北東へピーンと線を引いたようにつづいている。他ではみられない光景である。
山脈の西端に、まるい山頂をした高良山がみえた。標高三百十二メートルの低い山で、麓から山頂まで古びた石段が、山に巻きつくように昇っていた。
頂上には一千五百九十年前の西暦四百年(履中天皇元年)に創建された筑後一の宮(かつての国幣大社)が荘厳に鎮座している。
高良山は古代より政治、文化、軍事、交通の要衝であった。その事跡としては、景行天皇の行宮、神功皇后の田油津媛征討のとき山麓の旗崎に御駐輦、筑紫君磐井がこの山に拠って肥筑豊三州六国に威勢を振るった、などがある。
また大化改新以後はこの山下に筑後国府がおかれ、ちかくに国分寺も建造された。南北朝時代には征西将軍懐良親王がこの山を本陣として北敵を破り、ここに征西府を移された。戦国時代になると、豊後の大友氏がこの地に陣して諸豪を制圧した。豊臣秀吉も九州征伐の際、支峯吉見獄に陣を敷いたなど要衝の名そのものである。
この高良山は久留米市街から近い距離と、一息つきながら登れる高さから、「市民の山」として久留米市民に親しまれ、崇敬されて、いつもお参りの人が絶えなかった。
山頂か荒野眺めは雄大で、筑前、筑後、肥前の三国に跨がる広い大穀倉地帯の筑後平野がパノラマ状にひろがり、その真ん中に久留米市街があった。その北側を九州一の筑後川(別称筑紫次郎・千歳川)が悠然と幅ひろく流れている。
山も平野も四季それぞれんも色に染まって、いつ見ても、すばらしい展望である。
この山、この川は、久留米のシンボルであり誇りであった。
西条八十は「久留米小唄」でこう歌った。
♪筑後川
いそぐ旅路の あの水でさえ
久留米見たさに
オーサ ヤレソレひとめぐり
くる くる 久留米にゃ誰もくる
ホンニ バサラカ ヨイ ヨイ ヨイ
長兄はこの郷土の風景を、好んで描いた。その合間にポケットからハーモニカを取り出しては、勢いよく吹いた。
曲は「越後獅子」や、ハイカラさんらしく「青い背広でこころも軽くーーー」などであった。ベースを利かせて思いっきり吹いた。
また、手近の木の葉や草の葉を丸めて、口にあてて、上手に吹いた。麦の茎の中ほどを手折って吹いても、よく鳴った。草笛は辺りに「ピーピー」と強くひびいた。三吉も見よう見まねで吹いた。
第二章へ続く
坂田世志高
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
