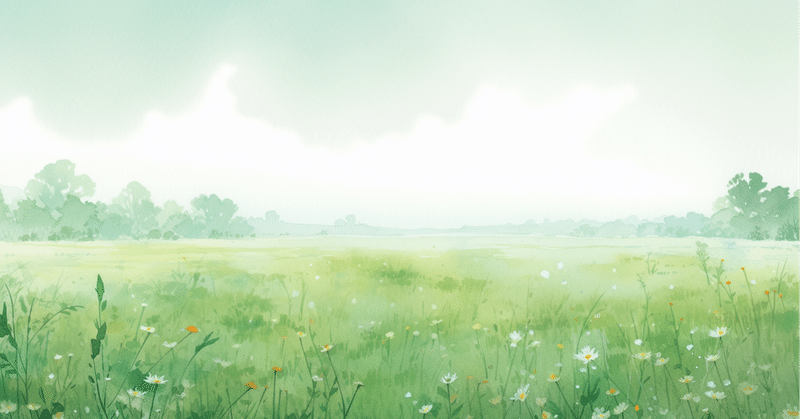
#04 【戦前|幼少時代】父の機嫌は木によって決まる

舞台
(福岡県)久留米
人物
主人公 :花山 三吉
家族構成:父、母、七人兄弟(五男二女)
三吉は四男坊
題名
草笛の記
物語
戦中 戦後 青春のおぼえがき

第一章 幼少時代
(一)大家族に育つ
(二)父母のこと
仕事ひとすじの父
父、良木への思いひとしお ★
大家族を支えた母
自然に恵まれた母の実家
(三)雄大な筑後の山河
第一章 幼少時代
(二)父母のこと
父、良木への思いひとしお
父は月のうち七、八日ぐらい山を歩き、神社やお寺を廻った。樫の木、楠の木、椎の木、タブの木など、材木店では、手に入りにくい立木を、持ち主から直接買い付けるためである。
それらの木は、直径が一メートルを超えるものが多かった。そういう大きい木が買えたときは、父はご機嫌だった。暦の吉日に呼びつけた樵夫(きこり)たちに、その木がいかに良い素性であるかを、熱っぽく自慢した。そして樵夫と一緒に現地に入った。
三吉も幼児期から、ときどき現地へ連れていってもらった。
樵夫は周囲の木に触らぬように、木のてっぺんから上手に枝を落し、本体を倒した。
街のなかの大木でも、そばを走る電線や、すぐそこの家の、塀や屋根に当たらぬように、ロープや手作りの器具などを使って、見事に切り落とした。
倒した木は、馬方が馬をうまく捌いて、道がかりの良いところまで引き出し、滑車を使ったチエーンブロックのような物で、慎重に馬車に載せ、市内の三カ所の製材所まで運んだ。
製材所では数カ月のあいだ放っておいて、木の癖を良く出した後で製材した。大きな帯び鋸が、勇ましい音を立てて木を切断していくと、それぞれにその木特有の芳しい香りが漂った。三吉はその香りがたまらなく好きだった。
製材したものは、すぐに持ち帰り、工場の裏の風通しの良い場所に、一枚ごとに陣木を敷いて高く積み上げた。こうして自然乾燥を行い、相当の日数を経過して、車や農機具の資材として使用した。この資材置場は子供たちの結構な遊び場であった。
続く
坂田世志高
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
