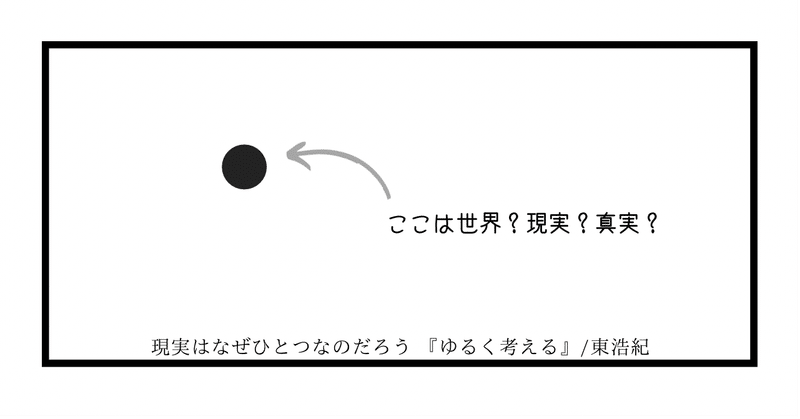
現実はなぜひとつなのだろう 『ゆるく考える』/東浩紀
「意味」に居る私
『黒い正方形』という、無対象を志向した絵画がある。

この絵画作品には「もの」が描かれていない。中央の正方形は単に描かれたカンバスの枠が折り返されたものである。マレーヴィチは自身を「無対象」を手法とする画家と位置づけているが、これは20世紀の大きな潮流のひとつである抽象だといえる。対象を精確に再現するという「リアリズム」を捉え直し、手法そのものを露出させる芸術意識のもと、マレーヴィチは「もの」を描くことをやめた。つまり何かを再現するときに求められる「約束事」を放棄したのである。シュプレマティズム(あるいは『黒の正方形』)は厳密にいえば、ある「もの」を抽象しているのですらない。そのかわりに絵画の本質とみなされたものこそ「色彩」であり、彼はそれを単なる「対象」の彩りではなく色彩のエネルギーとして自立させようとしたのである。
「約束事」とはつまり、絵画そのものが持つ《写実性》である。つまりは、絵画は何かを「再現」するプラットフォームであり続ける限り絵画的リアリズムは絵画に存在していない、と逆説的に示してしまうような事実のことを〈規定性〉のある「約束事」として保持している、ということだ。
新しい絵画のリアリズムはまさしく絵画のものである。なぜならそこには山のリアリズムも、空のリアリズムも、水のリアリズムもないからである。
これまで、物のリアリズムはあった。しかし、絵画の、色彩の諸単位のリアリズムはなかった。そうした単位は形態にも、色彩にも、相互の位置関係にも左右されないように構成されている。
いつでも私たちの視野は「中心となるもの」と、その「中心の周囲の背景となるもの」の、2つの要素から成立している。全ての事物に対して、ピントを合わせて視ることはできない。そういう意味では、全てにピントが合った絵画というのは、実は写実的ではない。

このような、ウィレム・クラース・ヘダによる静物画は、「徹底した写実性を伴いながら、その内には非現実性も含んでいる。」この命題が崩せない限り、この絵画は写実的ではないことになる。(写真も、グーグルマップも、これからリリースされるだろうグーグルマップライブもそう。)このような問いで追及されるのは、『写実性に付与された〈規定〉』についてだ。私たちは、事実について、俯瞰するための冷静な立場を持てるような、学知や知恵が必要なのではないか。この問題提起によって、上記した「約束事」の不要性を考えるに至ると思うのだ。
ようするに、私(たち)は何も見ていない。
上記の抽象画は、徹底した無対象(非現実的・非写実的)であるがゆえに、「(私たちが)何も見ていない」側に存在する「見えるもの」へ視点を移動させてくれる。無対象な黒い正方形が面前に表れることによって、私たちが今存在する世界が〈背景〉へと置き換わり、私たちが「見えないもの」として「見える」ように仕向けられる。
黒い正方形が、絵画のリアリズムに気付かせてくれる。そして、私たちの〈規定〉された現実、背景に退行した現実そのものを、「見えないもの」として可視化してくれるのだ。
そして、ウィレム・クラース・ヘダによる静物画のような、いっさいのものが前に歩みでてくるような「究極の背景」はそれ自体が存在し得ないということになる。「芸術」は、さまざまな誤認識からの解放を提起してくれる。
「世界」は、一義的(ここでは、「極めて写実的な」と言う方が今までの文章と繋がりやすい、かもしれない。)なものではなく、実に多様なものとして存在するしかない。よって、芸術や学問を振興することには意味が在るのだ。民主制の基本思想に倣えば、この振興は万人に平等に、半ば義務的に存在してもよいのではないかとさえ思う。
何者か見せられている現実に、私たちは存在している。しかし、私たちの実在は、「究極の背景」という『統一的世界』には存在していない。断続的に変容する自身の「価値観」や「意味」の中に、私という実在の意味が存在している、そういう示唆を感じる。
ゆるく考える
『ゆるく考える』は、批評家で作家の東浩紀による、「平成20年代」の思想が詰まったエッセイ集である。本著においても、上述したような「私のありか」的な話が、多分に散りばめられている。
特に印象に残った話に、「シミュラークルな想像に対する唯一性」がある。「たしかに!」と、誰もが思う内容だと思う。
ひとは、現実が凡庸で退屈で交換可能であるからこそ、むしろシミュラークルのなかに交換不可能なものを見てしまう。
たとえば、自転車で数分でいけるような「地元のショッピングモール」は、私にとって、小学生の時の青春を描いたキャンパスのようなもので、そのモールはわたしにとってかけがえのない、特別な場所であり、思い出であり続けている。過去、(都会ではない)田舎という現実を覆い隠すような、役割があった「モール」は、たしかに私の心に、「青春の唯一性」を思い描かせ、一種の陶酔を覚えさせる場所になった。
シミュラークルの想像力は、かつては強固な現実を解体し、人々はそこから解放するものだと考えられてきました。しかし、この20年ほどで明らかになってきたのは、むしろ、ひとは、現実が多様化し流動化しているからこそ、シミュラークルのなかに偽の唯一性を、偽の強固さを求めてしまうという傾向です。
「青春」という観念自体に対し、オリジナルを探求することは不可能であるのかもしれない。私は、小学生の青春を「モール」という反復性のある模造(シミュラークル)からしか、《もはや感じ取ることが出来ない》仕様に近似していると言える。
シミュラークルは、様々な観念に存在する。その内で現象している、なにかしらの「唯一性」、もしくは「究極な背景」や「統一的世界」は、シミュラークルなのだ。これは、私の実在の「意味」だ。この「意味」は、絶対的なものではなく、シミュラークルである。この「意味」自体で、他者の何かを判断することはできない。しかしながら、それゆえに私の実在は、この「意味」自体に存在している、と言えないだろうか。
(ちなみに「ジャスコ」のことを言っています。ジャスコ本当にスキ。)
キャンパスはキャンパスのみで存在できない
絵画を描くための「無地のキャンパス」は、その絵画自体によって、さらにいえば絵画の最小単位である絵具によって、その存在を認知されるに至る。しかし、「無地のキャンパス」でも、「何かが描かれたキャンパス」でも、そのキャンパス自体の存在は、何かの背景を伴って存在するしかない。無地のキャンパスに「何を思うか」、また何かが描かれたキャンパスに「何を思うか」、そこが重要だ。
強固な写実性は、そこに偽の現実を見させる。強固な抽象性は、そこに私自身の意味を見させる。そして、シミュラークルな現実は、写実性と抽象性の両義的な意味を見させる。(モールという物質的模造と、モールに付与した唯一的な観念)
私は、この徹底された合理的観念に、どこまで「軽薄」でいられるのか、試していきたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
