「入門」という言葉につられて
本日はリュートから離れて、雑多な話題を。
私の読書案内というか、音楽以外の趣味の紹介なども兼ねる感じの内容になりそうです。
どうも自分は昔から、「入門」という言葉に弱いようで、たとえば書店の棚にある『〇〇入門』というタイトルの本が目に入ると、反射的に中身をチェックしたいと思って手にとったり、あるいはネット上でも、書籍のタイトルに「入門」とうると、とりあえず「試し読み」のところをクリックしたくなります。
たとえそれらが、その時点での自分の興味あることとはかけ離れた分野に関する本であっても。
本を売る方の側に立てば、まさに私みたいな行動をとる人間を「釣る」べく、「入門」と言うタイトルを銘打っているであろうことは、まず間違いのないところです。様々な分野についての、これまでに印象に残った「入門書」を、いくつかご紹介します。
例によって、記憶を古い順に辿っていくことにすると、はじめて手にとった「入門」書は、おそらくこれです。

何なら、この本によって「入門」という言葉自体を知ったかもしれません。
ある世代以上の方ならたぶん懐かしい、保育社の『カラーブックス』シリーズ。「伝承から創作へ」という副題が、今となっては深く響きます。
この河合豊彰氏による折り紙本、捨てられていなければ実家にまだあると思いますが、早い時期にぼろぼろになってしまって、終わりの方のページは破けてなくなっていました。まあそれほど使い込んだということで・・
実際に折る機会こそめっきり減ったものの、おかげさまで折り紙は今でも大好きです。「入門」書で得た事柄が、今までずっと生かされている好例。
次は洋書の翻訳で、原題にはなかったタイトルに「入門」が入ったもの。

創元社が発行する「知の再発見双書」からの一冊です。
このシリーズは、理解の助けになる図版がとにかく多いのが特徴。
実際に買って今でも手元にあるのは、この「聖書入門」一冊だけ。
「まず聖書そのものを集中して読むべし!」
なんて、あのルター顔負けのアドバイス(?)をいただいてしまうかも・・とはいえ、最初からひたすら文字情報だけというのは、自分にはきついというのが本音です。
近ごろ、とある音楽家の方の演奏チャンネルの動画を見ていて、背景の本棚に、この「知の再発見双書」と思われる本がずらりと並べられているのに気づいて、関心するとともに少し羨ましくなりました。
対して、私の家の本棚ときたらあまりに雑多で、とてもお見せすることはできません・・
さて、こちらの音大に留学する前、日本の大学では「文学部思想哲学科美学藝術学専修過程」などという、何だかものものしいところに籍を置いていました。
そもそも「美学」が何なのかよく分からない時期に、とりあえず近所の本屋において目に飛び込んできて、試しに買って読んでみたのがこの本。

旧版の朝日選書のシンプルなデザイン、個人的にすごく好きです。
それはともかく、この本に関しては「入門」とは名ばかりの、むしろこの著者の思索の跡をたどりつつ人となりを知る、という性格の方が強いもので、実際に大学で学んだ「美学」は、ここで書かれたものとはかなり異質のものという印象を受けました。
この本も確か、捨ててはなかったはず。ふとまた読み返してみたくなりました。と思ったら、青空文庫に入っていたんですね・・
一般に、「入門」と名のついた書物ならば、できるだけ分かりやすい文章で書かれていて、論理・構成が明確で、内容は適度に浅く広く、というのが読み手として純粋に期待するところです。
しかし中には、その期待を見事に裏切られたものもあります。
極めつけがこれ。

大学初年度の数学の講義で教科書に指定されたこの本は、文系人間にとっては難解極まりなく、本当に苦しめられました。
このシリーズ全体が「基礎」数学と銘打っているので、なおさら「痒い所に手が届く」的な本なのかと思ったら、真逆でした。
単に理解力が足りないのだ、と言われればそれまでなのですが、この線形代数の単位を落としたことにより、中学以来の苦手科目だった数学に、完全に挫折し、それは今でも軽くトラウマとして残るくらいです。
とはいえ思うところもあり、一度古本屋に売ったこの本を、数年前に新品でまた買い直して最初から読み始めたところ、やっぱり最初の方で挫折。
さらに同じシリーズの「解析入門」(計2巻)となれば、理系の人々の中でも、もはや入門書を越え過ぎだと、悪評高い?そうです。
ここまでくると逆に、なんとかして征服してやろう、という気にもなりますよね。いや、ならないか・・
何にしても「〇〇入門」と聞いて、即座に真逆のイメージを思い浮かばせるのは、やはりただものではありません。
語学系の入門書も、ある時期に必要に迫られて随分世話になりました。
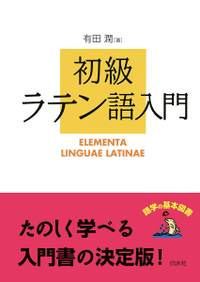
ラテン語の入門書を、今手元にあるだけで計4冊も持っているものの、
どれも一長一短で、うまくは使いこなせていないという印象。
この本の場合、「初級」と「入門」が両方タイトルに入っているので、それだけで飛びついてしまったのが丸わかりです。
「入門」というタイトルではないですが、世界思想社の『学ぶ人のために』シリーズも、何冊か持っています。最初に買って読んだのがこちら。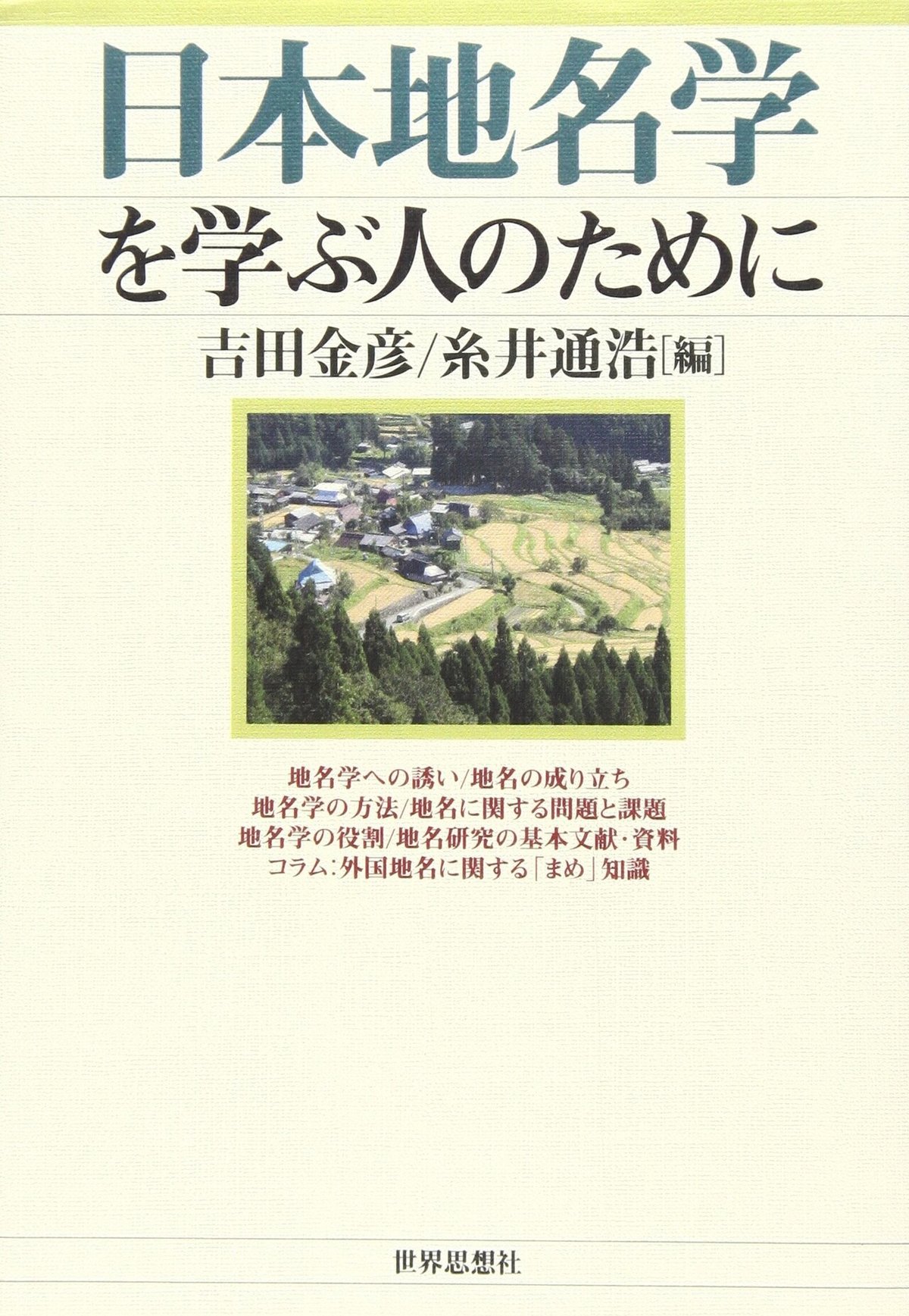
地名が好きというのは、自分の場合この本に出合う前からそうだったみたいです。『学ぶ人のために』シリーズで好印象なのは、さらに深く学びたい人の文献案内が充実していることと、その分野の専門家たちが分担して執筆したものでありながら、内容がすっきりとまとまっていることです。
ちなみに一番最近に読んだのが、『和歌史を学ぶ人のために』。
なかなか渋いでしょう?
せっかくなので、最後に洋書系の入門書も。

かつて大学のゼミで輪読したもの。
オックスフォード大学出版局ですから、薄い本でも「凝縮」された内容かと思っていたら、意外なことにこの「Music (音楽)」の巻については、エッセー調で軽めな感じを受けました。
『A Very Short Introduction』、通称VSIは非英語圏にあるの書店でも、高頻度で目にします。大学生あるいは大人の教養書の定番、という位置づけなのでしょうか。
このシリーズも、表紙のデザインが凝っていてなかなか面白いですね。
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
以上がざっと、私の「入門書遍歴」でした。
で、こちらのnoteに記事を書き始めてはや4カ月目に入りましたが、ぼちぼち有料コンテンツとして、より専門的かつ「入門」的な記事を書こうかと思っています。
ひょっとすると、これまで書いた記事のいくつかはさしずめ、「リュート入門」だったと言えなくもないです。しかし、どれも筆者の視点が強く入っている上に、資料・文献上の典拠などは充分に示していなかったので、私が考えるところの「入門」記事とは言えないかな、と思います。
そこで思いついたのが、ずっと前に別のブログにて「サルでも分かる!〇〇」という内容の記事を途中まで書いていたことがあって、それを模様替えした上で、内容も継続させてこちらで提供できないか、ということです。
さすがに前と同じタイトルは使えないので、そこをまずどうするかが懸案になっています。
でも何じゃかんじゃで結局、「〇〇入門」に落ち着いてしまう気が・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
