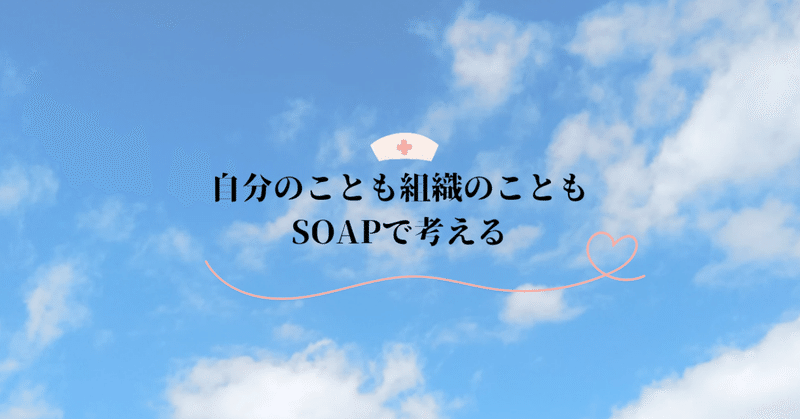
自分のことも組織のこともSOAPで考える
SOAP (ソープ)は看護師なら誰しもが知っている記録方式のことですが、実習では大きな記録用紙に手書きでみっちり書かないといけない雰囲気があるし、みっちり書いたうえでコテンパンに先生に修正の指導を受けるといったイメージが焼き付いてSOAP=めんどくさいもの、嫌なものとなっていることも多いのでは・・・?と感じていますがいかがでしょうか。
私はめんどくさいイメージがガッツリついていますが、一方で意外と便利なものだなぁとも感じています。
それは、患者さんや利用者さんへのアプローチを考えるためだけでなく、自分自身の分析や組織の分析からアプローチ(計画)を考えることにも活かせることに気づいたからです。
ちなみにSOAPの説明はこちらをご参照ください。
自分に活かす場合
日々仕事をしていると、上手くいったこと、上手くいかなかったこと、いろいろあると思います。そして、それに付随して「感謝されて嬉しい!」とか「感謝はされなかったけど自分としては頑張った!」とか「あのタイミングを逃してしまったのが悔しかったな」とか、いろんな独り言を脳内で言っていたり、同僚に漏らしていたりするはずです。
それをS:主観的情報とし、O:客観的情報は、その時の自分の振る舞いだったり、心拍数が上がってる、下がってるなど身体的な反応だったりを自分で自分のことを客観的に見た情報(メタ認知)を当てはめていきます。
私の場合はここまでやる中で、自然とA:アセスメントも進む感覚があります。
「あのときこう感じていたから上手く声をかけられなかったのかも・・・」とか。
そしてP:計画はアセスメントをもとに立てていく。何かに対する認知の問題っぽいなら認知を変えてみるプランを立ててみたり、認知を変えた上でどう行動するかまでプランを立ててみたり。
組織に活かす場合
組織に活かす場合は、一旦管理者の立場で書いてみようと思います。
S情報は管理者発信の主観的情報に加えて、スタッフからのS情報を入れていきます。
仕事がきついとか、残業を減らしたいとか・・・
O情報は実際の業務内容だったり、業務に必要な時間、残業時間、スタッフがその業務にどのように取り組んでいるのか、誰がいつその業務をしているかなどです。
Aとしては、◯◯は無駄な業務と考えられるとか、こうすれば効率化が図れるというアイディアなどが上がってこれば、Pはそれを実行する、してもらうということになります。
結局はPDCAと同じだけど、看護師ならSOAPのほうがしっくりくるかも
結局は立てたP:計画に対してまたS情報、O情報をとってA:アセスメントし、あらたなP:計画を立てることになるので、PDCAサイクルと同じことではあるのですが、
「S情報」というものををあえて分類することが、看護師ならではな感じがしています。
数値だけで判断しない、その人がどう考えて何を発言しているのか、思ったまま言う人なのか、思ったまま言わない人なのか、そんなことを考慮しやすい形になっているSOAPは看護師が、自分自身を振り返るにも、組織を改善するにも、看護師の特性を活かしやすくする要素があるんじゃないかと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
