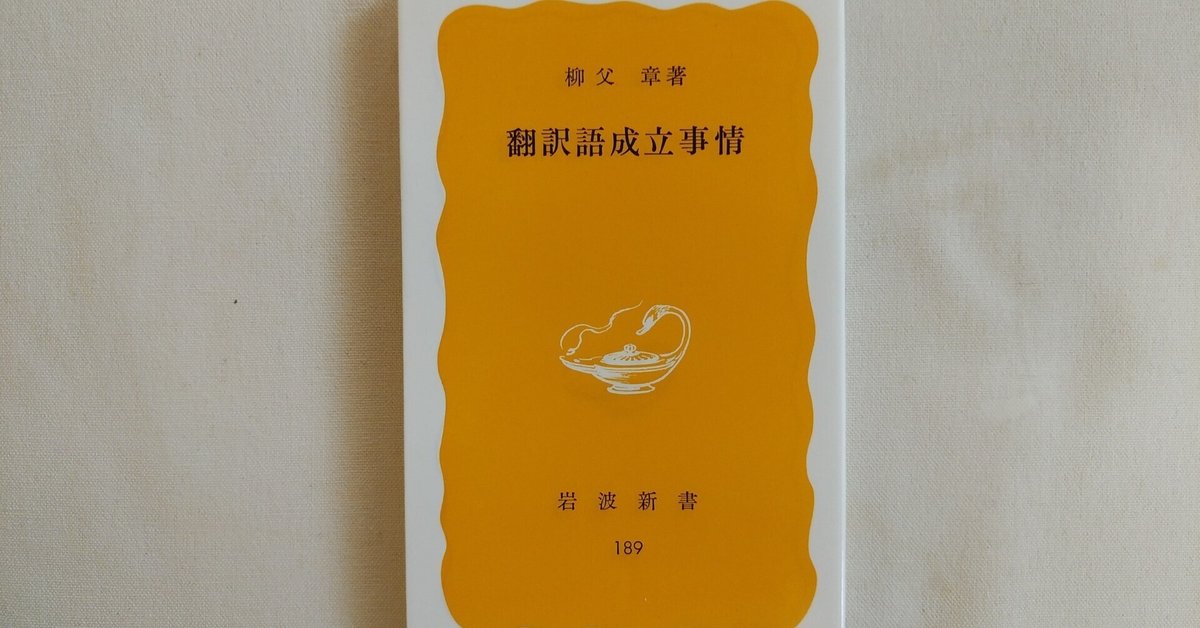
柳父章『翻訳語成立事情』(岩波書店)
現在、普通に用いられている言葉でも明治以前は日本語の中に無く、翻訳語の成立によって日本語に入れられてきた語は多くある。現在ではそれらの語が無ければ思考も困難なような基本語であっても、元々の日本語にはその観念さえも無かった場合もある。そうした観念は、翻訳語と旧来の日本語との合間に無理矢理挟み込まれて、うやむやになり、私たちは分かったようで実は分かってないまま、翻訳語を使ってそうした観念を論じているのではないかということが指摘されている。
本書では社会・個人・近代・美・恋愛・存在・自然・権利・自由・彼、彼女の10の語について論じている。えっ、これも無かったの、と驚くような基礎的な語ばかりだ。著者は辞書や論文などの豊富な例にあたり、鋭い考察によって日本語の裏事情を教えてくれる。
以下、自分の気になったところを忘備的にメモしておく。
1 社会
〈「社」ということばで、同じ目的を持った人々の集りや、その名前を指す使い方は、日本でも明治以前からあった。
明治初年の頃、この「社」ということばは流行語の一つであった。学識者の集り「文学社」、西南戦争中の救護団体「博愛社」など、また広く民衆の間でも、「社」を結び、何々社と名づけて人が集まることがよく行われていた。「新聞社」という言い方も、明治初年ごろからのことである。そして、おそらくこのような「社」流行の中心に、明治六年に結成された「明六社」があった、と思われる。明六社は、福沢諭吉、西周、加藤弘之、森有礼、中村正直など、当時の代表的知識人を集め、集会を開き、『明六雑誌』を発行して西欧新思想の啓蒙に努めるなど、時代の最先端にある華々しい存在だったのである。〉
いわく「同志社」もそうか。この明六社については覚えておきたい。明治のことを考える時に色々絡んできそうだ。また、「社中」って言葉も、言われると明治っぽいなーと思う。
〈ことばは、いったんつくり出されると、意味の乏しいことばとしては扱われない。意味は、当然そこにあるはずであるかのごとく扱われる。使っている当人はよく分からなくても、ことばじたいが深遠な意味を本来持っているかのごとくみなされる。分からないから、かえって乱用される。文脈の中に置かれたこういうことばは、他のことばとの具体的な脈絡が欠けていても、抽象的な脈絡のままで使用されるのである。〉
こういう指摘が本書の面白いところだ。
2 個人
〈日本語における漢字の持つこういう効果を、私は「カセット効果」と名づけている。カセットcassetteとは小さな宝石箱のことで、中味が何かは分からなくても、人を魅惑し、惹きつけるものである。〉
〈福沢諭吉は、日本の現実の中に生きている日本語を用いて、ことば使いの工夫によって、新しい、異質な思想を語ろうとした。そのことによって、私たちの日常に生きていることばの意味を変え、またそれを通して、私たちの現実そのものを変えようとしたのである。
それは困難な方法であった。扱うことばが、一つ一つ現実の重みを引きずっているからである。そこには、ことばだけの操作によって、ことばの「カセット効果」に頼って翻訳しようとする方法のあずかり知らぬ困難さがあった。〉
この本で福沢諭吉の翻訳に対する態度を知った。その当時ある日本語で外来の思想を語ろうとしたのだ。またその対極にある、日本製の漢語を使っての翻訳についてもよく分かった。今なら外来語をカタカナのまま使うのがそれに当たるだろうか。
〈この思考の行き詰まりのところで、「独一個人」という翻訳語が登場した。それは、あたかも思考の困難を解決するかのごとく現れている。この未知のことばに、それから先は預ける。前述の「カセット効果」に期待するのである。ことばは正しい、誤っているのは現実の方だ、というところで、一見、問題は解決したかのごとき形をとる。それは、以後今日に至るまで、私たちの国の知識人たちの思考方法を支配してきた翻訳的演繹論理の思考であった。〉
今でも用語で煙にまいたような評論を書く「知識人」は多い。
3 近代
〈一つのことばが、要するにいいか、悪いか、と色づけされ、価値づけされて人々に受けとめられること、これは日本における翻訳語の重要な特徴の一つである、と私は考える。〉
〈ことばがこうして、いいとか、悪いとか価値づけされて受けとめられている、ということは、ことばが、人間の道具として使いこなされているのではなく、逆に、何らかの意味で、ことばが人間を支配している、ということを示している、と考える。〉
ことばに価値づけ、というのも考えてみれば無意識に行っていることだろう。
〈本書では、翻訳語の成立の事情を考察するとき、以上のような視点を重視している。つまり、ことばの価値づけられた意味である。そしてこのことは、後に詳しく述べるように、ことばの乱用、流行現象、ことばの表面上の意味の矛盾、あるいは異常な多義性、というような面からとらえていくことができる。逆に見れば、「近代」などの翻訳語は、こうして乱用され、流行することによって、翻訳語として定着し、成立してきた、と言うことができると思う。〉
こうした翻訳語に依拠した抽象的な議論をする時に、すれ違いが起こるのはこうした成立事情も関係しているのだろう。
〈一九五〇年代に入って、「近代」は、時代区分の正式用語として認知されるようになった。〉
〈こうして「近代」は、一九五〇年代以後、次第に「近世」に代わって、正式の時代区分用語の地位を占め、ほぼmodern ageに対応する時代を指す翻訳語の地位を独占するようになった。それとともに、「近世」は、時代区分の正式の用語としての地位を失うか、または、中世の一部とか、中世と「近代」の間の時代区分用語として生き残る、ということになったのである。〉
現在の認識による「近代」が終わる頃にようやく近代が時代区分の用語になったということだ。modernをどう訳すか、山室信一『モダン語の世界へ』でもその根本的なところが問われていた。
〈一九一〇(明治四三)年の雑誌『文章世界』七月号に、「近代人とは何ぞや」という特集記事が載っている。〉
翻訳語が、その内容がよく分からないことを理由に流行することがある。
〈「近代」ということばの歴史をふり返ってみると、何度か、異常なほど流行した時があることに気づく。その最初の流行は、前述の一九一〇年前後、明治の終り頃で、とくに文芸の分野の人々にしきりに使われていた。〉
〈次に、この章の冒頭に引用した「近代の超克」座談会の頃の流行である。太平洋戦争中、一九四二年である。〉
〈さらに次の流行は、太平洋戦争の敗戦直後から始まっている。前の時代への反動として、この時代の「近代」は、プラスの価値をもつ一つのシンボルである。(…)さらにその反動として「近代主義」」批判がくる。〉
こうして、憧れ→マイナス→プラス→マイナスと価値も反転していく。
〈ことばの意味がこれほど多義的であるのは、もともとそのことばの意味というものが、ほとんどないからである。意味が乏しいから流行し、乱用され、そして流行し、乱用されるから多義的になるのである。〉
ことばの本質に触れている。「写生」然り、「リアリズム」然り。多義的であればあるほど、議論はすれ違いになりがちだ。
4 美
〈「美」という訳語は、こうして幕末頃からあったわけだが、おそらく漢字一字は翻訳語としてやや不安定であったのであろう。明治初期には(…)「美麗」という訳語の方がよく使われていた。〉
〈日本の伝統的美意識とか、世阿弥の美学、というような言い方がよく聞かれるが、このような問題のたて方は、自ずと翻訳的思考法をすべり込ませている、ということに注意したいと思う。なぜか。きわめて簡単明瞭なことなのであるが、近代以前、日本では、「美」ということばで、今日私たちが考えるような「美」の意味を語ったことはなかったからである。〉
これは陥りがちな思考のトリック。時代物のテレビドラマで、登場人物があたかも現代人のような思考をしていることはよくあるが、まず持っている観念そのものが違うという前提が、よく置き忘れられがちなのだ。
〈およそことばの意味は、「哲学者及審美学者」がきめるのではない。ことばが先にあって、その日常的意味をもとにして、「哲学者及審美学者」は、これをつごうによって抽象し、限定して使うのである。しかし、この限定された意味を、翻訳語として受けとめ、従って、完成された意味として受け取ることの多い日本では、この順序はとかく逆転して理解されがちである。〉
特に哲学的思考の妨げになっている。もしくは抽象度の高い議論の妨げになっている。
5 恋愛
〈loveとは、決して「魂」だけのできごとではない。しかし、魂と肉体とを区別して理解しようとする考え方、ものの見方がそこにはある。私たちの伝統的な「恋」や「愛」が、心と肉体とを常に切り離さず、一つに扱ってきたのと対照的である。したがって、loveの解釈として、「魂」だけをとくに強調する「恋愛」観も、当然あっておかしくなかった、と考えられるのである。〉
日本においてはloveにあたるものが無かったというそもそもの前提。
〈こうして観念として純化された「恋愛」は、当然、日本の伝統や現実のうちに、その実現をとらえることが困難になっていく。したがって、「恋愛」は、現実に生きている意味ではなく、日本の現実を裁く規範になっていく。これは、私たちの国の翻訳語の宿命である。そしてこの宿命が、(北村)透谷じしんの短い生涯や、さらに、彼の「恋愛」観に感動した人々、明治ロマン主義の詩人たちの、熱烈でかつ短命な行く末までも、おそらく動かしていたであろう。〉
明星派の人々もそうだ。
6 存在
〈まずbeingやSeinなどの二つの意味、ふつう言う「存在」と連辞の意味が、日本語では、「がある」ことと「である」ことというように、ともに一つの「ある」で言い表される、という意見であるが、「である」という言い方は、実は、beingなど西欧語の翻訳の結果として、いわばつくられた日本語なのである。〉
ここ、大事。英語を教える時に何が教えにくいって「be動詞」。be動詞の訳語として「である」がつくられたのであれば、「である」からbe動詞を教えるのは困難な訳だ。そして明治時代の苦渋の選択の結果が今でも何ら置換されずに使われているため、日本人の英語理解が中学段階で躓くのだ。これが分かっているのなら、もっと教え方を工夫出来ないかと思うが、日本語の言語の根幹に入ってしまっているので今更になると却って難しいというのはある。
〈日本語の「ある」は、とくに名詞化しにくい動詞である。一般に、日本語の動詞は、連用形で名詞化する。読み、量り、伸び、などに見られる通りである。しかし「あり」という名詞形が使われることは、まずない。〉
これが書かれたのが1982年。今(2023年)から約40年前だ。おそらく2000年代の後半か2010年代のどこかで「アリ」という言葉は使われるようになったと思う。もっと早いかも知れない。しかし作者が指摘するように元々かなり不自然な名詞化であったため、「あり」ではなく「アリ」と(旧来の日本語ではないように)カタカナで認識されることが多かったと思う。今ではそれもなくなり、ごく一般化している。言葉の変化の速さを思う。
〈翻訳に適した漢字中心の表現は、他方、学問・思想などの分野で、翻訳に適さないやまとことば伝来の日常語表現を置き去りにし、切り捨ててきた。日常ふつうに生きている意味から、哲学などの学問を組み立ててこなかった、ということである。〉
何か、難しい言葉をありがたがる風潮。それによって結局哲学的思考は日本に定着してこなかった。知識人の専売特許になってしまったのだ。それに抗うように、21世紀の現在、日常語で哲学的思考をすることが求められているのではないだろうか。
7 自然
〈「自然」とは、natureということばが日本にくる以前に日本語であった。それが、natureの翻訳語として用いられるようになって、以後、natureと等しい意味のことばになったわけではない。学者や知識人が、ことばの意味をどう定めようと、単なる記号ならいざ知らず、現実に生きていることばは、少数者の定義で左右できるものではない。また、巌本(善治)や(田山)花袋が、意識的にはnatureと同じと思いながら、伝来の「自然」の意味を動かしがたかったように、ことばの意味は、使用する人の意識をも超えた事実なのである。〉
同意。でもこれが分かってない「知識人」が多い。一部の人が使ったから言葉の意味が変わったかように論を進めるのは、おかしいと私は常に思っている。
9 自由
〈ここではとくに、その「自由」ということばに注目する。それは、当時の流行語であった。人々は、いろいろな場合に、このことばを口にした。
後にも紹介するように、適切でない場合に使われることが多かった。これもそうである。つまり、その意味が、あまりよく分かっていないのである。そして、意味がよく分からないことばだからこそ、好んで口にされ、流行するのである。すでにくり返し述べたように、翻訳語に特有の「効果」のゆえである。〉
今ならカタカナのままの外来語がそうだろう。日本語に容易に変換できるものでも、理解が曖昧なカタカナのままで使う方がありがたみが増す、という感覚。
〈一般に、どんな翻訳語が選ばれ、残っていくのか、という問いに答えることはやさしくない。しかし、およそ、文字の意味から考えて、もっとも適切なことばが残るわけではない、ということは言えるであろう。
一つ言えることは、いかにも翻訳語らしいことばが定着する、ということである。翻訳語とは、母国語の文脈の中へ立入ってきた異質な素性の、異質な意味のことばである。異質なことばには、必ずどこか分からないところがある。語感が、どこかずれている。そういうことばは、逆に、分からないまま、ずれたままであった方が、むしろよい。母国語にとけこんでしまっては、かえってつごうが悪いこともある。
日本語のなかで、音読みされる漢字のことばは、元来、異国の素性のことばであった。日本語は、この異国語を、異質な素性を残しつつ、やまとことばと混在させてきたのである。近代以後の翻訳語に、漢字二字の字音語が多いのも、この伝統の原則に自ずから従ったのである。そして、二字の字音語のうちでも、母国語にしっくりなじむことばよりは、どこか違和感のあることばの方がよい。人々が意識的にそう選ぶのではなく、いわば、日本語という一つの言語構造が、自ずからそう働いているのである。翻訳語とは、伝来の母国語からみれば、区別されたことばである。人々が直観的に感得できるような、区別のしるしをどこかに持っていることばなのである。〉
今まで外来語、翻訳語というものに持っていた疑問点が氷解するような文章。よく分からない哲学用語で理論武装する人の心理まで突いているような小気味の良い文章だ。
岩波新書 1982.4. 720円+税
