
最強陰キャナンパ師に学ぶ!?この現代社会において、メンタルを安定させる方法
パンデミックに、食糧危機、戦争など最近は、私たち人間のメンタルを大きく揺るがす危機が連続して起きています。
メンタルで言えば、日本では先進国の中では精神医療機関にかかる患者数が400万人と、異常な数となっています。
最近では子供のうつ病問題も起きており、メンタルに関する本や記事が点在している状況。
そんな現代において、誰にでもメンタルについてはとても重要な問題となってきていることでしょう。
この記事ではメンタルに焦点を絞り解説していきます、よろしくお願いします。
時間のない方は、5から読まれる事をオススメいたします。(題名のナンパ師と関係あるのは5番です、一番重要です(^o^)丿)
@まずメンタルが崩れるとは
この記事ではメンタルが崩れる=不安や恐怖=脳からノルアドレナリン(脳内ホルモン、または神経伝達物質)が出ている状態と定義します。
細かいことを言えば、セロトニン、ドーパミンがでていないと、メンタルは安定しませんがここでは主にノルアドレナリンを取り上げます。
過去記事において、脳と脳内ホルモン(ドーパミン、ノルアドレナリンなど)について書いた記事がありますので、そちらも参考下さい。
1.身体の生理状態を整える
過去記事でも書いてますが、
まずメンタルが崩れる理由の一つとして、
疲れ、栄養不足、睡眠不足などにより身体の生理状態が悪化することが挙げられます。

ジャンクフードばかりを食べても元気な人もいますが、どんな人でもこういうジャンクフードばっかり食べていると必ず身体やメンタルには影響はでます。(出やすい人と出にくい人とがいて、それは脳神経回路の違いによるものですが、それは後日、解説します。)
人間は36兆個の細胞からなりますが、その細胞は起床後、就寝まで活動することで、どんどん身体は疲れて酸化していきます。
人間の身体は元気なとき、健康なときは、弱アルカリ性にでありますが、活動したり、思考したり、食事(特に酸性食品は身体を酸性に早く変化させてしまいます。)したりすると、身体は酸化、つまり酸化していきます。
ちなみにこれをエントロピーが増大すると言います。(崩壊にむかうという概念)
https://www.shinsyuichi.jp/misolibrary/detail/5
睡眠を取ることにより、酸化した身体は、弱アルカリ性に戻そう回復するように作用しますが、酸性に傾いたまま起床し、回復が十分にできていないと、脳からはイライラや不安のもととなる、
ノルアドレナリンやアドレナリンなどが出ます。
なぜそうなるのか?はおそらくですが、
脳は身体が弱ってしまうと、外敵に狙われるかもしれない、ピンチだ!ということで、それに対して対抗するためにイライラ、不安の物質を出すことで対抗もしくは回避して命を守るためだと推測します。

まとめると食事の乱れ、睡眠不足などの、細胞、身体の酸化により、生命エネルギーが低下することで、脳内物質のバランスが崩れるという流れです。
逆にストレスを感じることで食事バランスが乱れるというパターンもあります。
どうしてもストレスを感じると、思考したり交感神経を使うことが多くなり、このとき細胞内のミトコンドリアの作るエネルギーがより消費されるのですが、このエネルギーのもとは酸素と糖です。
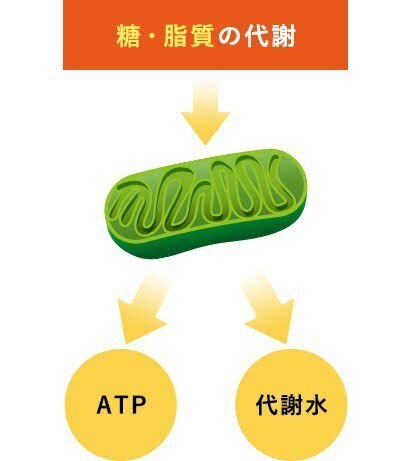
エネルギー消費が多くなると、糖、酸素を多く消費することになり、身体はあとで糖分をいつもより多くとろうとするということです。(過食など)
次の2番でも書いてますが、ストレスを受ける場所、ストレスを感じる人には極力会わない、いかないことが大切ということですね。
もともと戦前は和食中心による食文化で、ミネラル、ビタミンを始め、体に必要な栄養素をとれている人が多かったのですが、戦後欧米文化や、農地改革により、栄養不足に陥ってしまう人が、増加しました。(質的栄養失調は最近の流行りのワードの一つですよね)

2.外界の出来事に反応しない
現代社会において、ストレスを感じる原因の一位は人間関係と言われています。嫌な上司、親、学校のクラス内のヒエラルキーなど、人間関係によるストレス要因は様々でしょう。
例えば嫌な上司に怒られたとします。
その後は人間ですから、不安になったり、あるいはなんでこの私が怒られないといけないんだ!(●`ε´●)と逆に怒りに変わるときもあるでしょう。
このとき、身体の中では副腎という臓器によって、不安や怒りなどの元となる神経伝達物質が作られるのですが、怒りや不安が長く続くと、副腎はずっと稼働しなければなりませんので、疲労していきます。

副腎が疲労した場合何がいけないのか?
朝、人間は起床前に副腎からコルチゾールというドーパミンの元となるものがある程度作られるとすっきり起きれるしくみなのですが、
副腎が疲労するとそのコルチゾールがうまく作れなくなる、量が減ってしまうのです。
そうなると、すっきりした状態で起きれない→疲労が蓄積したたまま起床→そのまま学校、仕事に行く→疲れにより、自律神経が乱れているので、怒りやすくなる→さらなる人間関係ストレスが発生→また怒り、不安の脳内物質が出る→副腎が疲労する………
という悪循環が発生してしまうのですΣ(ಠ_ಠ)
ではどうすればいいのか?
ある本で反応しない練習という本があります。
怒りや不安になっても少し間をおいて、いちいち心で反応しないというやり方です。
笑顔を作るとドーパミンが出るのと同じく、ネガティブな事に対して、心が反応してしまい、それを行為、行動に出してしまうことで不安や怒りの脳内物質がさらに出てしまう。
そうではなく、何があっても反応せずにクールにやり過ごし、脳内物質を大量に出させないということですね。
あとは自分にとって不快だったり気を遣う人、場所、環境、グループとは付き合わないこと。
気を遣うことは交感神経をよく使うことにつながり、筋肉が固く縮まるので疲労が溜まりやすく、肩こり、腰痛の原因になります。
(筋肉が縮まるごとに、血液中の赤血球から酸素をカルシウムを使って細胞に送り込むという流れが加速し、酸素、糖、カルシウムイオンを無駄遣いしてしまうので、これもまた疲労の原因になります。)
3.人と比較しない
TVやSNSを開けば、ナイススタイルモデルや俳優や、いわゆるリア充と呼ばれる人たちの楽しんでいる姿を目にします。
そして若い子なんかは特にこのままだといけない!私もイケてるアピールしないと!😯と必死になって写真や動画の投稿をしてます。
中にはそんな人たちを見て比較して、私の人生充実してない、だめだ…😭とネガティブに勝手になってます。

これに当てはまるあなたは今すぐ比較する習慣を手放して下さい。比較するという習慣がある限り、何をしても極論楽しくないです。笑
そもそもなぜ人は比較するのか?を考えてみました。
これが一番大きな理由でしょう、学校での偏差値教育によるものです。
私達は義務教育のもと、学校という狭い世界の中で、お互いにテストの点数などで数値化され比較されます。数字が周りより低いことを周りからどやかく言われ、自己否定に陥りやすくなります。

このお互いが比較し合う教育システムの中に何年もいると、比較することが当たりまえという考え方、価値観(脳神経回路)が脳にインストールされます。そして大人になっても、周りの人と経済状況や仕事の立場、家庭状況を比べて、このままではだめだ!となり、大げさにいえば、一向に幸せにはなれない仕組みが成り立ちます。
上には上がありますから、比較してもしょうがないのですが。。(比較することでモチベーションがわき、努力できるという考え方もできますが)
こういうときにオススメなのは、自分に足りていない所に目を向けるのではなく、長所を伸ばすということをする。
もしアインシュタインが数学を勉強しているときに、周りから歴史、国語、英語の点数が低いじゃないの!数学はもう十分点数高いから、それはもう横に置いといて、先に3つから優先的にやりなさい!なんて言われ続け、数学の勉強に没頭しなくなっていたとしたら、相対性理論は生まれなかったかもしれませんよね🧐

比較によってモチベーションがあがって行動できるならそれはいいと思いますが、比較することで、自分=だめ人間というレッテルを貼ってしまうことが良くないのです。
ちなみに繰り返し、ポジティブでもネガティブでも思考することによって、脳には強く記憶されてしまいます。(長期記憶といいます。)
前のセルフイメージの記事にノミのジャンプの実験が書いてますが、思い込みというのはとても怖いのです。(ひどいと洗脳のレベルまでいきます。)
4.テンションのあがること、楽しいことをする
いくら運動、睡眠、食事を整えて、身体の調子を整えれたとしても、楽しいことをしてないと、なんのために身体の調子を整えたのかわかりません。もっと人生を楽しみましょう。

〜したい、より〜しなければいけないという思考で行動してしまったり、最近ではコロナウイルスによる、ステイホームによりイベントへの参加が減ったり、あるいは単純に人と人との触れ合いがなくなってきています。
基本的に楽しいことをするとき、脳からはドーパミンが分泌され、これは快楽物質と呼ばれ、幸せホルモンともいいます。
大人になるにつれて、勉強が忙しくなるにつれて、ついついやらなければいけないことを、優先しすぎるのは脳や心の視点からみても良くないです。親や周りの人に反対されようが、一度自分の好きなことを単純にやる、ということがメンタルにはとても大事です。
でないとふとした時に、私の人生、楽しくない、なんのために生きているの?なんていう不安な気持ちが必ず出ます。

ずっと義務的に、なにかを我慢してそれだけを行っていると、段々ストレスがたまる、もう少しいうと、脳の神経回路に電気が溜まってきます。蓄電されるイメージです。ノルアドレナリンやアドレナリンも出て、感情が乱れます。
電気、ストレスがある一定たまると、限界がきて、それを発散しようとして、怒りや不安が爆発し、ものや人にあたり、電気を発散しようとしてしまいます。
なので、理想はストレスが溜まる前に、その電気を何かしらで発散してしまうこと。
美味しいものを食べる、遊ぶ、飲みに行く、好きなアーティストのLiveにいくなどなど。。
やりたいと思ったら、やる!
シンプルにいきましょう。

5.明るく、元気に行動、振る舞う習慣をつける
悲しいのに、楽しいことがないのになんで明るく振る舞わないといけないんだ!(●`ε´●)と思う方もおられるとおもいますが、少々お付き合い下さいませ。(笑)
まず、ストレスがかかると人間の脳にはどういうことが起こるのかを見ていきましょう。
少し見にくいですが、この図を用いて説明していきます。(驚異のバイオフィードバックという本より引用)

ストレスというのは最初、外からの情報や刺激(道にヘビがでた!、親や上司に怒られた、仕事でミスしてしまったなど)が脳に五感を通して、送られます。
画像の中では悪い知らせ(電話)となっています。
そのあと、辺縁系(心)と呼ばれる所が反応し、続いて、感情を司る視床下部(扁桃体など)が反応すると、感情が作られます。

感情が作られたあと、交感神経などによる生理的反応というのが起こります。(怒りで全身に力が入る、不安で心臓がバクバクする、悲しみで涙が出るなど)
生理的反応が起こると、またそれを辺縁系(心)が認識し、泣いている、悲しんでいる状態の自分に対してまた反応して、感情がまたネガティブになっていく、という悪循環に陥ります。(私は泣いている、悲しんでいるんだ・・→心、辺縁系が反応→感情が揺さぶられ、さらに不安や悲しみが大きくなる)
簡単にまとめると、
①目、耳など五感から情報がくる
②辺縁系(心)が反応する
③感情が生まれ、生理的反応がおこる(心臓がドキドキする、涙が出る、筋肉が固まるなど)
④その反応が起こっている自分の状態を②の所の辺縁系、心がまた認識し、さらにまた③の生理的反応が起こる(心臓がドキドキする→私は緊張してるんだ。。と心が反応→さらに心臓がドキドキし、不安になる)
⑤ ②〜⑤を繰り返す悪循環がうまれる
という流れです。
ここでポイントは②の心の反応という所です。
極論をいえば、心が反応しなければ、ストレス(生理的反応)は生まれないということです。
そして反応するかしないかは、自分の意志で決めることができます。

例えば、朝から満員電車に乗っているときをイメージします。ぎゅうぎゅう詰めでストレスを感じて、辺縁系(心)が反応し、イライラしそうになる手前で、いちいち外の刺激に反応しないようにと、自分をコントロールする。
あとはこの人たちも朝から仕事で大変だな、頑張っているだな。。と解釈を変えて、心の状態をかえるようにして、ストレスをなるべく生み出さないようにする。
しかし、人間ですから全てのことにこれを使うことはまず不可能でしょうから、全てのシーンで使えなくても自分を責めることはしません。
そしてストレスの最も良くない点は、
・ストレスが来たあと、それに反応してテンションが下がる。
・そして自分を責めたり、比較したりして自己肯定感が下がり、さらに声やテンションが下がる。
・そしてそのネガティブな状態が続き、それが記憶、つまり当たり前になると、それが性格になってしまう。
だと私は考えています。
性格をもう少し詳しく解説します。
性格とは、いわば脳神経が集まったものです。(スピリチュアル界隈、自己啓発本では潜在意識と表現してます。)

ある習慣を続けると、かけ算の九九を覚えたときのように、その習慣を続けている自分像(セルフイメージ)が、脳、脳神経によって形成され、その習慣が長く続くと、脳神経回路に長期記憶されます。
ポジティブな身振り、行動、会話の仕方、考え方を続けると「ポジティブな身振り、会話、考え方をしている私」という情報が蓄積された脳神経回路が増えていき、それが大きなネットワークとなっていきます。そしてそれが当たり前になると、脳は「私=ポジティブな身振り、手振り、思考をする人」と認識し、いつもドーパミンがでで、安心した気持ちで過ごすことができるようになってきます。
逆にこれはネガティブな身振り、行動、会話の仕方、考え方でも同じです。それを続けるとそういう脳神経回路が作られ、ネットワークとなり、そのネットワークが自分像、自己肯定感の度合い、性格を決めてしまうのです。
そしてその性格に応じて、ノルアドレナリンやアドレナリンなどの不安、怒り、恐怖の脳内神経伝達物質をが優位に出ます。(なぜ性格に応じて、脳内神経伝達物質が決まるのかについては、過去記事の声のトーンや大きさで人生が変わる!で解説しています。)
なので、何があっても、無くてもいつも楽しく、テンション高く、元気に行動する、振る舞うこと。
男性ならいつもたくましく、力強く、女性なら笑顔を忘れず、おおらかに振る舞うこと。
難しそうに感じる人は、一番初めは、声を大きく、ハキハキと話す、できれば明るく話すことからが良いでしょう。コンビニに行けば、店員さんにハキハキとありがとうという、職場ではとりあえず挨拶を元気にする。。という具合に。
1番のところでカップラーメンなどのジャンクフード食べていても元気な人は元気であると、書きましたが、元気で明るい人というのは、過去からずっとポジティブな振る舞い、思考、行動を続けた結果、それが脳に脳神経回路から作られるネットワークとして作られているからと言えます。
つまり、元気で明るい人の脳には、そういう脳のネットワークがプログラムされているのです。

栄養学から言えば、ジャンクフードばかり食べていると、身体が酸化していき、脳内神経伝達物質としてはノルアドレナリンやアドレナリンなどの不安、怒りの物質が出やすくなるのですが、脳に元気で明るく振る舞う、行動してきたネットワークがある場合、メンタルが崩れることはほとんどありません。
もう少し詳しく言うと、そういう物質が脳から出たとしても、その物質はポジティブな脳回路、ネットワークにしか流れないため、いつもポジティブでいることができます。(ここは大変、説明が難しいです。)
逆にネガティブ、消極的なネットワークを持つ人は、例えばジャンクフードばかり食べたりして、身体が酸化し、ノルアドレナリン、アドレナリンが出やすくなると、そのネットワークにそれらの物質が流れてしまい、メンタルが落ち込みやすくなります。
過去、メンタルが落ち込んだりした経験のある人の脳には、ネットワークは消えることなく、残っており、ノルアドレナリンやアドレナリンが出ると、そのネットワークが起動されやすくなる、つまり、昔のネガティブな記憶がよみがえりやすくなります。なのでそういう人は、常に身体を酸化させないよう、健康に気を配りつつも、新しいポジティブなネットワーク回路を作ることが大切になります。

おまけですが、人気Youtuberに陰キャナンパ師の零時レイさんという方がいます。
この方、今では凄腕のナンパ師として数え切れないほどの女性のナンパに成功している方なのですが、昔は人と話すことさえ恐怖を感じるような、言わば対人恐怖症の方でした。
そんな状況の中で、ある心理学の本をきっかけに、色んな方と話しかけることから、始められました。まずは公園にいる人に対して、あいさつから始めていき、店員さんにありがとうと言う、世間話もする、、など段々レベルアップしていく中で、ナンパに出会います。笑
最初は女性に対して、極度の緊張の中、
コミュニケーションしていたのですが、場数を踏む、テクニックを覚えていくにつれて、段々ナンパがうまくいき、今では凄腕のナンパ師、人気Youtuberとなられております。
Youtubeで話している姿、ナンパしている姿を見ると昔の対人恐怖症のような要素はみじんもありません。
この方の変化をこれまでの解説で説明すると、
①人との交流を避け、明るく、元気に振る舞う、行動することがなく、ネガティブ回路で脳が支配されており、ノルアドレナリンなどが優位に出ていた
②明るく元気に振る舞うという習慣を取り入れ、それを何があってもへこたれず、継続した
③続けることにより、ポジティブな脳神経回路が形成された
④ポジティブなネットワークを持つことにより、脳が自分自身に対し、私は強いという認識がうまれ、外界に対して警戒する必要がなくなり、代わりにリラックス状態であるドーパミンが出るようになった
⑤ドーパミンが優位に出ることにより、いつもリラックスして行動することができるようになり、自信や、自己肯定感が上昇した。
というような感じでしょうか。
ここのまとめは先程紹介した、声のトーンの過去記事の内容を含みますので、よくわからない人はそれを読んでみて下さい。(マズローの5段階欲求の概念などが必要となるため)
私自身も、小学校低学年までは人見知りでしたが、少年サッカーをやり始めてから友達が増えて、人見知りの性格がなくなりましたが、これもこの話のメカニズムと同じでしょう。
友達ができて、その友達同士でよく遊ぶようになり、そうするとよく大声で笑ったり、色んなことにチャレンジしてみたりして、習慣が変わったからだと思います。
今回はとりあえずここまでとします。
書きすぎて疲れました(笑)
まだまだ書き足りてないですが😅
個人的にはやはり最後の5番目が一番大切だと思って、力説しましたが、いかがだったでしょうか🙄
Twitterもやってるのでよかったらフォローして下さい💪
ではまた次の記事でお会いしましょう✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
