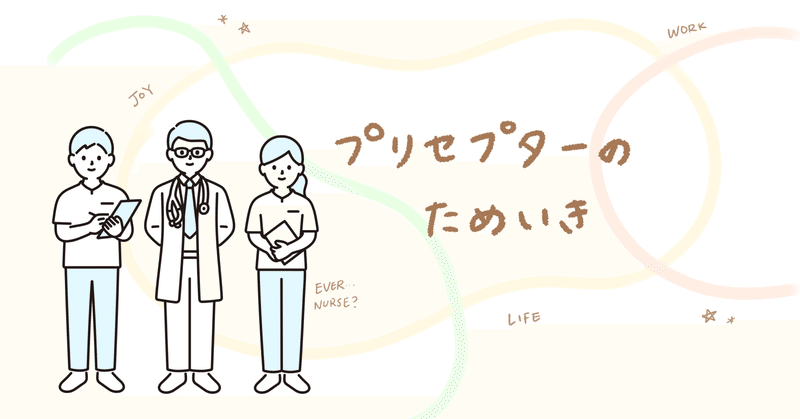
新人看護師との関わりでおすすめしたい習慣②仕事やめたいと相談された編
「仕事が合わないです。」
「○○さんと合わなくてつらいです。」
「やりがいが感じられません。」
仕事が嫌になって、辞めたくなることは誰もが経験したことありますよね。
仕事内容が合わない、人間関係のもつれ、思ってたのと違った・・・など理由も様々です。
新人看護師さんが4月に入職して半年が経ち、
初めは一心不乱に仕事を覚えるべく頑張っていたところから、気に入らないことが増え、仕事を続けていくことに自信が持てなくなったり、他の病院が魅力的に見えたりと変化が生じる時期です。
プリセプターのみなさんは、自分のプリセプティから「仕事をやめたいです」と相談されたときに、きちんと向き合い相談に乗ることが出来ますか?
これまでわたしも退職や転職に関しての相談を受けることが何度かありました。
真っ向から引き止めるわけにもいかないし、かといって辞めていいよとは言いにくい。(ケースによりますが)
基本、相談を受けた時の対応としては
辞めたいと思うほど大変な思いをしていることをまずは受け止める
詳細な理由を聞く
本当はどのように働きたいのかなど、本人の考え方を聞く
今の職場で働くことのメリット/デメリットを確認する
退職/転職することのメリット/デメリットを確認する
返答した内容を持ち帰ってもう一度整理してみることを促す
といった感じで関わります。
相手からの熱量が凄すぎてそうもいかない時もありますが・・・
さて今回はこれまで相談を受けたいくつかのケースを振り返ってみようと思います。
(もちろん個人や場所が特定されない書き方になります)
今後相談を受ける場面にあたった時、参考になれば嬉しいです。
Case1 仕事が大変だから辞めたい
「看護師業務が大変だから辞めたい」という例です。
みなさんご存知のように、看護師業務は肉体労働であり頭脳労働です。
体位変換や移乗に代表されるような肉体業務は体力に自信がない人にとっては辛いですし、命を支える重圧やお看取りの場面に神経をすり減らすことは考えるに容易いです。
それに加えて、血液や体液、排泄物などを日常的に取り扱うため不快に感じたり、感染のリスクに不安を抱えることも少なくありません。
最近ではコロナ患者の対応を余儀なくされる看護師が多数おり、業務負担は増える一方となっています。
なので、わたしは「看護師業務が大変だから辞めたい」と思うことはごく自然だと考えています。
それに対して「あなただけじゃないよ」「みんな大変な思いしているよ」とか言ったところで何の効果もないしむしろマイナスです。
まずは「本当にわたしもそう思う」「いつも勤務大変な中頑張っているよね」と大変さを共感し頑張っていることを評価します。
自分も大変なのですから、共感できるはずですよね。
次に具体的にどんなところが大変だと思っているかを尋ねて言語化させます。
漠然と大変であることだけを受け取っても何も解決できないからです。
それに続いて、本当はどうなりたいのか/どう働きたいのかを尋ねます。
現状の不満点と、願望を明確にすることでなんとなく道筋が見えてくる気がします。
例えば、
今は急性期病棟勤務。忙しすぎて業務を終わらせるのに精一杯。もっとゆっくり患者さんと関わりたいと思っている。→回復期やリハビリをやっている病棟に異動希望を出してみる
療養の支援ではなく、もっと専門的なことをやりたい。→手術室や救急外来に挑戦してみる
のような形で、部署異動で叶う形もあります。
院内にステーションを併設している病院であれば、訪問看護なども可能性としては広がります。
ここまで話を聞くときも、尋問みたいな聞き方はしないことを意識します。
あくまでお悩み相談の一環で、話の流れで聞けるように誘導すると自然になって良いです。
Case2 嫌な先輩がいて一緒に働きたくない
残念なことに、新人にはきつく言っても良いと考えている先輩看護師も少なからずいます。
ひと昔前までは、もっとそういった考えの方が多く、職場の雰囲気や実際の言動もあからさまだったと言います。
そういった環境で頑張ってきた先輩看護師はつい同じように振る舞ってしまうのかもしれません。
無意識に親にされてきた子育てを子どもにするという親子関係にもよく似ていますね。
また、「教える」と「叱る」を混同している方もいます。
「教える」とは、知識や技術を身に付けるようすることや、自分が知っていることを示すことをいいます。
一方で「叱る」とは、相手の非を厳しく指摘、注意することです。
新人看護師は、知識や技術、経験のどれもが不足しており、ヒヤリハットや細かなミスが目立ちやすいため、教えられたり叱られたりする場面が多いですよね。
そんなとき、おそらく問題となるのは叱られたときだと思います。
「アセスメントは足りなかったけど、そんなふうに言わなくてもいいじゃないか」
「あの先輩はいつも怒ってばかりでフォローしてくれない」
そんなことが積み重なるとあっという間に先輩後輩間の信頼関係は崩れてしまいます。
叱った先輩看護師からすると、
「きちんと気づいて指摘(指導)してあげているのに、どうしてそんな言われ方されなきゃいけないの」
と今にもヘソを曲げられてしまいそうですが、ここでは先輩ではなく新人さんの肩を持ってあげましょう。
まず大切なのは、嫌な先輩との間で起きた出来事について事実確認しておくことです。
どんなことをしたときだったのか、新人さん本人はどういう意図でその行動をしていたのか、先輩からどのような言葉で叱られたのかなど、話を深掘りします。
新人さんにとっては、「〇〇さんにまた怒られた!本当に腹が立つ」といったマイナス感情に共感してもらえれば嬉しいかもしれませんが、
そもそも新人さんのしたことは間違いだったのか?
先輩看護師の指摘内容は妥当だったのか?(言い方は別として)
という確認を取らなければ、ただ共感して、先輩を一緒に悪者にして終わってしまいます。
わたしは日頃、そういった出来事があったときには紙やスマホのメモアプリにざっくりと記録をするように伝えています。
後日、相談を持ちかけてくれるときに、当時の記録があった方が情報の正確性が高い印象があるからです。
一通りよく話を聞いてあげ、先輩からの指摘が妥当だったときには、自分の知識や経験から考えても指摘は妥当だったという事実を伝えます。
指摘がずれている、正しくなさそうというときには正しいやり方を伝えましょう。
それでも、プリセプティ本人にとって一番問題なのはその言い方、ひいては先輩看護師の人柄なのだと思います。
1番簡単な対処法としては、嫌な先輩とペアで働かないようにすることです。
本当は毎回プリセプターとペアであればプリセプティは安心かもしれませんが、当然ながら毎日そうはいきませんので、せめて嫌な先輩とは一緒にならないよう配慮します。
それでも解決が難しい場合には、異動を打診するなどの環境の調整を行う必要がありそうですね。
Case3 心身の体調を崩している
Case1、2で取り上げたことを含み、何かしらの理由で心身の体調を崩している場合には、もしかすると相談される前から欠勤や早退などの気になる様子があったかもしれません。
他にも、顔色が悪い、食事をあまりとっていない、以前よりメイクや髪型が手抜きになった、などの変化には要注意です。
そういった場合には、相談を受ける前に先回りして声をかけてあげられるとベストです。
プリセプティも、毎日を乗り越えるのに精一杯で相談することもできない状態でいる可能性があります。
あなたが声をかけてあげられたら、バーンアウトする前にきちんと休めるかもしれない。
病院を受診したり、休職したり、必要な選択をできるかもしれない。
そのためには日頃からコミュニケーションをとっておくことが大切ですね。
「そうそういい職場は見つからない」から退職を勧めない
ここまでのケースいずれも、異動や休職など退職以外の選択肢をまず提示してきました。
立場上勧めるものでもない、というのもありますが、勢いで退職するのは本当におすすめしていません。
なぜなら、自分が今の職場に感じている不満点を完全に解決してくれるような職場はそうそう見つからないからです。
わたし自身、転職活動は何回もしてきました。
転職エージェントに登録し、求人情報を見ては、ここはどうだろう、働きやすいかな、などと頭を悩ませる日々。
看護師という国家資格を持ってすれば、働く場所はたくさんありますし、すぐに内定をいただくことも可能です。
でも結局いつも、悩んだまま転職するわけです。
働いてみなければ見えてこない、不確定要素が多すぎるから。
前の職場のほうがまだマシだった、辞めなければよかった。
そんなふうに思ってしまうことも往々にしてあります。
退職を考えるのであれば、そのずっと前から転職活動はしておくべきです。
自分の望む働き方は何か。
どんな仕事はしたくないのか。
どんなことなら興味を持って取り組めるのか。
自分にじっくり向き合って、照らし合わせて考える時間が必要です。
在職・退職それぞれのメリット/デメリットについて考えるのも良いでしょう。
ちなみにわたしは、色々模索した結果として医療機関への転職は一旦断念しました。
わたしの望む働き方はそこにはなかったのです。
なので今はまったく違う働き方のために、いろいろ準備中です。
みんなが満足して働く事ができれば一番いいのですが、難しいですね。
心身の健康と、自分の幸せを大切に生きていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
