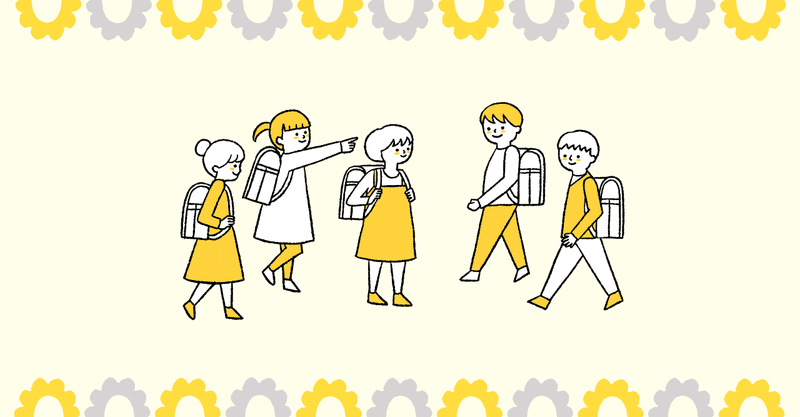
「小1の壁」のリアル2021 ―1学期&夏休み編―
娘が小学校に入学する前、何度も「小1の壁」という言葉を耳にしてきました。小1の壁とは、子どもが小学校に上がる時に直前する問題のことです。
うちの娘も今年の春に小学1年生となり、初めての夏休みを迎えています。今だからこそ残せる小1の壁のリアルを、今回はお伝えしたいと思います。
<このnoteは『COTETE Labo』掲載記事です>
「小1の壁」とは

小1の壁とは、子どもが小学1年生になった時、子育てと仕事の両立が難しくなることを指します。乳幼児期よりもラクになるはず…と思うかもしれませんが、そう甘くはありません。
実際に、スリール社が2018年に行った調査では「実際に小学生になり両立が大変になった」と回答した人が78.7%、さらに「4人に1人が小1の壁対策として転職など働き方を変更した」という結果も出ています。
小1の壁と一口に言っても、要素はいくつかあります。例えば、以下のようなものが挙げられるでしょう。
□ 学校の準備や宿題などのサポート
□ 夏休みなどの長期休み対応、
□ 保護者会や個人面談、PTAなど平日の学校活動
□ 保育園よりも預かり時間が短い
□ 会社によっては時短勤務ができなくなる
□ 子どもの交友関係、メンタルケア
このように複数の要素があるわけですが、どれを大変に感じるのか、もしくはもっと違う問題が出てくるのか、事情は家庭によってさまざまです。さらにこのコロナ禍で、昨年から今年にかけてはまた特別な状況もあります。
というわけで、以下に紹介するのはあくまで2021年版・我が家の記録。一つの参考にしていただけると幸いです。
1. 働き方を変えて正解だった
まず前提として、我が家はそもそも「3歳の壁」に直面して(壁ばっかりですね)幼稚園に入った結果、子育てと仕事の両立が難しくなり、その時に私が働き方を変えたという経緯があります。要は、小1の壁を先取りしちゃったというわけです(笑)
細かい話をすると長くなるので割愛しますが、今は週2勤務の会社員+在宅フリーランスという組み合わせ(複業)で働いています。これがやはり、小1の壁対策にも大きな威力を発揮しました。
例えば、毎日の準備や宿題の対応、平日の学校活動参加などは、自分の仕事をコントロールできるので柔軟に対応できています。幼稚園時代も何かと大変だったので、その延長線上というか、むしろ送り迎えが無くなった分ラクになった部分もあります。
その頃は苦肉の策でこういう働き方にたどり着いたのですが、今となっては先取りしておいて良かったなと思います。以前の週5フル勤務では、私には無理だったなと。
ちなみに、うちの会社は小1を過ぎても時短OKという恵まれた環境ですが、勤務先によって両立の大変さは全く違うだろうと想像します。
2. 宿題・勉強のサポートが大変

働き方の問題はクリアしたものの、一番大変だと感じるのは日々の宿題や勉強のサポートです。国語・算数の宿題が毎日それなりにありますし、音読を何度も聞いて、計算カードに付き合い、プリントの丸付けも親がしなくてはいけません(学校によります)。
この時間の捻出がなかなか難しいところです。フルタイムで働いている皆さんはどうしているのでしょうか…?我が家では今のところ、以下のように取り組んでいます。本当は、夫にも分担してほしいところ。
● 国語の音読:夕飯の支度をしながら聞く
● 算数の計算カード:寝る前にベッドで
● プリントの丸付け:子どもが夕飯を食べている間、もしくは朝
そして夏休みの宿題も大変!国語・算数ドリルに計算カード、絵日記、自由研究・工作、あさがお観察、ピアニカ練習、日々の生活記録などなど。保護者会で説明を聞いて、思った以上のボリュームに驚きました。
平日はいつも通り仕事をしているわけで、これらを進めていくのが正直負担だなぁと感じています。分からないところのサポートも必要ですし、少しは予習もしたほうがいい?など、勉強面での不安もありますね。
3. 学童保育は大好き、しかしお弁当は負担
そもそも学童に入れるかどうかで状況は全く違います。エリアによっては定員オーバーで待機児童になる可能性も。私はイレギュラーな働き方ではありますが、就業時間数はクリアし、ちょうど今年から大幅に増員されたこともあって、運良く入ることができました。
最初は小学校+学童という新しい環境になじめるか、少し不安もありました。しかし、実際に新生活が始まってみるとなんのその、今は楽しく通っています。授業のない学童の方が好き!と言っているほど(笑)
大変なのは、やっぱり夏休みのお弁当。これも幼稚園時代の“免疫”はありましたが(週2~3日はお弁当でした)それでも一定期間毎日続くのは負担です。なかには給食を導入している自治体もあるようなので、うらやましいなと思ってしまいます。
4. 学校とコミュニケーションが取りづらい
そのほか気になるのは、先生と直接コミュニケーションが取りづらくなる点です。幼稚園では送り迎えの時に話すことができましたが、小学校では子どもが聞いてきたこと、連絡帳、配布プリントが頼り。あいまいな情報や判断しづらいことに困る面もありました。
先日、個人面談で小学校での様子を初めて聞くことができましたが、やはりそういう機会は少ないものです。子どもの友達関係や困っていることなど、より意識的にケアしていく必要があるだろうなと思います。
さいごに

以前は「小1の壁」に対してぼんやりと不安を抱いていましたが、結果的に「大変な面はあるけれど何とかやれている」というのが我が家の現状です。
子育てと仕事の両立は、働いている以上ずっと向き合っていくテーマですが、その都度何とかする!それしかないのかなと思います(笑)
なんだかんだ言っても、小学生になった我が子は一回り大きく、頼もしく成長しています。そんな一度きりの姿を見逃さないよう、無理なく楽しい日々を送っていきたいですね。
▼妊活・子育てサポートアプリ「COTETE(コテテ)]
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。よろしければ「スキ」やSNSでシェアしていただけると、とっても嬉しいです! いただいたサポートは書籍購入など、今後のnoteに活かすために使いたいと思います。
