
『ドーナツ経済学が世界を救う』の読書感想(前半)
「目の前にある現実と闘っても、ものごとは変えられない。何かを変えたいなら、新しいモデルを築いて、既存のモデルを時代遅れにすることだ」
(発明家 バックミンスター・フラー)
『経済学』ときくと、お金が好きな人のための学問、という印象をもってしまったりしますが、本書では『これまでの経済学』から抜け出して『これからの経済学』の考え方へとかわっていくことを目指します。
キーワードは此方。
#SDGs #社会課題 #人新世 #貧困 #環境 #資本論 #コモンズ
目次
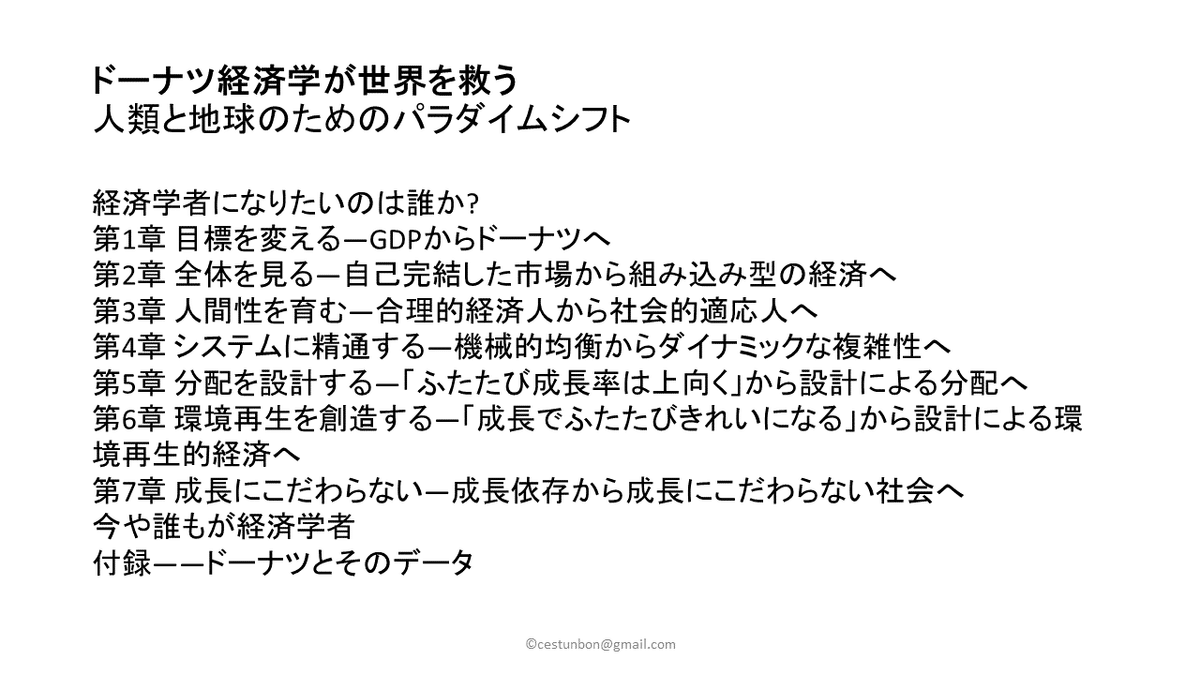
ドーナツの中に入るには
本書のコンセプトの核心である『ドーナツ』とは何か。
本書のドーナツとは「自然に迷惑をかけない」ようにしながら、「人々が不自由ない生活をおくれる」世界のことです。

経済的な不足のある地域や人々は、水や食料、教育やエネルギーといった「生活に必要な資源」が手に入らず、貧窮してしまう。。
一方で、過剰な経済的発展は、気候変動や海洋酸性化を引き起こし、生物多様性を失い、未来の人々が地球で生きていくことを難しくしてしまう。。
少なすぎるところがあってもダメだけど、多すぎるのもダメ。
そういうこれから必要になる経済の考え方が、このドーナツのようです。
ちなみに、ドーナツで、ぱっとわかりやすい表現にしているのは『図のチカラ』著者ケイト・ラワースを信じているから。人々に真実を伝えるための配慮や思いやりが行き届いているのも、本書の大きな魅力かもしれません。
二十一世紀の人類の目標がドーナツのなかに入ることだとしたら、その目標の実現の可能性をもっとも高められるのは、どんな経済学の考え方か?
「学生は古い考えをどのように捨て去ればいいか、いつ、どのように考えを変えたらいいかを学ばなくてはいけない。(中略)いかに学んで、忘れ、ふたたび学べばいいかを学ばなくてはならない」
(未来学者 アルヴィン・トフラー)
さよならGDP、こんにちはドーナツ
個人、企業、国。これまではみんな、成長を求めてきました。
GDPをどこまでも大きくしていくだれよりも早く。
しかし、そういった「じぶんたちがもっとも力のある存在になる」ことを目指したビジョンや価値観、世界観には限界がきています。

「人間の生活そのものを豊かにすることに(開発の重点)を置くべきであり、人間の生活の場である経済を豊かにすることに置くべきではない」
(ノーベル経済学賞受賞 経済学者・哲学者 アマルティア・セン)
「もったいない」「いらないものは買わない」というミニマリズムの考え方も、行き過ぎた成長に適切なブレーキをきかせるための声なのだろうとおもいます。
SDGsの目標をすべてを覚える必要性はありませんが、『不足』と『超過』を回避する、という2つの心構えをもつことは、だれにでもできる有効なマインドセットかもしれません。
経済でだいじなのはお金だけじゃない
70年にわたり、経済学の全体像(マクロ経済)だった『フロー循環図』。
そこにはお金の流れはありましたが、原動力となるエネルギーもなければ、生物や資源とのかかわりは表現されていませんでした。
かつての市場は効率的で絶対的存在で、企業が労働力と資本を集めて利益を最大化する主役であり、人々は労働力を提供し、或る種『搾取』され続ける存在でした。加えて、家の中の働きや教育は金銭のやり取りがないために、軽視というか無視されてきました。

それはおかしい。全体像を捉えられていない。
では、これからの経済学にとって、捉えるべき全体像とはどのようなものなのでしょうか。
地球 生命を支える。その限界に配慮しよう
社会 土台である。そのつながりを育もう
経済 多様である。システムのすべてを支えよう
家計 中核である。その貢献を重んじよう
市場 強力である。じょうずに組み込もう
共同財(コモンズ) 創造の源である。可能性をひきだそう
加えて、国家の責任、金融の利用、企業の目的、貿易の公平、勢力の乱用防止といった要素(役者たち)も、これからの経済には必要です。
地球の外からエネルギーを送ってくれる太陽の存在から始まり、それが電力のようなエネルギーや石油といった資源になり、生物や植物の力を借りて、食料や住居が与えられている。それを人は廃棄し、熱に変えていく。その逆戻りできない大きな流れのなかで、生活し、ものをつくり、生きている。
経済的活動の主体は、個人・市場・国・共有財の4つ。
無尽蔵ではない地球の中で、個人や共有財が担うべき役割は大きくなっていくのでしょう。市場や企業の成長に多くの命を燃やすのは、だれにも幸福をもたらしません。
これからの豊かさの1つは、社会資本であることは間違いなさそう。。
「コミュニティのつながりは、市民社会の心温まる話という次元に尽きるものではない。はっきりと目に見える形で、わたしたちを賢くしたり、健康にしたり、守ったり、豊かにしたり、あるいは公正で安定した民主主義の維持に長けた人間にしたりする働きが、社会資本にはある」
(政治学者 ロバート・パトナム)
解釈次第では、「SNSのいいね!こそ幸せ」となりそうですが、それはここでいうつながりとは違うものなのかもしれません。
やっぱり、人間っていいな
そんな社会の中で生きる、われわれ人間とはどんな存在なんでしょうか。
「わたしたちが人間の性質をどのようなものと考えるかで、実際の人間の性質は決まる」
(経済学者 ロバート・フランク)
経済学者にとって都合のいい人間像とは、「計算高く合理的で、じぶんのことを最優先して利潤を求める」ような存在です。そうやって(経済学者にとっての)理想化しておくと、研究がはかどったんでしょうかね。

研究対象も集めやすい人たち(多くは大学生)なので、結果としてWEIRD(Western/Educated/Industrialised/Rich/Democratic)に偏ります。
実際の人は、あらゆることを知ってるわけでも、いつも同じことをするわけでもなく、気分や周りの人の言動に反応して意思決定したり、売り買いしたりします。(羊の群れのように周りに流されることもあります)
「どんなことをだいじにするか」も変わります。利己的なふるまいをすることもあれば、思いやりや誇りを大切にすることもある。刺激に感化されてコロコロ変わることもあれば、一貫性に重きをおくことも。
偏見をもったり変なバイアスがかかることもありますが、直感で判断することで未然に危険を回避したり、周りからの後押しやつっつき(ナッジ)、人々とのつながりや道徳・規範で、道を正すこともできます。
じぶんたちを見つめ直し、「人間っていいなぁ」とおもえる生き方や選択ができるようになれば、ドーナツの中にいられる人の数も、そこで過ごす時間も、おおきなものになっていくのかもしれません。
ここまで読んでくださり有難うございました!
後半も良かったら御覧ください。
