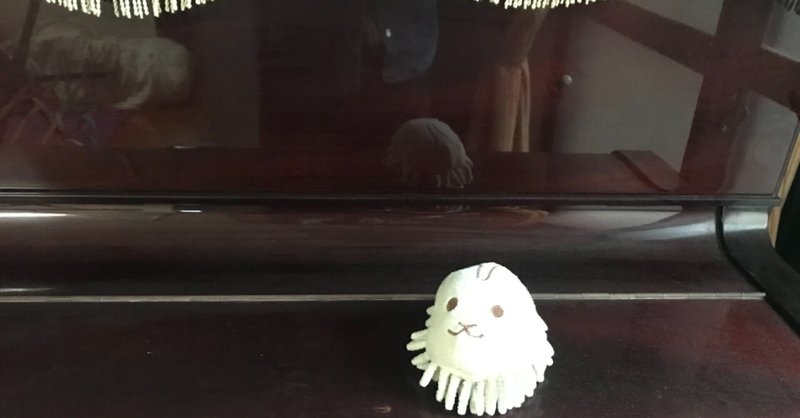
5月15日(土)言葉に残る時代の記憶〜「意志」の19世紀的解釈など
自分が関わった仕事じゃなくても、何かの広告がネット上で話題になったりすると、少し嬉しかったりするんですが、逆に面倒くさかったり、更に悲しかったりすることもあって。まあ、余計なことは考えず単純に喜んどけば良いんだろうし、自分が関わってないなら関係ないよと無視しても構わない話ではありつつ、何と言うか、職業病みたいなところもあるのかも知れないが、広告というのは、良くも悪くも、それを話題にするなど何らかの反応をする人のヒトトナリを可視化してしまう(☆1)ようなところがあり。
それはさて置き、1週間の振り返りを。
打合せ時に「テープ起こし」などという言葉を久方ぶりに聴いて、ああまだ使うんやとある種懐かしい気持ちになると同時に、一瞬、自分という存在がリニアに進行する(orそのように洗脳されている)歴史たらの中に「正しく」位置付けられたような、あまり面白くない不自由な感覚に襲われ。そうかそう言えば、とソシュール先生の言う言語の線状性(☆2)などを想起。
21世紀の今日、取材時に「テープ」を回す人なんてまずいない。が、取材時に録音した音源をテキストに置き換える≒視覚化する作業を指して「txtデータ化」「MP3起こし」なんて言い方する人には会ったことがなく。【テープ起こし】という語彙がどの程度「一般的」なのかわからないが、時代の状況と乖離しつつ、コトバとしては生き残っている。余談ではありますが、この、時代≒世界の残響音が奏でる音楽のような何かを、自分はコトバのダブと呼んでいる。
【日曜大工】はどうだろう。それをやる人が「平日の昼間は家にいない」前提がコモンセンスとして共有されてない社会では通じにくそうだ。もちろん、観光関連/小売り/外食など_流行り病の影響でなかなかそうはいかなかったりもするが基本的には_土日が忙しい職業も当たり前にありつつ、不思議な常識はいつの間にか形成されるらしい。ついでに言えば【平日】(☆3)なんてコトバも、いつまで使われているんだろう。
あと、先週書き忘れたというか書かなかったことなんですが、森鷗外『妄想』(☆4)を読んで思ったこと。21世紀の今日、ある種の好事家たちの意志(☆5)というワードを巡るやり取りについても、まずは19世紀の残響音をたっぷり含んだダブミュージック的に捉えてみたらどうだろう。
以下、カットアップ引用→…ショウペンハウエルを読んでみ/個人の不滅を欲す/失錯を無窮にし/個人は滅びて人間という種類が残/滅びる写象の反対に、広義に、意志と/意志が有るから、無は絶対の無ではなくて、相対の無で/意志が、Kantの物その物で/自殺をしたって種類が残る。物その物が残/ハルトマンの無意識というものは、この意志が一変して出来たのであっ/それはとにかく、辻に立つ人は多くの師に逢って、一人の主にも逢わなかった。
☆1)ヒトトナリを可視化してしまう:
広告コピー特にキャッチフレーズには、多かれ少なかれ「炎上」を誘発しかねない要素が含まれていたりするので仕方ないっちゃ仕方ないんですが。クソ真面目な人の場合その人の生来の誠実さよりむしろ偏狭さや頓珍漢な厳格さ、ちゃらんぽらんな人の場合は大らかさや明るさよりもだらしなさや考えの浅さなど、あまり見たくない部分が戯画的にあぶりだされてしまうケースが多い。
☆2)言語の線状性:
アカデミックに持って回った言い方だが、要するに「順番通りに並んではじめて意味を成す」性質のこと。例えば、りんごを食べたいときor購入しようとする際、り/ん/ご の順を無視して「すません、ごんりちょーだいか」と発話したのでは話が通じないだろう。人間なんて(©吉田拓郎)その程度には悲しい一生物種に過ぎない。
☆3)平日:
激しくユダヤ=キリスト教的な概念でもある。
☆4)森鷗外『妄想』:
ちくま日本文学全集『森鷗外』p46-77
☆5)意志:
クロウリーの言う「意志」または「セレマ」についても、(ラブレーがうんぬんよりも)カント前後の哲学の潮流をざっとなぞった上でアプローチすることで、無駄で頓珍漢な迷走をある程度避けられそうに思えたり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
