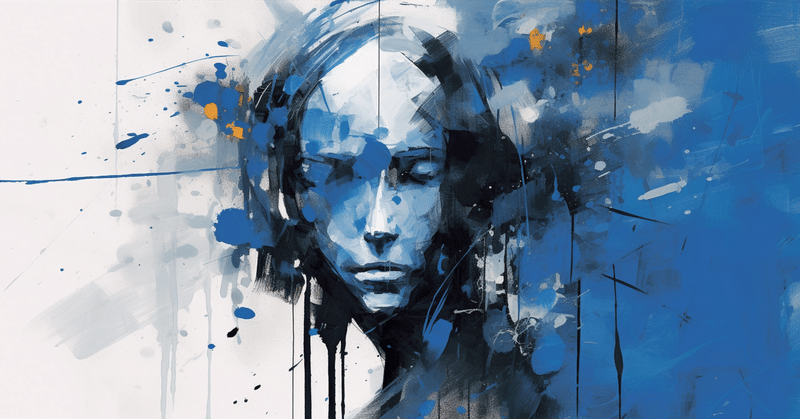
これは凄い!精神の病を巡る変遷を書いた名著『誰も正常ではない』

精神「病」を巡る冒険を描いた名著『誰も正常ではない』
「最近でウツっぽくて」とか「うちの子がADHDって診断されて」という言葉がもは何の違和感もなく日常会話になったのはいつの頃だろう。
先進国の中でもトップの自殺率を誇る病んだ国、日本において精神病っていうのは実は身近な話題だ。仕事を休職するためにうつ病の診断書を出してもらった過去がある自分としては、この精神の病を巡るロイ・リチャード・グリンカーの本はとても勉強になる本だった。
精神医学の歴史、現代で使われている言葉の変遷、そして現代のアプローチについてという、とても包括的な本でありながら読みやすいのである。いやぁ、すごいものを読んでしまったと、ここ2、3日ずーっと余韻に浸っている。
精神「病」はいつから精神病になったのか? 資本主義と精神病の深い関係
著者のロイ・リチャード・グリンカーは人類学者で、曽祖父と祖父が精神科医という家系。祖父に至ってはなんとかのフロイトの治療も受けた事があるほど筋金入りの精神科医一家。
祖父も著者に自分たちの跡をついで精神科医になって欲しかったそうな。
そんな著者は自らの家の来歴をたどりつつ、精神を巡る病がどうやって近代資本主義の社会においてスティグマ(偏見・汚名)化されたかを辿っていく。
本書は3部構成で、第一部で精神医学と精神病の歴史。第二部で戦争が与えた精神医学への影響を、第三部で現代の状況を展開している。
資本主義社会と精神「病」
人類学という強みを生かして精神「病」を社会の枠組みから著者が説明するこの本のハイライトの一つ。精神病というのは近代的なものではないが、精神病がスティグマとなったのは大変最近のことが明かされる。
精神病がスティグマとなったのは資本主義の発展の結果なのである。資本主義において個人の肉体=労働力は資本であり、働くという行動が至上とされる。
これに対して己の肉体を労働力として社会に還元しない個人は役立たずとして排斥されていく、だから精神病患者は閉じ込められ、人目に触れないように周辺化されてたのだ。
当然この発想は他のアイデンティティを持つ人々にも適用され、多くの女性や性的マイノリティの人々が排斥され、差別の対象となっていく。もちろんそこには人種への偏見も含まれる。
資本主義社会において、精神を患っていない男性こそが「正常」とされてきたのである。
正直読んでて息が詰まるけれども同時に、今生きる中で感じる違和感の正体を少し理解出来た気がする。いかに自分の見ている世界が普段接する言葉によって影響しているかと実感。
戦争と精神医学の甘い関係? 戦争によって変化していくスティグマ
第二部では精神医学の転換期が語られる。
長らく精神の病を個人の責任へと転換し排斥してきた資本主義社会に、とんでもない変化の波がやってくる。それまではごく一部の人しかならないと思っていた精神病、実はそうではない!という事が発覚。
精神医学に迫った変化の大波の名は戦争だ。第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争。国民全員を巻き込む現代の戦争において、精神を病む兵士の数は膨大な数に及んだ。
これは異常だ!と精神医学は方針転換を迫られる。病んだ兵士の治療をするために精神科医を増やすことが求められ、かつ患者を治療を受けさせることが必要だったのだ。
そうしてシェルショックという言葉が生み出される。それまでは社会の中で排斥されている病とは違い、これは一種の名誉ある国民病と見なされる言葉だ。
なにせ現場は戦場だから、病んだ兵士をガンガン治療してどんどん戦前に送り出す必要がある。診断名に忌避感を覚える言葉はだめだと、新たな診断名が開発された。
PTSDという言葉が生み出されたのもこの頃。戦争で病んだ兵士たちに、治療を受けて欲しいから。これ以外にも作中は今では普通になってしまった言葉や、概念がどれだけ戦争から生み出されたかが紹介される。
正直、こんなにも戦争と精神医学に関しての言葉が戦争に起源を持つと知って驚いた。
もはや誰もが「正常」ではない 固定化された病からスペクトラム(領域)化されていく精神「病」
第三部ではこれまでの変化の歴史を踏まえて、現代においての精神病の定義が語られる。現代の精神医学の特徴の一つは精神病が明確な一つのラベルではなく、スペクトラム化にある。
スペクトラムとは領域を示す概念で、物事は明確な違いが分かる場所もあれば曖昧で区別が出来ないものを含んでいるというモノ。例えば昼から夜に切り替わる時間帯、昼と夜は明確に区別出来るが日が暮れている間はどちらとも判別しにくいのと同じだ。
この考えが自閉症や統合失調症などに現在用いられている。こういう症状が出るから自閉症、統合失調症と決め打つのではなく、多くの症状の中であなたはこのへんに位置すると診断している。
いわば条件を全て満たすことよりも、どのように症状が表れているかを重視する考えにシフトしてきているのだ。そして治療によって患者が自立し、社会の中で生活することに注視する、いわば脱病化だ。
近代資本主義社会が生み出してきた「正常」に対する病的な固執に対抗する現状がここでは語られる。読んでいてとても前向きになれるというか、決して楽観的にはなれないけれども、ちゃんと変化の波を感じられる。
第三部を読み終わると、本書を執筆するいきさつを語る「はじめに」がなんとも感慨深い。
知ってくこと自体が戦いだ
この本を読んでるといかに自分が普段使う言葉、接している言葉に縛られた見方をしているかがよく分かる。身につけてしまった偏見を捨てるには、やっぱり知っていくことが大事だなぁって思ってしまった。
あとこの本がユニークなのは著者の一家が精神医学にどっぷり浸かっているること。曽祖父の偏見を批判的に書いたり、著者の伴侶も精神科医であったり、子どもが自閉症であることも語られる。
この精神科医一家という個人史と精神医学というマクロな歴史、これだけでも読み応え抜群なので、ぜひ分厚さに怯えずうっかりと読んで欲しいなー。
読み終わると偏見と戦うには読むというのも立派な行為だと妙な高揚感に包まれた。これからも生き抜くためにどんどんと読んでいくぞー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
