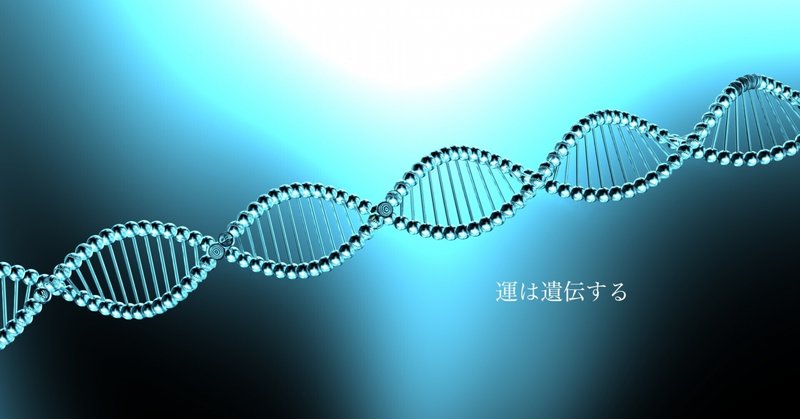
一側面ばかり見るのは当然ダメ──『運は遺伝する』読書感想文
本書の内容を一言でいえば「人間の資質は遺伝によって決まる部分が一定の割合で存在する」ということ。
体質、得意なこと、IQの高低など、親が持っている資質が子どもに大きな影響を及ぼすんです──と言われたら「そりゃそうでしょうよ」と言いたくなるのは私だけだろうか。
書籍データ
本書の使い方
誰もが気づいていることではあるけど、「あなたの社会的に評価される優れた(劣った)資質はおおよそ遺伝子によって定められているものです」と言ってしまうと、「じゃあ後天的教育や努力ではどうにもならんのか」という身も蓋もない方向の論調が生まれる事を懸念して、社会遺伝学では専門家がそこに踏み込んで言及することには非常に慎重になっているとのこと。
そんな薄氷を履むようなテーマを話題にした、作家の橘 玲さんと行動遺伝学を専門とする教育学博士である安藤寿康さんの対談が本書の内容。
絶対に誤解してはいけないのは、遺伝が影響するのはあくまで”割合”と”期待値”の高低の問題であって、人間の資質がすべて遺伝で決まるとはどこの誰も言っていないということだ。
本書の主張の正しい使い方としては、下記にあげる部分が一番ではないかと思う。
自分に有利にはたらく土俵を見つける
(努力も才能も遺伝的要因が大きいという前提の下で)まずは2割の努力をして、8割の素人を圧倒できるブルーオーシャンを探せばいい。
強者の土俵で戦う事を避け、自分の能力が優位性をもつ市場を見つけることができれば、それが成功への近道になります。とてつもない才能がなくても、とてつもない努力ができなくても、競争相手の平均を上回っていれば、十分な利益(金銭的収入と高い評価)が獲得できるでしょう。
遺伝的な部分も含めて自分を正しく理解し活用することが「人的資本の最強の法則」であるという主張。心底、同感。
子どもに期待するな
おそらく安藤さんが教育学の博士だからということもあって、本書では教育に関するトークテーマも多くみられる。
橘:親が熱心に子育てすれば、誰でも大谷翔平や大坂なおみのように慣れるという幻想が広まるのは、ほとんどの子どもにとっては悪夢ではないでしょうか。
なぜか私たち人間は、子どもという次世代に大きな期待を持ってしまうようにできているらしい。
「うちの子天才じゃない?!」って、子どもに対して一度でも思わない親はいないのではないか。ちなみに私は何度もある。
しかしそういう人間らしい愛情からくる一瞬の親バカと、自分とは別な人間である子どもに自分の期待を背負わせることの差異を自覚しなければいけないと思う。
どんなに努力しても大谷翔平になれないとわかっていて、なんで身体を壊すまで小さな子どもに練習を積ませるのか。
自分ができるから、もしくは自分より子どもができると思うから、という(特に根拠がない)理由で本人の性質や意志を無視した教育が行われているのを目にするのは忍びない。
例えば知能に関しては、遺伝率が上がるのはせいぜい20歳くらいまでだと本書の中で安藤氏は述べる。
小さい頃はある程度やれば伸びる。けれどそれはあくまで前借りして頭に突っ込んでいるに過ぎない。時が来れば通常のスピードで学習を進めてきた「地頭」が良い子にいずれ追い抜かされることを、果たして無理してまで前借りでやるべきなのかと個人的には思うのだ。
もちろん、低年齢からの学習や飛び級にぴったりとはまるタイプの子どもも一定数いる。しかし99%以上の子どもは、小さい頃は自分の身体を介してこの世界を学ぶ取り組みを最優先するのが良いのではないか。
小学生時分の、あの時間を思い出してみよう。
怪我の治癒の具合に生命の神秘を感じて、
投げたボールの行く末や水の中での不自由さに物理の法則を学んで、
友だちとのケンカで自分の意のままにならない人間心理を学んで、
今日は天井の木の節の数を数えたから、明日はごはん茶碗の米粒数えてみようかな、とか。今日は角砂糖こっそり食べて気持ち悪くなったから、明日は5粒までにしておこうかな(バレるし)とか、こっそり醤油直飲みして塩分過多はやばいって気づいたり。
学校からの寄り道中にかいだ良い匂いの根源、
吸った甘い蜜の出る花の名前、
怪しい空き缶の中身、猫のフンの埋まる砂場みたいな「危険ゾーン」、
ジャンケンに負けて友だちのランドセルを持つことになって知る自分の力の限界。結局、駆け寄って戻ってきてくれる友だちの優しさ。
子ども時代は、そういうことにめいいっぱい身体と頭を使えばいいんじゃないかって思う。
みんなそういう「無駄なこと」「バカなこと」と片づけられるようなことして、育ってきたんじゃないのかな?
子ども時代こそ、そういう余白って必要だよね?
で、子どもにその余白を与えられる余裕のある大人が、子どもたちの「個性」と呼ばれる遺伝子レベルで関与しているかもしれない差異をきちんと感じ取って個々の能力が最善に向くように育てていけるといいのだろうなあ。
遺伝子情報というものの捉え方
遺伝子情報は、センシティブな個人情報だ。
この本の中でもかなりのページ数を割いて取り上げられているテーマが、「犯罪の因子となる可能性の高い遺伝子」
遺伝子はプラスに働く作用だけでなく、統合失調症になりやすい、幻覚を起こしやすい、他者批判的になりやすいなど性格的な傾向にも大きく関与する。
肥満になりやすい遺伝子を持った人物が肥満になるのは、本人の努力いかんの話ではないので、その罪を本人に帰すのはフェアではないというのはわりと万人に共通の認識だろうけど。
では、統計上、犯罪を犯しやすいとされる遺伝子の型をもった人物が犯罪を犯したら「本人のせいではないのか」。
また、遺伝子の型による差別や格差という問題もこの情報が普通のものとして扱われるようになればなるほど助長するだろう。
遺伝子情報はあくまで人間としての良し悪しを決めるわけではなく、「今存在する社会」との関わりの中で、役に立つ・役に立ちずらいの指標とするだけの情報なのだが、問題なのは世間はそうは見ないだろうということなのだ。どんなにお題目は立派でも、下記のような振る舞いが一般にしかも無意識に蔓延しているから。
リベラルのいう「多様性」は、自分たちの許容する範囲でのみ認められて、そこから外れる異物は許さない。 〜中略〜 「同情・共感できるパーソナリティであれば、人種や民族、性的嗜好やジェンダー・アイデンティティにかかわらず、”自分らしく生きる”権利を認めますよ」ということですが、この原則は、社会的な望ましさから外れた人には適応されない──日本に限らず、世界的に見ても、「リベラルこそが不寛容」という傾向になってきています。
ここ、うなる。
多様性はマイノリティに対するものだけでなく、マジョリティの中の主流から外れた思想に対しても適応するべきものなのに、随分なご都合主義ですよね? とチクリ。
あーほんとに、不寛容ばかりで、多角的に捉えられない思考ばかりで、嫌になっちゃうな。
(実際、私の周囲はそんなことはないんですが。世の中見回すとそういうことを感じる機会も多いかな)
多様性に関しては、自分の経験も踏まえてぼんやりと思うところがあるので、それは別な記事で書こうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
