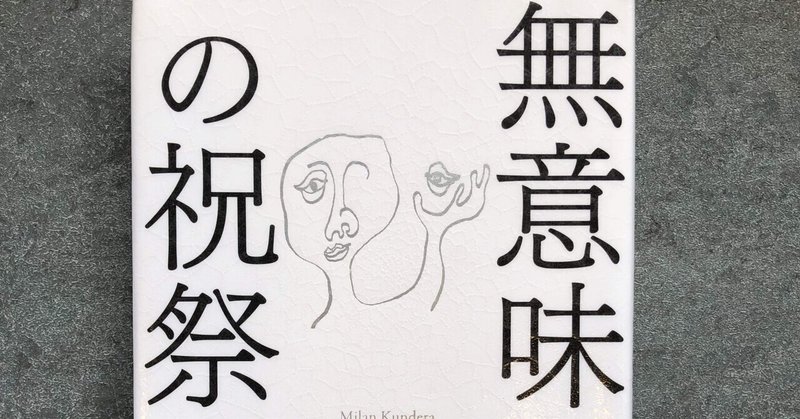
無意味の祝祭
著者 ミラン・クンデラ
訳 西永良成
出版 河出書房新社 2015/04/20 印刷 2015/04/30 発行
2013年のクンデラの作品であり、僕の中では読後、クンデラの到達点のような作品であった。賛否両論になりそうではあるが、僅か140ページ足らずの中にありとあらゆるものが詰め込まれ、全てはとるにたらない小さなこと、すなわち、無意味なことにこそ喜びがあるのだとクンデラが人生を達観してユーモラスに思想を語っていたように思えた。
あらすじ
共通の師匠「私」(クンデラ)を持つ4人の男がどうということのないカクテル・パーティーに参加することになる。
第1部ではパーティーの主たる参加者たちの紹介がされ、師匠から4人に渡されたフルシチョフの「回想録」を軸にそれ以降の話が進んでいく。
主な登場人物
アラン...母親のトラウマを持つ。へそフェチ
ラモン...クンデラの分身的な老教授
カリバン...パキスタン人
シャルル...4人の統合のような存在
私...おそらくクンデラであろうと考える。上記4人の師匠
ダルドロ...ラモンの知り合いでカクテル・パーティー主催者、ナルシスト
カクリック...控え目でダルドロとは対照的な人物
テーマ
本書は非常に哲学思想的な、そしてすべてが詰め込まれたクンデラの思想の結晶のようなものが根底に流れている。
回想
存在
他者を通してみる自分
無意味の祝祭
回想
著者ミラン・クンデラはプラハの春において、旧チェコスロバキアの民主化と自由を積極的に支援し運動に参加し、1975年にフランスへと亡命せざるを得なくなった。(2019年に国籍復権)
当時のスターリニズムや共産党による全体主義的な思想、政治を回想する。
時は流れる。そのおかげで、まずぼくらは生きている。つまりは告発され、裁かれる。やがて、ぼくらは死ぬ。それでもなお何年かはぼくらを知っていた者たちとともに残っている。だが、たちまちのうちに別の変化が生じる。つまり、死者は古い死者になり、古い死者のことを思い出す者はだれひとりいなくなって、彼らは虚無の中に消えていく。ただ何人か、きわめて稀な者たちだけが人々の記憶にその名を残すにすぎない。ただし、そんな稀な者たちも、どんな真正な証人もいなくなり、実際のどんな思い出もなくなってしまうから、操り人形に変えられてしまうのだ。
『無意味の祝祭』ミラン・クンデラ著 河出書房新社 (p29)
性愛の方向からみる存在
アランが第一部の冒頭でへそについて瞑想する。
大抵は性愛の方向の特徴として(男から女への)以下のようなものであろう。
1.太もも
わくわくする長い道のりであり、太ももの長さ=ロマンティックな魔力の強さ
2.尻
露骨さ/陽気さ 目標への最短距離
3.胸
女性の聖化=イエスに授乳する聖母マリア
4.へそ
?!
アランは何故か、これらではなく、ある日、へそに心を奪われた。
人間が生まれてくるのは母からであるが、母と胎児はへその緒で繋がれている。そのへそについてアランは最後まで瞑想することになる。
へそとは胎児とのつながり、つまり、未来への道ともいえる。
他者を通してみる自分
老教授のラモンがリュクサンブール公園を散歩していると、知人のダルドロに出くわす。
ダルドロはかなりのナルシストで構ってちゃんなのだが、そのダルドロはちょうど主治医にガンの疑いがあったが、ガンでは「なかった」と告げられた帰り道であった。
1か月間自分はガンかもしれないと精神を過酷な試練にさらされていたダルドロに、ラモンが「きみも人生を楽しんでいることがわかるよ」と気楽に告げる。
すると、ラモンは自分は実は「ガンなのだ」と嘘をつき、悲壮感と静かに寄り添う姿をラモンの瞳に映る自分自身を見て上機嫌になる。
全く無意味な嘘をつくことによってラモンは自分自身で自分の機嫌を直すからまだマシなようにも思える。
他人の中に映り込む虚構の自分の姿に酔いしれるという、「無意味」の価値がわからない「頓馬」の代表格的な人物のダルドロ。
これとは対照的なのが、カクリックという人物である。
平凡でも面白くもなく、愚にもつかないこと
=コミュニケーション相手にとっては、聡明な答えもどんな機転も必要としない
=居心地がよい
といった特徴を兼ね備えた、無意味は人を解放するということを感覚的に知り抜いている人物である。
すなわち、無意味の価値が分かっている人物だ。
一方、ダルドロはナルシシズムな側面がありながらも、高慢ではないため、気の優しい人間でもある。
と、ラモンは評価する。
ダルドロのシニカルなナルシシズムは前回紹介した「存在の耐えられない軽さ」で登場するフランツ的なものでもある。
無意味の祝祭
第1部から第6部までのオペラ的なものに「私」すなわちクンデラの間奏を交えて第7部で圧巻の終演を迎える。
偉人であろうと、極悪人であろうと、平凡な人間であろうと、意志の自由がある。
この意志というのは死んでしまうと無意味なものへと昇華していく。
ショーペンハウアーの偉大な観念を引き合いに出して、このことをスターリンを登場させて語らせる。
世界は表象と意志に他ならない
ショーペンハウアー
これは、「我々に見えるままの世界の裏には客観的なものなど何もない。巨大な意志によって現実がある」と小説の中のスターリンが語り始める。
わたしはいったい、だれにたいしてじぶんを捧げたのか?
わたしはじぶんを人類に捧げたのだ
しかしその意志が弱まり、くたびれ、うんざりし、支えきれなくなったスターリンの美しいとされた夢はガラガラと崩れ去った。
要するに、スターリンの巨大な意志も無意味なものになったということだ。
無意味とは人生の本質であり、無意味を認め、愛さなくてはならない。
無意味を愛するすべを学ばなくてはならない。
とクンデラは切々と最終楽章のために指揮棒を振るように語る。
ダルドロにとるにたらないような無意味な嘘をつかれたラモンは、最後、ダルドロに、これまた無意味な嘘をつく。
すると、ダルドロはその嘘を受け止め、またラモンの瞳の中に映り込む虚構の自分を見つめて上機嫌になって去っていく。
人生ってそんなもんだよな。とふと思った。
他人を通して虚構のような自分を時には見つめて、自分で自分の機嫌を取るダルドロは憎めない奴だった。
また、回想録の中のカリーニンも愛すべき人物だ。
カリーニンやダルドロだけではない。
スターリン含め登場人物全てがクンデラの優しいユーモア溢れる歌劇のような人生、歴史という芝居の中の愛すべき俳優に思える。
それぞれに無意味の大切さを提示してくれている。
トマトが赤くなっただけなのに、何故か嬉しいこと。
夕焼けが綺麗だなと思えること。
家に帰ろうとそうすると思えること。
ささやかな家族が待つ夕方の家路。
娘がいない、いない、ばーに夢中になること。
無意味とは、とるにたらない小さな出来事。
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
