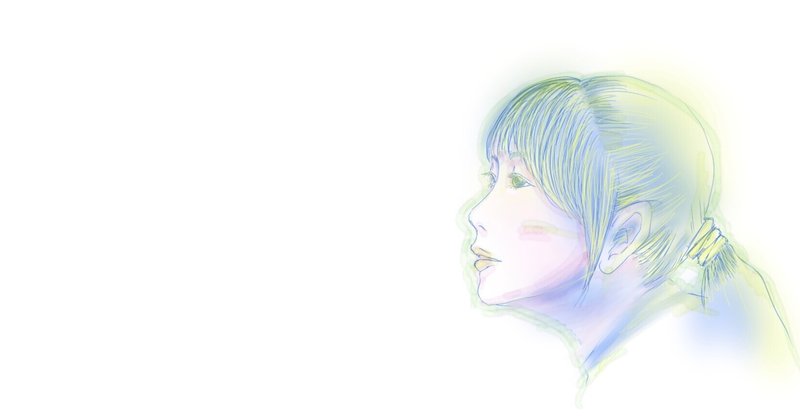
短編小説「その彼」

右から一歩、左で二歩目。そして、また、右足。見下ろす。いつの間にか、汚れた爪先。聞こえる、踵に擦れる砂音。一度、目を閉じて、再び、開く。南から波の音。規則正しく、一定間隔で届く。深呼吸を二度。背中に木々が擦れ合う声。
もういいかい。まだだよ。いつのことだろう、懐かしい誰かの声が聞こえた気がした。もう一度、聞きたかった。片手にヘッドホンを抑える。
もういいかい。
まあだだよ。
そう声にした。誰がいるわけでもない。虫もいない。鳥もいない。もちろん、人もいない。 僕以外は誰もいない。
聞く人のいない、その問いかけは、どこに届くはずもなく、発声の途端に色を失い、墜落してしまった。真新しくなった、どこかの海岸の砂上。海上には、年数を経て、崩れかけたテトラポッド。空はたぶん、青いのだろう。昨日や、一昨日、昨年や、一昨年のように。目を閉じた。その青さを、この世界のことを、僕が知る過去のことを、ひとつひとつ遡ってみようかとして、やめた。それはあまりに長く、入り乱れた道だ。とぐろを巻く蛇のように入り組んで、もつれにもつれた歴史なのだ。
「君は」
思い出す、波打際。
憶えている、初夏の海辺。
僕はこの手に抱きしめた、温もりのことをよく憶えていた。さざめく水面は降りしきる光を乱反射して明滅を繰り返していた。どこか遠くで雷音が聞こえた、気がした。それでも、僕たちは、その砂浜から離れなかった。
「知ってる?」
僕に振り返る彼女は笑っていた。白いワンピース。麦わら帽子。リボンに赤い花を飾っていた。そのころはいた、誰か、に、踏み折られた一輪を拾って、僕が彼女の帽子に挿したのだ。一度きりの眩い季節に、とてもよく似合っていた。
「これが海。君がいる砂浜は海岸。私がいるのが海」
知ってる? 頬を赤くして彼女は言った。膝のすぐ下までの浅瀬に浸かって歩きながら、白い手を振り、彼女は僕を誘ってくれたのだ。
「気持ちいいよ。ほら」
君もおいでよ。近くに見ると透き通るのに、顔を上げるとその水面は鮮やかに青い。これが、海。地表の70パーセントを占めるという、海。美しい星の理由。この星が美しい、そのわけ。
「海」
思わず落ちた声。立ち上がった波が僕の声を飲み込んだ。この星のすべての命を産んで、育み、いまなお、永遠を示唆する、母なる海。海と、産み。産まれた生物。その還る故郷である、海。君は僕の手を引いた。素である、液体に足を差し込んだ。足首の真横を小さな魚の群れがすり抜けた。光が集まって、弾けた。千切れた光は再び集まって、賑やかに騒いで、そして散った。海に驚く僕を見て、彼女は笑っていた。
その微笑みこそが光だと僕は思った。
光が失われて何年になるだろう。僕は指折り数えた。右手の親指から始まり、左手の小指まで。それを何度も往復した。10以上を繰り返した。150年近くが経過したのだと、ついこの間も確認したことを思い出した。誰とも話すことのない生活は、記憶が曖昧になる。それとも、さすがに年齢を重ねて認知能力が落ちてきたのだろうか。僕はその不安を笑った。仮にそうだとしても、誰が困るわけでもない。僕はいまや、この星でたった一人なんだから。
それに、と、付け加えた。忘れたいことばかりじゃないか。この星に生まれてから、人は戦争ばかり繰り返してきた。まるで、人は人を殺戮するために生まれてきたかのようだ。かつて、友であった人々は皆、死んで行った。生き残った人も、やがて、年老いて倒れた。彼らは戦争を反対したが、しかし、人は戦争をやめはしなかった。
最初の世界大戦。二度目の世界大戦では核兵器が使用され、やがて、その兵器をそれぞれの国が保有するに至り、三度目の世界大戦は、その兵器の誤爆から始まった。実験のために輸送されていた核が国境沿いで爆発し、それが三度目の大戦のきっかけになった。四度目の世界大戦は、宇宙空間からミサイルが放たれ、数百に及ぶそれは地球を氷河期にした。植物。動物。そして人。太陽のない暗がりで、生命は順に消滅していった。地表は凍り、海も汚れて泥の沼と化した。そのころ、虫たちも死んで行った。
僕はその星を彷徨い続けた。残骸と化したマーケットを食い漁り、食べ尽くしては、次の街を探した。どこまで歩いても無音だった。
それでも、痕跡を探して、僕は録音を、録画を続けた。
「こんにちは。生き残っている人はいませんか」
こんばんは。誰か。聞こえませんか。
この三十年は、生き残っている人を見かけていない。長い氷河期に、おそらく絶滅してしまったのだろう。冷凍庫こそ残っているが、太陽すらない。花も実もならない、氷の星なのだ。
「おはようございます」
いつか、歩いた海を見つけたかった。永遠に青いものが、永遠そのものがそこにあるのだと僕は考えからだ。
「こんばんは」
本来は永遠であったそれらは、人の行いによって消失した、かに思えた。
「あれは」
濃い灰色の坂道を頂へ。登り詰めた、瞬間。視界には、あの眩い青が広がっていた。幻だろうか。システムの誤作動だろうか。網膜の異常かもしれない。僕は考えられる可能性のひとつひとつを確認した。すべてに異常があるのかもしれないし、あるいは、目の前の光景が現実かもしれなかった。
「海」
思わず僕は走り始めた。あの青。弾ける光。すべての生命を産んだ、海。僕たちの母。まぶたに、あの子の微笑みが蘇る。それは、光。
ほら。
声。陽だまりから届く、鈴のような声。思い出す。覚えている。忘れるはずのない、声。幻でもいい。最後の力を振り絞って、僕は彼女のもとへ向かった。
「初めまして!」
あれ。名前は。なんだっけ。たった一人の、大切な人なのに。名前がわからない。君を呼ぶことができない。君は。その名は。システムが狂っている、そのことに気づいたとき、僕は転倒してしまった。運動野への神経接続が停止している。時間切れ、なのか。再起動して見上げた空。
「お久しぶり」
覗き込む顔。優しい微笑み。何十年ぶりだろう、あの懐かしい女の子。僕の額にタブレットをかざす。
「君が撒き続けた種から芽が育ちました。空気も少しずつ回復してる。視えるかな?」
雲の切れ間に太陽。そしてわずかに青い空。海と見紛った、青。氷はもうすぐに溶けるだろう。幻聴なのか、集音システムの異常かと思った、鳥の声。
「おつかれさまでした、ミスター……」
僕の名前。それは僕につけられたコードネーム。型式番号はRX-2038-01-16-rob。ニューヒューマン。君が作った、新しい人は、人類の戦争史を見てきました。視てきました。最後の戦争でこの星が終了したのだと考えていました。
「ゆっくり休んで。ありがとう」
彼女は僕のシステムを終了させるのだと言う。目を閉じる。まぶたにはその微笑みが残る。良かった。皆さんのお役に立てて。良かった。また会うことができて。
「最後に一言だけ。いいですか」
まぶたには彼女の微笑み。花の匂い。柔らかな、春の日差し。そう。これが地球。僕たちの星。だよね。
「もちろん。どうぞ」
動かなくなった手を握ってくれた。ぬくもり。人の手の温もり。
「僕を生んでくれて、ありがとう」
不死ではなかった。僕は、人間として、生きることができたんだ。波の立ち上がる音が聞こえて、それから、調和の訪れた世界は、海底よりも静かになった。
to be next……
artwork and words by billy.
#宇宙SF
サポートしてみようかな、なんて、思ってくださった方は是非。 これからも面白いものを作りますっ!
