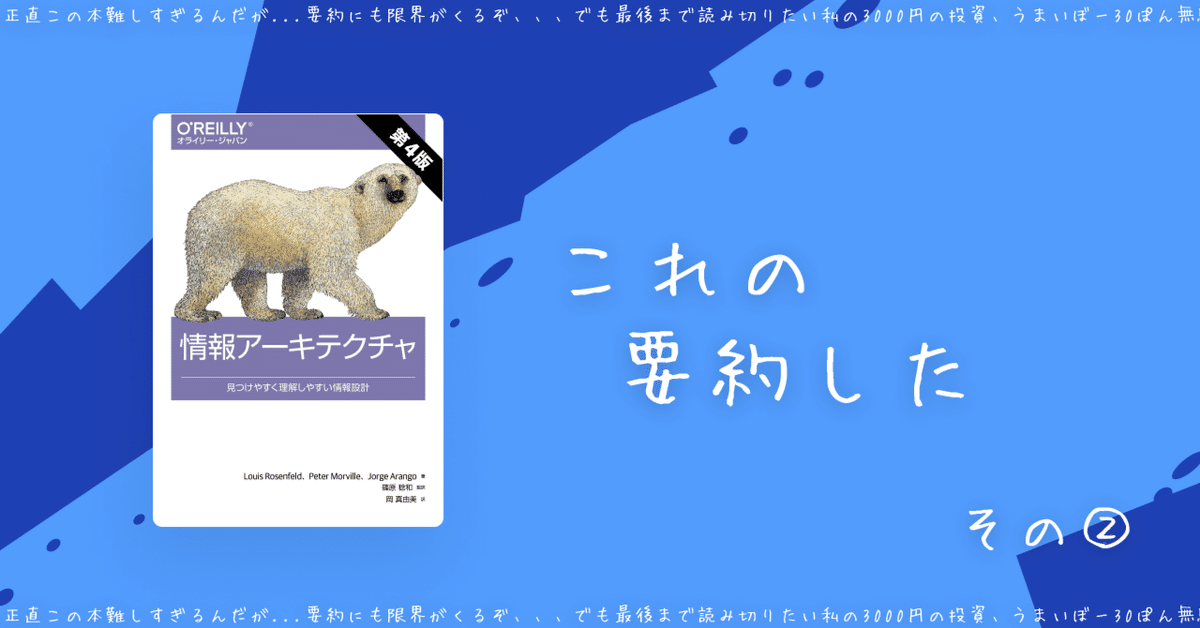
UI/UXデザインにおける情報設計の本読んで要約してみた その②
こんにちは、UIデザイナーのゴロ丸です。
前回、いいねしていただきありがとうございます。。。
励みになりまして、続きを遅れながら投稿させていただきやす🤲
前回は、ユーザーがどのように情報を探すのかについてでした。気になる方は以下からお読みください!🌈
https://note.com/bibimuu12/n/na6859ca09e4c
今回は、ユーザーの情報探しをどのようにサポートできるかの話になります。
次のセクションに書いてある「建築物の設計から考える情報設計のシステム」はあんまり面白くないから飛ばしてもいいかもww😂
建築物の設計から考える情報設計のシステム
現実の建築物の設計では、窓の大きさ、空間の取り方、床をどうするかなどを定義していくと思います。これと同じ様に情報設計では、ナビゲーション、セクションラベルの定義などを行うことで何ができるサイトなのかをユーザーに知らせることができています。
つまり、情報設計はこういったラベルやキーワードを定義していくことで成り立つシステムといえます。🧐
また、建物には入り口があり、そこから入場し、中の椅子に座ったり、買い物したりします。これと同じ様に情報設計でもトップレベルでいくつか入り口があり、そこからさらに深い階層に入ってアクションを起こしていきます。こう言った構造にすることによって、ユーザーはこのサイトが何のサイトなのか、何ができる場所であるのかを理解することができます。
このように現実の建築物の設計と情報設計のシステムは似ているようです。
個人的にこの章で感じたこととしては、基本的にこの様な上から下にアクションを起こす行動は現実のユーザーの行動に近いのかなと思いました。🤔
銀行のアプリ、買い物のアプリ、SNS、何を作るにしても情報構造は現実の行動とリンクしている場合が多いかと思います。
例えば、人と話すときに無意識のうちに特定の人を選択して話しかけるという行為はLINEなどで特定の人物を選択してからチャットを始めるという情報構造とリンクしているなと、、、。🤔
このように人間の行動の延長線上に存在するサービスがほとんどなため、私たちはどのアプリケーションを使うにしろ、ある程度は対応できるのかもしてないですね。🙃
情報設計のシステムについてはこのようになっていましたが、では、実際ユーザーの情報探しをどのようにサポートできるのでしょうか?🤔
もう予想はついているかもしれませんが、スーパーで例えると、ユーザーはスーパーの中に、いろんなコーナーが存在していることが天井からぶら下がっている看板を見てわかると思います。そんなとき、お菓子🍦の食べたいユーザーはお菓子コーナーに入って目的のお菓子を探すと思います。これと同じでwebサイトでもナビゲーションで何があるのかを指し示すことでユーザーの情報探しをサポートできます。また、個人的な意見として、建物に入る前に何ができる場所なのかがわかるように、webサイトも入ってすぐに何ができるサイトなのかを雰囲気で伝えることも大切かなと思いました。😯
情報設計によるユーザーをサポートする4つの技
情報設計によるユーザーをサポートする4つの技とは以下のものです。
①「分類分け」→サイト自体のコンテンツのカテゴライズを行う。(売り手か買い手かなどをユーザーに選ばせて適切なコンテンツを表示する)
②「情報表現」→ユーザーが特定の情報を理解できる言葉で表現する。(グルーピング)
③「ナビゲーションシステム」→メニューをサイト内に用意しユーザーがサイトをブラウズできるようにする。
④「検索システム」→コンテンツを検索できるようにする。(SEO対策やクエリー言語も含む)
ユーザーの探している情報は何かを考え、上記の技を使う必要があり、これをトップダウン型の情報設計といいます。
一方で、よりユーザーに彼らが求めている情報を届けるためには、サイト内で情報をグルーピング化することで、webのシステム自体の検索機能によって検索されやすい状態になる必要があります。これをボトムアップ型の情報設計と言います。
サポートする手段はもちろん他にも色々あると思いますが、この本ではこの4つについてメインで書かれているので、自分たちでもっと他にもサポート方法があるかを模索しても良いかもしれません。🧐
サポート手段その①「分類分け」の問題点と解決策
この本によるとこの分類分けには、4個の問題があります。
まずは言葉の定義は曖昧性です。例えば、「android」の対義語は何でしょうか?「iphone」と答える方が多いのではないでしょうか?🧐しかし、実際は「iphone」ではなく、「IOS」です。そもそもandroidはOSの名前であり、iphoneはデバイス名なのです。「android」「iphone」と先に情報設計したままプロジェクトを進めてしまうと大問題になりかねますよね。そのため、言葉の定義には注意が必要です。しかし、この例えの場合は、場合によって世の中の認知と合わせて「android」「iphone」としても良いかもしれませんね。✌️
2つ目は、情報環境の不均一性の問題です。webサイトには動画や画像、商品説明のテキストなどさまざまなコンテンツがあり、その情報量は各webサイトによって異なります。そのため、これといった分類方法がなく、自分たちで考えて分類分けする必要があるのです。これによってそれぞれの人が共通してもつカテゴライズ方法がないので、カテゴライズするのが難しいのです。
3つ目は、考え方の違いです。2個目でも言ったようにカテゴライズ自分たち(サービス企画者側)が行う必要があります。そうなってくると、どこからどこまででカテゴライズするかは人の考え方によって異なります。解決策として、自分たちの主観でカテゴライズするのではなくユーザー調査や競合調査をすることで世間一般的にはどのようにカテゴライズされているかを分析し、ラベリングをしカテゴライズする必要があります。
4つ目は、社内政治です。カテゴライズする中で上司にこっちの方がいいのでは?などと言われ、より良いかもしれない情報設計が崩れる場合があります。これを防ぐ方法として、確実な根拠となるエビデンスを用意しておくことやあらかじめ他の人に賛同してもらえるように根回しをおこなっておくことも重要だそうです。ただ、カテゴライズにおいて正解はないので、お互いに意見を受け止め、協力してより良い情報設計を実現するのが良いかもしれませんね。
サポート手段その①「分類分け」の方法
この本によるとこの分類分けの方法は、以下のようなものがあります。
アルファベット順。これは、ユーザーが既にそのものについてあらかじめ知識がある場合に有効です。
時系列。地理。
トピック分け。これは、サービス提供側で情報を勝手に分けるものです。
タスク分け。これは、figmaのツールバーなどが当たります。
顧客分け。これはターゲットユーザーがはっきりに種類に分かれている場合に有効です。
メタファー。例えば「ストーリー(インスタ)」「ハドル(スラック)」などがそれに当たると思います。
このような分類分けの方法がありますが、ユーザーは探すものがわからない曖昧なままで調べることがあることを考えると、情報は基本的に複数の情報で分類分けしておくことによって、ユーザーが目的の情報にたどり着けるようにしておくのが良いでしょう。
また、階層によって分類することも可能です。例えば、トップダウンのアプローチがあります。これは、料理という大きな分類の下に中華、イタリアンなどが分類されていくように上からだんだん詳細に分類されていくものです。しかし、これにも一点問題があります。それは、分類またぐものが存在するということです。例えば、男性湯と女性湯があったとして、トランスジェンダーの方はどちらに入るべきかとなったときに、社会的な性別もしくは生物学的な性別どちらで分類するかによってどちらに入るかが変わります。このようにAかBか分けたいのにAB両方の性質を持っている場合にどうするのかというものがトップダウンでのアプローチのなかで多く存在するとユーザーが階層の中で迷子になり分類分けの意味がなくなってしまうので注意です。
さらに、ハッシュタグなどによって社会的に自動で分類分けが行われるパターンもあります。
次回へ続く、、、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
