
【レポート】計画的偶発性理論におけるキャリア形成において偶然を味方にすることは可能なのか?
自己評価:抽象的な可能性の意味を捉えるためレポートにふさわしくないテーマ
「キャリアの大部分は、予想外の出来事によって決定づけられる。」
これが、20世紀末に提唱されたクランボルツの「計画的偶発性理論」の主張でしたね。
主な理論の内容は、以下の通りです。
①予期せぬ出来事がキャリアを左右する。
②偶然の出来事が起きたとき、行動や努力で新たなキャリアにつながる。
③何か起きるのを待つのではなく、意図的に行動することでチャンスが増える。
実際、近年は、新型コ○ナウイルスの流行など、予想だにしなかった出来事が連続していますよね(^^;
先読みの難しい社会情勢においては、プライベートでもしかり、組織のひとりに、将来の目標を明確に決めさせることは困難な状況になっています。
だからこそ、いかに偶然を引き寄せる努力を個人や社員に促せるかが、家庭の、また、企業の命運を決めると言っても過言ではありません。
計画的偶発性理論では、偶然をチャンスにするためには、5つのスキルが必要とされています。
<5つのスキル>
好奇心Curiosity. 興味を持つ
持続性Persistence. 簡単にあきらめない
柔軟性Flexibility. 柔軟にチャンスを活かす
楽観性Optimism. 前向きに取り組む
リスクテイクRisk taking. 結果が分からなくても、 行動を起こす。
人生には、様々な転機があります。
結婚や離婚、出産・子育て、子供の独立、介護による帰省、予期せぬ失業、病気による行動制限など・・・・・・
転機には喜ばしいことばかりではなく、それまで大切にしていたことも手放さなければならないこともあります。
セレンディピティ(Serendipity)とは、「偶然の産物」「幸運な偶然を手に入れる力」を意味する言葉です。
イギリスの小説家・政治家であるホレース・ウォルポールが生みだした造語で、「セレンディップと3人の王子(The Three Princes of Serendip)」というおとぎ話が語源になっています。
「セレンディップの三人の王子たち―ペルシアのおとぎ話」(偕成社文庫)竹内慶夫(編訳)

【参考図書①】
「「探偵小説(ディテクティヴ・ノヴェル)」の考古学―セレンディップの三人の王子たちからシャーロック・ホームズまで」メサック,レジス(著)石橋正孝(監訳)池田潤/佐々木匠/白鳥光/槇野佳奈子/山本佳生(訳)

「セレンディップと3人の王子」とは、王子たちが旅先で優れた能力や才気によって、有益なものを偶然発見して手に入れるという物語です。
単なる「偶然の発見」ではなく、「幸福な偶然を引き寄せる力」とも言えるでしょう。
セレンディピティとよく似た言葉で「シンクロニシティ」があります。
シンクロニシティとは、「意味のある偶然の一致」を意味する言葉です。
どちらの言葉も「偶然」という点では同じですが、シンクロニシティは、あくまでも起こった現象そのものを指します。
それに対してセレンディピティは、幸運な偶然を得る主体的な力のことを指すのです。
幸運な偶然を引き寄せるためには、自分が何に関心を持っているのかを明確にすることが大切です。
このように自分なりのテーマを持って過ごすことで、チャンスと巡り合ったときに見逃さずに掴むことができるはずです。
まずは興味関心があるテーマを持って、普段とはちがう行動をしてみることをおすすめします。
英語には”memo”と”note”という単語があるのですが、その違いは少し複雑なんだよね^^;
まず、”memo”の意味は?
この単語は、「memorandum」の略です。
紙に書かれた情報という意味では、日本語の「メモ」と同じですが、英語のメモの基本的な定義は、「誰かの為に書かれた人と共有するための情報」という定義です。
つまり、日本語のメモ=英語の"memo"ではありません。
日本語のメモは、英語では"note"に近いんだよね。
と言う事は、以下の言葉は、自分の琴線に触れた言葉たちを書き記した内容なんだけど、この記事でみなさんと共有した時点で、"memo"に変化したってことなんだ(@@)
へ~面白いね(^^)
【関連記事】
【備忘録】僕らは言葉でできている Vol.1
https://note.com/bax36410/n/n494e47650936
【備忘録】僕らは言葉でできている Vol.2
https://note.com/bax36410/n/n65c8948dddb7
【備忘録】僕らは言葉でできている Vol.3
https://note.com/bax36410/n/nf09bcc893e7a
【備忘録】僕らは言葉でできている Vol.4
https://note.com/bax36410/n/n0bdbb53d212c
【備忘録】僕らは言葉でできている Vol.5
https://note.com/bax36410/n/n077f32458cae
では、"note"の意味は?
先ほど述べた様に、こちらが日本語のメモの意味に近くて、"note"は、「自分の為に書かれた他人と共有しない情報」なので、げぇ^^;
noteに書いちゃダメじゃんか(爆)
そうそう、ノートのことを英語では、"notebook"と言いますが、"notebook"の中に書かれているものが"note"で、また、"note"は、日本語と同じく短い文章を指しています。
なので、短い文章を書きたせる付箋のことは"sticky note"と言うしね(^^)
【関連記事】
出逢いは、いつでも偶然の風の中にあって・・・・・・
https://note.com/bax36410/n/n134dc5e47cb2
さて、ここから、「計画的偶発性理論」におけるキャリア形成において偶然を味方にすべく、色んな角度からセレンディピティに関する"情報"をメモランダムに一挙公開しておきましたので、お暇なときにでも、お立ち寄りくださいm(_ _)m
長~~~いので、途中抜けOKです!(^^)/
文字数:92,816字
[ 発見(気づき):参考または参照文献・資料等 ]
【セレンディピティは偶然のチャンスを活かす力を指すキーワード】
セレンディピティは「偶然」と「察知力」の二つの要素があり、「偶察力」と呼ぶことも可能である。
セレンディピティは、「当てにしていないものを偶然にうまく発見する能力」と定義されており、
・発見・創造する能力とは、偶然を最大現に活かす能力である。
・感性を研ぎ澄まし、察知力を養えば偶然は偶然でなくなる。
偶然の幸運に出会う能力よりも具体的で主体的(発見する>出会う)なニュアンスが感じられる。
これを契機に「偶然に思いがけぬ発見」をするには、「不思議に感じたことは、それを追求すれば原因がある」と信じることが大事である。
この”不思議に感じたこと”を放置すれば、そのまま”偶然”は通り過ぎていくのである。
それが何であるかがわからなくても、とりあえず「あれ?」と思ったこと、あるいはやっていて“ひっかかる”ことに注目することは、発見への第一歩である。
具体的な発見の手順は、まず、オャッ!と気付く感動から初めてみると、そのような事象、現象に出会ったときは、それを観察して記録を残し、ネーミングしておくことである。
さらに、課題の認識を行い、これに関する連想が働きやすい状態にする。
情報交換は積極的に行い、関連記事を見つけたときには、手軽にファイリングできるシステムを作っておく。
行動範囲を拡大して、思いがけぬ連想の生じる機会を促進する。
因果関係が解明できれば仮説をたてて、これを検証する。
そして、思いもよらぬ因果関係を明らかにすることになれば、これは発見であり、これを応用することから創造が生まれる。
以上をまとめると、セレンディピティを活かすための手順は、
1.ひっかかったことを観察し、記録する
2.名前を付ける
3.課題の形に変換する
4.関連する情報を集める
5.仮説を立て検証する
という5つのステップになる。
このように、自分が何となくやってしまっている、あるいは無意識にできてしまっていることに改めて目を向けて、その方法やメカニズムを上記の手順で考えてみることで、セレンディピティを発揮し、未踏の領域への第一歩を踏み出すきっかけを作ることができそうである。
成功している人や昇進が早い同僚を見ると「たまたま運がよかっただけ」と舌打ちし、「自分は運がないな」と自虐的になってしまう。
こんな妬みの心理は、「やる気」を失わせる一因だが、確かに幸運・不運は人それぞれにあるように思える。
しかし、「たまたまの幸運」は、単にどこからかやってくるものではない。
ある偶発的なことが身の周りで起こったとき、それを幸運に結びつけるか見逃すかは「心がけ一つ」と思う。
「出会いは宝物」というのは、人生訓の常套句だし、「一期一会」という故事もある。
幸運な出会いが度重なって、初めて「一期一会」という言葉の重みを実感するのかもしれない。
しかし、これを人生訓として受け取るだけでは、物足りない気がしする。
偶然には、何か秘密が隠されているのではないかという思いが折りに触れ去来していた。
もちろん、「偶然の秘密」など、おいそれとわかるはずはない。
このテーマは、ショーペンハウアー、ニーチェ、ハイデガーなどの大思想家たちを悩ませた哲学の一大命題である。
「偶然」に関心を寄せながらも、我々の理解は「偶然とは不思議なものだ」というレベルに止まっている。
その理解が突如、一気に飛躍することになったのは、「セレンディピティ(SERENDIPITY)」という言葉だった。
辞書を引くと《あてにしていないものを偶然にうまく発見する能力》と記されていた。
しかも、この言葉はR・K・マートンという米国の科学社会学の大家によって使われ、科学的発見にまつわる“偶然性”を説明する言葉として注目されている。
まず、言葉の由来を、歴史を遡りながら紹介しておこう。
マートンがこの言葉を最初に使ったのは、1945年の論文である。
その10年後には研究論文「セレンディピティの旅と冒険ーー歴史的意味論と科学社会学に関する研究」(未完)を著し、科学的発見にしばしば見られる偶然性を「セレンディピティ」と名づけて自分の科学社会学理論の新しいコンセプトとして公表した。
例えば、リンゴの落下を見て万有引力の理論をつくりあげたニュートン、乳しぼりの牛痘にかかった人は天然痘に罹らないことを知って種痘を開発したジェンナー、蛍光スクリーンが光るのを見てX線を発見したレントゲン・・・・・・
これら歴史的な発見は《あてにしていないものを偶然にうまく発見する能力》が閃いた成果である。
マートンの論文は話題を呼び、議論を巻き起こした。
ただし、「セレンディピティ」は、マートンの造語ではない。
この言葉と出合ったのは《いわばブラブラ歩きをするように、何気なく『オックスフォード英語辞典(OED)』を拾い読みしていた時だった》と自著のなかで書いている。
【参考図書②】
「小さなことばたちの辞書」ウィリアムズ,ピップ(著)最所篤子(訳)

この言葉の誕生は18世紀まで遡る。
ホレース・ウォルポールという英国人文筆家が、知人あての手紙のなかで初めて使ったことが知られている。
その経緯は、次のようなものだ。
ある王妃の肖像画が彼のもとに届き、その額に家紋を入れることになった。
しかし、王妃の一族の家紋が定かでない。
調べようとしていると、名家の家紋を記した古書が偶然見つかり、無事に額を仕上げることができた。
彼には、似たような体験が何度もあったらしく、それを《「セレンディピティ」と私が名づけた不思議な力によると考えています》と手紙に書き、言葉の由来についても次のように記している。
《以前読んだ寓話「セレンディップの3人の王子」では、旅に出た王子が次々と起こる偶然のできごとに対し、それぞれの場に応じた察知力を発揮して思いがけぬ発見をしていきます。
これらの発見は本来探していたものとは違うのですが、とても大切な発見なのです。》
「セレンディップ」とは、現在のスリランカ共和国のことで、同国の3人の王子の冒険物語はペルシャからアラビアを経てヴェネツィアに伝えられ、1557年に『遍歴セレンディップの3人の王子』として出版されている。
ちなみに、さきの手紙は1754年に書かれており、寓話の出版からちょうど2世紀後に「セレンディピティ」という言葉が生まれたことになる。
さらに、それからまた2世紀後の20世紀半ばにマートンによって、その言葉が再発見された。
2世紀ごとの周期も単なる偶然だろうが、「セレンディピティ」の由来にふさわしい、意味ありげな歴史ではある。
ところで、マートンの再発見以後は、未来の2世紀後を待つことなく、「セレンディピティ」をめぐる話題はじわじわと広がっていた。
1964年にはこの寓話の児童向けの本が米国で出版され、最近では1998年に記号論の大家、ウンベルト・エーコの「セレンディピティ」という本が出版され、原典のイタリア版寓話も2000年に復刻された。
「セレンディピティー―言語と愚行」エコ,ウンベルト(著)谷口伊兵衛(訳)

日本でも着実に関心が高まっていた様だ。
とりわけ1985年に米国の化学者が専門誌に書いた「セレンディピティ的発見のための教育」という論文の影響が大きかったという。
同論文では、「科学者が研究するとき、発見と創造のすべての場面で活用できるセレンディピティを認識し、研究生に教育することが重要である」と強調され、それ以後、日本の科学界、教育界ではすでに専門用語として定着した感がある。
そのおもしろさを紹介したいのは、この本であり、日本で初めて書かれたセレンディピティの解説書である。
「偶然からモノを見つけだす能力―「セレンディピティ」の活かし方」(角川oneテーマ21)沢泉重一(著)

では、この能力を体得するにはどうしたらいいか?
澤泉重一さんの同書には、技法がいくつか紹介されているが、なかでもカギとなる技法は澤泉さんのこんな体験から説き起こされている。
かつて米国の国内便の機内で、豊富な海外経験をもつ商社マンと隣り合わせたときのことである。
機内サービスで客室乗務員から「Coffee or tea?」と聞かれて、商社マンは「コーヒー」と返事をしたのだが、乗務員は何度も頭をひねってばかり。
結局、大声で5回も6回も返事を繰り返した挙げ句にやっとコーヒーがつがれたが、乗務員は納得した表情ではなく、商社マンも憮然としていた。
ここで、「発音が悪かったんだな」と了解してしまえば、それで終わりである。
しかし、海外経験豊富な商社マンの発音が通じなかったのか?・・・・・・と隣席の著者は、目的地に着くまであれこれ原因を考えた。
しばらくして閃いたのは、こんな仮説だった。
「コーヒー」と「ティー」だから、「コー」と言っただけで伝わるはずなのに、なぜ伝わらなかったのか?
それは、「コー」のあとに続く「ヒー」で乗務員が混乱してしまったからではないか?
「f」は下唇をかんで発音する。
ところが、商社マンは下唇をかまなかったから、「ヒー」と「ティー」がごっちゃになってしまった。
そう確信して著者は、遠くにいる乗務員にカップをかざして見せ、下唇をかむ口まねだけをしてみた。
すると見事にコーヒーが運ばれてきた。
おもしろくなって、それ以後もカフェに行くといつも同じ実験を繰り返し、ひとり悦に入っていたそうな。
きっかけは「アレッ?」と感じた、ささやかな偶然である。
その驚きや実感を多くの場合は、「こんなこともあるんだな」程度に考えて、すぐに忘れて去ってしまう。
しかし、そこで「ちょっと待てよ」と踏みとどまってみることが肝要だ。
そのとき、驚きや実感の不思議さを、自分なりに納得させる仮説を立てることがポイントである。
仮説を立てるためには、偶然のできごとをじっくりと考え直すほかない。
そして、仮説を立て、それを検証するなかで偶然のなかに「原因ー結果」の道筋が見えてくる。
つまり、「偶然」に潜む「必然」がにわかに姿をあらわすのである。
これで、澤泉重一さんの積年のテーマである「偶然の秘密」が解明されたとは言えないが、たしかに、この技法には、偶然から幸運をつかむ能力、つまり、セレンディピティを身につける秘訣がありそうだ。
順序立てて表現すると、次のようになろうか。
(1)偶然その現象に出くわす。
(2)常識からはずれた現象に興味をしめす。
(3)常識を疑い、そこに新たな仮説を立てる。
(4)その現象を徹底的に分析し、仮説を裏づける。
これが本当に「幸運を呼ぶ黄金律」かどうかは、お試しあれ!、というほかない。
ただし、この技法が単なるマニュアルに終わらないために、澤泉重一さんがとりわけ強調していることがある。
それが「当事者意識をもつ」ということである。
例えば「会社は誰が動かしていると思いますか?」との質問に対して「社長です」「実質的には部長です」などと答えが返ってきそうが、「いや、会社を動かしているのは君自身。君がそう意識しなければ、会社はうまく動かないよ」。
「当事者意識」とはこれである。
当事者意識を心がけていれば、自分の行動に責任を持つようになる。
そうなると、小さなことにも心配りをするようになり、単なる偶然も大切なチャンスに見えてくる。
こうなれば、もうセレンディピティを体得したようなものなのかもしれない。
「当事者意識」をもって「偶然」にこだわる。
この心がけこそが幸運を運んでくるのだ、というのがセレンディピティの“肝”ということになろうか。
[ 教訓 ]
【セレンディピティは思わぬ発見をする特異な才能】
Gooの英和辞書で検索してみると、「Serendipity:思わぬ発見をする特異な才能.」という説明がでてきた。
れっきとした英単語として存在するセレンディピティ。
流行語のイメージがあるが、語源は古く18世紀に遡る言葉で、スリランカの寓話「セレンディップと3人の王子」に由来するとのこと。
ニュートン、アルキメデス、メンデル、ジュール、アインシュタイン.......。
歴史上の発見が偶然の産物だったという逸話はよく聞くし、近年では、ノーベル賞受賞の報がある度に受賞者や評論家がセレンディピティを口にする。
少し驚いたのだが、セレンディピティは、能力であると定義されている。
能力であるならば意図的に磨くことができるとすれば、その能力を育てるアイデアを学んでおけば良いと考える。
一読して思ったのは、世の中には本物と偽者のセレンディピティが存在し、厳密に切り出して考えるには、ふたつを区別しておく必要があるのではないかということ。
大きな成功を収めた場合に、特に、日本社会は、偶然や他者との出会いに起因することにして、その成功を説明した方が、社会的に受容されやすい。
話題としても物語性があるので、メディアが取り上げ、話が伝播しやすい。
つまり、意図的にせよ、無意識にせよ、成功を物語化するプロセスで、セレンディピティを発見、作成、拡大してしまっている可能性を感じる。
これもセレンディピティに含めても広義では問題はないが、育てる能力として見るならば、偽者として排除しておくべき例だと考える。
本物のセレンディピティは、私は次のようなものではないかと考えている。
・性格や行動特性、ツキとアウェアネス情報によるセレンディピティ。
偶然の発見が高確率で発生するには、ふたつの条件が必要なのではないかと思う。
ひとつは「経験の豊富さ」であり、もうひとつは、「経験から意味を見出す能力」である。
この2要素の積を、常時、高い値に保つ能力がセレンディピティなのではないか?
以前、ツキを科学する経営本が最近売れていた時期が有った。
これらの本もセレンディピティの能力を高めることと同義のような気がしている。
ポジティブシンキングというのは、状況を肯定し気分による機会損失を最小にすることにあるのだとしたら経験の豊富さの技術である。
社会関係の技術としては、アウェアネス情報による機会拡大が有効なのではないか?
自分の関心や行動を他者の目に触れるようにしておくことで、予期せぬ展開の確立が高まる。
強い関心を持ち続けることで、状況から意味を見出すことが多くなるということも重要な要素だと思う。
脳は無意識のうちに情報処理を行っている。
脳は、雑踏の中で呼ばれた自分の名前を認識するカクテルパーティ効果のように、関心のあるテーマには認知レベルで敏感に反応することができる。
”Japanity”とは、セレンディピティの反対語。
「誰もがやっていることを追いかけて、必然のところで発見する能力」。
海外の学者が日本人研究者を揶揄した言葉らしいが、「パラダイム」を発明したトーマスクーンの科学論でいうなら、”Japanity”は「通常科学」の技術である。
これはこれで重要で、パラダイムシフトを起こすような「イノベーション」ばかりでは科学もビジネスも動かないと考えられる。
むしろ、セレンディピティで語られるような成功の土台は、”Japanity”によって築かれているようにも感じる。
人間の機会の増大や人脈拡大に役立つインターネットは、セレンディピティ技術だと言えると思う。
以前話題のOrkut(オーカットまたはオルカット)などのソーシャルネットワーキングは、まさにその先端なのではなかっただろうか?
だから、セレンディピティって言葉が注目されていたのだろう。
この言葉の意味は「偶然からモノを見つけだす能力」。
例えば、雑誌を買いに本屋に行き、うろうろ廻っているうちに、昔の友人に偶然会い、大きなビジネスの話に発展した・・・・・・とか。
ノーベル賞とかの大発見は、このセレンディピティが多く現れるようだ。
田中耕一さんも、失敗から大きな発見していた。
そんな大それた事じゃなくても、日常の生活の中でもそんな偶然ってありる。
それを偶然と考えないで、なにか楽しいことの「お告げ」と考えたら楽しいと思う。
これからも「偶然」を楽しみにしていきたいと思う。
[ 一言 ]
たまには神様を驚かせてみるのも、新しい発想を得るにはいい方法(@@)
私はザ・ドリフターズの「もしもこんな○○がいたら」というコントが好きでした。
例えば、ウルトラマンの正義は、観る者が共感しうる義理人情が原点だけど、もしも、義理人情に厚過ぎる宇宙人だったら?
みたいなことを想像するのって楽しいですよ♪
でも、地球は、えらいこっちゃな!(爆)
↓以下、おまけ付き。
ドリフ大爆笑/もしも、こんなタクシードライバーがいたら(志村けん編)
https://www.youtube.com/watch?v=J4eW2isc24w
[ メモ帳 ]
答えのない時代に、メモが最強の武器のひとつになると考えています。
そんな考えを持っているので、多くの機能をそなえたワープロソフトは非常に強力だけど、その反面、起動に時間がかかったり、全体的に動作が遅かったりするよね。
昨日も、ワードの使い辛さにイラッとしたし(--)
文章を書こうと思ってから、また、メモを取ろうと、ワープロソフトを立ち上げるまでの間に、「あれ・・・・・・。何を書こうとしたんだっけ?」と創作意欲を失くしてしまったことありませんか?
だから、手書きのノートも必須なんだけど、如何せん、字が汚いから、後で読もうとしても読めない(爆)
そんな自分の業を補うため、高速に起動して軽快に動作するテキストエディタを使えばすぐに作業を始めらるよね。
思いついたアイデアを書き留めるメモとして。
プログラマーさんは統合開発環境の代わりにソースコードの記述に、物書きさんはワープロソフトの代わりにコラム・エッセイー・小説の下書きに。
いろいろな用途で気軽に素早く使えるテキストエディタ「Mery」を使用しています。
行番号表示やルーラー表示、正規表現検索といった標準的な機能を複雑な設定無しに利用できるテキストエディターです。
多くのプラグラム言語・スクリプト言語(Java、JavaScript、C++、C#、HTML、XML 等)に対応しており、予約語の強調表示や入力補完機能も搭載されているため、プログラミングにも適しています。
また、プラグイン機能やマクロ機能によって、機能を自由に拡張することができます。
テキストエディタは、「メモ帳(Notepad)」で満足されている方もいると思いますが、Meryを使えば、Notepadには戻れなくなると思いますよ(^^)
さてと、偶然に関する「本の内容」や「参考になる出来事や記事」などの情報を、自分の知見にするためのインプットとしてメモした内容を公開しておきますね。
以下の様なメモ帳の使い方のポイントやコツを無視していますので、ご容赦ください^^;
①5W1Hを意識して記載する
②日付と場所を記載する
③要点とキーワードのみを記載する
④色ペンを使用して重要度を視覚的に示す
⑤事実と所感を整理する
⑥インプットとアウトプットを区別する
【果報は寝て待てを教訓にしたセレンディピティのススメ】
果報は寝て待てを教訓にして、セレンディピティのススメについてまとめておく。
1.セレンディピティとは
Litterarum radices amarae sunt, fructus jucundiores.(学問の根は苦いが、果実はそれだけうまい)
才能とは持続する情熱である。(モーパッサン)
哲学の病の主たる原因⇒偏食。
人は自分の思考をたった一種類の実例で養っている。(ウィトゲンシュタイン)
少数派は時々正しい。多数派はいつも間違っている。(ジョージ・バーナード・ショー)
「万人にとっての真理」という一見中立的で普遍的な知は誰のための、何のための知であったか?
その「真理」の名において、誰が排除され何が抑圧されたか?(上野千鶴子「<わたし>のメタ社会学」)
運命というのは努力した人に偶然という橋をかけてくれる。
インドの突端に「インド洋の真珠」と呼ばれるセイロン島がある。
1972年に完全独立を達成してスリランカと改称するまでは、長らくセイロンと呼ばれていた島国である。
ペルシャ時代にはこの島をセレンディップと呼んでいたという。
ペルシャが世界に権勢をはっていたころ、ペルシャ人にとってセレンディップはロマンの島であったらしい。
SF作家アーサー・C・クラークはスリランカに住んでいるが「セイロン島は、ひとつの小宇宙だ」といい、「セレンディピティ」の島だという(『スリランカから世界を眺めて』The View of Serendipハヤカワ文庫)。
「スリランカから世界を眺めて」(ハヤカワ文庫)クラーク,アーサー・C.(著)小隅黎(訳)

「セレンディピティ」というのはイギリスの首相ロバート・ウォルポールの一番下の息子で「オトラント城奇譚」(1765年)などを書いたゴシック小説の大家ホレス・ウォルポール(Horace Walpole)が童話「セレンディップの三王子」(Three Princes of Serendip)について書いた言葉に由来する。
「オトラント城奇譚」(講談社文庫)ウォルポール(著)井口濃(訳)
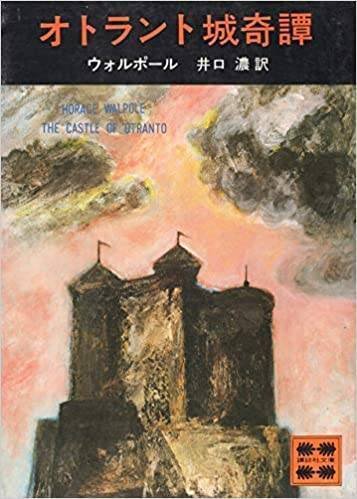
彼の1754年1月28日付けのホラス・マン(Horace Mann)宛の書簡に“this discovery, indeed, is almost of that kind which I call Serendipity, a very expressive word.”と書いてあったのだ。
もとは、ペルシャの説話でヨーロッパに初めて紹介したのは、Christoforo Armeno(クリストフォロ・アルメノ“Cristoforo”とも表記)著のPeregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippoという書名のイタリア語の16世紀の本だという。
これを翻訳で読んだウォルポールが新語を造ったのだ。
次のような話である(英語訳は原作に忠実ではないようだ)。
その昔、セレンディップの王国時代に3人の聡明な王子がいた。
王子たちにはそれぞれ賢い家庭教師がついていた。
家庭教師たちは教育の仕上げに、旅でいろいろ経験させたいと進言し、王子たちは王である父に、見聞を広めるために航海に出たいと申し出た。
そこで王は国を悩ませていた龍を退治する方法を探すように命じる。
父と相談しながら構想を練り、計画をたて準備万端ととのえた王子たちは意気揚々と船出するが、緻密な計画はすぐに頓挫する。
周辺国を踏破し、非常に発見が困難とされる龍の珠などの宝物を持ち帰るように命じられているのだが、暴風雨に見舞われ、海賊に遭遇し、次々に思いがけないできごとが起こって、思いがけない冒険を強いられる。
王子たちは果敢に立ち向かい、そのたびごとに成長していく。
船出する前には予想もしていなかった体験を積んで、さまざまな貴重な収穫を得たのであった。
王から頼まれた探し物は得られなかったが、立派に成長したことが何よりの宝物だと王は迎える。
求めていたもの以外のものを手に入れることができたのである。
めでたし、めでたし・・・・・・
「正論」に囚われなかったのがよかったのだ。
【狙ったものよりもその横にもっと面白い発見がある】
Oxford English Dictionaryには“serendipity”は次のようである。
[f. Serendip, a former name for Ceylon]
A word coined by Horace Walpole, who says (Let. to Mann, of Jan 1754) that he had formed it upon the title of the fairy-tale 'The Three Princes of Serendip', the heroes of which 'were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things they were not in quest of'.]
The faculty of making happy and unexpected discoveries by accident
...1880 E. SOLLY Index Titles of Honour Pref. 5 The inquirer was at fault and it was not until some weeks later, when by the aid of Serendipity, as Horace Walpole called it --that is, by looking for one thing and finding another-- that the explanation was accidentally found.
「予期せぬ掘り出し物」「掘り出し物上手」「偶然の発見・・・・・・」というような意味である。
「狙ったものよりも、その横にもっと面白い発見がある」と考えるといい。
松本清張は『黒い手帖』の中でデビュー作の「西郷札」を書いたのは「百科事典を偶然に開いたとき、同名の項目が目に触れたからである。
「黒い手帖 (改版)」(中公文庫)松本清張(著)

自分の読みたい個所の対ページに「さいごうさつ」というのが見えたので、何気なく読むと・・・・・・」と書いている。
「発見」という言葉をいきなり宇宙のどこかに恒星を発見するようなものだと考えてはいけない。
今まで「分かっていたのに気がつかないことが明示化されること」であり、「これまでの結びつきではない、別の結びつきを見つけること」である。
セレンディピティというものが成立するのは、何かを求めている人がある事柄をずっと探しているからで、元々はそこにあったかもしれないものなのだが、意識することによって「前景化」(foregrounding)して見えてくる、ということなのだ。
何かを意識して散歩すれば、町の様子が違って見えるようなものである。
高橋英夫の「今日も、本さがし」(新潮社)にはドイツの文芸学者クルティウスの話が紹介されている。
「今日も、本さがし」高橋英夫(著)

クルティウスは当時、入手困難とされたワイマール版のゲーテ日記を探していたという。
ある日、ソーセージを買って、包み紙を見ると、それが何と探し続けていたゲーテ日記の一枚であったばかりか、求めていたまさにその部分だったという。
この経験からクルティウスは「精神がひじょうに緊張しているときには、そのための努力をしなくても、求めるものが与えられる」と書いているという。
セレンディピティというのは「偶然」を「必然」に変える能力である。
セレンディピティが起こる原因は明らかで、同じ記号でも意味を感じなかったのに意識のアンテナを張ったことで、意味を持ち始めるということである。
クルマに全く興味がなかった人が購入することになって、クルマ全体に興味が拡がり、買ってみると同じ車種があちこちにあることが分かる、なんてことがある。
こんなに売れているのか!なんてことが買って初めて分かるのだ。
神秘的な説明をすればユングのシンクロニシティ(同時性=偶然の一致)というものがある。
最も有名な話は、女性の患者が夢で黄金のスカラベ(コガネムシ)をもらったと告白した途端、カウンセリングしていた部屋にまさしくコガネムシが飛来して窓にぶつかったというものだ。
夢と部屋とは、何らの関係を持っていない。
しかし、患者がユングに懸命に語ろうとしたこと、ユングが患者を熱意をもって理解しようとしたこととが共鳴しあい、偶然の一致を生んだと考えられる。
この原因をユングは、人間の意識の“元型”に求めた。
ローマ帝国時代に、時を隔ててよく似たルチウスという皇帝(スラとアウレリアヌスという名前)がいた。
ともに5年間の在位、片や「人々の復興者」いま一方は「世界の復興者」と共に崇められ、内戦の後の即位、さらに彼らの後3人目の皇帝の始末もそっくりで、約350年を隔ててローマ復興を成し遂げた。
歴史の繰り返しは小説の間でもみられる。
タイタニックの悲劇を小説で先に書いていた作家がいたし、ヒトラーが魅せられていたワグナーのオペラ『リエンツィ』のストーリーは後のヒトラーの終生をなぞったものだった。

南方熊楠は「やりあて」という言葉を使った。
これは「意図通り」に偶然が重なって物事が上手く展開して行くということで、セレンディピティの対語にあたる。
熊楠は、地球の西半球と東半球のそれぞれの特徴的な二種の粘菌を同時に近い場所で発見した時に使った。
明治三十六年七月十八日、土宜法竜(子分 法竜米虫殿)宛書簡から、「南方曼陀羅」に関する部分を抜粋する。
「ここに一言す。
不思議ということあり。
事不思議あり。
物不思議あり。
心不思議あり。
理不思議あり。
大日如来の大不思議あり。
予は、今日の科学は物不思議をばあらかた片づけ、その順序だけざっと立てならべ得たることと思う。
(人は理由とか原理とかいう。
しかし実際は原理にあらず。
不思議を解剖して現象《げんしょう》団とせしまでなり。
このこと、前書にいえり、故に省く。)
心不思議は、心理学というものあれど、これは脳とか諸感覚とかを離れずに研究中ゆえ、物不思議をはなれず。
したがって、心ばかりの不思議の学というもの今はなし、またはいまだなし。
(中略)
現に今の人にもtactというがあり。
何と訳してよいか知れぬが、予は久しく顕微鏡標品を作りおるに、同じ薬品、知れきったものを、一人がいろいろとこまかく斗《はか》りて調合して、よき薬品のみ用うるもたちまち欺れる。
予は乱妨にて大酒などして、むちゃに調合し、その薬品の中に何が入ったか知れず、また垢だらけの手でいろうなど、まるでむちゃなり。
しかれども、久しくやっておるゆえにや、予の作りし標品は敗れず。
この「久しくやっておるゆえ」という語は、まことに無意味の語にて、久しくなにか気をつけて改良に改良を加え、前度は失敗せし廉《かど》を心得おき、用心して避けて後に事業がすすむなら、「久しくやったゆえ」という意はあり。
ここに余のいうは然らず。
何の気もなく、久しくやっておると、むちゃはむちゃながら事がすすむなり。
これすなわち本論の主意なる、宇宙のことは、よき理にさえつかまえ中《あた》れぱ、知らぬながら、うまく行くようになっておるというところなり。
故にこのtact(何と訳してよいか知らず。)。
石きりやが長く仕事するときは、話しながら臼の目を正しく実用あるようにきるごとし。
コンパスで斗り、筋ひいてきったりとて実用に立たぬものできる。
熟練と訳せる人あり。
しかし、それでは多年ついやせし、またはなはだ精力を労せし意に聞こゆ。
実は「やりあて」(やりあてるの名詞とでも言ってよい)ということは、口筆にて伝えようにも、自分もそのことを知らぬゆえ(気がつかぬ)、何とも伝うることならぬなり。
されども、伝うることならぬから、そのことなしとも、そのことの用なしともいいがたし。
現に化学などに、硫黄と錫と合し、窒素と水素と合して、硫黄にも正反し錫にも正しく異なり、また窒素とも水素ともまるで異なる性質のもの出ること多い。窒素は無害なり、炭素は大営養品なり。
しかるに、その化合物たる青素《シアン》は人をころす。
酸素は火を熾《さか》んにし、水素は火にあえぱ強熱を発して燃える。
しかるに、この二者を合してできる水は、火とははなはだ中《なか》悪きごとく、またタピオカという大滋養品は病人にはなはだよきものなるに、これを産出する植物の生《なま》の汁は人を殺す毒あるごとし。
故に一度そのことを発見して後でこそ、数量が役に立つ(実は同じことをくりかえすに、前の試験と少しもたがわぬために)。
が、発見ということは、予期よりもやりあての方が多いなり(やりあて多くを一切概括して運という)。」
ちなみに“serendipity”の反対は“japanity”といわれ、他人のやったことについていくことという意味がある(まだ、辞書に載っていないが・・・・・・)。
『セレンディッポの三人の王子の旅』(ヘンツェのオペラ『鹿の王』は『セレンディップの三王子』を基にしている)
【発想の転換】
「僕らは空の高さを知らないニワトリのような生き物である。」
フレミングは化膿菌の研究をしていて、たまたま混入した空中の青かびのコロニーのは化膿菌が生えなかったことからペニシリンを発見した。
他のノーベル賞の受賞者もセレンディピティによるものが多いが、ノーベル自身がセレンディピティのおかげでお金持ちになった。
ニトログリセリンが発明されていて、爆発力があることは知られていたが、安定した薬品ではなく、とても実用的なものではなかった。
ある日、珪藻土の上にこぼしたところ、安定して使えることが分かった(異論もある)。
古くはアルキメデスの「ユリイカ」があるし、キニーネの発見やニュートンのリンゴ、ジェンナーの種痘、水銀写真、合成ゴム、エックス線、経口避妊薬、サッカリン、そして最近のバイアグラまで科学は発見の歴史である。
特に、ニュートンは、ケンブリッジ大学がペストで閉鎖されたため、リンカーシャー・ウールソープの故郷に帰っていた時に発見したのだった(1678年に最初の神経衰弱の発作に見舞われて自宅に引きこもったとされる)。
失敗は成功の元。
お酒が清酒になるのは慶長時代でそれま濁り酒だった。
慶長5年(1600年)のころ、摂津の鴻池の酒造家、山中勝庵の酒蔵で、ある男が叱られた事に対する鬱憤晴らしで酒の中へ灰をほうり込んだところ、清らかに澄んだ酒となった。
カマドの灰はアルカリ性で、濁りの成分が凝集されて沈殿し、その上澄みが清酒ということらしい。
西鶴の『日本永代蔵』には、「江戸酒つくりはじめて一門さかゆるもあり」とあるが、鴻池は新開発の清酒を江戸に運んで財をなし、すでに元禄には日本一の富商となっていた。
「日本永代蔵 全訳注」(講談社学術文庫)井原西鶴(著)矢野公和/有働裕/染谷智幸(訳注)

大阪の両替商・鴻池の飼い犬のエサは尾頭つきの「鯛の浜焼き」に、ウナギを卵焼きで巻いた「う巻き」という噺が、上方落語の「鴻池の犬」に出てくる。
実際には文人、芸術家らのパトロンとなり、元禄文化が花開いたと言われ、俳諧集「西鶴五百韻」は西鶴が伊丹の鴻池本家で創作した成果の一つだった。
2000年に受賞した白川英樹は東京工業大の助手時代、学生が行ったポリアセチレンと呼ばれる有機高分子の合成を体験するという単純な実験が失敗。
大学院生が触媒の濃度を1000倍間違えたためできた“失敗作”の薄膜が、最終的な大発見へと白川を導いた。
有機高分子に導電性を持たせることができるかどうかという研究にも取り組んでいた白川は、偶然できた薄膜の性質を探る研究に乗り出した。
銀色の薄膜もできたが、それをどう生かすか。
それを大きく飛躍させたのが、同時受賞したアラン・ヒーガーとアラン・マクダイアミッドの両博士との出会いだったという。
2001年に受賞した野依良治の不斉合成も、別の実験をしていて、偶然発見に至ったらしい。
「寝耳に水」の受賞だった田中耕一の「レーザー脱離イオン化法」も「タンパク質分子の質量を測るため、レーザーを当ててイオン化する手法を考えたが、専門家から非常識と言われた。
「私は専門家ではない。
常識にがんじがらめになっていたら、今の研究成果はなかった」と述べた。
さらに「溶媒にグリセリンを混ぜて一回失敗、それを「もったいないからと使って2回目の失敗。
結果を早く見たいと思い、乾く前にレーザーを当てて、実は3回も失敗した。
「そのおかげでとんでもない大発見をした」という。
ただし、これらの「偶然」は少々くせものである。
偶然を招き寄せる力があったからだ。
ここから、田中耕一の最初の自伝は『生涯最高の失敗』(朝日新聞社)という名前になった。
「生涯最高の失敗」(朝日選書)田中耕一(著)

「機会は備えある人だけに恵む」(パスツール)
このような例は枚挙にいとまがない。
古来、科学における歴史的な大発見や独創的な論理的展開は、セレンディピティに負うところが多い。
セレンディピティを収穫するセンス。
天才的ひらめきは確かに革新をもたらす。
科学の発見などについては、例えば、次のような本を紹介しておく。
「セレンディピティ―思いがけない発見・発明のドラマ」(DOJIN文庫)ロバーツ,ロイストン・M.(著)安藤喬志(訳)

「創造的発見と偶然―科学におけるセレンディピティー」(科学のとびら)G. シャピロ(著)新関暢一(訳)」

「「ふと…(セレンディピティ)」の芸術工学」(神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ)赤瀬川原平/佐々木正人/宮本隆司/柳田理科雄/カスパー シュワーベ/夏目房之介/藤田紘一郎/森政弘/鈴木成文(監修)杉浦康平(編)

セレンディピティそのもののメカニズムは未だはっきりとは解明されていないが、大発見が起こるときの状況を定性的に整理し、概ね次のような段階が必要であるといわれている。
偶然その現象に出くわす。
常識からはずれたその兆候に興味を示す。
常識を疑い、そこに新たな仮説を立てる。
その兆候を徹底的に分析し、新たな仮説を裏付ける。
ある現象が起こらないことには、発見のしようがないので「偶然」の出来事は必要条件の一つである。
しかし、起こった出来事に気づかなかったり、常識の枠にとらわれてしまって実験ミスとして片付けてしまっては、発見にはつながらない。
また、ここまで至ったとしても、新たな仮説を裏付けるに至らなければ、これもまた発見にはつながらない。
すなわち、「出会い」と「実践する行動力」が必要だと言われている。
失敗を怖がっていたら何もできないし、失敗しないことに固執する人間は失敗を認めない人間になってしまう。
大切なのは失敗しないことではなく、失敗からどれだけ学ぶか、ということである。
ちなみに「パウリ効果」というものがある。
物理学者ヴォルフガンク・パウリが実験が不得手でよく機材を壊したことから生まれた言葉で、機械装置・電子装置を問わず、ある人物がその装置に触れただけで、あるいは近くに寄っただけで不可解な壊れ方をした場合、その人物が装置にパウリ効果を及ぼしたと言う。
最もすごいのは、ゲッチンゲン大学の研究室での真空装置の爆発事故があった時だ。
爆発事故の現場近くにパウリはいなくて、パウリのせいにはできないはずなのに、後で調べると、事故のあった時、ゲッチンゲン駅に停車した電車の中にパウリがいたことが判明した!?
J・C・カリエールとG・ベシュテルが編集をした『珍説愚説辞典』(国書刊行会)というのがある。
「珍説愚説辞典」J.C.カリエール/G.ベシュテル(著)高遠弘美(訳)

奇書『万国奇人博覧館』(筑摩書房)がパワーアップされた本である。
「万国奇人博覧館」カリエール,J.‐C./ベシュテル,G.(著)守能信次(訳)
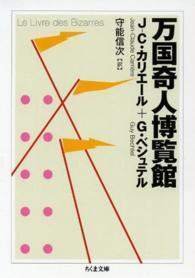
長くて的を得た副題は「世界史や個人の伝記にまつわる、わけのわからない言葉、間違い、誤綴、莫迦げた考え、大胆すぎる仮説を含む。それに加えてかなりの数の愚かしい言葉、ありとあらゆる種類の狂気や空想、空疎な駄弁もあり」になっている。
ジャン・クロード・カリエールは『小間使いの日記』『昼顔』『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』『欲望のあいまいな対象』など、ルイス・ブニュエル監督作品や『ブリキの太鼓』『スワンの恋』などシュレンドルフ監督作品の脚本家としても知られる人である。
ベシュテルは堅実な歴史学者で『万国奇人博覧館』ではブクテルと表記されていた。
彼らが14年の歳月をかけて古今の言説を集めた。
ところが、序文にあるように、「珍説」「愚説」とは何かという定義が難しい。
ガリレオの地動説は発表当時、珍説愚説どころか邪説だったが、今では天動説の方が珍説になっている。
時間とともに珍説が正説に、正説は愚説にひっくり返る。
中には珍説愚説でありながら、正論ということもある(だからセレンディピティはセイロン生まれなのだ)。
この本(「偶然からモノを見つけだす能力―「セレンディピティ」の活かし方」)から、例えば「日本人」に対してのフランスの立派な学識者たちによるこっぴどい差別発言が読める。
百年ちょっと前まで、日本人は単なる「好色な野性猿」に過ぎないし、野蛮で醜い獣の状態から進化することなどありえないと断言されていた。
H・G・ウェルズだって1902年に書いた「空想」の中で「航空機がいつか、大量輸送手段として使われるようになることに、私は懐疑的である」と書いている。
未だに、イギリスでは地球が平たいことを信じている学会があるというが、こうした説がいつか正説になることがあるかもしれない(←ある訳ないが・・・・・・)。
編者はフランスの小学校で珍説愚説の授業を義務づけるように提案しているが、確かに失敗から学ぶことも多いのである。
編者は「流派を超えて、もう一度人間を考え直」そう、「精妙な部分だけでなく、頑迷な頭や古い部分もふくめた、全体としての人間を」という。
そしていう。
「『愚かしさ』はある種の希望であり、果物の種のように人間の中心に存在する」。
とはいえ、愚説は愚説かもしれない。
1980年に無謀な人体実験まがいの遺伝子治療を手がけ、批判を浴びた米国のマーチン・クライン博士は「科学研究は多数決により進歩したためしはない」と言い放った。
生命倫理をめぐり開かれた米議会の小委員会だった。
この発言の現場にいた生命倫理学者の木村利人は、会場が緊張とどよめきにつつまれ、民主党のゴア委員長は博士の人権意識を鋭く批判したと伝えている。
「どちらが正しいのか、歴史の審判を待ちたい、といいたいところだが、現代科学は一旦間違えれば絶望を招く淵を歩いている。
ベストセラーになったM・S・ペックの「平気でうそをつく人たち」(草思社“People of the Lie”)は、次のように書いている。
「平気でうそをつく人たち―虚偽と邪悪の心理学」(草思社文庫)ペック,M.スコッ(著)森英明(訳)

実際には、科学者もまたわれわれ一般の人間と同様に道に迷うことが多い。
ところがわれわれには、科学者を、知的迷路のなかを導いてくれる「哲人王」として祭りあげるという強い性行がある。
われわれは、知的怠惰から、科学的思考というものが趣味や好みと同様にそときの流行に左右されるものだ、ということを忘れ去っている。
科学の権威筋が現在口にしている意見は、最新のものというだけであって、けっして最終的、決定的なものではない。
養老孟司が「まともな人」(中公新書)でオリジナリティについて書いている。
「まともな人」(中公新書)養老孟司(著)

「自慢ではないが、私にオリジナリティーはない。
そんなものがあったら原稿は売れない。
あまりにもオリジナルなものは、誰も理解しない可能性があるからである。
誰かが理解するようなもの、そんなものはオリジナリティーではないではないか。
(中略)
じつは、私はきわめてオリジナルな人たちを知っている。
そのほとんどは自分自身の理屈で、自分独自の感情に従い、個性的に行動した人たちである。
そういう人たちはたいてい精神科の病院で治療を受けている。
忘れてはいけないことは自説を信じ続けることである。
どんなに正しい学説であっても最初から受け入れられるとは限らないからである。
そして・・・・・・
セレンディピティは発想の転換である。
とはいっても、みんながみんなノーベル賞を取れる訳ではない。
A・H・マズローは特別な才能を持った人が発揮する創造性と、普通の人が日常生活の中で発揮する「自己実現としての創造性」を区別しながら、両者の間にある共通性や関連にも言及している。
つまり、大切なことは創造性をノーベル賞クラスのものとばかり考えないで、ふだんの生活から生まれるものだと思うことだ。
ノーベル賞の江崎玲於奈はトランジスターの研究でみんな不純物を取るのに一生懸命で、これが至難の業だったので、逆に不純物を入れて研究した。
その結果、「エザキ・ダイオード」というものが生まれたのである。」
因みに、江崎玲於奈は、「創造性が肝要といっても、・・・・・・安直な教育ガイドがあるわけではない」と前置きして、しかし「ノーベル賞を取るために、してはいけない五つのこと」を挙げている(「個人人間の時代」読売新聞社)。
「個人人間の時代―ニューヨークから」江崎玲於奈(著)

〈1〉従来の行きがかりにとらわれ過ぎてはいけない。
さもなければ飛躍の機会を見失う。
〈2〉他人の影響を受け過ぎてはいけない。
〈3〉無用なものはすべて捨てなければならない。
〈4〉闘うことを避けてはいけない。そのためには独立精神が必要である。
〈5〉安心感、満足感に浸ってはいけない(何か絶対なものを信じなければいけない)。
穐山真澄ほか「創造性研究ハンドブック」(誠信書房)は次のような生活態度・特性がある人が創造的な人だという。
「創造性研究ハンドブック」穐山貞登/堀洋道/古賀俊恵(著)

関心の広さ
好奇心の強さ
好みの複雑さ
あいまいさに対する寛容さ興奮しやすさ
熱中しやすさ
忍耐強さ
強情さ
勤勉さ
機敏さ
野口悠紀雄は「「超」発想法」(講談社)の「発想はどのように行われるか」というまとめで次のように書いている。
「「超」発想法」野口悠紀雄(著)

〈1〉創造的な活動においては、あらゆる可能な組み合わせをいちいち比較考慮するのではなく、直感的な判断によって無視皆組み合わせを最初から排除している。
この直感的判断を支配しているのは、「審美的感情」である。
〈2〉重要な科学的発見の多くは、偶然のきっかけで得られたように見える。
しかし、重要なのは、それに先だって、発見者が「考え続けていた」ことだ。
これが潜在的な意識の活動を始動し、そこで発想が行われていたと考えられる。
したがって、発見のプロセスを、没頭期、潜伏期、啓示期に分けてとらえることができる。
科学にブレークスルーをもたらすときは、どこかにセレンディピティがあるように思う。
謙虚に自然界に教えを請う、自然現象や生物現象を丹念に観察する姿勢がセレンディピティを収得するセンスにつながるように思える。
既成概念の強い秀才は謙虚さに欠けて、セレンディピティを見逃す可能性がある。
自分の仮説にしがみつくあまり「あ、これは失敗した・・・・・・」と容易に方向を変えてしまって、宝物のような現象を見過ごしてしまうかもしれない。
不思議な現象の再現性を追求するしつこさがもうひとつのセンスであろう。
昔話に「ぼっこ食い娘」というのがある。
長者の娘に求婚しに行った男たちがみんな逃げ帰ってくる。
娘が棺桶から死体を取り出して食べているというのだ。
ところが、ある男がよく観察してみると鬼のお面をかぶった娘がお餅で作った人形を食べていることが分かった。
見破られた娘は、「この人こそ夫にふさわしい」といって、めでたく結婚する。
これは山姥だと思い込んだ男たちへの教訓なのである。
アンリ・ポアンカレも関数論の発見が他のことをしていた時、道路を渡ろうとしていたとか、馬車に乗ろうとしていた時にインスピレーションが生まれたという。
モーツァルトはビリヤードをしている時に『魔笛』のメロディが生まれたというし、ハイドンは仕事に詰まるとチャペルに行ってアベマリアの祈りを捧げた時に構想が浮かんだという。
ノーベル賞の湯川秀樹は漢文学者の家庭に生まれ、兄弟とも文科系である。
尾崎紅葉も夏目漱石も、日本の古典や外国の小説も読んだ。
旧制中学時代には、文学サークルに所属し、同人誌に童話を書いたこともある。
「文学的な「美」も理論物理学が私たちに見せてくれる「美」も、そんなに遠いものではないと、今でも思っている。
それどころか、暇ができたら、童話でも作りたいという気持ちは、今でも私の心の底に残っている。」(湯川秀樹『旅人』から引用)
「旅人―ある物理学者の回想 (改版)」(角川ソフィア文庫)湯川秀樹(著)

湯川の話に老子や荘子などの中国の古典がよく出てくるが、それは物理学の思考を邪魔するのではなく、助けとなっていたのである。
漢学の家の湯川を物理学へ導いたのは長岡半太郎との出会いだった。
「一流の科学者になりたかったら小説をたくさんお読みなさい」と諭されたのだった。
ノーベル化学賞を受賞した福井謙一は小学生のころ、絵描きになりたいと思った時期があった。
旧制中学時代には文学博士を夢見ていた。
旧制高校時代は理系の学生だったのに、もっぱら勉強したのは文系の学問だったという。
「創造をめざすには、せまい勉強はためにならない、努めて広く学ぶことが大切」と福井は書いている。
空想力、想像力は、創造力とは無縁ではない。
入沢康夫に「未確認飛行物体」という詩があり、「薬缶だって、/空を飛ばないとはかぎらない。」と歌っている。
ヤカンだって空を飛んで砂漠の花に水をやって戻ってくるかもしれないのだ。
日本のセレンディピティの同義語に「棚からぼた餅」があるが、似て非なるものである。
なにもしないで実りは得られない。
宝くじが当たったり、1億円を拾ったりするのとは違うのである。
オリジナリティなんてものも降って涌いてくるものではない。
天地開闢の時に全て出尽くしたと考えれば楽だ。
我々が書いている言葉なんて、全部載っている本がある。
辞書という本だが、そんな風に諦めたところから始めて、小さな工夫を積み重ねて行こう。
ものの見方を変えていこう。
科学の発見だけでなく、凡人の僕らにもセレンディピティはある。
教師の話で説明は忘れたが・・・・・・
・脱線の方をしっかりと覚えていたり、宴会よりも二次会の方がおかしかったり。
・間違って借りてしまった本が面白かったり。
・映画館の二本立て(古い!)で目当ての映画よりもB級映画の方が感動したり。
・レコード(古い!)を買ってB面(古い!)の方がよかったり。
・ミスタードーナッツへ行っておまけの方がよかったり。
・姉とつき合っていて妹の方と結婚してしまったり。
・落語の「猫の皿」のように猫よりも餌を食べている皿の方が高かったり。
もっとも「猫の皿」は行商人がたまたま入った茶店の猫をふと見ると、その価値三百両という「高麗の梅鉢」で餌を食っていてなんとか手に入れようとするお話なのだが、亭主を騙して猫と一緒に皿を買おうとすると、亭主は「皿はダメです。その皿があるとなぜか猫がよく売れるんです」。
つまり確信犯だったというオチ。
原話は江戸時代の戯作「大山道中膝栗毛」である。
【視点を変える】
セレンディピティとは、逆に、水を飲もうとしてコップばかりを探していて、目の前の水道から飲まないことがある。
ワープロがないから文章が書けないとか、電卓がないから計算ができないと思ったことはないだろうか?
ちょっと発想や視点を変えれば、いくらでも代わりを見つけることができる。
発見ができない理由の一つに人間は記号に振り回されるということがある。
これをハイデッガーは「“として”構造(Als-struktur)」と呼んでいる。
文学碑周りをしていた時にクルマが燃えて、僕は水を探したのだが、賢いおばさんは番茶の入った水筒を出してくれた。
僕は水筒「として」しか考えていなかった訳だし、消化するものを欲しいのに水「として」あるものを求めていたのである。
人は既に意味づけられた世界の中に住んでいるのであって、自分で意味を作るのは至難なのである。
制服に憧れるのも同じ「“として”構造」からである。
内容よりも形式を優先させてしまうのだ。
エサとの間にガラスを置かれるとニワトリは前にしか進まず、エサにたどり着けない。
一歩下がって見れば分かるのだ。
仏教に「横超」という言葉がある。
突破できない厚い壁にぶつかった時に、いったん曲がって道を横に逸れてみることだ。
一歩下がるというマイナスの勇気が必要なのだ。
例えば、眺める高さによって事態は違って見える。
鳥瞰図というのは古来から描かれてきたものだが、ベトナム戦争の頃、虫観図の必要が言われた。
上空から爆撃する鳥の目ではなく、爆撃される虫の目で見よう、と。
ときに宇宙からの目、いわば宙観図で眺めてみるのもいい、とカール・セーガンは語った。
「人間の独善の愚かさを教えてくれるだろう」と。
そうそう、視点を変える前に視点というものをもたなければならない。
アメリカ・メジャーリーグは野茂が行くまでも中継していたが、つまらなかった。
視点がなかったからだ。
イチローが行ってから、視点が大きく変わった。
視点というと大げさかも知れないが、要するに、自分の関心の在処(ありか)のことである。
旅行した後、その町への愛着が行く前と帰ってからと違うようなものである。
メディアは常に視点を変えなければならない。
反対側の視点からのコメントがなければ中正に欠けると非難される。
多数の意見だけでなく少数意見も伝えなければならない。
ゲームでも勝者を讃えるだけでなく、敗者の視点も大切だ。
黒人女性で初めてアカデミー賞を取ったハル・ベリーは3年後に『キャット・ウーマン』でゴールデン・ラズベリー賞の最悪女優に選ばれて、何と授賞式に参加した。
そのスピーチで「良き敗者になることができなければ、良き勝者になることもできない」と語った。
そして「あなたたちには二度と会わずにすみますように」と言って会場を後にした。
藤子・F・不二雄のSF「ミノタウルスの皿」は食べる側、食べられる側の視点を逆にしていて、名作である。
視点を変えるのが上手な人もいる。
「藤子・F・不二雄「異色短編集」 〈1〉 ミノタウロスの皿」(小学館文庫)藤子・F・不二雄(作)

河合隼雄は「「出会い」の不思議」(創元社)の中で兄の河合雅雄が梅棹忠夫からウサギの行動を見て「道徳の起源」をやれ、といわれた時の話を書いている。
「「出会い」の不思議―河合隼雄セレクション」(創元こころ文庫)河合隼雄(著)

個々の事実の精密な検討と、突然の視点の飛躍というのは、梅棹学のひとつの基本となっていると思う。
自分の目で見、自分の足で歩き、自分の体で感じる。
対象に密着してのきわめて具体的な確かめが行われた後に、それを離れて見る視点が常人と次元を異にするのである。
梅棹氏の名を有名にした『文明の生態史観』などには、それがよく出ているのではなかろうか。
「文明の生態史観 (改版)」(中公文庫)梅棹忠夫(著)

宮柊二に「あたらしく玉取換へし眼鏡にて仰げば空の春の星青し」という歌があるが、眼鏡を買い換えた時に周りの風景が全く違って見えてきて驚くことがある。
具体的にどんな風に視点を変えることができるだろうか?
次のような視点が考えられる。
近づいて見る
離れて見る
斜めから見る
裏側から見る
裏返して見る
逆さまにして見る
鏡に映して見る
透かして見る
立体的に見る
フィルターをかけて見る
比べて見る(似たものや違ったものと)
壊して見る(切って見る)
形を変えてみる
並べて見る
地と図を反転させてみる。
なくして見る
ぼんやりと見る
歴史的に見る
五感を使ってみる(食べてみる、触ってみる、音を出してみる・・・・・・)
何よりも知ってほしいのは、視点は一つではない、ということだ。
美術史家ジョン・バージャーの「イメージ」(PARCO出版)は“Ways of Seeing”というのが原題で、見方にはいくつもあるということを強調したものである。
「イメージ―視覚とメディア」(ちくま学芸文庫)バージャー,ジョン(著)伊藤俊治(訳)
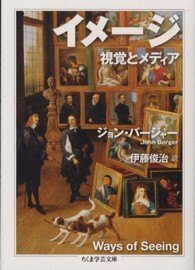
美術を見るときには3つの法則があり、一つは作者の意図、二つ目は見る側の要因(とりわけジェンダー)が関係し、三つ目は女性は常に見られる側で、男性は見る側だったことを忘れてはいけないという。
月は空に高く上っている時は小さく見えるが、地平線近くにあると大きく見える。
比較するものがあるかないかで見かけの大きさが違うのだ。
裏返して見る、の典型は赤瀬川原平の「宇宙の缶詰」だろう。
「超芸術トマソン」(ちくま文庫)赤瀬川原平(著)

これはただのカニ缶の外のラベルを内側に貼っただけのものだが、僕らのいる側の、全宇宙がそのカニ缶の中に入ってしまったことになる。
鏡の世界が不思議だというのはノーベル賞の朝永振一郎の本にある(片目で見ても左右反対なのに上下はどうして反対にならないのか)が、鏡像にしてみると違ってみえることがある。
安野光雅は右手を描く時に左手を鏡に映して描くと書いていた。
形を変えてみるというのは人間とコーヒーカップの共通点を見つけることである。
位相幾何学(topology)の問題だが、人間はドーナッツと同じ構造だと気づくことである。
並べて見る、地と図を反転させて見るというのはゲシュタルト(Gestalt)である。
見るというのは受動的だが、描くということで見方を提示するのが画家である。
一点透視法(透視図法)を見つけるまで人類はさまざまな描き方をした。
日本では例えば源氏物語絵巻」などの王朝絵巻は「吹抜屋台(ふきぬけやたい)」という手法で描かれている。
「源氏物語絵巻―伝・藤原伊房・寂蓮・飛鳥井雅経筆」(日本名筆選)

これは文字どおり屋根や天井、間仕切りの壁や建具の一部を取り払って斜め上方からのぞき込むように屋内の人物や調度を描くものである。
主に、屋内にいる主人公や男女の機微を手に取るように知ることができるのである。
映画のクロースアップの手法を先取りしている。
映画ではどこかにピントを合わせると他に合わないというカメラの特性が映像を規定していた。
ところが、グレッグ・トーランドが「パン・フォーカス」(全焦点)レンズを工夫することによって、映像が変化し、映画史上に残るオーソン・ウェルズの「市民ケーン」が誕生した。
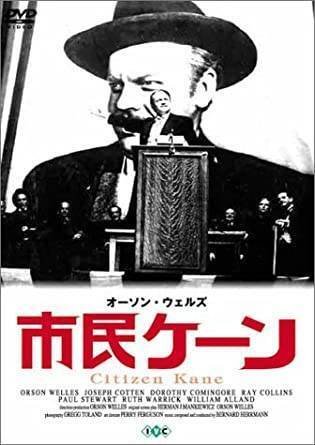
まず最初は、自分の視点を疑ってみること、次に「常識」的な視点を疑ってみることだ。
小さい頃放送されていたNHKの「ブーフーウー」は人形が踊るというものであったが、どうして動いて、お姉さんとも喋って、箱の中に入れられるのか分からなかった。
おかあさんといっしょ 「ブーフーウー」
https://www2.nhk.or.jp/archives/search/special/detail/?d=youth001
脚本を書いていた飯沢匡が実は3種類の人形を使っていたと書いていたのでアッと驚いたことがある。
2004年に放送されていた保険会社のCMに子象が親象と並んで川で水を飲もうとすると、川岸が崩れて流れに落ちてしまうものがある。
その後、親象が鼻をまきつけて救い上げる。
こんな画期的なシーンをどうして撮れたのだろうと思っていたが、実は後半の部分は演出だという(今野勉「テレビの嘘を見破る」新潮新書)。
「テレビの嘘を見破る」(新潮新書)今野勉(著)

調教師が別の象を使って10時間がかりで撮った。
それを紹介する朝日新聞の記事を引用した演出家の今野勉は「40年以上もテレビ番組の制作にたずさわってきた私も見破れなかった」と書いている。
言われてみれば、後半は別角度から撮っているのだから不自然である。
だが、うまく作り込んだ映像はプロもだましてしまう。
およそ映像には多かれ少なかれ作り手の作為が忍び込んでいる。
どんなに視点を変えても肉眼では見えないところがある。
世間という土壌に数々の名作の花を咲かせた山本周五郎は、作中人物に語らせている。
「どんなに賢くっても、にんげん自分の背中を見ることはできないんだからね」(『さぶ』」新潮文庫)。
「さぶ (改版)」(新潮文庫)山本周五郎(著)

ひとの視線を借りて、初めて見えるものもあるのだ。
SF映画で宇宙船の戦いがある時に、どのように撮影すればいいだろうか?
多くの人はミニチュアの宇宙船をピアノ線などで吊して撮影するというだろう。
しかし、これでは自由自在に動かすことができない。
映画「スター・ウォーズ」は、エピソード1以降の宇宙船の撮影の仕方を変えたという。
つまり、宇宙船ではなくて、カメラの方を動かすのである。
観客に見える映像は全く変わらない。
カメラを自在に扱える技術の裏づけが必要だが、まさに視点の転換である。
次のようなクイズがある。
次の●を全部、4本の一筆書きで描け、というものである。
有名すぎて今さらというクイズだが、視点を変える必要性を考えるために出しておく。
● ● ●
● ● ●
● ● ●
同じように枠を外して考える問題に「同年同月同日に同じ父親、同じ母親から生まれた二人がいますが、双子ではありません、どうしてでしょうか?」というのがある。
《答え》双子じゃなくて、三つ子以上だった。
映画「いまを生きる」の中でロビン・ウィリアムズが演じる先生が学生たちを机の上に立たせるが、まさに視点を変えている。
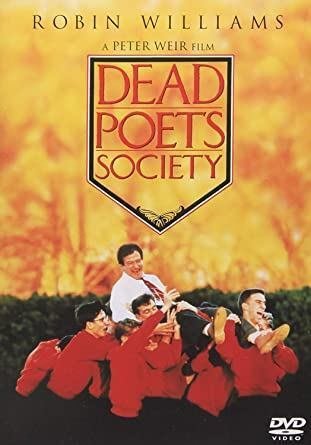
【関連記事】
高く澄みわたる冬の空。
https://note.com/bax36410/n/n39350a47b2aa
想像するだけでなく、実際に机の上に立ってみることが必要だ。
厚底靴を非難する声が多くて、例えば、石川三千花「服が掟だ!」(文藝春秋)には、猿岩石(古い!)ではなくて、「靴岩石」だと書いてあるが、実際、ちょっとでも背の高くなる靴を履くと、視線が高くなって、世の中が違ってみえることがある。
「服が掟だ!」(文春文庫)石川三千花(著)
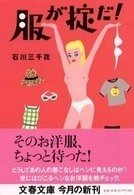
目を海外に向ければ、ルネサンス時代のヨーロッパで、上流婦人の間でチョピン(chopine)と呼ばれる厚い靴底の靴が大流行したことがあった。
木やコルクの台座に鉄製の輪をつけ、表面を豪華な布地か皮革で覆い、刺しゅうを施した靴である。
小アジアが起源といわれる。
中世以後、チョピンはトルコからのイスラム文化の流入とともにイタリア、スペインに伝わり、英国、ドイツはじめヨーロッパ一帯に広がった。
ゆったりとしたスカートを着て、チョピンを履くと、どの女性も見違えるほど背が高く見える。
30センチに及ぶチョピンもつくられた。
これを履くと女性は独りで歩くことができず、二人の侍女を左右に置いて、肩につかまって歩く、ということになった(加藤秀俊「衣の社会学」(文藝春秋))。
「衣の社会学」加藤秀俊(著)

まるで日本の花魁(おいらん)や京都の舞妓さんの“こっぽり”と変わらない。
ただ、ヨーロッパで厚底のチョピンがはやった理由は当時の道路が汚物やごみでいっぱいで歩きにくかったからだという。
エコロジーが進んでいた江戸時代の日本人には信じられないことだが、汚物をそのまま道路の捨てていたからだ。
セレンディピティというのはあるもので、須賀敦子「地図のない道」(新潮社)には、
「地図のない道」(新潮文庫)須賀敦子(著)

当時の高級娼婦だったコルティジャーネがこんな靴を履いていたことが書いてある。
特に、ヴェネツィアではアクア・アルタと呼ばれる高潮のためにも発達したと書いてあった。
彼女らの悲しい歴史が描かれているが、後に映画『娼婦ベロニカ(A DESTINY OF HER OWN)』にコルティジャーネが主人公で厚底靴も少し出てくる。
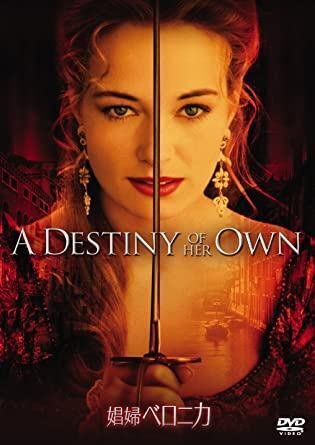
ヴェネツィアのチョピン(1600年頃)など見ていると、日本の現代女性たちも違う風景を楽しみ、自分を違った人格に感じたいと思えば、理解ができるのである。
文句を言う前に一度厚底靴を履いてみよう!
すると、女子大生が花魁になったのではなく、花魁が大学生になって勉強していると思えてくるはず(?)である。
何ごとにもちょっと距離を置いて見ることが大切だ。
とはいって、簡単ではない。
マルクスは、「ドイツ・イデオロギー」の中で、ドイツ人はドイツの文化にどっぷりと浸っていると批判しているが、では、マルクスだけがどうして特権的な仕事ができたのか、ということがある。
「ドイツ・イデオロギー (新編輯版)」(岩波文庫)マルクス/エンゲルス(著)広松渉(編訳)小林昌人(補訳)

エンゲルスは、マルクスを天才としているが、にわかには信じがたい。
「イヌは名詞である」というのは、「メタ言語(後段言語)」というが、なかなか、高見に達することはできないと、凡人は知っておいた方がいいだろう。
メタというのはツッコミだ。
エピメニデスのパラドックス(「クレタ人は、みなウソツキだとクレタ人が言った。」)を思い出せばいい。
内田樹は、メノンのパラドックスについて、次のように説明している(「知に働けば蔵が建つ」NTT出版)。
「知に働けば蔵が建つ」(文春文庫)内田樹(著)

ソクラテスは、かつて「「問題を解決する」という言い方は背理である」と言ったことがある。(メノンのパラドクス)
もし、問題を解決できることがわかっているなら、問題は存在しないことになるし、問題を解決できないことがわかっているなら、誰もそれを問題としては意識しないから、やはり問題は存在しないことになる。
多くのパラドクスがそうであるように、このパラドクスも「時間的現象」を無時間モデルに適用することによって背理となっている。
時間というファクターを入れるとパラドクスは解消する。
私たちが問題を立ててそれに解答するというのは、「問題を解決できることが暗黙裏にはわかっているが明示的にはわかっていない」という時間的現象なのである。
確かに、私たちは、「解答できることがわかっている問題」しか取り扱うことができないのだけれども、「暗黙裏にわかっていること」が「明示的にわかる」レベルに移行するまでには時間がかかるのである。
どんなエリアの研究者でも「この方向に行けば答えに出会える」という直感に導かれて研究を行う。
この直感が訪れないものは、そもそも研究を始めるということができない。
鉄道や航空で「うっかりミス」と呼ばれる事故がある。
すぐに「気のゆるみ」と決めつけられるのだが、実は、こうした事故を「気のゆるみ」と片づけておいてはなくならないのである。
「気のゆるみ」というものを人間はするものだ、という視点から議論を始めないと、いつかまた、別の人が「気のゆるみ」事故を起こしてしまう。
産業災害研究の世界には、“ハインリヒの法則”というものがあり、これは、「同じ人間の起こした同じ種類の330件の災害のうち、300件は無傷で、29件は軽い障害を伴い、1件は重い障害を伴っている」というものだ。
更に、「障害を伴うにせよ伴わないにせよ、すべての災害の下には、おそらく数千に達すると思われるだけの不安全行動と不安全状態が存在する」。
ハインリッヒの法則で300の無傷の事故と29の軽い障害を伴う事故のときに事故の潜在危険を認知できないと1件の重い障害を伴い事故を起こしてしまうともいえる。
例えば、2003年にJR北陸線で停車駅を間違うという「うっかりミス」が連続した。
実は、この年のダイヤの改正で、それまで停車駅が固定していたのに、列車によって、同じ「サンダーバード」でも止まる駅がまちまちになったのだ。
乗っている我々でさえ、「ええっ、こんなところに止まるの?」と思える駅で止まるのだから、ベテランほど戸惑うものだ。
飛行機事故は、事故が起きてもパイロットは問責されずに真実を語ることが要求される。
つまり、起きた事故は仕方がないので、次を防ぐ、という方策なのだ。
あなたの周りにも「うっかりミス」は許されない、などと息巻いている人はいないだろうか?
自分が無謬だと思ったとたん、神様になってしまうのだ。
そして、人間は神様にはなれない。
カーリングは、トリノ五輪以降、日本でも人気が出始めたが、私が初めて見たのは、記憶が正しければビートルズの映画『ヘルプ!』だった。
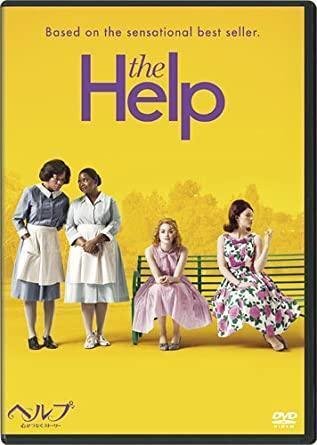
冗談のようなゲームだと思っていたら、きちんとしたルールがあることが分かった。
テレビでゆっくり見て、果たして見ているだけでルールが分かるだろうかと思ったことがある。
アメリカのノーベル賞受賞者R・P・ファインマンは、冗談が好きな物理学者であるが、物理学とは神様がやっている壮大なチェスのルールを探り当てるようなものだと語っている(「ファインマンさん ベストエッセイ」(岩波書店))。
「ファインマンさんベストエッセイ」ファインマン,リチャード・P.(著)大貫昌子/江沢洋(訳)

宇宙規模で行われる神様のチェスを物理学者は、時おりその盤を片隅からちらりとのぞき見て、それを手がかりにゲームのルールや駒の動きを推測するようなものだ。
時には、いきなり敵陣で駒が成るなど、予想外の展開に驚くこともある。
科学哲学者のカール・ポパーは、マッハの確証主義を批判して「科学的精神」というのは、仮説が「うまく適合しない」事例を探し出し、その反証事例によって、その仮説が反駁されるかどうかを吟味することを最優先するような知の働きだといった。
つまり、自説がうまく妥当する事例ではなく、自説がうまく妥当しない事例に引かれ、それによって、自分の立てた仮説を自分自身で書き換えることに知的興味が集中するような人をポパーは「科学者」と呼んだ。
そうでない人は「神様」であり、そんな科学は「擬似科学」なのである。
歴史を振り返ると、マルクスにしろ、ダーウィンにしろ、フロイトにしろ、本人の意図から離れてすべてを説明しようとする追従者が生まれ、万能感を生んだ。
マルクスは「マルクス主義者ではなかった」といわれる所以だが、その追従者たちは解剖によく切れるメスを使っていたつもりが、切れすぎて対象を殺してしまうことが多かった。
ローマカトリック聖者の候補者について生涯の事跡人格について調査論告するともいう「悪魔の代弁人」(Devil's Advocate/promoter of the faithとも)という手法がある。
主に、アメリカのことだが、ある学説や政策の妥当性を確かめるためにこの方法を採ることがある。
これについて朝日新聞の記者だった白井健策が「書く前に」(「エッセイの書き方」(岩波書店))で次のように書いている。
「エッセイの書き方」日本エッセイスト・クラブ(編者)

直訳すれば「悪魔の代弁人」いう意味である。
一般には、「他人の弱点をとらえて難癖をつける人」のことをさすことばだが、そもそもはカトリック教会でのしきたりからきた表現である。
カトリック教会では、特定の人々を聖人や福者として列する、ということをする。
その場合、聖人や福者に列せられるべき理由として、候補者たちの奇跡・徳行に関する証拠を提示しなければならない。
そうすると、それらの証拠の信頼性を見聞する役割が必要になる。
この任に当たるのが列聖(列福)調査審問検事といわれる人々で、これすなわち「悪魔の代弁人」というわけである。
つまり、聖人にしないように(悪魔の味方をして)あら探し、こきおろしをする人々、という含みである。
20世紀前半には「ピルトダウン人」として有名な原始人類の頭蓋骨が発見され、人類学界を揺るがしたのだが、後に捏造と分かった。
犯人はコナン・ドイルという説もあって真相はまだ分かっていない(と思う)。
ネス湖のネッシーは捏造だという人が出てきたが、犯人も捏造だという人がいて真相はまだ分かっていない(と思う)。
2000年には、藤村新一という人による旧石器発掘の捏造が発覚したが、周りに誰も「悪魔の代弁人」がいなかったことになる。
疑義を挟む人はいたのかもしれないが、「悪魔の代弁人」のような制度が機能していなかったことになる。
「ゴッドハンド」と呼ばれ始めたころからおかしいことに気づかなければならないのに。
哲学には、「ソーカル事件」という有名な事件があって、今更書く必要もないが、アラン・ソーカルという物理学者が哲学者たちの勝手な科学論の振り回しに怒って(?)『ソーシャル・テキスト』というカルチュラル・スタディーズの専門誌にパロディ論文を応募したのだが、真に受けた編集者が載せてしまったという事件があった。
詳しくは、「知の欺瞞」 (岩波書店“Impostures intelectuelles”) を読めばいいが、如何に思想が怪しい言説に包まれているのかが浮き彫りにされた。
「「知」の欺瞞―ポストモダン思想における科学の濫用」(岩波現代文庫)ソーカル,アラン/ブリクモン,ジャン(著)田崎晴明/大野克嗣/堀茂樹(訳)

文科系の学問が悪いと思うかもしれないが、史上最大の捏造は物理学で行われている。
2002年にベル研究所の有名な研究者ジャン・ヘンドリック・シェーン(32歳)が解雇されたが、実験データを改竄したことが外部の調査委員会によって明らかになったためだ。
データが改竄された研究の中には、シェーンをはじめとする数名の科学者による超伝導(超電導)、分子電子工学、分子結晶といった最先端分野の研究が含まれていた。
研究結果は、『サイエンス』誌、『ネイチャー』誌といった有名な科学雑誌にも掲載されていて、売れっ子教授だった。
2005年には、世界で初めてヒトのクローン胚からES(胚性幹)細胞作りに成功したとする論文を米科学誌サイエンスに発表したソウル大の黄禹錫(ファン・ウソツク)教授が、研究成果のES細胞は存在しないと認め、論文撤回をサイエンス側に要請して認められた。
黄教授は、「ゴッドハンド」といわれ、韓国の国民的英雄として慕われていて国家プロジェクトにする予定だっただけに、騒然となった。
科学と政治が結びつく時、悲劇が起きる。
プロジェクトが大型化すればするほど政治力が必要となってくるから科学者は研究室の中だけで暮らせないのだ。
旧ソ連のルイセンコ事件がよく知られる。
農学者ルイセンコは、メンデルの遺伝学を否定したのだが、当時の共産主義思想に都合がよかったため党と政府の強い支持を受け、生物学界を牛耳って、農業科学アカデミー総裁に上り詰めた。
そして、学説に反対する生物学者を徹底的に政治的迫害した。
小麦の起源の研究で知られる世界的遺伝学者バビロフは、獄死に追い込まれ、米科学誌に論文をのせた別の大物学者も「非愛国者」と非難され、自説を放棄した。
多数の生物学者が追放の憂き目をみたが、当のルイセンコも独裁者スターリンの死によりやがて失脚の運命をたどった。
浮き世離れしているはずの言語学でもニコライ・マールの理論が猛威を振るい、多くの優秀な言語学者が粛正された。
ただ、さすがのスターリンも自ら間違いを認め、マールの言語=上部構造論を否定した。
ブレヒトは戯曲『ガリレイの生涯』の中で「科学の目的は、無限の英知への扉を開くことではなく、無限の誤謬にひとつの終止符を打ってゆくことだ」(Es ist nicht ihr【die Wissenschaft 】 Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tuer zu oeffen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum.)とガリレイに語らせている。
ブレヒトがこの作品を書いたのは、祖国ドイツがナチズムに支配されていた時代で、学問の自由や科学者の良心が踏みにじられ、ユダヤ人であるアインシュタインの学説を攻撃する物理学者らが暗躍したからでもあった。
往年の007シリーズでは国際秘密組織スペクターが敵となっていたが、みんなが不正に向かって働くことなどあるだろうかと思って見ていた。
しかし、オウム事件以降、科学と社会との関係は、しっかり考えなければならないと思うようになった。
フランスの微生物学者パスツールは、「科学に国境はないが、科学者には祖国がある」と言ったが、国家などの組織から離れて研究することは難しくなっている。
言葉の視点を変えるとジョークやユーモアになるが、視点を変えることは言葉でいうほど簡単ではない。
というのも、言葉自体が我々の思考を呪縛するものだからだ。
イタロ・カルヴィーノは、「カルヴィーノの文学講義」(朝日新聞社)の中で次のように書いている。
「アメリカ講義―新たな千年紀のための六つのメモ」(岩波文庫)カルヴィーノ(著)米川良夫/和田忠彦(訳)
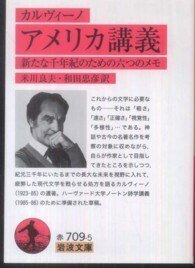
ときとして私には、何かしら疫病のようなものが人類をもっともよく特徴づけている 能力、すなわち言葉を用いる能力を駄目にしているのではないかと思われることがある。
言葉の伝染病といったもので、その兆候は、識別的な機能や端的さの喪失、あるいは、また、表現をおしなべてもっとも一般的な、没個性的で、抽象的な決まり文句に均一化させてしまい、その意味を稀薄にして、語と語が新しい状況に出合うと きに発する火花をいっさい消し去ってしまおうとする一種の無意識的・機械的な振舞いとして現れている。
また、こんな例もあり面白い。
ある大学で、学生に座席表を書かせると、時々、学生から見た座席表を作るものがいる。
教師の立場で欲しいのは、教壇から眺めた学生の位置と名前なのだが、視点を変えることができない。
簡単な幾何学の問題でも、視点を変えることができずにつまってしまう。
セレンディピティというのは、心に補助線を入れることなのである。
将棋や碁の名人は、即座に相手の立場から盤上を眺めることができるのに、素人にはできない。
また、ある学校がPRビデオを作る時に、環日本海時代を表すために地球を逆さまにしたCGを作ってもらって、「私たちは発想の転換を大切にします」と流した。
ところが、何かおかしい。
結局、気象学の先生も見逃していて、雲の動きが逆になってしまっていた。
逆さまになった時も左から右に流れるままになっていて、元に戻ると東から西へ流れるようになるのだが、見逃していた。
視点を変えることは本当に難しい。
視点をちょっと横にずらせば、逃げ道があるのに、目の前のガラスに阻まれる蠅のごときが我々の姿なのである。
視点を変えるだけでなく、ひっくり返すことが大切だ。
最も鮮やかな例は、天動説から地動説への「コペルニクス的転回」であろうし、ドーキンスは生命体が遺伝子を残すのではなく、利己的な遺伝子が生命体を「遺伝子の使い捨て容器」として使っていると逆転させたし、ホイジンガやカイヨワは、遊びから、逆に、人間を照射したし、ホルクハイマーやアドルノは、合理化が進めば進むほど文明は野蛮さを深めるという「啓蒙の弁証法」を考えた。
写真家の藤原新也は、「あの人がさかさまなのか、わたしがさかさまなのか」という写真を撮っている。
長沼行太郎は、「思考のための文章読本」(ちくま新書)で次のように「転倒の思考」について述べている。
「思考のための文章読本」(ちくま新書)長沼行太郎(著)

転倒の思考は、順序を変えることによって、もともとあったのに、今では気づかなくなっていること、忘れてしまっていること、(従来の説明の順序では)隠されていることを明るみに出す、つまり起源、出生の秘密をあらためて思い知らせてくれる。
卑近な例で考えれば、健康をもっとも意識するのは病気の時である。
健康が分かるのは病気を通してであり、ありのまま過ごしていると気づかない。
幸福だって同じで、不幸になって初めて強く意識するものである。
同じように理性というのも理性だけで考えていては分からない。
狂気というものを通して初めて考えることができるのだ。
これを見事にやってのけたのがミシェル・フーコーで、視点を変えることによって、考古学のように「知」を掘り出したのである。
バルトはまず、フーコーが、≪『狂気と非理性――古典時代における狂気の歴史』において≫狂気という人間の普遍の本性に属すると考えられてきたものを歴史の変遷のなかに置き直し、また従来医学の問題とされていたものを文明の問題に移し替えた、とする。
歴史の観点から見るなら、同じ狂気が、中世には気違いと呼ばれ、十七世紀を中心とする古典時代には狂人とされ、やがて精神病医ピネル(1745-1826)によって、罪人と同一視されていた狂人を精神病者として、初めて医学の対象とされたのであった。
しかし、フーコーは、こうして、その名称の変遷を重ねてきた狂気を医学の対象とは考えていず、バルトの理解するところでは、「狂気とは病気ではなく、世紀によって変化する、おそらく異質的な意味であり、狂気とは理性と非理性、眺める者と眺められる者とが形づくる一対に純然たる機能なのである」。
狂気が病気でなく意味であるとすれば、各時代の歴史的、社会的背景が作り出す記号作用の全体的構造のなかで、精神錯乱なる現象は捉えられねばならないであろう。
これが、フーコーの実現した第一の構造分析である(通時的分析)。
次に、狂気とは、理性と非理性、観察する者とされる者とが一対をなす機能であるとすれば、これを共時的観点から見れば、問題は超歴史的なある種の形式(フォルム)であり、「社会全体のレベルで、排除される者と包含される者とを対立させ、また結合するひとつの相補性」なのである。
この点がフーコーの探求した第二の構造分析であった。
中世には、追放、古典時代には強制収容、近代には病院への拘禁に分かれたにせよ、常に、同一であるのは、社会規範にはずれた者を排除するというひとつの行為である。
社会的正常者がありうるためには異常者がいなければならず、この意味で両者は相補的関係にあり、排除は狂気のほかに、シャーマニズム、犯罪行為、同性愛等々に及ぶものである。
「ロラン・バルト―世界の解読」篠田浩一郎(著)
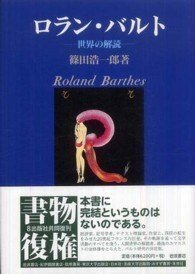
目的と手段を間違って逆に考えてしまう人が多い。
英語を学びたい、という人の多くが目の前のコミュニケーションを避けていつか会える英米人との会話を夢見て、目的を考えずに英語を学んでいる。
いつか役に立つ、というのだが、そんなヒマがあったら、今役に立つことをしたらどうかと皮肉の一つも言いたくなる。
三浦俊彦の小説「サプリメント戦争」(講談社)に出てくる登場人物の一人は例えばカップめんを食べたあと、こんな錠剤を飲む。
「サプリメント戦争」三浦俊彦(著)
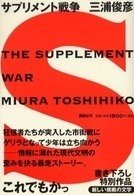
ビタミン剤各種、いちょう葉エキス、アガリクス、高麗人参、田七人参、大豆レシチン、エゾウコギ、すっぽん生血、葉酸、ブルーベリーエキス、牛黄、霊芝、ウコン、ソバ若葉等々。
それで体調はいいのか、と聞かれると「さあねえ」。
そして答える。
「僕は健康マニアじゃなくてね、健康食品マニアなんで・・・・・・」。
「健康のためなら死んでもいい」という人も多い。
酒もダメ、タバコもダメ、美食もダメとなると「生きていることが健康に悪い」ということになる。
考えられるべきことは、既に考えられている。
言葉だって、オリジナルな言葉を使えるはずがない。
内田樹は、「剽窃と霊感の間」という文章をホームページで書いているが、オリジナルとのズレが大切なのである。
視点をずらすことが重要なのだ。
内田樹は、以下(「」内参照)の様に語っていた。
「間違った解釈だとわかっていて本なんか出すなとお怒りの方がいるかもしれない。
だが、それは短見というものである。
だって、「解釈が間違っている」ということ以外に、研究者には、オリジナリティを発揮する機会がないからである。
正解はどの問いについても一つしかない。
誰が読んでも、そこに到達するような解釈についてオリジナリティの存在する余地はない。
解釈者の固有性は、唯一「誰にも真似ができないような仕方で正解を逸する」ということのうちにしか棲息できないのである。
バカを言うな、自然科学ではそんなことはないとさらに怒る方がおられるかもしれない。
そんなことはない。
どのような精密科学といえども宇宙の森羅万象ことごとくを理論的に解明できているわけではないからである。
世界は、謎に満ちている。
宇宙の涯には何があるのか?
ビッグバンの前に時間はどのように流れていたのか?
誰も答えることができない。
だから、あらゆる科学的仮説は「世界についての不十分な解釈」であることを認めなければならない。
そして、科学者のオリジナリティは、まさに「彼に固有の不十分さ」を示すというかたちでしか発揮することができないのである。
私が「剽窃」plagiarismということの犯罪性を自明のものであるように語ることに対して、わりと懐疑的なのはそのためである。
私の書いている考想のほとんどは先賢からの剽窃である。
使っている日本語は私が作り上げたものではないし、私が頻用する修辞やロジックもすべて「ありもの」の使い回しである。
それでもなお私にむかって「ウチダは剽窃者だ」という批判がなされないのは、「先賢の考想を借用」しているつもりでいる私の借用の仕方が微妙に「他の人とは違う」からである。
私は聞いたとおりのことを繰り返しているつもりなのだが、必ずそれは他の聴き手とは違う聞こえ方で私に届いているのである。
この「他の聴き手とは違う聞こえ方」や「他の読み手とは違う読まれ方」を差配しているのは、私自身ではない。
私の中の「他者」である。
「剽窃者」とはこの「私の中の他者」が十分に他者でない人のことである(わかりにくいなあ)。
情報の伝達を汚す「私の中の他者」の未知度が高まると、それは「剽窃」ではなく「霊感」と呼ばれる。
私たちは模倣や反復を脱して真にオリジナルな知見や考想を語ることはできない。
これは原理的に不可能である。
私たちにできるのは、「私たちのうちなる他者」ができるだけ未知のものであることを願うことだけである。」
ロシア文学者の江川卓(といっても野球の“すぐる”でなくて“たく”)は、「謎とき〈罪と罰〉」(新潮選書)で視点を見事にひっくり返した。
「謎とき『罪と罰』」(新潮選書)江川卓(著)

「ロージン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ」は、天才にはそれができると言って金貸しの婆さんを殺したのであるのだが、この奇妙なイニシャルはロシア文字ではPPPとなる。
Pで始まる名前の実効的な比率は0.2%でしかなく、ぞろ目になるのは600万分の一の確率しかない。
当初ドストエフスキーはロジオンでなく、ヴァシリー(B)すなわちBPPとしていたが、ある時BをPにして、これを逆さにすると666という数字になると気づいた。
ヨハネ黙示録13章では凶悪なネロ皇帝をヘブライ語で書くと「その数字は666」となるというのだが、これを主人公の名前に忍ばせたのだ。
つまり、『オーメン』なのだ(こんな名作知らなきゃダミアン?(^^;)。

また、「ラス」+「スコーリニコフ」の「ラス」は<分かれる>、「スコーリニコフ」は<派>で「分離派」、つまり、当時の宗教的異端派だということが分かる。
逆に、彼には、殉教者たるキリスト自身も投影されている証拠がテキストのそこかしこに見いだされるという。
さらに、当時のロシアのカルト的宗教の落とす影、「罪」の意味、「罰」の意味、なぜ彼は「斧の峰」で殺したのか、ソーニャを愛していたのか、彼とソーニャに肉体関係はあったのか・・・・・・などが書かれた面白い本になっている。
更に、先の獣の前で行うことを許されたしるしによって、地上に住む人々を惑わせ、また、剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を造るように、地上に住む人に命じた。
第二の獣は、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像がものを言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば、皆殺しにさせた。
また、小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、自由な身分の者にも奴隷にも、すべての者にその右手か額に刻印を押させた。
そこで、この刻印のある者でなければ、物を買うことも、売ることもできないようになった。
この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。
賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。
数字は人間を指している。
そして、数字は666である。(「ヨハネの黙示録」13章14~18節)
視点を変えると芸術になる。
現代美術は、視点を変えただけのものが多い。
福田美蘭は、古典の視点を変えることで創造している。
ボッティチェリの「春」でも、別の角度から見たらどうなるか、という絵画が多い。

「だからどうなの?」といってしまえばお仕舞いなのだが、それを楽しむのが文化なのである。
作曲家ジョン・ケージの「4分33秒」は「演奏されない音楽」だ。
4'33" John Cage(Orchestra with Soloist, K2Orch, Live) / 4分33秒 ジョン・ケージ けつおけ!
https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8
演奏者は4分33秒の間一音も発しないのに全3楽章ある伝統的傑作。
「4分33秒」の第2番は、「0分00秒」という演奏すらしえない曲である。
でも、観客は何も演奏されなくても勝手に自分の先入観から音楽を考えて奏でているし、演奏者も観客の音が聞こえる。
その場の人数や雰囲気で同じ演奏のはずが、違うし、受け止め方も様々だ。
音楽通の人に対する嫌みでさえある。
ただ、こうした芸術はやったもの勝ちで、みんなに模倣されると困る。
発想の勝利なのだ。
文学が有効であるのは、今まで省みられなかった視点から描いているからである。
こんなところにも真実があったのか、と読者に考えさせるから人を感動させるのである。
人生には「別解」が必要なのだ。
土佐日記は、紀貫之が女性に仮託した仮名文で、旅のこと。
「土佐日記(全)」(角川ソフィア文庫)紀貫之(著)西山秀人(編)
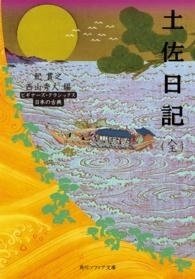
失った愛児のことなどを記したものだ。
アメリカの田舎の駅に時計が二つあった。
いつも違った時刻を指しているので、ある老人が駅長を捕まえて、「この二つの時計、合っていたことがない。いつもバラバラになっている。みっともない。合わせておいたらいいだろう」といった。
すると駅長は、「同じ時刻だったら、二つある甲斐がありませんから・・・・・・」と答えた。
この話から言語学者のマーティン・ジョーズ(Martin Joos)は、言葉にも同じことをいうのに、いくつもの言い方、スタイルがある。
ごくごく丁寧な言い方、改まった言い方、普通体、会話の調子、俗語的表現、全部で5つのスタイルがある。
というので、『5つの時計』(The Five Clocks. Indiana University Press, 1962)という本を書いた。
The Five Clocks (International Journal of American Linguistics,)by Martin Joos
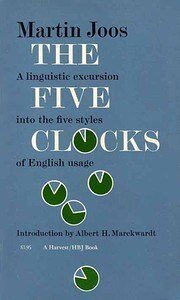
もちろん、冒頭に駅長のエピソードが引用されている。
そう言えば、鮎川哲也も推理小説「五つの時計」を書いていたのを思い出した。
「五つの時計―鮎川哲也短編傑作集〈1〉」(創元推理文庫)鮎川哲也(著)北村薫(編)

桃太郎はおとぎ話ではなく、侵略的な物語だという話を聞いたことがあるだろう。
これを更に異質な物語に変えたのが芥川龍之介である。
「桃太郎」(青空文庫)芥川龍之介(著)

鬼ケ島が「天然の楽土」として描かれる。
平和な島を侵略し、あらゆる罪悪を犯すのが桃太郎だ。
降伏した鬼との問答が興味深い。
「征伐の理由は?」に「犬猿雉の忠義者を召し抱えたからだ」と桃太郎。
「召し抱えたのはなぜ?」には「征伐のためだ」と、大義のなさを痛烈に皮肉った。
その少し前、彼は中国旅行をした。
そこで出会った知識人に「最も嫌悪する日本人は桃太郎だ」と言われ、虚をつかれたようだ。
その衝撃が桃太郎像の転倒につながった。
大正末期のことだった。
そう言えば、松岡圭祐が都内で改造ガスガンを使った殺人事件が発生した際、被害者ふたりのうちひとりの胸の上に芥川龍之介の『桃太郎』が小冊子風に綴じられて置かれていた見立て殺人ものの推理小説を書いていおり、面白かった。
「´ecriture 新人作家・杉浦李奈の推論〈6〉見立て殺人は芥川」(角川文庫)松岡圭祐(著)

太宰治の「走れ、メロス」が書かれた昭和15年(1940年)より、
「走れメロス (改版)」(新潮文庫)太宰治(著)
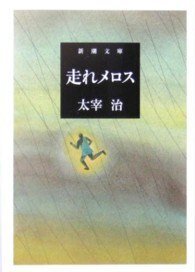
20年前の大正9年に鈴木三重吉が同じ題材で「デイモンとピシアス」というのを書いている。
「日本児童文学名作集〈上〉」(岩波文庫)桑原三郎/千葉俊二(編)

ピシアスがメロス、デイモンは人質となった友人セリヌンティウスであるが、三重吉版では二人ともピタゴラス派の知識人であり、3日の起源は切られず、太宰版のようなメロスの迷いと諦めがない。
だから、メロスの「私を殴れ」「私は、途中で一度、悪い夢を見た」、友人の「同じくらい音高く私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った」がない。
金子みすゞの詩「大漁」なども視点を変えたものとして有名だ。
「金子みすゞ童謡全集」金子みすゞ(著)矢崎節夫(監修)

ただ、弔いをするから人間なのだ、という視点に立てばまた違った見方が生まれる。
「大漁」金子みすゞ
朝焼け小焼けだ
大漁だ
大羽鰯(おおばいわし)の
大漁だ
浜は祭りの
ようだけど
海のなかでは
何万の
鰯のとむらい
するだろう。
詩人、宗左近の「詩のささげもの」(新潮社)には、発表当時、作者は小学2年生という、たきぐちよしお君の「さかなは/目を あいたまま/しんで いる/きっと/たべられるのまで/見ようと/しているんだね」(「さかな」1968年)のという詩がある。
「詩のささげもの」宗左近(著)

宗は読後の感想を、「恐れ入りました。・・・・・・深々と頭を垂れるよりほかはありません」と書き留めているが、これもみすゞと同じ視点だ。
ジョン・アップダイクの「ガートルードとクローディアス」(白水社)も視点を変えた、美しい物語である。
「ガートルードとクローディアス」アップダイク,ジョン(著)河合祥一郎(訳)

ヒロインのゲルータは16歳の頃、父の薦めで粗野な大男と結婚し、一人息子をもうけるが、武骨な夫は女心を解せず、満たされぬ結婚生活を送っている。
31歳を迎えた時に、外国暮らしが長くて話題が豊富で「ぞくぞくするほど奔放な話し方」をする男クローディアスが現れる。
仕事で不在の夫の空白を埋めるかのように、彼とのつきあいが始まっていく。
相手は夫の弟で《トリスタンとイゾルデ》の物語と同じ構図の禁断の愛だ。
やがて夫に知られることになって、悲劇的な様相を帯びてくる。
息子は理知的でハンサムなのだが、神経質でカンの強い一人っ子だ。
夫と息子ハムレットに翻弄されてゲルータ(ガートルード)は次第に消耗してくる・・・・・・
映画ではニコール・キッドマンが好演した『アザーズ』も面白い。
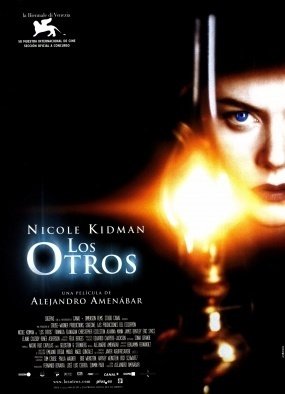
ピエール・グリパリの「木曜日はあそびの日」(岩波少年文庫)の中にやさしい、子どもの悪魔が出てくる。
「木曜日はあそびの日」(岩波少年文庫)ピエール・グリパリ(著)金川光夫(訳)

昔むかし、緑色の大悪魔と黒い悪魔の間に生まれた、由緒正しい子どもの悪魔の話である。
子どもが学校から帰ってくるとお父さん悪魔が何をしたと聞いた。
「え・・・・・・と、書き取りと、問題を二つと、歴史と、地理をちょっと・・・・・・」
これを聞くと父さん悪魔は、かわいそうに両手で自分の角をつかみ、まるでむしろ取らんばかりに引っ張るのでした。
「いったい何の因果で、こんな子供ができたんだろう?
思えば何年も前から、お母さんとわしは、いろいろな犠牲を払って、おまえに悪い教育を受けさせ、悪い手本を示し、おまえを立派な、意地悪い悪魔に育てようと努力したものだ。
ところがどうだ!
おまえときたら、誘惑に乗るどころか、問題なんか解いておる!
さあ、いいか、よく考えてみろ。
いったいおまえは、これから先どうするつもりなのだ?」
「ぼくは心やさしいひとになりたいのです。」
子供の悪魔は、答えるのでした(^^;
【垂直思考と水平思考】
水平思考とは、横になって寝ながら考えることではない。
デ・ボノの「水平思考の世界」(The Use of Lateral Thinking, Penguin 1967)は、水平思考をすっかり有名にした。
「水平思考の世界―固定観念がはずれる創造的思考法」デボノ,エドワード(著)藤島みさ子(訳)

視点を変えること自体は、今までも強調されていたことだが、これを「水平思考」と名付けたところに視点の良さがある。
一カ所に穴を掘り進んでいくと、別の場所に穴を掘ることができなくなる。
垂直思考(Vertical Thinking)は、このように同じ穴を深く掘るということであり、水平思考は別な場所にも穴を掘るという考え方である。
いわば水平思考は、一定の方向に向かったパターンを離れて、別のいくつかのパターンへ移動することを求める。
頭脳の機能は垂直思考に傾きがちであるから水平思考が必要となってくる。
動物園のライオンが檻から逃げ出して危険だったら、人間が檻の中に入ればいい。
泥棒が多い国では、泥棒を刑務所に入れるよりは、自分が刑務所に入ればいい。
実際、泥棒対策用の格子をつけた家は、刑務所に見えてくる。
デ・ボノの説明の中で最も有名なのが小石の問題である。
ある商人が金貸しに多額の借金をしていて牢屋に入れられそうになった。
年を取った金貸しは商人の娘を好きになって取引を申し出た。
袋に白と黒の小石を入れて、娘が白を取ったら借金も全て帳消し。
黒が出たら借金は帳消しにするが娘を差し出すという条件だ(私なら借金を帳消しにして娘をもらうが・・・・・・)。
ところが、娘は金貸しがこっそりと黒い小石を二つ入れるのを見てしまう。
垂直思考をする人は次のような3つの考えをするだろう。
娘は小石を取るのを拒否すべき。
娘は袋の中に黒い小石があり、金貸しをイカサマ師として暴露すべき。
娘は自分の父親が投獄されないように黒い小石を選んで自らを犠牲にすべき。
しかし、1の解決だと父親は投獄されるだろうし、2の解決だと娘の命が危うくなり、3だと金貸しと結婚せざるを得ない。
水平思考ではこうなる。
娘は袋の小石を取って見せずにそのまま道路の石の中に紛れさせ、「まあ、分からなくなったわ、でも、残っている石を見れば、私が落とした石が白か黒か分かるわ」というのである(僕が金貸しだったら、慌てて持っている石を捨ててしまうが・・・・・・)。
これで思い出すのが一休さんのトラ退治である。
「僕が捕まえますから、どうか追い出してください」というのは水平思考でなければ生まれてこない。
ジェイムズ・ジョイスのお話にも「悪魔と猫」というのがあって、難所でなかなか橋ができなくて苦しんでいると悪魔が現れて最初に渡ったものを貢いでくれるなら作ってやる、という取引になるというお話だ。
「猫と悪魔」ジェイムズ・ジョイス (作)ジェラルド・ローズ (画)丸谷才一(訳)
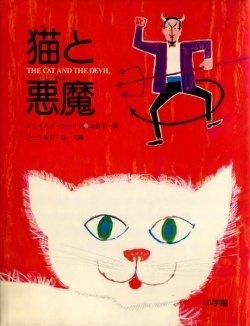
そして最初に渡ったのは猫だったというオチである。
これらが分かれば次の問題も簡単だ(「頭の体操」のどれかにあった(^^;)。
アラブの王様が二人の息子に財産を分けるといった。
二人で馬を競争して遅く着いた方に財産を分け与えるという。
二人は競争を始めたのだが、熱い砂漠をのろのろと行くのはたまらない。
そこへ賢者がやってきて、二人に知恵を授けた。
すると、二人は慌ててゴールを目指した。
どうしてか?
答えは、馬を取り替えた。
そうすると、早くゴールした方の人間が勝つことになる。
メディア学のマクルーハンも映像的メディアの社会は垂直思考から水平思考に変化していくと言っている。
水平思考の伝統は彦市、吉四六(きっちょむ)さんや大岡裁き、曽呂利新左衛門などの日本の頓知話に受け継がれている。
西欧では、ヘルメスからティル・オイレンシュピーゲルなどが現れて頓知と愚鈍さで社会の良識を逆撫でしていく。
これらは破壊と創造のトリックスターである。
さて、この話を友人にしたら「白い石を握って袋の中に手をつっこみ、白い石を出せばいいわ」と言った。
まあ、あまりいい解決ではないが、不可能でもない。
公開の場でもう一度やるべきとか、顔の白粉を黒い石につけて白くすればいいとか、いずれにしろ、他の可能性もいろいろと考えることが水平思考であり、頓知であり、頭の柔軟体操である。
子供の好きなクイズも水平思考を育てるのに重要である。
例えば「人が十人乗ったら舟が沈みました。どうしてでしょう?」というのがあって、答は、「潜水艦だった」というものであるが、別に潜水艦でなくても他の答をいろいろと考えることができる。
創造性というのは、一つの答を見つけるのではなくて、より多くの答を見つけるのである。生物学者の今西錦司は言った。
「真実は何も一つでなくてええんや」!
作家の保坂和志が「直」・「並」の思考と言っているのも水平思考・垂直思考と同様のことである。
思考することは、本当はなかなか前に進まないことだ。
「つまり何が言いたいんだ。」とか「早く結論を言え。」とか、「もう、本当にじれったいんだから・」とかそいういう考えは「直」の考え方で、思考することとは別のことだ。
おかしな例だけれど、麻雀でも将棋でも囲碁でも、強い人ほど、なかなか手<方針>を決めない。
可能なかぎり方針を曖昧にしてゲームを進行させる。
弱い人はそれに耐えられなくて、すぐに方針を明示する。
明示するとは狭くすることだ。
で、「直」でない考え方とは何か。
私はそれをいちおう、「並(へい)」の考え方と呼ぶことにしている。
並列、並置、併存・・・・・・
「併」と書いてもかまわない。
「平」でもかまわない。
「直」のように、スパッとしてなくて、序列もないような意味なら、なんでもかまわない。
いろいろな要素が、あまり脈絡なく頭の中にある状態。
一つの題材についてすぐに結論を求めない状態。
「近所の猫の毛の系譜」と「ニューヨーク市場の株の高さに対する懸念」と「羽生善治の将棋の特異性と普遍性」と「生命と物質と同列に還元主義的に説明することの意味と無意味」・・・・・・が、頭の中に並存している状態。
明快さでなく、説明から洩れる不明瞭さに親しみを持つことが、「並」の思考で、それは<思考する>というよりも、<思考に住む>という感じだろうか。(「転位する思考1」(読売新聞1997年1月6日))
最後にもう一つ、水平、垂直ネタを。
スズキ目の海魚。
全長約60センチメートル。
からだは楕円形で側扁し、体高が高い。
口は小さく、歯はくちばしのように見える。
幼魚は灰青色の地に七本の黒い横帯がある。
雄は成長するにつれて縞模様が不明瞭となり、口の周辺が黒くなってクチグロと呼ばれる。
磯釣りの好対象魚。
夏、美味。
北海道から南シナ海にかけて分布。
シマダイ。
というのは『大辞林』の「いしだい」の説明であるが、一般常識と違う部分がある。
それは「黒い横帯」というところで、誰が見ても「縦縞」の間違いだと思うだろう。
しかし、これは専門家が人間の立ち姿のように魚も頭を上に置いて見るからである。
足はどうだろう?
いーかね。
「烏賊(イカ)の足」というのも『大辞林』の「いか」に以下の通り書いてあるように、足ではなく、手なのである。
頭足綱十腕目の軟体動物の総称。
体は円筒状で一〇本の細長い腕をもつ。
二本の触腕は長くて、先端だけに吸盤を備え、えさを捕らえたりする。
他の八本は短く、内側に吸盤が並ぶ。
胴の左右にひれ、外套(がいとう)膜背部に甲がある。
口にはキチン質のあごがあり、俗に「からすとんび」という。
敵にあうと腹部の墨ぶくろから墨を出して逃げる。
体長25ミリメートルのヒメイカから、触腕を含めて15メートルを超えるダイオウイカまで種類が多い。
食用。
干したものは「するめ」と呼ぶ。
日本近海には百数十種がすむ。
[季]夏。
これは水族館で泳いでいるのを見るのが一番早い。
実際に観察するのと干物を見るのとでは大きな違いがある。
自分の依って立っているところの「準拠枠」(frame of reference)をひっくり返すことが大切なのだ。
なお、欲張りな人は、水平思考も垂直思考も含めた「画鋲型思考」を唱えているようだ。
【対位法的思考】
つまり、全く別の世界に存在すると思われていたことを結びつけることが大切だ。
アーサー・ケストラーの「ホロン革命」(工作舎)は第二部が「創造的精神」になっていて「科学上の発見は、無から有を生み出すものではない。
「ホロン革命―部分と全体のダイナミクス」ケストラー,アーサー(著)田中三彦/吉岡佳子(訳)

それは、もともと関連して存在していながら、別々に取り扱われてきた概念、事実、脈絡などを組合わせ、関係付け、統合するものである。
「この雑種交配こそ創造性の本質なのだ。」と述べて、エールステッドが電気と磁気の相互作用を発見した事例などを挙げている。
ユーモアとウィットの創造性についても論じている。
「ベルグソンやフロイトの理論を含め、これまでの理論はユーモアを孤立した現象とみなすばかりで、喜劇と悲劇、笑いと泣き、そして芸術的インスピレーション、喜劇的創造性、科学的発見の間にある密接な結びつきに光をあてようとはしなかった」が、科学も芸術も喜劇も、その創造性においては共通の基本的パターンがあるという。
「これまで関連することのなかったべつべつの精神的構造を統合し、新しい統一体からインプットした以上のものをえる、それが科学的創造性である」とし、この活動をユーモアの分析から始める。
というのも「創造のプロセスがはっきり姿を現すのは、ユーモアとウィットである」からで、ユーモアの理論で「ズレの理論」といわれるものをバイソシエーション(bissociation=associationの“bi-”で「二つからの連想」)という概念で説明する。
一つの思考基準(単一平面での思考)とかかわるのをアソシエイト(associate)と呼び、二つの思考基準にかかわることをバイソシエイトと言う。
創造的な思考というのは互いに相いれない二つの領域、二つの論理や基準が同一平面上で活動する精神活動である。
関連のなかった別々の精神的活動が結合して、新たなアイディアが生み出される訳である。
「巧妙なジョークの創造にも、またそれを理解する『再創造』の活動にも、ひとつの平面から他の平面へ瞬間的に飛びうつるという、愉快な心のゆらぎがある」といい、ユーモアはこの「瞬間的に飛びうつる」ことが大事だというのだ。
固定観念からの解放が大切なのだと説く。
シュールレアリズムではデペイズマン(転置)と呼ばれる手法である。
最も有名な「解剖台の上のミシンと雨傘の偶然の出会いのように美しい」というように、事物を非日常的で偶然的なコンテクストに置くことである。
ごく最近では椎名林檎の「無罪モラトリアム」「勝訴ストリップ」などがある。
動にも、ひとつの平面から他の平面へ瞬間的に飛びうつるという、愉快な心のゆらぎがある」といい、ユーモアはこの「瞬間的に飛びうつる」ことが大事だというのだ。
固定観念からの解放が大切なのだ。
俳句では「取り合わせ」とか「二物衝撃」とか「配合」と呼ばれる手法も同じである。
一つの素材しか使わなければ「一物仕立て」というが、例えば、「くろがねの秋の風鈴鳴りにけり 蛇笏」は一物で、「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 子規」などというのは二物である。
俳人の坪内稔典は「俳句レッスン」(『國文学』2001年7月号)で「取り合わせで作る俳句は、作者の感動を表現するというよりも、作った俳句によって感動する俳句。
つまり、感動の発見装置としての俳句だ。
小学生に、感動とか思いを五七五で表現せよ、と言えば困難を強いることになるが、取り合わせだったらとても気軽に出来る」といい、更に「取り合わせは、合理的に説明のつく場合は面白くも何もないが、子どもたちは五七五音に制約されてかなり強引に取り合わせを行う。そのためにしばしば突拍子もない取り合わせが行われ、片言的な俳句が出現する」「取り合わせる両者の関係があまりに近いと平凡な作品になる。逆に遠すぎると、読者には読み取りが難しくなる」と書いている。
異質な物と物、物と人、人と人を組み合わせることによって、新しい、力強いものが生まれてくるのである。
そうすることによって、放送局と視聴者が結び付くし、視聴者は視聴者なりの視点で僕らが思いもつかない別のものとつなげて文化を考えはじめるかも知れない。
これはファンタジーでも同じだ。
ジャンニ・ロダーリは、「ファンタジーの文法 物語創作作法入門」(ちくま文庫)の中で異化効果を生み出す技術<ファンタジーの二項式>という考え方を示している。
「ファンタジーの文法―物語創作法入門」(ちくま文庫)ロダーリ,ジャンニ(著)窪田富男(訳)

ファンタスティックな物語が始まるのは、二つのある距離をもったことばのぶつかり合いからだというのである。
例としてガラス瓶と山、で、山の中のガラス瓶、ガラス瓶でできている山、ガラス瓶のなる樹のはえている山、ガラス瓶に入った山、などなどと発想していって、その違和感のようなものから、物語を広げていくと言うような発想法である。
「犬」と「たんす」で考えればたんすを背負った犬がいれば面白いし、またたんすの中に犬がいればそれもまた面白い。
何か物語が動き出す予感が生まれる。
ロダーリは、「闘争のないところに生はない」また「想像力とは精神のことであり、精神が誕生するのは闘争の中であって、平穏の中ではない」と語っている。
同じようなことを、詩人のシェリーは「理性は物事の間にある差異を、そして想像力は物事の間にある類似を尊重する」という言葉で語った。
「バタフライ効果」というのがカオス理論で知られている。
北京のチョウの羽による空気の動きが、めぐりめぐってニューヨークで大暴風を巻き起こすという効果である。
これくらいの意外性がほしい。
詩人のイェイツは「われわれは他人と口論してレトリックを作り、自分と口論して詩を作る」という台詞を吐いたが、足し算ではなくて、かけ算になるような出会いが求められる。
サイードは、「オリエンタリズム」「文化と帝国主義」で「対位法的」(contrapuntal)思考が大切だというが、二つを融合させるのではなく、互いに響き合うようにすることが大切なのだ。
「オリエンタリズム〈上〉」(平凡社ライブラリー)サイード,エドワード・W.(著)今沢紀子(訳)
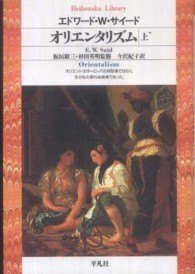
「オリエンタリズム〈下〉」(平凡社ライブラリー)サイード,エドワード・W.(著)今沢紀子(訳)
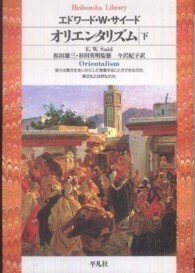
「文化と帝国主義〈1〉」サイード,エドワード・W.(著)大橋洋一(訳)

「文化と帝国主義〈2〉」サイード,エドワード・W.(著)大橋洋一(訳)

バッハの『フーガの技法』『二声と三声のインベンション』『平均率クラヴィア曲集』などが、右手と左手の旋律がそれぞれ独立して旋律を奏でながら、同時に掛け合いをするように、共鳴させるのだ。
「文化と帝国主義」の中でサイードはディッケンズ、コンラッド、ジェイン・オースティン、キップリング、カミュらの小説に「対位法的読解」(contrapuntal reading)を施し、これらの小説の時代背景である「帝国主義」(=植民地の存在)が、抜き差しがたく織り込まれているさまが、明らかにしている。
ある場合は、「帝国主義」の残忍さに異議が唱えられ、ある場合は植民地の存在はプロットの背景として簡単に触れられるに過ぎないが、どんな場合でも、作品と「帝国主義」の所属関係(アフィリエーション)が色濃く刻印されている。
「西洋/非西洋」という創られた図式、それが「文明/未開」、「正義/不道徳」といった図式に容易に変遷していくこと、植民地が永遠に続いていくだろうという根拠も反省もない予感、それらのものを共有する文学と「帝国主義」は、互いに滋養・強化する共犯関係を免れないことになる。
「対位法的思考」から「ポストコロニアル」(コロンブスが「インディアン」を、ではなく「インディアン」がコロンブスを発見したと考える)の思想が生まれる。
「対位法的思考」というとものすごく難しく聞こえるが、日本の特に笑いの文化の基礎にあるボケとツッコミ(大夫と才蔵とも言い換えることができる。
鶴見俊輔『大夫才蔵伝-漫才をつらぬくもの』(平凡社1979)のことである。
「大夫才蔵伝-漫才をつらぬくもの」鶴見俊輔(著)

ツッコミが垂直思考で、ボケが水平思考なのである。
ツッコミばかりでは何も生まれない。
うまくボケが入ることで物事が進むし、新しい観点が生まれるのである。
シェイクスピア劇にも道化はしばしば登場する。
あんまり出しゃばりすぎて王に叱られて言うせりふが「無理が通れば道化ひっこむ」。
僕らは王様ではないが、せめて心に道化を「お抱え」にするゆとりが必要であろう。
小さい頃、小学校の国語の教科書に載っていたのが豊田佐吉の話だった。
イギリスの織機の展示会を何度も見に行って同じものを作り上げたという話なのだが、日本ではこうした追随ばかりが奨励された。
「ファースト・ペンギン」という英語がある。
最初に海に飛び込んだペンギンのように、危険をかえりみず未知の分野に挑戦した人をさすという。
米国のゲームソフト業界には、それにちなんで「ファースト・ペンギン賞」などというものがある。
独創的な新機軸のソフト開発者に授与される。
最初にナマコを食べた人のように、勇気のある日本人が出てこなければならない。
「ナマコの眼」(ちくま学芸文庫)鶴見良行(著)

セレンディピティは、古くは、「コロンブスの卵」としても知られる。
ケクレのベンゼン環の発見(ロンドンの二階建てバスに乗っていた時に、互いに尻尾をくわえた蛇の夢を見た)やウォルター・ハントの発明した先端に穴の開いたミシン針の発明(追ってきた原始人の槍の先に穴が開いていた夢!)など分かると当たり前のことに思えるが、そうではない。
コロンブスは、1493年に新大陸から帰国すると、バルセロナの宮廷で盛大な歓迎式典の招かれたが、皆がみな彼を賞賛したわけではない。
「誰でも西へ行けば陸地にぶつかる。当たり前のことだ」と言って、水を差す人が出はじめた。
その時、コロンブスは卵を指し示し、「誰かこの卵をたてることが出来る人はいますか」と謎をかけたのである。
何人かが挑戦してみたが、誰もたてることは出来ず、しまいには怒り出す人が出る始末である。
コロンブスは、卵を引き寄せ、テーブルで軽くたたいて卵を立てて見せたのである。
これがいわゆる「コロンブスの卵」(Columbus' Egg)といわれる出来事だ。
ところが、これはペンゾーニの「新世界史」(1565年)の中で紹介されている話だが、ヴォルテール(「習俗論」第145章)にいわせれば、コロンブスの前にブルネッレスキが行ったことだという。
ブルネッレスキ(ブルネレスキ)というのは一点透視法(透視画法)の「発明者」と言われ、フィレンツェのドゥオーモ(クーポラ)を完成させた男だが、この難しい建築のコンクールが行われた時に「画期的アイデア」をひっさげて乗り込んだ。
ところが、アイデアが盗まれるので模型は見せられない、という。
「平らな大理石に卵を立てられる者がいたら、その者の独創性を信じて任せたらいかがでしょうか」ということになり、他の応募者がことごとく失敗する中、ブルネッレスキはためらうことなく、卵の端を潰して大理石に立てた。そんなのは誰でもできる、というのに対して、ブルネッレスキは「私が模型を見せたら、おまえたちは同じように、自分たちもそういうふうにクーポラを造るつもりだったと答えるだろう」と笑い飛ばしたという。
コロンブスよりも半世紀も前のことで、ジェノヴァ生まれのコロンブスはどこかでこの話を聞いていた可能性がある。
ちなみにブルネッレスキのアイデアというのはクーポラの円蓋を二重にするというものだった。
厚さ4メートルの円蓋の上に屋根の部分になる厚さ80センチの外屋根を載せて、軽量でしかも大きな中空の円蓋を載せることに成功したのだ。
「誤解」のところでも書いているが「コロンブスの卵」には後日談がある。
立春に生卵が立ったという「新発見」が1947年の立春直後に話題になったことがある。
東京、上海、ニューヨークで成功したと当時の新聞が報じた。
当時の専門家は「寒いと中味の密度が濃くなって重心が下がるから」「中身が流動体だから倒れない」などと原理らしきことを解説するものの、根拠が弱い。立春以外はどうなのかもあいまいだった。
物理学者の中谷宇吉郎が冷静な目で分析して実験を試みた(「中谷宇吉郎随筆集」岩波文庫)。
「中谷宇吉郎随筆集」(岩波文庫)中谷宇吉郎(著)樋口敬二(編)

結論は、いつでもちゃんと立つのである。
「コロンブスの卵」のように底を割らなくても底には三脚や五徳のような微小の突起があり、狭い範囲で根気良く中心を探せばいいわけだ。
「何百年の間、卵が立たなかったのは、皆が立たないと思っていたから」「人間の歴史が、そういう瑣細な盲点のために著しく左右されるようなこともありそうである」。
常識を疑ってみる。
気になることは自分で確かめる。
大量の情報があふれる現代こそ、その姿勢が生きてくる。
もう一つ、大切なことは卵が立つということを知っていて立たせるのは容易だということだ。
「立つ」という仮説さえあれば、後は簡単なのだ。
ちなみにルネサンスは、イスラム経由でギリシャ・ローマの古典知識が西欧に注入されたのであって、必ずしも内在的な要因で生まれたのではない。
外からの目がルネサンスを生んだのである。
また、1492年はコロンブスのアメリカ到達の年であるが、この年はまた西欧からイスラム勢力が追い落とされた年でもある。
スペイン最後のイスラム拠点だったグラナダが落ち、イサベル女王の財布に冒険航海支援の余裕が生まれたから、コロンブスの発見が生まれたのである。
【中心と周縁】
中心と周縁をめぐる人類学的考察を知っているだろうか?
これは最初に社会学者シルズが1961年の論文「中心と周縁」で明らかにしたと言われるが、体系化したのはアメリカのビクター・ターナーや、特に日本の文化人類学者・山口昌男である(「文化の両義性」「文化の詩学」岩波)。
「文化と両義性」(岩波現代文庫)山口昌男(著)

「文化の詩学〈1〉」(岩波現代文庫)山口昌男(著)

「文化の詩学〈2〉」(岩波現代文庫)山口昌男(著)

中心というのは、制度やパラダイムやエピステーメー(フーコーの用語でいえば、意識しにくい文化的な枠組み)の中心をいい、周縁というのは中心から最も離れたところを指す。
一つのパラダイムができると「通常科学」として長らく通用するのだが、そうしたパラダイムや制度の中心にいると、それが行き詰まった時に立ち行かなくなる。
つまり、文化のダイナミックな変化、文化変動は文化の中心部分と周縁部分の二つの綱引きによって力学的に変化するというものである。
なお、パラダイムはトマス・クーン「科学革命の構造」(みすず書房)の用語で、科学は、段階的に変化するのではなく、「通常科学」から革命を経て不連続的に起きると考えるものである。
「科学革命の構造」トマス・サミュエル・クーン(著)中山茂(訳)

例えば、天動説から地動説への変化、燃焼に関するフロギストン(燃素)説から酸化説への変化など。
ただ、クーンはその後、「解釈的基底」(hermeneutic basis)と呼びかえ、更に紛らわしいと「学問領域のマトリックス」(disciplinary matrix)という用語を提案した。
でも、パラダイムをパラダイムと呼ぶパラダイムができてしまっていて広く「思考の枠組み」という意味で使われることになった。
科学は連続的に進歩すると考えるのを「ホイッグ史観」というが、断続的な科学革命によってパラダイムは転換し、その前後では、使用される色々な概念は「通約不可能」であって、相互翻訳は不確定に留まるとした。
あらゆる科学的理論は「仮説」だ。
目の前の現象を説明するためにとりあえず作ったお話なのだ。
だから、アインシュタインは、科学者の栄光とは「彼の立てた仮説が、あとに出されたさらに包括的な仮説の中に、限定的事例に打倒する理論として引き続き居残れること」にある、と語った。
先に述べたように、カール・ポパーは科学的精神というものが自説を傍証する事例ではなく、自説を反証する事例を優先的に探索するような知性のあり方のことである、と書いている。
科学というのは反証可能性(falsifiabirity) がある。
つまり、一つの反例を挙げればその理論が崩れる、そうした反例を挙げることが可能性としてあるものが科学的だという。
科学は、帰納的ではなくて、演繹的だという考えにもなっていくのだが、何でも説明できてしまい、反例を出しようがないものは科学ではないということになる。
占星術や精神分析理論は、反証不可能であるから非科学(pseudoscience)であり、マルクスの歴史理論も、当初は反証可能性を備えており、実際に反証されたのだが、その後継者達によって、結局反証できなくなってしまったと批判している。
フロイト理論も似たようなものかもしれない。
日本人の多くにとって宗教と科学は矛盾するものだと思えるが、欧米の科学者はそんな風には思わないらしい。
処女懐胎とか多くの奇蹟などが出てくる聖書をトンデモ本だと誰も思わないのである。
ケプラーの法則を発見したドイツのヨハネス・ケプラーは、天文学と占星術の双方をこなしていた。
ハレー彗星を「発見」したイギリスの天文学者E・ハレーは、地球空洞説(hollow Earth theory)を唱えたことがある。
空洞の中には三つの内球があり、発光する大気に満たされている。
北極のオーロラはそのガスが地上に漏れ出したものだという。
この空洞説は、その後も20世紀初めまで何度か現れ、北極には巨大な穴があって地底世界に続いていると唱えられた。
冷凍マンモスもその証拠だというのだが、飛行機の北極探検でそんな穴はないと分かると、さすがに提唱者は消えた(M・ガードナー「奇妙な論理1 だまされやすさの研究」ハヤカワ文庫)。
「奇妙な論理〈1〉―だまされやすさの研究」(ヤカワ文庫)ガードナー,マーティン(著)市場泰男(訳)

「奇妙な論理〈2〉なぜニセ科学に惹かれるのか」(ヤカワ文庫)ガードナー,マーティン(著)市場泰男(訳)

ジュール・ヴェルヌの「地底探検」は、アイルランドの死火山の噴火口から地底世界に侵入し、恐竜や原始的な生活を送る人類と遭遇するというSFだが、ハレーなどの説をうまく取り入れたものだった。
「地底旅行 (改版)」(角川文庫)ヴェルヌ,ジュール(著)石川湧(訳)

ロバート・アーリック「トンデモ科学の見破りかた―もしかしたら本当かもしれない9つの奇説」(草思社)という本が出たが、私には、次のどれもトンデモ科学のように見える。
「トンデモ科学の見破りかた―もしかしたら本当かもしれない9つの奇説」アーリック,ロバート(著)垂水雄二/阪本芳久(訳)

○銃を普及させれば犯罪率は低下する
○エイズの原因がHIVというのは嘘
○紫外線は体にいいことの方が多い
○放射線も微量なら浴びた方がいい
○太陽系には遠くにもう一つ太陽がある
○石油、石炭、天然ガスは生物起源ではない。
○未来へも過去へも時間旅行は可能
○光より速い粒子「タキオン」は存在する
○「宇宙の始まりはビッグバン」は間違い(寅さんは「物の始まりが一ならば国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、助平の始まりがこのオジサンっての」・・・・・・)
アーリックはトンデモ度を分けている。
トンデモ度ゼロは「そうであってもおかしくない」。
トンデモ度一は「おそらく真実ではないだろうが、誰にもわからない」。
二は「真実でない可能性はきわめて高い」、三は「ほぼ確実に真実でない」。
9テーマのうち、トンデモ度三は3テーマ。
そしてゼロも3テーマである。
ちなみに「タキオン存在説」も、トンデモ度ゼロだそうだ。
つまり、トンデモ科学か否かは、未来の判断に任せるしかないのだ。
立派な科学でもトンデモ科学になることもある。
車いすの天才物理学者スティーブン・ホーキング博士は、強い重力で何でも吸収してしまう天体ブラックホールについて、光さえ抜け出せないと考えられていたのを、1970年代に提唱した理論の中で「ブラックホールは少しずつ光を放射しながら、最後には蒸発して消えてしまう」と主張し、物理学界に大きな衝撃を与えた。
博士は、同時に、光はブラックホールから漏れ出すものの、吸収された物質の姿や性質などの「情報」は破壊され、2度と外部に出ることはないとも予言した。
だが、この予言は、「情報が完全に消滅することは無い」とする物理法則(量子論)と矛盾するため、ブラックホールを巡る「情報のパラドックス」と呼ばれ、論争の的になっていた。
97年には、ブラックホールの「裸の特異点」の存在をめぐって、研究仲間のプレスキル・米カリフォルニア工科大教授らとの賭けに負け、博士が「裸」を覆うTシャツを贈ることになった。
2004年には、プレスキル教授に「ブラックホールからはいろんな情報を取り出せる」という意味を込めて百科事典を贈ったという。
さて、科学革命はどこで起こるか?
クーンは、「変革者はふつう非常に若いか、危機に陥っている分野に新しく登場した新人であって、古いパラダイムで決定される世界観やルールの中に他の人たちほど深く埋没されていない」と書いている。
つまり、周縁から起きるのである。
例えば、明治維新というのは、江戸やその周辺の人々によって行われたのではない。
「薩長土肥」という江戸から遠く離れて暮らしている人々によって遂行されたのである。
学問も多くの場合、中心にいると全体がぼけてしまってわからなくなことがある。
中心には制度やパラダイムやエピステーメーを破壊する力が失われている。
新しいものはその中から生まれるのではない。
「トリックスター」などの「文化英雄」が周縁からやってきて中心を破壊し、創造する。トリックスターは周縁から現れる。
そして、中心の秩序を破壊して、新しいものを想像していく。
坂本龍馬などは、トリックスターの典型である。
トリックスター(“trickster”で“-tar”ではないが、これは“spinster,gangster”と同じ「人」の意味)というのは、神話や民話に登場するいたずら者のことをいう。
道化の神話的形象といえるが、これは例えば、西アフリカにおけるいたずら者の神や、アフリカ全土で語られる野兎や蜘蛛、亀といった動物であったりする。
北米インディアンの神話においても、コヨーテやワタリガラスなどの動物になったり、人間の姿をとったりしている。
彼らには共通して、機知、機転、狡猾さ、気まぐれ、悪ふざけなどの性格がみられる。
また、この世に混乱と破壊を引き起こすと同時に、しばしば混乱のなかから未知の文化要素を生み出し、破壊のあとにふたたび新しい秩序をもたらすという文化英雄的役割も果たしている。
ヨーロッパ絵画も日本の浮世絵やアフリカの彫刻など周縁を取り込むことで新しいものを生み出している。
音楽でも、以前、エンヤを代表とするケルト音楽が人気であるが、そのちょっと前は中南米で、その前はアフリカだった。
スペインの歴史家・コラールは、「ヨーロッパの略奪-現代の歴史的解明-」(未来社)の中で、ヨーロッパ文明は自身の本質である技術文明を他文化に略奪されてしまったのだと言う。
「ヨーロッパの略奪-現代の歴史的解明-」ディエス・デル・コラール(著)小島威彦(訳)

ヨーロッパが略奪したのではなく、その逆なのだ。
スペインはある時代、西ヨーロッパをリードして政治的、経済的、軍事的、文化的「中心」として君臨していた。
その後、没落して周縁=辺境になってしまったが、西ヨーロッパも20世紀には中心の座から降りてしまった。
情報を発信するという立場は、逆に考えれば、情報が奪われるということでもある。
同じような目で、東の中心で「中華思想」をもっていた中国にも当てはまることだ。
中心は文化の構造が硬直化してさまざまなレベルで生産力を失って停滞していく。
そして周縁が・・・・・・
もっと卑近な話をすれば、21世紀の日本経済は、既に、東大―大蔵省―官僚などの中心では救えなくなっている。
更に、中心商店街の衰退と郊外店の振興を考えればよく分かるだろう。
ラブホテルが林立するのも周縁の地域である。
非日常的空間で、匿名性に満ち、心理的にも解放感を醸す場所になっているのである。
中心というのは垂直思考で周縁というのは水平思考と言い換えることもできる。
周縁の思考、すなわち「ポストコロニアル」の思想をセレンディピティと言うこともできる。
言語の面でも同じことがいえる。
中心 周縁
大人の言葉 子どもの言葉
日常語 詩的言語
共通語(標準語) 方言
男性語 女性語
中心にあるものは既にできあがっている秩序ということになり、逸脱できない。
保守的で安定するとマンネリズムという沈滞に陥ってしまう。
周縁にあるものは不安定で、まだ新しいものが生まれる可能性がある。
周縁が言葉や文化を活性化して、中心になっていくことがあるが、それが安定して沈滞すると、また周縁を取り込む必要が生まれてくる。
言語の場合は、揺れが生じて、中心が揺るがされ、そのうち、交替していくことが多い。
また、子どもの言葉に新鮮さを感じるのは中心的な規範・基準などから離れた言い方で、これを意識して行えば詩の言葉になる。
何が正統で、何が異端か分からない「ポストモダン」な状況が続いているが、「パラダイム・ロースト」の時代を迎えていることになるのだ。
【M・タイプとP・タイプ】
論文やエッセーを書くときに、直線的に結論に向かって書いていく人がいた。
それでいて、しっかりとした文章になるから不思議である。
論理の破綻がなくて、内容がきちんと伝わった。
ソシュールの物言いをすれば、通時的(ディアクロニック“diachronic”)な流れで書いていることになる。
書き方は、人に依って、結論から書いたり、サビから書いたりと、違いが見られるのが面白い。
共時的(サンクロニック“synchronic”)な書き方だといえる。
アングロ・サクソンにとって時間を守ることは、強迫観念に近いが、スペインなどでは遅刻がステータス・シンボルになっていて、より遅刻した方が地位が高いとされる。
日本も後者で、女性は男性を待たせた方が地位の高さを示せるようだ。
ただ、スペイン人でも昼食の時間だけはよく守る。
というのも、ビジネスの時間は「世俗的な時間」にすぎないが、昼食の時間は「神聖な時間」だからだ。
時間の感覚に二つのタイプがあると人類学者のE・T・ホールはいう(Hall, E.T. 1983 The Dance of Life. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday.)。
M・タイプ(Monochronic Type)とP・タイプ(Polychronic Time)である。
M・タイプの人は予定を立てることや敏速さを重視する。
時計やカレンダーの時間を重視する北アメリカのような文化はM・タイプである。
一度に一つの物事だけを行う。主に企業、政府、専門的職業、エンターテイメント、スポーツといった公的世界を支配している。
時間が一直線に過去から未来につながっているように捉えられている。
当然、時間は節約したり、借りたり、分割したり、浪費したり、無駄にしたり、つぶしたりすることのできる「もの」になっている。
「時は金なり」というのがアメリカ建国の父・フランクリンの言葉だることからも想像できよう。
P・タイプの文化ではものごとが起きるという、そのことが重要なのであって、時計の時間やスケジュールに固執しない。
地中海の人々が典型例。現在のスケジュールを守ると言うより、人間のかかわり合いと相互交流に力点を置く(人間、人間関係、そして彼らの存在の核である家族を志向)。
人が何かしていることや、していることが成就することが大切なのである。
したがってM・タイプの人に比べて時間厳守はあまり重要ではなくなる。
つまり大切だと思うモノを完了させるには予定したことや約束を容易に反古にすることもある。
家庭、特に女性を核として全てが転回しているような伝統的な家庭ではポリクロニックな時間が優勢である(子どもを何人も育てる)。
M・タイプを垂直思考、P・タイプを水平思考と考えることもできる。
同時に何かを進行するというのは、M・タイプで垂直思考の人にはできないことである。
M・タイプは、一度に一つのことだけに集中できるが、コンパートメント(小部屋)化のために自分たちの活動をより大きな全体の一部であるというコンテクストのなかで考えることが少ない。
コンパートメント化は、コンテクストを縮小させ、自身と他者を疎外する。
組織においてもP・タイプは関わり合いと相互交流に力点を置くため、構造は浅く単純。
どんなに脈絡もない情報の断片も集められ、記憶される。
いったん仕事を分析してからは、的確な情報によって驚くほど多くの部下を掌握できるが、M・タイプは一人または二人の人間を集団から切り放し、特定の人、あるいは2、3人の人との関係を密接なモノにする。
例えば、政府の部署は統合する方向をたどり、大きくなるにつれ閉鎖的になり、それ自身の構造に盲目的になる。
(ダムを造ることに専念しすぎて環境破壊を招くなど)作業をスケジュール化し、仕事の各部分の分析は個人にまかせる。
そのため、組織の成員の人間性無視が際だつようになる。
従って、P・タイプや水平思考というのは人間回復の思想なのである。
【考えるということの姿勢】
考えるためにも姿勢が大切だ。
経済学者の内田義彦は、「学問への散策」(岩波書店)で次のように書いている。
「学問への散策」内田義彦(著)

「社会科学にしろ、何にしろ、およそ考える場合の基本姿勢には二つあると思う。
一つはうつむいた姿勢であり、一つは天井をむいてポカンとしているそれである。
(中略)
仕事をしている場合、夜中にふっといい考えが浮かぶことがある。
新しい土俵の誕生であり、既知の事実との新たな遭遇である。
が、そのままではせっかくの土俵も、思い出した事実も、雲散霧消してしまう。
あおむきの姿勢は土俵を外すには適合的でも、土俵の中で煮つめていくには不適当なのだ。
とっさに起き上がって集中しうる姿勢となり、書くことである程度ディベロップしておく。
少なくともICに吹き込んでおく。
突撃の態勢に移るわけだ。
そのばあいには絶対に一度きめた土俵を動かしてはいけない。
これがコツなのであって、絶対に土俵を動かしてはいけないという無理から、実は、諸事実と土俵の衝突がはっきりしていて、そこで、土俵を外すという次の作業が出てくるのである。
その二つが基本姿勢で、その基本姿勢の衝突をうまく捉えたのが「ソファのパイプに学問の本質がある」というマックス・ウェーバーの言葉である。
ウェーバーの言葉を覚えなくてもいい。
肝心なのは、それぞれの姿勢がもつ働きを、肉体感覚として、鮮明に覚えておくことである。
日本の社長の椅子が天井にむき易く出来ているのは、土俵を外して考えるのに適合的なためか、それとも無能者が威張るのに適合的なためなのかよく知らん。
学者についていえば、常にうつむいているという姿勢で私が想像するのは、思考停止のそれである。
というのはこの姿勢は受動的思考のそれであるからだ。
いずれにしても自然体とは縁がない。」
【専門と学際】
ノアの方舟は、素人が造り、タイタニックは専門家が造った。
何かの専門家というと、それだけで完結しているような気がするが、専門家だから間違わないということはありえない。
セレンディピティを可能にするには、学際的(interdisciplinary)な考えを持つことも大切である。
人類学と言語学とか近い分野だけでなく、まるで違う分野と考えを交信しあうことも重要だ。
商売の方では「異業種交流」が盛んになっているが、学問の方はまだまだ「たこつぼ」に入ったきり、一歩も踏みだそうとしない学者も多い。
初めての自動焦点カメラを開発する時に、焦点を調整するモーターがなかなかコンパクトに納まらず、困ったという。
開発していたのは、電気系の技術者だったそうだが、そこへ機械系の技術者が来たら、「どうしてゼンマイを使わないのだ」と言われて、ゼンマイで廻すことで開発に成功したという。
電気系の人は、モーター、機械系の人はゼンマイが最初に思い浮かぶものらしい。
いずれにしろ、自分の固い殻に入っていては何も生み出せない。
学際的というと大げさだが、サイードは、「知識人とは何か」(平凡社)で「知識人とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらには権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である」といい、知識人には二つの道が開かれている。
「知識人とは何か」(平凡社ライブラリー)サイード,エドワード・W.(著)大橋洋一(訳)

専門主義とアマチュアリズム。
しかし、「一般的な教養を犠牲にして、人を特定の権威なり規範的な考えかただけに迎合させる」専門主義を選ぶと「専門家という地位を確保するためにすべてを犠牲にした結果、自発性の喪失がおこり、他人から命じられることしかしなくなる」。
そしてこれに「ゆさぶりをかけるもの」がアマチュアリズムだという。
山口昌男は日本の「文化英雄」の一人だと思うが、際だった特徴は学際性、つまり、知的横断性、クロスオーバーだった。
まっとうな学者は、領域侵犯などしないものだから、嫌う人も多かった。
しかし、社会に新たな価値を創造するためには、山口のような「いかがわしさ」がどうしても必要だった。
これについて四方田犬彦が次のように反論している。
「専門外のことについて思い切った発言をすることは、気楽なように見えて、実のところひどく危険で勇気のいることなのである。
第一、どこから批判や反論の球が飛んでくるのか、見当がつかない。
たとえばぼくは社会的には映画史が専門ということになっているが、それでは在日韓国人や国際紛争の問題について発言するとき、専門外のことだからといって気楽かというと逆である。
いったいどんな人間によって自分の書いたものが読まれ、理解され、あるいは誤解されるか、というリスクを背負いながら書かないわけにはいかない。
その点、国際関係論の専門家は学問という「客観性」に守られ、多くの専門語という武器を携えているかぎりにおいて、ぼくよりもはるかに安全で安定した地点から発言できるだろう。
だが、とぼくはいわせてもらおう。
専門(あるいは業界といいかえてもいい)という砦に閉じこもっているかぎり、どうしても口にしてはならない言葉が存在している。
それは「王様は裸だ!」と叫ぶことである。」
自戒を込めていうと、エンジニアとして一つの職業だけを続けていると、その中の思考法にすっかり浸かってしまうことがある。
違う世界で、少しでも仕事をすると、エンジニアとしての自分の位置が見えてくることがある。
自分のいる業界になれてしまって、視野が狭くなる。
「二足のわらじ」と昔はいったものだが、複眼的思考を持つ必要がある。
別に副業に就かなくても、違う業種の人や、価値観の人と話すことは大切だ。
ホームページを持つことも複眼的思考の鍛錬となる。
一つの趣味なりを前面に出すと、必ず同調する人がいて、その人はまるで別の観点から趣味を見ていることがある。
少なくとも、他流試合で揉まれることになる。
欧米では、科学者の「アウトリーチ活動」という言葉が日常的に聞かれる。
科学者が市民との対話を通じて市民のニーズや疑問、不安を認識することまで含めた活動を意味するという。
英国では、科学研究助成機関が研究者にアウトリーチ活動を義務付けたり、研究者の昇給基準にしたりしている。
米国でも成立したナノテクノロジー法がアウトリーチ活動をナノテク研究の一環と位置付けたように、重要視されている。
日本でも「出前授業」や「一般公開」といった形で実施されてきたが、どちらかといえば、単なる一方向の広報活動になっていることが多い。
むしろ、欧米の「カフェ・シアンティフィック」のように、カフェやバー、書店などで少人数の参加者が科学者と気軽に対話する試みが望ましい。
生活に密着した場で科学を語りあうことは、市民が科学を文化として楽しむきっかけにもなる。
そして、新たな発見につながっていくはずだ。
【サファリとテンベア】
Mais le vrai voyageur sera ceux qui partent pour partir.----Baudelaire(ただ行かんがために行かんとするものこそ、真の旅人なれ---永井荷風『あめりか物語』のエピグラフ)---ボードレール「旅」
「あめりか物語 (改版)」(岩波文庫)永井荷風(作)
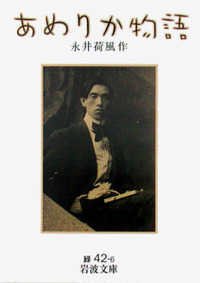
東アフリカの共通語、スワヒリ語に「サファリ」(safari)という言葉と「テンベア」(tembea)という言葉がある。
サファリというのは、「狩猟狩り」だと思われているが、もとは目的を持った旅である。
これに対してテンベアというのは目的をもたずに放浪する旅である。
トイレに行くのもサファリなのである。
目的だけをめざして行くサファリは、途中にかいま見る景色や邂逅する人との触れあいが少ない。
目的を持たずにさまようテンベアでは、いつどこにたどり着くか分からないが、その時その時の出会い、発見に満ちた旅になる。
「路上観察学」というのも「トマソン運動」というのもテンベアの思考がなければ生まれてこない。
「路上観察学入門」(ちくま文庫)赤瀬川原平/藤森照信/南伸坊(編)

そして、思考も垂直思考、水平思考に倣ってサファリ型とテンベア型に分けることができる。
思想的にも「お散歩」することが大切なのである。
高速道路を道なりに進むことではない。
将棋の羽生善治に「高速道路理論」というのがある。
過去の対局の棋譜がデータベース化されており、局面に応じて、どの棋士がどんな手を打ったかがすぐわかる。
定跡(囲碁では「定石」)や手筋の研究も容易になった。
その結果、ある程度の強さまでには、時間がかからずに到達することができる。
高速道路を突っ走るようなものだというのだ。
問題はその先で高速の下り口まではたどり着けても、そこで大渋滞に巻き込まれたかのように、先へ進むことができないでいる。
下の道をゆっくり散歩できる気力をもっていないといけないというのだ。
確かに!
移動というのは目的地に行くだけではなかったはずだ。
ウンベルト・エーコは、「エーコの文学講義」(岩波)の中で「なにか重要な、もしくは魅力的なことがおころうとしているときには、道草の技量を磨く必要がある」といい、「森は散策の場所です。狼や人喰い鬼から逃れるためにどうしても抜け出る必要がないのなら、のんびりするのも悪くありません。木立ちのあいだを抜け、草むらを彩る光をながめたり、苔や茸や下草の様子をじっくり調べたりして。のんびりするというのは時間を無駄にすることではありません」と話している。
「エーコの文学講義 - 小説の森散策」ウンベルト・エーコ(著)和田忠彦(訳)

民俗学者で旅の達人だった宮本常一も大正12年、故郷から初めて大阪に働きに出るとき、父親から十カ条の旅の心得を教えられた。
「宮本常一の旅学―観文研の旅人たち」福田晴子(著)宮本千晴(監修)

その第一が「汽車の窓からよく外を見よ」だった。
田や畑に何が植えられているか。
育ちはどうか。
村の家が大きいか小さいか。
駅の荷置き場にどんな荷が置かれているか。
参考までに、宮本善十郎さんの言葉「父の十箇条」を紹介しておく。
(1)汽車に乗ったら窓から外をよく見よ、田や畑に何が植えられているか、育ちがよいかわるいか、村の家が大きいか小さいか、瓦屋根か草葺きか、そういうこともよく見ることだ。
駅へついたら人の乗りおりに注意せよ、そしてどういう服装をしているかに気をつけよ。
また、駅の荷置場にどういう荷がおかれているかをよく見よ。
そういうことでその土地が富んでいるか貧しいか、よく働くところかそうでないところかよくわかる。
(2)村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上ってみよ、そして方向を知り、目立つものを見よ。
峠の上で村を見おろすようなことがあったら、お宮の森やお寺や目につくものをまず見、家のあり方や田畑のあり方を見、周囲の山々を見ておけ、そして山の上で目をひいたものがあったら、そこへはかならずいって見ることだ。
高いところでよく見ておいたら道にまようようなことはほとんどない。
(3)金があったら、その土地の名物や料理はたべておくのがよい。
その土地の暮らしの高さがわかるものだ。
(4)時間のゆとりがあったら、できるだけ歩いてみることだ。
いろいろのことを教えられる。
(5)金というものはもうけるのはそんなにむずかしくない。
しかし使うのがむずかしい。
それだけは忘れぬように。
(6)私はおまえを思うように勉強させてやることはできない。
だからおまえには何も注文しない。
すきなようにやってくれ。
しかし身体は大切にせよ。
三十歳まではおまえを勘当したつもりでいる。
しかし三十すぎたら親のあることを思い出せ。
(7)ただし病気になったり、自分で解決のつかないことがあったら、郷里へ戻ってこい、親はいつでも待っている。
(8)これからさきは子が親に孝行する時代ではない。
親が子に孝行する時代だ。
そうしないと世の中はよくならぬ。
(9)自分でよいと思ったことはやってみよ、それで失敗したからといって、親は責めはしない。
(10)人の見のこしたものを見るようにせよ。
その中にいつも大事なものがあるはずだ。
あせることはない。
自分のえらんだ道をしっかり歩いていくことだ。
(宮本常一「民俗学の旅」講談社学術文庫、p36-38から引用)
「民俗学の旅」(講談社学術文庫)宮本常一(著)

今は、電車の中でもバスの中でもひたすら音楽を聴いてマンガを読んでいる人の何と多いことか。
散歩した時に見かけた花が、家でたまたま開いた雑誌で紹介されているということがある。
偶然なのだが、実は感性がそれだけ広がって、今まで見過ごしていた事柄にも関心が持てるようになったということだ。
川本三郎が「あのエッセイこの随筆」(実業之日本社)で書いているが、散歩というのは近代になって西洋から入ってきた。
「あのエッセイこの随筆」川本三郎(著)

江戸時代には、目的もなく街中をうろつく行為はさげすまれ、どんなに歩きまわっても何の収穫もないこと。
また、金を持たずに店頭をぶらつくことを「犬の川端歩き(犬川)」と言った。
明治時代になると、ステッキが散歩に欠かせないアクセサリーとしてはやり出した。
文学作品に登場する散歩者の早い例は、森鴎外「雁」や夏日漱石「三四郎」であるという。
漱石はロンドン留学中、紳士がステッキ片手に街を優雅に歩いているのをみてそれにならったという。
大佛次郎の『散歩について』という随筆もある。
それは知識人(高等遊民)やそれにならった学生だったという。
坪内祐三は、「古くさいぞ私は」(晶文社)の中で、アメリカの思想家ケネス・バークのキー・コンセプトの一つ、“perspective by incongruity”(「不調和による展望」とされるが、“incongruity”「ごちゃまぜ」)を「寄り道しながら見えるもの」と意訳して説明している。)
「古くさいぞ私は」坪内祐三(著)

寄り道していると、まっすぐの道に歩いていては気がつかない展望に出会う。
その展望は、寄り道した者だけが知る特別の展望だ。
まっすぐに道を歩いている時に見えるものは、もし見落としたとしても、いつでもガイドブックが教えてくれる。
しかし、寄り道で見える特別な展望は、そうはいかない。
大学で学ぶ学問も、そういうものだ。
教室での授業は、まっすぐな教えだ。
そのまっすぐな教えを、いかに効率よくさばいていけるのかの能力を、大学受験では問われる。
それはそれで人間に必要な能力だ。
人生のある時期を、そういう能力の錬成に費やすことは無駄ではない。
けれど、それだけでは、まあ、半分。
また、「ストリートワイズ」(晶文社)の中で「ささやかな未知」が大切だとして、福田恆存の言葉(新潮社版「小林秀雄全集」第十二巻「考へるヒント」の解説)を引いている(表記は変えてある)。
「ストリートワイズ」(講談社文庫)坪内祐三(著)

吾々が道を歩いている時、一里先の山道に目を奪う様な桜の大木があることを吾々は知らない。
そういえば、私も、東京/青山に、隔週で一年半、二泊三日の長期研修で来ていた時、散歩して坂を下りている時にいきなり、東京カテドラルが見えてきて、「なにごとにおわしますはしらねどもかたじけなさに涙こぼるる」と西行が伊勢神宮を前に感嘆したような気分になったものだ。
ドイツの科学者ヘルムホルツは「素晴らしいアイデアは、晴れた日にゆるやかな山の斜面を登っていく時によく現れる」と語っているという。
かつて「美人論」を書いた井上章一も散歩が好きだという。
「美人論」(朝日文庫)井上章一(著)

ある日、京都の河原町を歩いていたらカーネル・サンダースの人形の前で写真を撮っているアメリカ人を見つけて、この人形が日本にしかないことを知り、「人形の誘惑 招き猫からカーネル・サンダースまで」(三省堂)を書いた。
「人形の誘惑―招き猫からカーネル・サンダースまで」井上章一(著)

カントは、毎日同じ時刻に同じ所を散歩したので、町の人から時計がわりにされた。
女流作家のヴァーノン・リーは各国を遍歴して作品を遺したが、「地霊」というものを信じていた。
人間に対する観察眼が鋭いシェイクスピアも散歩が好きだったに違いない。
戯曲家のアーノルド・ウェスカーは『彼ら自身の黄金の都市』という劇で、主人公に「バッハの方がシェイクスピアより先に天国に着いたのではないか」といわせている。
もちろん、バッハ(1750年没)の方がシェイクスピアよりも遅く亡くなったのだが、シェイクスピアは寄り道が好きだったから、まっすぐ天国へは行かなかったのではないか、というだ。
知りたいことしか書いてないマニュアルに頼らず、「ささやかな未知」を探して生きたいものだ。
日常を非日常の目で眺めることが大切だ。
異人の目で物事に接することが大切だ。
今和次郎の考現学や赤瀬川原平らの路上観察学もそうした流れから生まれている。
赤瀬川は、「奥の横道」(日本経済新聞社)の「見える竜安寺と見えない竜安寺」の中で次のように書いているが、赤瀬川はお寝しょがひどくて修学旅行に行かなかったという。
「奥の横道」赤瀬川原平(著)

この竜安寺というのは、教科書その他であまりにも知りすぎているので、それをもう一度確認するという感じがあるのは否めない。
たとえばこの寺がぜんぜん無名で、たまたま住職と路上で知り合って、ちょっと寄りますかといわれて、何も知らずに来てこの石庭の縁側に立ったら、やはり感動してしまうだろう。
何だこれは、と思って、思わず縁側に坐って、そのままじーっと眺め入るということになるだろう。
でもいまはもうそれを知っている。
頭で知った上でのことなので、縁側に坐っても、それらしくそれを演じるということになってしまってはどうもいけない。
竜安寺に限らず、いまは何ごともそうである。だから外人になれたらいいのになと思う。
いまの世の中で感動を得るには、できるだけ無知でいることである。
散歩するというのは時間に変化を持たせることだ。
チェンジ・オブ・ペースなのだ。
直線的に時間を使っている時に、ふと別の時間の使い方をするのが新しい発見につながる。
惰性から逃れるということでもある。
芭蕉は、奥の細道を歩いたから、生涯の旅人だと思われているが、40歳をすぎて宗匠となって「芭蕉翁」と呼ばれるようになって初めて、大がかりな旅をしたのである。
恐らく周りに門弟ばかりで、日常性に埋まりそうになってしまったのだろう。
別の視点、非日常を求めて旅をしたのである。
ルーチンワークからの脱出が偉大な文学を生んだのである。
もちろん、きちんとした目的があったのだろうが、テンベア型な旅をしている。
文化というのは結論ではなく、プロセスだ。
細部だ。
寄り道だ。
こだわりだ。
それが楽しめない人に文化は語れない。
ムダの効用、ということも言いたくないが、ムダはムダであるだけで意味がある。
余白にも意味があるように。
デジタルの百科事典を持っているがちっとも楽しくない。
それは知りたいことが直線的に分かるからであり、「散歩」の部分がないからである。
大学も自分が学ぶことがはっきりしていたら誰も行かなくなるだろう。
自分の知らないことに出会えるから「ときめき」があるのであり、何だか分からないけどすごそうなことに出会うから、面白いのだ。
有用性ばかりの大学になったら、誰も行かなくなるだろうって思っていたけど、そんな大学が多いいにも関わらず、文科省が公表した学校基本調査(確定値)によると、2021年度の大学進学率は54.9%で過去最高だったことが分かった(前年度比0.5ポイント増)。
短期大学と専門学校を含む高等教育機関への進学率は83.8%で、こちらも過去最高だった(同0.3ポイント増)。
これを知って、驚いた。
専門学校でいいから・・・・・・
「急がば回れ」ということわざは「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」という連歌師の宗長の歌から生まれたという。
昔、東から京都に入るのには琵琶湖を横切る矢橋港からの船便と、瀬田の唐橋へ回る陸路のコースがあった時代の話だ。
船は近道だが、比叡おろしの強風を受けるので欠航が多い。
また危険でもあるので、陸路の方がいいという具体的忠告だったという。
ラテン語でも“Festina lente.”というが、急いては事をしそんじるのである。
谷川俊太郎の「あいまいなままに」にこんなくだりがあった。
「谷川俊太郎 あいまいなままに」(人生のエッセイ)谷川俊太郎(著)鶴見俊輔(監修)

「楽しむことのできぬ精神はひよわだ、楽しむことを許さない文化は未熟だ。
詩や文学を楽しめぬところに、今の私たちの現実生活の楽しみかたの底の浅さも表れている。」
【産婆術】
日本でも法科大学院(日本版ロースクール)が2004年に本格的に開校されたが、アメリカではハーバード・ロースクールを描いた『ペーパー・チェイス』などに描かれているようにとても難しい学校として知られている。
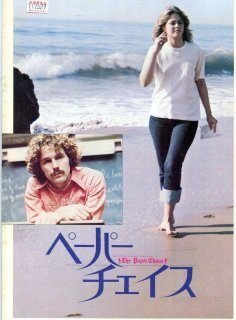
ここの教育の基本は「ソクラテス・メソッド」である。
教授は学生を積極的に指名し、問答を繰り返しては正解を求めていく、という方法で行われる。
次の授業まで大量の宿題が出される。
これを読みこなして初めて授業に参加できるのである。
そして、教師はその中の問題点は何か、ということを聞いていき、名前をチェックして、合否を判定することになっている。
ただし、最近ではもっとソフトに聞いていく方式に変わりつつあるようだ。
『ペーパー・チェイス』を見た時、正直羨ましかった。
憧れたのだが、実際にそんな授業を受けろというと、私は、後込みをしたかもしれない(^^;
ソクラテスは、産婆術(“maieutike”お母さんの職業だった)で知られる。
すなわち、第1に、自分には知恵を産む力がないこと、第2に、人の精神に宿った知恵を安定・促進させること、第3に、仲人として相応しい教師を紹介すること、第4に、産れた知恵が育てるに値するか否かを判断すること、である。
つまり、ソフィストのように知識を授けるのではなく、相手が自ら知恵を産むように導くのであり、これ方法が《問答法dialektike》である。
こうして弟子と徹底的な討論を通して真理を得ようとしたのである。
「自分は牛(アテネ)を起こしておくためのアブである」と喩えたが、これは表面的には、自分はなにも考えを出さず、ただ他人の見解を吟味検討し、あらを探すことでもあり、「ソクラテスの皮肉」とも言われ、多くの人々から反感も買った。
『ペーパー・チェイス』のように教師も大変である。
あんな授業をしろ、といわれるととてもできない。
ただ、他人と問答することによって真理が生まれてくるというのは本当だ。
学生に簡単なことを聞かれて、自分なりに説明する時に、全く違う事柄と結び付くことがある。
セレンディピティなのだ。
会社などでは「ブレスト(ブレーン・ストーミング)」の形で行われているが、この基本は、相手を否定しないことだ。
健全な対話、これこそが望ましいのだが、日本でコミュニケーションは発達していない!?
一例を上げると、本当の自分を見せないように、若い人はペルソナ(外界に適応するための社会的・表面的な人格)を作っている様に感じる。
“人当たりがよく、怒らず、地味で主張しない”というペルソナ。
本心を見せず、そのペルソナを通じてコミュニケーションをとり合うから、余計に相手のことがわからなくて不安になる。
仕事で出会う人だって仮面をかぶっているわけであるから、本心はわからない。
その状態で、相手のニーズをつかむのはとても難しいのだが・・・・・・
【知の相対化】
ボルヘスの小説「学問の厳密さについて」(「創造者」国書刊行会)には実物大の王国の地図を作る地理学者が出てくる。
「創造者」(岩波文庫)ボルヘス,J.L.(作)鼓直(訳)
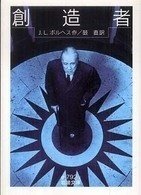
詳しい地図を作ろうとすると実物大になってしまった。
人々はそれを「無用の長物と判断して、無慈悲にも、火輪と厳寒の手にゆだねてしまった」。
地図はそこに情報が載っているから有用なのではなく、そこから情報が抜け落ちているからこそ役に立つ。現実の不完全な模倣だから役立つのである。
シェイクスピアは全てを相対化する目をもっていた。
自分だって笑うのだ。
真面目な劇だと思われている『ハムレット』の中にも笑いは多い。
「ハムレット (改版)」(新潮文庫)シェイクスピア,ウィリアム(著)福田恒存(訳)
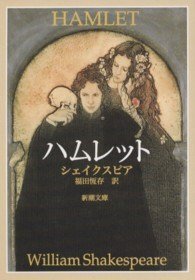
復習を果たすために狂気をよそおっていたハムレットが王妃の部屋で隠れていた家臣のポローニアスを刺し殺したと知った国王クローディアスは自分が危険だと思ってハムレットをイギリスに追いやることにする。
その理由を廷臣たちに説明して「むつかしい病気はむつかしい手段によってしか癒されぬもの」という。
後に墓掘りの道化がこのイギリス送りを「気がちがったからでさ」と言ってのけ、「あそこじゃ気がちがっていても目だたねえ、なにしろみんな気ちがいばっかりだから」とうそぶく(第五幕第一場)。
ここで当時も今もイギリス人は大笑いする。
シェイクスピアは自分自身を笑っているのだ【ちなみに「むつかしい」という言い方は西日本のものだが、満州生まれの小田島雄志のご両親はどこの生まれだったのだろう】。
独善的な人というのはどこから得たかもしれない「信念」を絶対だと信じて「布教」する人の別名である。
自分の思想や研究は深い、と思っているかもしれないが、他人から見れば、赤ちゃん用のバスタブに浸かっているだけかもしれない。
自分の理論や思想の根拠というのを洗い直して見ていないのである。
神のご託宣を大衆に与えるだけというような「司祭型」の学者では、今日のような錯綜とした文化状況にはうまく適合できない。
一元的パースペクティブでは通用しない。
そのためには学問や芸術領域を横断し、多様な地域の文化伝統を射程に入れる必要がある。
答えのない時代に必要な「知」は、「重箱の隅型」の学問ではなく、少し祝祭的な雰囲気もある「闇鍋型」の研究である。
ジル・ドゥルーズの言葉でいえば、ツリー型の「知」を求めて枝葉末節を研究するのではなく、リゾーム(根茎)型の「知」である。
そこではすべての起源や「中心」を探し出すことはできない。
西洋哲学はすべての起源や目的となる究極的な存在を求めようとして成立したものであるが、変化することもなく、常に同一に留まる「同一者」的存在を見つけることができなくなっている。
秩序をノモス、無秩序や混沌をカオスというギリシャ語で表すことがあるが、合理性を求めて、あまりにもノモス的な思考がはびこってしまった。
カオス的な思考をしなければ、正解のない時代を生きることができない。
これから必要とされるのは「呪術師型」「カオス型」の攪乱する「トリックスター」的な知識人である。
秩序や効率や目的に結びつけて行動する「司祭型」「ノモス型」では答えなき時代を生きることができない。
大切なのは遊び精神にあふれた文化英雄である。
ジル・ドゥルーズの言葉でいえば、「ノマド(遊牧地)」で遊ぶ「逃走する主体」ということになるだろう。
カオス研究の第一人者であるダヴィッド・ルエールは「偶然はこの世界において本質的な役割を果たしている」と述べているが、我々に必要なのはチャンス・オペレーション、つまり、偶然を活用することである。
山口昌男は、「知の旅への誘い」(岩波新書/中村雄二郎との共著)の中で、人間の生における光と影の部分を対比させ、影の復権による「全体知」の回復の必要性を説いている。
「知の旅への誘い」(岩波新書)山口昌男/中村雄二郎(著)

夢、無意識、祭り、極限状態、芸能、神話といったいくつかの人間的経験の枠組みを通して見てもわかるように、人間は因果律論につじつまのあう方向だけに沿って生きているわけではない。
こうした様々な要素の一見非合理的に見えるが、理性的な次元だけでは充実した全体的な生を営むことはできない人間の、表面的な生の補充の営みになる。
仮にこうした一見でたらめと見える部分が影の部分だとすると、人間は、こうした影の部分との秘かな対話を試みないで、深い意味での統一を保つことはできない。
こうして山口はこれまでの理性的なものと見られてきた<知>を、光と影の部分に区別して次のような表を作っている。
光の部分 影の部分
表層の意識の整合性 生真面目さ
因果性 理性
日常生活の現実 現在
司祭的知性 イデオロギー
ことばの論理 一元的現実
中心 深層の意識の旅
笑い 荒唐無稽
狂気 祝祭の現実
始原の時 道化型知性
想像力 肉体の論理
多元的現実 周縁
文化も人間も言葉も影があるから面白いのであり、光だけのタテマエだけの一元的な世界で生きてはいけないのである。
20世紀の芸術家たちが模索したことも知の相対化である。
意味のあるものを分解して構築しなおすことで新しい物を生み出そうとした。
「脱構築」(「ディコンストラクション」deconstruction)と呼ばれるものである。
コロッケの方が美川憲一よりも偉いと思う心のことである。
グリコの飴よりもオマケを愛する心である。
「人は何で殺してはいけないのか」と問う心である。
一つの答えを求めるのではなく、問いを見つめ直すことである。
分からない、というのも一つの哲学である。
何でも言われた通りに納得し、目の前の事象をそのまま受け取ってしまうのは惜しい。
寺田寅彦は「科学者とあたま」という随筆で、頭の悪さを推奨している。
「寺田寅彦 科学者とあたま」(STANDARD BOOKS)寺田寅彦(著)
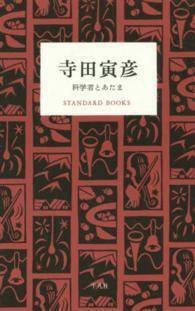
分かり切ったと思えることでも、立ち止まって考えてしまう。
科学者はそうした「呑込みの悪い朴念仁(ぼくねんじん)」でなければならない、と書いている(小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集 第四巻』岩波文庫)。
「いわゆる頭のいい人は、言わば足の早い旅人のようなものである。
人より先に人のまだ行かない所へ行き着くこともできる代わりに、途中の道ばたあるいはちょっとしたわき道にある肝心なものを見落とす恐れがある。
頭の悪い人足ののろい人がずっとあとからおくれて来てわけもなくそのだいじな宝物を拾って行く場合がある。
頭のいい人は、言わば富士のすそ野まで来て、そこから頂上をながめただけで、それで富士の全体をのみ込んで東京へ引き返すという心配がある。
富士はやはり登ってみなければわからない。
目はいつでも思ったときに閉じることができる。
しかし「耳の方は、自分では自分を閉じることが出来ないように出来て居る。
何故(なぜ)だろう」(寺田寅彦「俳句と地球物理」ランティエ叢書)。
「俳句と地球物理」(ランティエ叢書)寺田寅彦(著)

眠っていても危険を察知できるから、など思いつきの答えはできるかもしれない。
しかし何となく見過ごしたり、気がつかなかったりしていることに疑問を抱く。
科学者に必要な才能は、分からないことを見つけることである。
もう一度いうが、セレンディピティというのは、日常化した思想を、思考法をもう一度見つめ直すことである。
松岡正剛のいうように「知の編集術」と言い換えてもいいが、自分がどのような思想、思考法、文化に染まっているか見つめ直すことである。
その意味では「知の相対化」であり、何よりも常識を疑い、他人のいうことを鵜呑みにしないことかもしれない。
今の人は、当たり前になっていて分からないだろうが、クリネックス・ティシューが出てきた時には驚いたものだった(爆)
柔らかさと丈夫さという相反する「常識」が2枚重ねにすることで解決されていた。
こんな簡単なことなのに誰も製品にしなかったのである。
「起承転結」などという論理の運び方も日本独特だし、結論を周りからぐるぐると固めて行く手法である。
アメリカなどではストレートに結論に向かって行く(同じ英語圏でもイギリスの論文とアメリカの論文ではストレートさが違う)し、ドイツではテーゼ→アンチテーゼ→ジンテーゼというように論理を進めていく。
イスラムの論理の進め方はいまいち分からないし、北朝鮮の論理の進め方もまるで違うようだ。
これに関してはKaplan, Robert B. "Cultural Thought Patterns In Inter-Cultural Education."Language Learning,16(1 and 2), 1-20.という有名な論文があり、次の通りである。
英語は直線的パターンであり、セム語は「並立構文」を使用する。
東洋諸語は、「間接性」によって特徴づけられており、「渦巻きのようにぐるぐる回る」といえるような「様々な脱線的な見方」をする。
ロマンス語は、脇道にそれたり無関係な材料をとりいれる自由が大きいと特徴づけた。
ロシア語は、「構造的に関係している従属的な要素を挿入して拡充する」例だとしている。
論理というか談話の展開法も同じように考えられる。
【帰納と演繹と創造的推論】
観察から新しい現象をみつけ、モデルを作って、それを理論的に検討しながら演繹的に物性の予測に結びつけていく方がいい。
科学の進展には「技術」と「発見」と「アイディア」が必要だ。
理論先行型の研究というのは発見・ブレークスルーには能率が悪い。
いろいろな方法論を考えた後に“ふと”出てくるものである。
経験だけでは語れない。
物事をモデルを上手に作って解明していく必要がある。
言語学はかつては経験科学だった。
残っているテキストを解釈していくものであったが、人間の自然言語というのは経験論・帰納論では語ることができない。
人間は無限の文を作ることができるし、無限の文を理解することができる。
それをソシュールのように「類推」とか、マルコフの「有限状態文法」などでは解けない。
そのために、チョムスキーは「原理とパラメータのアプローチ」(Principles and Parameters Approach)というモデルを用意して、演繹的に言語を研究しようとしたのだった。
それまで文献を中心とした科学だったのをチョムスキーは演繹的な実験科学に変えた。
帰納論的な手法で全ての文を集めてから文法を作ることはできない。
文は無限にあるからだ。
演繹論的にモデルを作って、現実と照らし合わせながらモデルを変えていく方法でなければならないとチョムスキーは考えたのだ。
演繹を考えたのはルネ・デカルトだからチョムスキーは、「デカルト派言語学」を標榜している。
デカルトは、「方法序説」の中で、真理を探究する方法として次の四つの規則を採用している。
「方法序説」(岩波文庫)デカルト(著)谷川多佳子(訳)

偏見にだまされず自分で真と認めるものだけを受け入れること。
大きな問題は分割して考えること。
単純な認識をつみあげて順序よく考えること。
全体をよく見て見落としがないかを確認すること。
ただし、「答えのない時代」にどれだけ有効か、分からない。
橋本治の「「分からない」という方法」(集英社新書)はまさに20世紀の病を克服しようとした試みだが、「人の言う方法に頼るべき時代は終わった」といい、「二十世紀は理論の時代で、『自分の知らない正解がどこかにあるはず』と多くの人は思い込んだが、これは『二十世紀病』と言われてしかるべきものだろう」としている。
「「わからない」という方法」(集英社新書)橋本治(著)

自分がぶち当たった壁や疑問は、自分オリジナルの挫折であり疑問である。
「万能の正解」という便利なものがなくなってしまった結果なのではない。
ただ、チョムスキー理論の人の論文の中には、時々、本当にこういうだろうかと言語直観を疑うような例文が並ぶことがある。
シャーロック・ホームズはいう。
「人は理論的説明にあうように知らず知らずのうちに事実の方を曲げるものだ」。
ちなみに、フランシス・ベーコン(Francis Bacon)は1620年に出した「ノヴム・オルガヌム」(Novum Organum)で哲学を3つのタイプに分けた。
「ノヴム・オルガヌム - 新機関」(岩波文庫)フランシス・ベーコン(著)桂寿一(訳)

クモ型とアリ型とハチ型だ。
クモ型というのは自分の体からクモの糸を次々に出して網を作るが、同じように自分の原理・原則を中心にして、すべての観念をひねり出し、推理の網を張り巡らせるもの、つまり、演繹的手法である。
アリ型というのはひたすら地上を這い回って餌を集めるアリのように、個々の事実ばかりを集め、データをたくさん集めればいつか判断できると考える、帰納的手法を指す。
ハチ型というのは花から花へ移動しながら餌を集めてくるもの。
材料を集めてくるが、そのまま使わず、ハチの巣のように自分の力で形を変えるの。
精神の生み出した原理や観念に頼ることも、観察から得た個々の事実だけに固執することもせず、変化させて、理性の中に蓄えることこそが大切だとベーコンは考えたようだ。
論理には「帰納」(induction)と「演繹」(deduction)だけしかないように思われているが、チャールズ・パースによって提唱されたアブダクション(“abduction”「発見の論理」「創造的推論)」というものがある。
シャーロック・ホームズが用いるような推論である。
ウォルポールが「セレンディピティ」という言葉を友人に宛てた書簡で初めて用いたときには、「幸運な偶然の発見」ではなく、むしろ、アブダクションに近いことを意味していたと伝えられている。
例えば、三人の王子が旅の途中でラクダを曵いた商人に出会ったとき、ラクダそのものを見ないで、その足跡や道端の草の食べられた跡などから、ラクダの身体的な特徴を的確に言い当てたエピソードを指して、「目指す答えに到達するための能力」を意味するものとして使ったとされる。
それが違う方向に進んでしまったのだから、世の中は面白い。
アブダクションを有馬道子「パースの思想」(岩波書店)によって、パースが作った例を挙げてみる。
「パースの思想 - 記号論と認知言語学 (改訂版)」(岩波オンデマンドブックス)有馬道子(著)

私が部屋にはいって、そこにいろいろな種類の豆のはいった多くの袋をみつけたとしよう。
テーブルの上には一握りの白い豆がある。
そして、しばらく探した後で、それらの袋の一つには白い豆ばかり入っているのをみつけたとしよう。
すぐ私は一つの蓋然性、言いかえれば妥当な推理として、この一握りの豆はその袋から取り出されたと推論する。
このような推論を仮説を立てるという。
そこで、次のようになる。
仮説:この袋から出る豆はすべて白い。
規則:ここにある豆は白い。
結果:ここにある豆はこの袋から出たものだ。
∴事例
次のようにもいう。
アブダクションは説明のための仮説をつくる過程である。
それは新しい考えを導き出す唯一の論理的な働きである。
というのは、帰納は価値を決めるだけであり、演繹は単なる仮説の必然的な結果を導き出すだけである。
演繹はそうであるに違いない(must)ことを証明し、帰納は実際に(actually is)そのように働いていることを示し、アブダクションはそうであるかも知れない(may be)ことを単に示唆するだけである。
それを正当化する理由としては、その示唆から帰納によって検証されうる予言を演繹によって引き出すことができるということ、そしていやしくも私たちが何かを知ることになったり現象を理解するようになったりするということがあるとすれば、そうしたことがもたされることになるのはアブダクションによるより他にないということだけである。
何もないところから何も生まれないから教養とか知性とかが必要になってくる。
知識がなければ、新しい知識が生まれるはずがない。
白紙から生まれるのではない。
しかし、教養とかアカデミズムには陥穽もある。
目の前の現実が見えなくなることもある。
上野千鶴子は「<わたし>のメタ社会学」(『岩波講座・現代社会学1 現代社会の社会学』岩波1997)で次のように書いている。
「差異の政治学 (新版)」(岩波現代文庫)上野千鶴子(著)

「「教養」や「オリジナリティ」に神秘的な意味を与える必要はない。
「すでに知られていること」が何か知ること。
それと自分の考えていることがどう違うかを分節する能力を持つこと。
「異見」はそのようにして創られる。
次のようにもいう。
人は訓練によって「情報」の量を増やすことができる。
ひとつは自明性の領域を懐疑と自己批判によって削減することによって。
もうひとつは異質性の領域に対して自己の受容性を拡大することによって。
パラダイムは当事者の経験を構成する世界観の根底をなしており、「説得」や「論破」によって取り替えることができるようなものではない。
経験を組み替えるカテゴリーの萌芽は「臨床の知」の中に満ちみちている。」
・・・・・・それは<わたし>の「外から」しか訪れない。
<わたし>にとってエイリアンなものを「聞く力」を持つこと。
「当事者のカテゴリー」こそ、パラダイム革新の宝庫である。
【仮説の立て方】
仮説の立てかたについて。
(作業)仮説というのは学問にとっても、人生にとってもとても大切なものだ。
モデルと言い換えてもいいが、とりあえずの推理・説明を考えて全体像を見直すのだ。
そして、違ったら仮説を直せばいい。
情報を相対化することによって、外観で物事を判断しなくなる。
丸谷才一の「思考のレッスン」(文春文庫)にはこのあたりのコツがよくまとめられている。
「思考のレッスン」(文春文庫)丸谷才一(著)

考える上でまず大事なのは、問いかけである。
いかに「良い問」を立てるか、ということ。
「不思議だなあ」という気持ちから出た、かねがね持っている謎が大事で、実際、古くからだと思っていたり、どこでもと思っている事柄が自分の周りだけのことだったりする。
自分のなかに他者を作って、そのもう一人の自分に謎を突きつけて行くとよい。
「謎を自分の心に銘記して、常になぜだろう、と問い続けることで謎を明確化、意識化することが大事。
そのために自分の中に『他者』を作ってその自分に謎をつきつけてゆく」ことだ「当たり前なんだ」とか「昔からそうだったんだ」と納得してはいけない。
他者の目、異文化の目で眺めることだ。
次に「比較と分析」ということが非常に有効だ。
ある主題なり対象なりの中で、特に自分が関心を抱いている要素にこだわって分析してみる。
さらに、別のものと比較しながら分析すること。
そして、直感と想像力を使って仮説を立てること。
「仮説は大胆不敵に」「あっと驚くようなものを立てるという芸術的奔放さが大事」という。
仮説を立てるには、「多様なものの中に、ある共通する型を発見する能力」が必要だと書いている。
その際に重要なことは「見立て」であるとして、次のようにいう。
同種のものが別の外観で存在することを発見する。
同類を見つけて同類項に入れる。
これは他の言い方でいえば、「見立て」ですね。
この「見立て」というのはアナロジー(類推)ということで、元々は「和歌・俳諧などで、ある物を別のものと仮にみなして表現すること。なぞらえること」だが、一見かけ離れたところに同じ構造を見抜くことである。
例えば、フロイトは深層心理を説明するのに氷山を思い浮かべたのかもしれないが、氷山を見て深層心理を発見したのかもしれない。
そうした発見というのは実は詩人の行為と似ている。
意味が定まった言葉から脱却して、全く新しい意味を発見するのが詩人だからだ。
「見立て」はパロディと言い換えてもいい。
ジョームズ・ジョイスの『ユリシーズ』は、
「ユリシーズ〈1〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)

「ユリシーズ〈2〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)

「ユリシーズ〈3〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)

「ユリシーズ〈4〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)

ホメロスの『オデュセイア』のパロディだし、
「オデュッセイア〈上〉」(岩波文庫)ホメロス(著)松平千秋(訳)

「オデュッセイア〈下〉」(岩波文庫)ホメロス(著)松平千秋(訳)

ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」は、
「ツァラトゥストラかく語りき」(河出文庫)ニーチェ,フリードリヒ・W.(著)佐々木中(訳)

仏教の「如是我聞」から取っていて、作品は『新約聖書』、主人公はゾロアスター教の創始者のパロディになっている。
井上ひさしは、漱石のパロディで「ドン松五郎の生活」とか「吾輩は漱石である」など多くのパロディを書いている。
「ドン松五郎の生活」(新潮文庫)井上ひさし(著)

「吾輩は漱石である」(集英社文庫)井上ひさし(著)
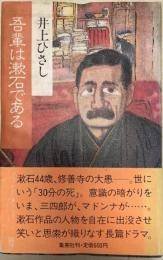
すべての作品は過去の作品のパロディだ、ともいえるのである。
きれいな言葉で言えば、古典に現代的価値を見出しているのである。
型を発見したら、その型に対して名前をつけること。
例えば、フロイトが、息子の母親に対する愛着を「オイディプス・コンプレックス」と名づけたように。
名づけによって考えが整理されて、思考がさらに深まる。
「キーワード思考」と言い換えてもいいが、キーワードが生まれるのは全く別な物を「見立て」る力があるからだ。
思考は文章の形で規定される。
文章力がないと、考え方も精密さを欠く。
大ざっぱになったり、センチメンタルになったり、論理が乱暴になったり。
文章力と思考力はペアである。
「対話的な気持ちで書く」というのが書き方のコツだと。
自分の内部に甲乙2人がいて、いろんなことを語り合う。
考えるときには対話的に考える。
しかし、それを書くときには、普通の文章の書き方で書く。
書き出しに挨拶を書くな。
書き始めたら、前へむかって着実に進め。
中身が足りなかったら、考え直せ。
そして、パッと終れ。
「見立て」の達人は、昔、「見巧者」(みごうしゃ)といったが、達人はもちろん、丸谷才一だが、斎藤美奈子も鋭い。
「読者は踊る」(文春文庫)のタイトルだけを見ているだけでも楽しい。
「読者は踊る」(文春文庫)斎藤美奈子(著)

一部を抜き出すと・・・・・・
「消えゆく私小説の伝統はタレント本に継承されていた」
「字さえ書ければ、なるほど人はだれでも作家になれる」
「芥川賞は就職試験、選考委員会は『じじばば』の巣窟だった」
「女子高生ルポの商品価値はナマ写真ならぬナマ言説」
「汝、驚くなかれ。いまどきの聖書の日本語訳」
「死ぬまでやってなさい。全共闘二十五年目の同窓会」
「みんなひれ伏す『在日のアウトロー』という物語」
「〈すわ震災〉のチャンスを即興芸で語った人たち」
「哲学ブームの底にあるのは知的大衆のスケベ根性だ」
「学問は人の上に人を造る。超勉強法は疑似出世本だ」
「身内の自慢話が〈だれも悪くいわない本〉に化ける条件」
「近代史音痴の国で起こったお笑い歴史教科書論争」
「マニアなのかマヌケなのか。クラシック音楽批評の怪」
例えば、全共闘と暴走族を「見立て」て、次のようにいう。
「確かに、中国の簡体字で書いた立て看(立て看板)を書いていた全共闘とスプレーで漢字表記の落書きをする暴走族には同じ傾向がある。
団塊世代に批判的なのは、昭和30年代生まれの人が圧倒的に多い。
彼らは「全共闘には乗り遅れ、暴走族には早すぎた」世代だったりもするのだが、考えてみれば、全共闘と暴走族はひと皮むかなくても同質ではないだろうか。
両者の特質を列挙してみればわかることである。
反権力志向である
群れて、あばれる
警察を当面の敵とする
スタイルを重視する
結束がゆるい
意外と思想がない
「族」は壁にスプレーで小むずかしい漢字は書くが、長じて作家や評論家となり「あの頃、僕たちは政治の季節のなかで・・・・・・」などと書いたりしないだけマシか。」
斎藤には、この他にも『妊娠小説』『紅一点論』『文壇アイドル論』など面白い「見立て」がいっぱいだ。
【研究と教育(実践)】
アメリカの文明史家のロバート・スクラーは、映画の聖地ハリウッドを両者の闘争の場所と評して「創造のエリート」がいて「管理のエリート」がいるから映画が栄えたと語った。
管理のエリートは、経費を削り、少しでも収益を高めようとする。
創造のエリートは、おのが感性と美意識の忠実な僕(しもべ)であろうとする。
そのせめぎ合いが映画を育ててきたという。
最近、大学でも教育と研究を分けるべきだという議論が進んでいる。
一面、正しいのだけれど、それではあまりにも寂しいのではないかと思う。
こうした論調に乗って「うちは教育機関だから研究などしなくてもいい」と校長がいう学校もあるという。
教育と研究、研究と教育というのは物事の裏表であって、切り取ればどちらもついてくるものである。
誰かに伝えることのない研究は自閉的で、広がりがない。
研究の裏打ちなしに、ただ教材研究だけをして講義ができると思ったら、それは教育の荒廃を招くだけである。
教師がゆとりを失ったら、学生はもっとゆとりを失ってしまう。
ゆとりを失うと、社会に歪みや軋轢が生まれてくる。
そして、崩壊していく・・・・・・
大学などは独立行政法人になったが、大学が金儲けばかり考えていていいのだろうか?
学者を大事にしない国は滅ぶ、と孔子は言ったのだが、『論語』なんかは論外なのだろう。
自動車の運転でもまっすぐ前を向いている人が優良ドライバーなのではない。
適当に脇見をしながら、全体像を確かめ、時には後ろを振り返りながら前進するものである。
資格や免許ばかりを目指すのは専門学校でいい。
それらも含めてもっと先を見つめる教育が求められているのではないだろうか?
【複雑系思考法】
複雑系(Complex System) というパラダイムがある。
これまでの科学が捨象して成立していた現実をリアリティのあるものとしてとらえるものである。
複雑さそのものの中に、ある種の「解」とか「方向性」を見出そうとする試みである。
1+1=2にならない世界を考えるのだが、実際の人間の動き、自然現象などは1+1=2に決してならない。
さまざまな要素が絡んでくるからである。
複雑(complicated)ということとは違う。
要素が多くて複雑なだけだったら、時間はかかっても分析できるが、要因が絡んでいて、容易に解けない状態だと思っておいてほしい。
『ジュラシック・パーク』の中でカオスの専門家イアン・マルカムが「たとえパークの恐竜を全部メスにして繁殖を防いでも、100%安全はありえない。生命は生きる道を自分で見つけ出す」とパークの失敗を予言して、その通りになる。
自己組織化というものがあるのだ。
カオス理論というのは「北京で蝶々が羽ばたくとアメリカでハリケーンが起きる」というものだ。
これは、日本人には分かりやすい。
パチンコは、天釘を狙って打ち出すのが普通だが、同じところを狙っていても結果は大きく違う。
筒井康隆のSFに大物理学者がパチンコ屋に行って、研究を重ねて衆人が見守る中で打ち始めるのだが、あっと言う間に負けてしまう、というのがあるが、あんな単純なゲームでさえ、予想ができないのである。
これは「初期値鋭敏姓」というが、ほんのわずかの違いが結果を大きく変えて北京の蝶々の話になるのである。
単純系の思考というのは、実験室の中だけの話だ。
ガリレオがピサの斜塔から重さの違う球を落としたら(実際にはやっていないといわれる)、軽い球の方が遅く落ちるはずだ。
2倍勉強すれば2倍賢くなるというのは、机上の空論で、中には、勉強のしすぎでアホになる奴も出てくるのである。
これが当てはまるのは、受験と受験戦争に勝ち残ったキャリア官僚にしか通じない話である。
どんなに努力しても報われるとは限らないけれど、努力せざるを得ないのが人生である。
つまり、ゆらぎがあり、カオスであり、ファジーであり、非線形なのである。
線形で考えてはいけない。
非線形で物事を見なければならない。
サファリというのは線形であるが、テンベアは非線形である。
自然現象にはゆらぎがあり、人間の行動にもゆらぎが見える。
鳥などの群は中心がなくても全体として意志を感じるが相互関係だけで行動している(ボイド【birdoidの略】の研究という)。
1.衝突回避=近すぎる群の仲間と離れ、衝突を避ける。
2.速度調節=周りと速度を合わせる
3.求心力=群の中心の方へ向かおうとする
要素還元主義と呼ばれる、要素間の関係を無視して、分解していけば真理に達するという「因果律」による科学では全体がつかめなくなってしまう。
古典力学は、相対性理論や量子理論の挑戦を受けて大転換をしなければならなかった。
進化という不可逆でエントロピー拡大の法則に反するような現象を扱っている生物学はもともと近代的方法と無縁の分野だったが、科学の新しいあり方を提案している。
生命現象を見ると、生きていることと死んでいることはまるで違うが、なぜ生きているかという原因を探ろうとしても分からない。
生きていることは死んでいないこと、死んでいることは生きていないことと脱構築的な解釈しかできない。
まして、人間はどこでどうなるか分からない複雑系の動物だ。
ドーキンスの『わがままな遺伝子』のように、利他行動が当たり前のように日本人は働くが、自分とは無関係の要因で会社が倒産することだってある。
不条理に生きなければならないのである。
大砲の弾丸の軌道を予測する時には「初期条件」が明確に与えられるとこれによって微分方程式が立てられるなど弾丸の性質は変わらない。
ところが、人間はその間にどんどん変わっていく。
人は変われるのである。
不可逆的な時間(生物は誕生→成長→死)のことをノーバート・ウィナーは、「サイバネティックス」の中で、「ベルグソン的時間」といい、可逆的な時間のことを「ニュートン的時間」と呼んだ。
「サイバネティックス―動物と機械における制御と通信」(岩波文庫)ウィーナー(著)池原止戈夫/彌永昌吉/室賀三郎/戸田巌(訳)

多くの学問は原因があって結果が生まれると「因果律」で考えている。
医療の場合、これを医学パラダイムということがある。
ウイルスがあって病気になる、という因果関係が分かるから治療するということになる。
これに対して、臨床心理学パラダイムは原因を考えないというものである。
例えば、父親の死によって心の病になった場合、父親の死を元に戻すことはできない。
フロイト理論などは原因よりも治療に重きを置くのはこのあたりの事情がある。
臨床心理学には臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助、研究・調査・発展がある。
臨床心理査定は「診断」、臨床心理面接は「治療」と医学パラダイムで語っていたのを現在では言葉を変えている。
例えば、「醜貌恐怖」というのがあり、誰が見ても美人である人が醜いと思い込んでしまうことがある。
フロイトは、この主観的な現実を「内的現実」と呼んで、いわゆる客観的な「外的現実」から区別した。
臨床の知で必要なのは、こうした仮想現実もまた現実であると考えることなのである。
ユングも、もっとラジカルにイメージこそが現実をつくるのだ、とした。
イメージが本物か偽物かは、そもそも問えない。
イメージそれ自体に意味があるのだ。
ユングはこれらから「元型」という普遍的なものを見出した。
仮想現実も、人が体験しているという限りでは現実性をもつ。
ちょうど触れたり嗅いだりするものを体験することと、何ら変わりがない。
イメージを通して「現実」を作り出しているのだから。
「胡蝶の夢」ではないが、何が現実性を持っていると言い切れるのだろうか?
たまごっちやルーズソックスがどうして流行したか、という問いは考えてみるのも面白いかもしれないが、たった一つの答えを見つけることはできないだろう。
現象の全体を、複雑なものを複雑なまま、「あるがままに」とらえることが大切なのである。
言語学は、「ハマグリ」が「浜+栗」から来ているということは問題にするが、海岸が「ハマ」とされて理由までは問わないし、問えない。
今ある言語を「あるがままに」とらえる学問が言語学であるし、記号論もまた世界を「あるがままに」をとらえる学問なのである。
カオスというのは「混沌」である。
「荘子」(内篇七「応帝王篇」)に有名な“渾沌(混沌)”の説話がある。
「荘子 内篇」(ちくま学芸文庫)福永光司/興膳宏(訳)

「中央の帝(渾沌)にたいへんなもてなしをうけた南海の帝・(しゅく)と北海の帝の忽(こつ)はその好意に報いるべく、目・鼻・口がない渾沌の不便さを助けてやろうとして、その顔に毎日一つずつ穴を開けてあげた。
ところが7日めになって渾沌は死んでしまった・・・・・・
(二人の帝の名の“・忽”とも漢字で“すばやい・たちまち”の意味)。
生きるのに便利な目鼻をつけてやって一安心と思ったその相手(渾沌)が死んでしまった。」
「渾沌(混沌)」は“自然の姿”であり、それに目鼻をつける(秩序づけをする)と自然本来の姿が失われる・・・・・・という寓意が込められている。
倨傲にも“人間は自然と峻別されるべき存在、人間こそ自然を統御する存在(自然の支配者としての人間)”である・・・・・・などというのではなく、荘子の世界では「自然のささやかな一部にすぎない人間よ、おごるなかれ」の思想が貫かれていると言ってよい。
なお、荘子には、「万物斉同」の思想、自然環境に関連する「共生」「棲分け」の思想、空の青さ/楽器の共鳴/落雷の電気に関する興味深いテーマが並んでいる。
「あるがままに」、つまり、「レット・イット・ビー」なのである。
【まとめ】
●セレンディピティはひらめきとどう違うのか?
・勘や直感とどのように違うか?
いわゆる長嶋監督のような「動物的直感」とは違う。
あることがらを考えていて、行き詰まった時に初めて生まれるものである。
・どんな瞬間に役立つのか?
水平思考が行き詰まった時である。
前がよく見えてもガラス張りということがある。
本当に見つめるには少し横から回らなくてはいけない。
・いつもセレンディピティを考えつづける必要があるのか?
絶えず自分の仮説やモデルが正しいのか検証する必要がある。
●非日常性のセレンディピティ
・場を変える
昔から三上(さんじょう)といって文章を練るのに最適の三つの場所。
すなわち、馬上・枕上(ちんじよう)・厠上(しじよう)【欧陽脩『帰田録』】。
発想も同様で同じ場所にいては何も生まれない。
非日常性を求めて街を散歩したり、森を散策したりするといきなり発想が生まれてくる。
もちろん、他人と同じことをしていては日常に埋まるだけである。
・自己PRの公開テストのすすめ
自分が今どんな位置・文化・思想にあるか考えるために自己PRをすればいい。
今は、ブログやホームページがある。
他人と自分はどのように違うか考えてみる必要がある。
・ユーモアの勧め
ユーモアというのは固定した観念を解きほぐし、別の角度から見るところから生まれるものである。
心にゆとりを!
・発想を温める
行き詰まったらゆっくり考えて頭を冷やす。
小さな発想が生まれたら少しずつ大きなものにしていく。
・無意識にゆだねる
ケクレは、夢の中で6人の小人が輪になって踊っているのを見てベンゼン環を発見した。
セレンディピティの多くに夢が絡んでくることから分かるように無意識のものだ。
頭を叩いても痛いだけで何も生まれてこない。
酒を飲んでも肝臓を痛めるだけだ。
・ひらめきと決断
ひらめきは“ふと”やってくる。
ノーベル賞をもらった福井謙一などは、枕元にメモを置いていたという(我々が実践する とゴミのような訳の分からない文章が残るが・・・・・・・)。
●仮説で育てるセレンディピティ
・まず大胆な仮説を立てよ
始めに仮説ありき。
ウソでもいい、大きな仮説を立てる必要がある。
・演繹的発想のすすめ
セレンディピティは経験論ではなくてモデルを作ることだ。
自分の小さな経験を頼りにしていると新しい発想ができない。
・仮説に揺らぎをもたせる
「作業仮説」から始めて徐々に仮説を手直ししていく。
・初めに海鼠(なまこ)を食べた人
どうしてあんなものが食べられるのか分からないが、最初に食べた人は勇気があったと 思う。
今はちゃんと酢醤油などで食べるが最初からあんな料理にしようなんて誰が考えたのか。
他人と同じことをしていては何も生まれない。
・兆候を見過ごすな
必ず答が近くに見つかっているはずだ。
無理と思わず、少し休んで考え直そう。
デジタル思考からアナログ思考へ。
言語的思考を繰り返さず、図形的思考を実践しよう。
左脳思考から右脳思考へ!
●想像活動の時間的経過
ワラスGraham Wallas(イギリスの政治学者、社会学者)の4段階説(Wallas' formula for the art of thought)
“The art of thought” (Harcourt, Brace, and the World, 1926) で創造のプロセスを次の4段階に分けた。
(1)準備(preparation):創造への欲求が生じた後,必要な情報を集め技術を習得しておく
(2)あたため(incubation):(孵卵期とも)考えが熟して自然に出てくるのを待つ
(3)ひらめき(illumination):(啓示期とも)何かの拍子にアイデアが生まれる
(4)検証(verification):アイデアを評価し、修正する
ジェームズ・W・ヤングは、「アイデアのつくり方」(TBSブリタニカ)の中で(1)の段階を資料集めの段階と、心の中でその資料に手を加える(ここではカードを使ったりもする)の段階に分けた5段階を提案している。
「アイデアのつくり方」ヤング,ジェームス・W.(著)今井茂雄(訳)

「ブレーンストーミング」を考案したオズボーン(Alex F. Asborn)は“Applied imagination”(1953)の中で(1)見当づけ、(2)準備期、(3)分析期、(4)着想期、(5)孵化期、(6)統合期、(7)評価期の7つの段階を提案している。
●A・オズボーンのアイデア・チェックリスト
チェック項目 視点(意味)手帳の例
他に使い道がないか 現在のままで新しい用途は?
Put to Other Use(転用) 例:ノートにも使えるようにする
他からアイデアを借りたら 他に似たものはないか、何かの真似はないか
Adapt(応用) 例:カレンダーをつけて日記にする
変えたら 意味、色、動き、音、匂い、形
Modify(変更) 例:システム手帳にしてデータベース化
拡大したら 何かを付加したら、時間をかけたら、回数を増やし たら、長くしたら
Magnify(拡大) 例:思い切り大きな手帳にする
縮小したら 取り除いたら、小さくしたら、圧縮したら、軽くし たら、短くしたら
Minify(縮小) 例:思い切り小さな手帳にする
代用したら 誰か代わりになる者はいないか、他の材料では、他 の場所では、Substitute(代用) 例:パソコンにする・電子手帳を考える
組み替えたらか 要素を入れ替えたら、順序を変えたら、原因と結果 を入れ替えたら
Rearrange(再配置) 例:カレンダーとノートを逆にする
逆にしたら 反対にしたら、上下を逆にしたら、役割を逆にした ら
Reverse(逆転) 例:目的までの日付を逆にする
組み合わせたら 混合したら、ユニットを組み合わせたら、各種取り 合わせたら
Combine(結合) 例:手帳と本を組み合わせる
※星野匡の「ださく似たおち」:オズボーンのリストの覚え方(だ=代用できないか・さ=さかさまにしたら・く=組み合わせたら・似=似たものはないか・た=他の用途はないか・お=大きくしたら・ち=小さくしたら)
●《参考》野口悠紀雄『「超」発想法』(講談社)の基本5原則
「AI時代の「超」発想法」(PHPビジネス新書)野口悠紀雄(著)

(1)発想は、既存のアイディアの組み換えで生じる。模倣なくして創造なし。
(2)アイディアの組み換えは、頭の中で行なわれる。
(3)データを頭に詰め込む作業(勉強)が、まず必要。
(4)環境が発想を左右する。
(5)強いモチベーションが必要。これまでの「発想法」の殻を打ち破る。
【最後に】
ニーチェは、「ツァラトゥストラはかく語りき」で精神の三つの変容について語っている。
「ツァラトゥストラはかく語りき」(講談社まんが学術文庫)フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ(作)堀江一郎(/十常アキ(著)

精神はラクダからライオン、そして子どもへと変化する。
ラクダは、「汝なすべし」の義務精神の象徴である。
ライオンは、「われは欲す」の自立を意味する。
子どもとは、「無垢であり、忘却であり、新しい開始、遊戯、己れの力で回る車輪、始動の運動、“然り”という聖なる発語」であるという。
つまり、「創造という遊戯のためには、“然り”という聖なる発語が必要であり、そのとき精神は己れの意欲を意欲し、世界を離れて己れの世界を獲得する」というのである。
19世紀の科学はラクダ、20世紀にライオンへ変化したが、21世紀に子どもになれるだろうか?
長谷川真理子は、「科学の目 科学のこころ」 (岩波新書)である雄が雌に求愛して相当な投資をしている場合、気持ちを切り替えて他の雌に求愛することはなかなかできないことを「コンコルドの誤り」といって次のようにいう。
「科学の目 科学のこころ」(岩波新書)長谷川真理子(著)

「コンコルドは、開発の最中に、たとえそれができ上がったとしても採算の取れないしろものであることが判明してしまった。
つまり、これ以上努力を続けて作り上げたとしても、しょせん、それは使いものにならない。
ところが、英仏両政府は、これまでにすでに大量の投資をしてしまったのだから、いまさらやめるとそれが無駄になるという理屈で開発を続行した。
その結果は、やはり、使いものにならないのである。
使いものにならない以上、これまでの投資にかかわらず、そんなものはやめるべきだったのだ。
このように、過去における投資の大きさこそが将来の行動を決めると考えることを、コンコルドの誤りと呼ぶ。
(中略)
コンコルドの誤りは、人間の活動にしばしばみられる。
元祖のコンコルドもそうだが、作戦自体が誤っているのに、これまでにその闘いで何人もの兵隊が死んだから、その死を無駄にすることはできないといって作戦を続行するのもその例である。
過去に何人が犠牲になったかにかかわらず、将来性がないとわかった作戦はすぐにやめるべきである。」
大陸移動説を提出しウェーゲナーに対し、その当時のアメリカ地質学会の大物の一人は、「大陸が安易に動くなどという考えが許されるならば、われわれの過去数十年の研究はどうなるのか?」といって反対したというが、これなどは、過去の投資に固執する考えを如実に表わした言葉といえるだろう。
ところで、コンコルドの誤りは、人間が動物の行動を解釈するときに犯す過ちであって、動物自体がコンコルドの誤りを犯しているのではない。
コンコルドの誤りは誤りなのであって、誤りであるような行動は進化しないはずだからである。
ではなぜ人間の思考は、コンコルドの誤りを犯しがちなのだろうか?
この誤りには、何か人間の思考形態に深くかかわるものであるように思われる。」
外国のこととは笑っていられない。
日本では、国家予算の3%を使って建造した戦艦大和が全く役に立たないで沈んだという教訓がある。
軍艦の時代から航空機の時代に変わったのに気づかなかったのである。
しかも、航空機の時代を世界に知らしめたのは日本軍による真珠湾攻撃だったのに・・・・・・
今、日本が苦しんでいる中海干拓や吉野川堰など大型投資の多くも「分かっちゃいるけど止められない」という青島幸男の「スーダラ節」感覚の惰性で続いているだけだ。
四国の観光業界では、「桃栗(ももくり)3年、橋1年」という。
本四連絡橋は開通して1年しか客が来ず、その後は、赤字という歓迎せざる客がやってきたことを揶揄する言葉だ。
誤りは、メンツや未練に拘泥せず、早めに改めることである。
恋愛でも同じで、一度嫌われたのに相手が振り向いてくれることはまずない。
ストーカーになって警察に捕まるのがオチである。
ちなみに、フランスが国策で巨額を投じて開発したけれど、国際的なマーケットでは誰も買い手がつかなかったものにコンコルドの他に、高速増殖炉スーパーフェニックス、TGV(韓国は買ったけれど・・・・・・)、ミニテルがある。
実は、学問の世界でも「コンコルドの誤り」にあふれている。
パラダイムが変わっても、長い間、そのパラダイムで研究をしてきた学者にとって急に捨てることはできない。
これが「パラダイム・シフト」を阻止する一つの理由になっているのだ。
自分の体にしみ込んでいるものであって、自分を否定される痛みを感じることさえある。
いきなり教科書を黒く塗れといわれるようなものである。
教科書が黒くなっただけではなく、心まで黒くなることがある。
司馬遼太郎は、「坂の上の雲」の中で「精神主義と規律主義は、無能者にとって絶好の隠れ蓑である」と書いている。
「坂の上の雲〈1〉 (新装版)」司馬遼太郎(著)

個人のこだわりや形式主義が、考えることを阻み、本質をむしばんでいく。
仕事で非常に成功した方法論があるとしても、それはその時の、時代の流れや状況でうまくいったのではないかと冷静に考える必要がある。
こだわりを持つことは正しい信念に思えるが、新しい柔らかな考えができないと同義語である。
新鮮な知識や情報という栄養が入ってこなくなって、結局立ち枯れていく。
花や木と同じように、今日の栄養を得るために地下に根を広げなければならない。
強い自我は、人を枯らすのだ。
ダイエーの中内功は、流通に革命をもたらしたのだが、最初の成功が後でも続くと考え、「万能感」を持つようになり、「カリスマ」になってしまった。
時代に合わなくなったことを受け入れられなかったのだ。
ちょっと待て、人は急に変われない!のである。
日本人の特に政治家が強調する言葉に「ホウレンソウ」というのがある。
人間関係で生きていく上で必要なのは「報告、連絡、相談」なのだそうだ。
城島明彦の「ソニーの壁」(小学館文庫)を読んでいて驚いたことに、ソニーには「引継」というものがない、というのだ。
「ソニーの壁―この非常識な仕事術」(小学館文庫)城島明彦(著)

ある人が部署を代わってきても、誰も引き継いでくれない。
自分自身のやり方でやればいい、ということになるのだ。
もちろん、分野によっては大変な非効率になるのだが、最初から自分自身の新鮮な目で仕事を見ることの大切さを説いたものである。
教師も引継を受けるが、下手に「この子はこんな・・・・・・」というような偏見を引き継ぎたくない。
そういえば、東京工業大学などでは退官した教授は二度と大学に戻らない、という話を聞いたことがある。
アメリカにもそんな大学があるから真似ているのだろうが、つまり、教授が来て、今やっている研究にとやかく言うのは(いい忠告というのもあるだろうが)、今やっている人にとっては余計なことでしかない、という認識から生まれてきているものだ。
こうやってセレンディピティについて書けば書くほど、偏見を与えているのかもしれないが・・・・・・
科学とは関係のない(といっても言語学も言語科学ということがあるのだが、我々の言語学は方向が違う)分野の人間がどうしてセレンディピティなどについて語れるのか!という問題について触れておく。
フランツ・カフカは「ある戦いの記録」(『カフカ全集2』新潮社)で次のように言う。
「決定版 カフカ全集2 ある戦いの記録、シナの長城」カフカ,フランツ(著)前田敬作(訳)

「しかし、月と名づけられたきみをあいかわらず月とよんでいるのは、もしかしたらぼくが怠慢なのかもしれない。
つまり、日常言語というのは怠惰の産物なのだ。
「月が昇る」という言い回しがあると、月はずっと昇っていくものだという思考から人間は逃れることが難しい。
月は月でなくなってしまっているかもしれないのに、みんなが月だというと、訝ることなく、月だと言ってしまう。
ぼくがきみを<奇妙な色をした、置き忘れられた提灯>とよんだら、きみは、なぜしょんぼりしてしまうのだ。
同じように「日が昇る」という言葉も、本当は「地球が太陽の周りを回って今いる所から見た地平線から太陽が少しずつ出てくる」とでも言わなければならないのに「日が昇る」と言い切っていまい、「真実」から離れてしまうのである。
言語という、人間を人間たらしめている最大の「檻」(こうして「檻」だと言い切ってしまうとみんな「檻」だと思ってしまうが・・・・・・)から離れるには詩的言語を生み出したり、言語から離れて思考することが大切になってくる。
「魔女」などいないのに、一旦、「魔女」という言葉が生まれてしまうと、「魔女狩り」に追い立てられるのが人間である。
魔女でなくても、ラベリングというか、人にレッテルを貼ることは日常茶飯事だ。」
ドロシー・スミスの「Kは精神病だ」という論文(『エスノメソドロジー』せりか書房)では、ある女性が周囲の人によって「精神病」だと見なされていく過程を研究し、その過程が他の人との些細な食い違いの積み重ねによること、また、一旦その人が「精神病」と見なされると、それまで見逃されていたことまで「証拠」になっていくことを指摘した。
「離婚」という言葉の重さは今の人には分からないかも知れないが、いいことかどうか分からないけれど、これを「バツイチ」と呼ぶようになって、言葉の重みが取れた。
「不倫」も「フリン」とカタカナで書くことで軽くなってしまった。
「ばいしゅん」も「えんじょ交際」から更に「えんこう」と略するで軽くなり・・・・・・
言葉にも「コンコルドの誤り」があふれている。
失意や反感を恐れるあまり、既にその名に値しなくなったものを惰性で呼び続けることの何と多いことか!
ソクラテスは愛とか正義とかのふだん使い慣れている言葉がどんなに根拠のない思い込みから発しているにすぎないかを話し合いのなかで一つひとつ暴いていった。
この対話は「ドクサ(思い込み・偏見)の吟味」と呼ばれるが、今までの生育歴、学校、社会教育の過程でいつのまにかつくり上げられてきた慣習としての体に、アレ?と気づいて立ち止まって、自分を見なおし始めることであり、これは自分自身の感受性と思考によって行動すること、言いかえれば疑うことへの出発だ。
ニーチェは『華やぐ知恵』の中で独創性について次のように書いている。
「ニーチェ全集 〈第1期 第10巻〉 華やぐ知慧/メッシーナ牧歌」ニーチェ(著)氷上英廣(訳)

「独創性とは何か。
万人の前の前にありながら、まだ名前を持たず、まだ呼ばれたこともないものを、見ることである。
人の常として、名前があってはじめてものが見えるようになる。
独創的人間とは、命名者である。」
科学哲学者のガストン・バシュラールは、引き算が大切だという。
つまり、人間はあまりも多くの情報を持ち、固定観念に縛られている。
物事の本質を見るためには足し算でたくさんの情報を得るのではなく、むしろ、引き算をしていかなければならないというのだ。
同じことは、「芸術は爆発だ」の岡本太郎が「自分の中に毒を持て」(青春文庫)の冒頭の「自分の大間違い」に次のように書いている。
「自分の中に毒を持て (新装版)」(青春文庫)岡本太郎(著)

「人生は積み重ねだと誰でも思っているようだ。
ぼくは逆に、積みへらすべきだと思う。
財産も知識も、蓄えれば蓄えるほど、かえって人間は自在さを失ってしまう。
(中略)
人生に挑み、本当に生きるには、瞬間瞬間に新しく生まれかわって運命をひらくのだ。
それには心身ともに無一物、無条件でなければならない。
捨てれば捨てるほど、いのちは分厚く、純粋にふくらんでくる。
今までの自分なんか、蹴トバシてやる。
そのつもりで、ちょうどいい。」
記号論とは、何かと言われたら、定義をしないのが記号論だと答えることにしているのだが、「王様は裸だ」と暴くことに近いかもしれないということがある。
オーソン・ウェルズのラジオドラマ「火星人襲来」が本物のニュースと間違われ、全米でパニックを引き起こしたのは1938年10月30日である。
事実とフィクションが入り組んだ新しい放送メディアの危うさを告げたこの事件には、もうひとつ隠れた教訓があった。
意外なことに、このドラマが現実のものではないと見抜いたのは、子供たちだったということだ。
子供らにはラジオから流れる声が、いつものウェルズの声だと分かったのだ。
だから、子どものようになれ、という訳にはいかない。
何も知らないでは大人とはいえないからである。
だから、そうした引き算のためには大変な努力が必要になってくるのである。
例えば教師が一番扱いにくいと感じる学生は、自分が「馬鹿」であると信じ込んでいる「馬鹿」だ。
「馬鹿」だから何をしてもダメだという固定観念が悪循環を作る。
その「馬鹿」の悪循環から逃れなければならない。
先入観をなくせ、先入観を捨てよ、というのは簡単だ。
フランシス・ベーコンだって先入観を「イドラ」(偶像)と呼び、正しい知識獲得の妨げになると説いた。
ただ、強調しておかなければならないことは「偏見」や「先入観」や「固定観念」や「制度化された見方」から逃れるのは容易ではない。
「先入観が悪い」というのも実は偏見である。
これらをなくして何かを理解することは不可能だからである。
恋愛ということを知らなくて『源氏物語』は読めないということだ。
早期教育で『源氏物語』が「読める」子どもが生まれたとしても、これで「理解」したことにならないのと同じである。
子どもの考えが偏見もなく、自由だからいい、という人もいるが、ただモノを知らないだけなのだ。
子どもは純粋なのではなくて、未熟なだけだ。
先人が何を言っているか知ることは大切だ。
しかし、先人の言うことが正しいとは限らない。
そんな姿勢が大切だ。
「コンコルドの誤り」の誤りどころか、人間は自分に都合の悪い図式を否定する傾向がある。
これを心理学者のレオン・フェスティンガーは「認知的不協和の理論」といった。
例えば、タバコが肺ガンにつながる、という知識に接すると、自分は喫煙をしているという知識と、喫煙は肺がんになるという知識との間には不協和が生じてくる。
この認知的不協和を低減するために、肺がんになるという知識を打ち消すような情報を探すなど、不協和を低減するためのさまざまな方法がとられる。
いわば、戦前の日本軍の大本営情報状態になることがある。
自分でウソを流しておきながら、いつの間にか自分に都合のいい情報だけを信じる方向に走ってしまうのだ。
晩年のエジソンも狂気に走ったひとりだ。
人に宿る霊的な知性は死後も存在すると考え、死後の世界との交信装置の開発に取り組んだ。
「天才とは1%のひらめきと99%の努力のたまもの」という名言も、むしろ1%の霊感の重要さを訴えたのだという。
最後まで電化の方式を直流にこだわって、交流が危ないということを証明するために電気椅子を発明したことは有名だ。
また、発電機の改良に挑戦した研究者に「そんなことができたら5万ドル払う」といい、彼がみごと成功すると「君はユーモアがわからないのか」と支払いを拒んだ。
怒った研究者は、ライバル社に移り「発電の天才」と呼ばれる業績をあげた。
土星型原子模型の提唱で世界的な業績をあげた長岡半太郎も1924年に「水銀を金に変える実験に成功した」と発表して世間の注目を集めたことがある。
結局はもちろん、間違いだったのだが、大阪大学初代学長を務めた男でも十数年間その誤りから抜け出せなかったのだから思い込みは怖い。
チョーサーの「カンタベリー物語」(岩波文庫)はカンタベリー大聖堂に詣でる巡礼者がさまざまな物語を語る話だ。
「完訳 カンタベリー物語〈上〉 (改版)」(岩波文庫)チョーサー(作)桝井迪夫(訳)
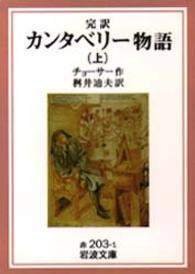
「完訳 カンタベリー物語〈中〉 (改版)」(岩波文庫)チョーサー(作)桝井迪夫(訳)

「完訳 カンタベリー物語〈下〉 (改版)」(岩波文庫)チョーサー(作)桝井迪夫(訳)

錬金術師の徒弟が出てきて、宿の主人に師匠のことを話すうち、「あまりに知恵がありすぎると、人はそれをあやまって使う」と語りだし、「わたしの主人もそういうことなんです」。
ついには師匠の錬金術のいいかげんさを暴露し、それを耳にした師匠は宿から逃げ出した・・・・・・
ドイツの精神医学者ランゲ・アイヒバウムが天才の多くが分裂病圏の人だと述べたことは有名である。
彼の説によれば、正常であるということは、ただ平凡であるに過ぎないということになるかもしれない。
すると、正常はよくて、異常は悪い、と単純に決められなくなる。
【一言】
インターネットというか、このハイパーテキストというのは、ネットワーク的で、拡張しやすい、自由に飛べるセレンディピティ・・・・・・
予期しない発見があるどこにいくかわからないものなのである。
こうしてみんなと出会えるのもインターネットの、セレンディピティのおかげである。
「セレンディピティ」という言葉を科学以外の思わぬところで発見することもある。
オードリー・ヘップバーン主演の『パリで一緒に』(Paris When It Sizzles)という映画(1964年)はウィリアム・ホールデン演じる脚本家が映画の中で映画を作っていくという劇中劇になっているのだが、この中でセレンディピティが出てくる。

ホールデンから「昔からある言葉で、どんなことが起きても幸福を生み出すことができる能力だ」と説明される。
私の見た字幕では「楽天」と訳されていたが、これを聞いてヘップバーンが「楽天?」と聞き返すのだ。
どんな困難の中にあっても希望の光を発見する才能がセレンディピティなのである。
2001年にはジョン・キューザック主演の『セレンディピティ』という映画もできた。
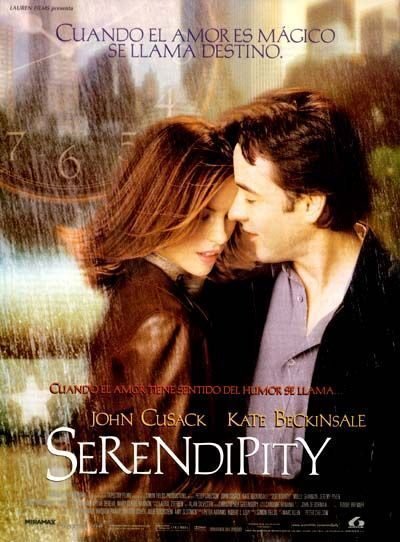
女優のケイト・ベッキンセールがとてもいい映画だが『めぐり逢えたら』に似たような設定というのが悔やまれる。

しっかし、こんな文章ばかり書いていて何になるだろう?と不安になることがある。
だが、セレンディピティというのは、生活の知恵なのだ。
井上ひさしが「出っ歯の十得」を書いたのを真似て安野光雅は「出っ腹の十得」というのを考えて、曰く「孫を雨宿りさせられる。
上にものを置いて机代わりに使える。
いざというとき大事なところを火傷しなくてすむ。
カメラのフィルム交換の時にちょっとした台になる。
雨の日でも花火ができる。
土左衛門になった時は早く見つけてもらえる・・・・・・」だそうだ。
そして、阿川佐和子は、「いつもひとりで」(大和書房)の中で結婚しない十得を考えている。
「いつもひとりで」(文春文庫)阿川佐和子(著)

「門限がない。
友達と長電話をしていても亭主に文句を言われない。
毎日毎食、料理を作らなくてすむ。
自分の都合で寝坊ができる。夜更かしもできる。
お風呂場から裸で出てきても大丈夫。
テレビを独占できる。
ワイシャツのアイロンかけをしなくていい・・・・・・」
そして、子どものいない十得は「お弁当を作らなくていい。交通事故にあったんじゃないかとヒヤヒヤしないですむ。受験戦争の苦労がない・・・・・・」。
頭をプラス思考に向けようと思ったら、できるだけ具体的な例を思い浮かべるにかぎる。
つまり、セレンディピティはプラス思考で生きていくことにつきるのである。
実際、ノモス的人間に囲まれていると、カオス的人間は生きにくい。
生きづらい。
周りがみんな敵に見えてくるものだ。
ゴーゴリの短編に「鼻」(岩波文庫)がある。
「鼻/外套/査察官」(光文社古典新訳文庫)ゴーゴリ,ニコライ・ワシーリエヴィチ(著)浦雅春(訳)
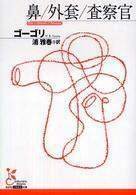
朝、ある役人が鼻のにきびを見ようと鏡をのぞいて驚いた。
鼻がなくなり、のっぺらぼうなのだ。
逃げた鼻を探すため彼は街へ、と幻想的な物語を滑稽に描く。
「不合理というものはどこにもあり勝ちなこと・・・・・・こうした出来事は世の中にあり得るのだ」ともっともらしく書くのがおかしい。
いきなり虫になるカフカの世界や、みんな犀になっていくイヨネスコの世界も不条理だ。
私自身も、いつか、セレンディピティができ、カオスの大切さを周りに納得してもらえる日が来ると、信じて生きていこう。
「果報は寝て待て」という言葉がある。
文献では正保2年(1645年)発行の俳諧作法書『毛吹草(けふきぐさ)』の中の、ことわざ集の中に「くはほうはねてまて」と登場する。
何もしないで寝ているのではない。
人事を尽くして天命を待つということだ。
家宝が空の上から降りてくるのでは決してない。
「あなたはどうやって万有引力の法則を発見したか?」と聞かれたニュートンは答えたのが有名だ。
「ひたすら考えつづけることによって」とニュートンは答えた。
ということで、果報は寝て待て!
三年寝太郎のように寝ころんで、水平思考をしようっと!
そうそう、まことに不思議なもので、「果報は寝て待て」を実証するような研究がなされていた。
2004年の1月に発表された記事である。
独リューベック大学の研究で十分な睡眠が「ひらめき」を促すことが分かった。
研究グループは、18―31歳の66人が、8つ並んだ数字の列を7つの数字の列に変換し、7番目に来る数字を答えていくゲームをするうちに、7つの数字の並び方の規則性を発見できるかを確かめた。
ゲームでは「1、4、9」の数字からなる8つの数字の列を使う。
並んだ数字が「同じだったらその数字を選ぶ」と「違ったならもう一つの数字を選ぶ」だけがルール。
変換した7つの数字の列には7番目が2番目と同じになるという規則性がある。
このゲームを3回した後、〈1〉8時間寝た〈2〉8時間起きていた(夜間)〈3〉同(昼間)――の3グループに分かれ、再び同様のゲームを10回行った。
この結果、再挑戦でひらめいて規則性を見抜いた人は、〈2〉と〈3〉のグループではともに22人中5人(22・7%)だったのに、〈1〉では2倍以上の13人(59・1%)に上った。
事前の学習なしに、ただ寝た後にゲームを行っただけでは、ひらめきに差はなかった。
研究グループは、一時的に蓄えられた記憶が、睡眠中に再活性化され、記憶として整理される過程で、それまでの知識や記憶と相互作用し、ひらめきを促したと推論している。
余談だが、息抜きがうまいことも指導者として大切だ。
第二次大戦で英国を勝利に導いたチャーチルは空襲下のロンドンでも昼寝の習慣を守っていた。
ニクソン元大統領は、「指導者とは」(文藝春秋)で、アイゼンハワーやケネディなどの大統領に向けられた、休暇が多すぎるとの攻撃を間違いだと一蹴している。
「指導者とは」(文春学藝ライブラリー)ニクソン,リチャード(著)徳岡孝夫(訳)

正しい決断を下せるかどうかが重要で、ゴルフで気晴らしができるなら「遠慮なく書類を擲ってゴルフ・コースに出るべきだ」と勧めている。
アハ体験ということが喧伝されるようになった。
分からない図形があって、一度アハと分かると以後はそれ以外には見えなくなるようなものだ。
これを広めた茂木健一郎「「脳」の整理法」(ちくま新書)には、次のような言葉が書かれている。
「「脳」整理法」(ちくま新書)茂木健一郎(著)

是非、心に留めておきたい。
「学習とは、教室の中で答えの決まったドリルをやることだけではありません。
先に見たように、脳の中の神経細胞の間の結びつきは、常に変化し続けています。
脳は、いわばつねに学習し続けているのであり、その中で、「鯉」はやがて「竜」になるような変化が訪れることが実際にあるのです。
学習の機会は、日常生活の思わぬ局面で訪れます。
街を歩いていて、ふと耳にした言葉や、集会で偶然出会った人の話。
新聞でたまたま目にした記事。
家の近所を散歩していて気づいたこと。
日常の行為を繰り返す中で、偶然出会う体験の中に隠れている偶有性を私たちの脳が整理する中で、思わぬ発見がある。
その発見が「私」を変えていき、ときには、自分自身の人生を変える劇的な変化をもたらす。
そのような、人生における絶えざる学習のプロセスの中に埋め込まれているのが、セレンディピティなのです。
今日のように、急速に変化する時代には、ある一定の知識を身につけておけば、それで一生十分ということはありえません。
むしろ、自分の脳をオープンにしておいて、いつでも生きるうえで必要な何かが入ってくるように、スペースを空けておく必要があります。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
