
【本棚のある生活+α】2023年1月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
今週から、毎週、週末にでも、月毎に読破した本と鑑賞してみた映画を備忘録として紹介してみたいと思います(^^)
月イチペースで、今月、読んでみたい本とかを、先月の内にリストアップして、特に、今月何冊読むとか決めずに、通勤時とか隙間時間等を活用して読んだりしています。
また、ぶらっと立ち寄った本屋さんの平台を眺めたり、古本屋の棚を眺めていて手にとってみた本が自分の感性にマッチしたら、この本の様に、リストに縛られることなく購入(^^)
「活字中毒養成ギプス―ジャンル別文庫本ベスト500」(角川文庫)ぼくらはカルチャー探偵団(編)

私も活字中毒だと思うけど、重度活字中毒者たちの世界は、とても濃厚で奥深いなあ、と改めて感心させられました(@@)
さてと、朝晩、爽やかな風が吹いて来はじめて、灯火親しむ頃になると、そんな本の世界で、ゆっくりと、のんびりと、気楽に読書に耽りたいものですね。
本を愉しむ♪
時には立ち止まり考え、時には感嘆の吐息をもらし、本を愉しむ。
ひとりの時間を退屈せずに過ごせるので、そんな時間を持っていたいし、持っていただきたいなぁ、と思います(^^)
本を愉しむ読み方は、それはそれで、さまざまですよね。
本を愉しむには、色々あって、必ずしも読むばかりが能ではないし、ね。
文を愉しむ、表現を味わう、会話に酔う、ストーリーを追うなどなど。
本がだんだんにたまるのも愉快だし、読まない本をいたずらに積んでおくのでも、粋なものです(^^)
いずれにせよ、読みたくなったら、読んだらいいし、別段、読まなくても問題ないから。
でも、少しは、本を愉しみたいと思っているのなら!
例えば、前述の様な本のガイドブックを参考にして、お気に入りを探しに、ぶらっと本屋さんや古本屋さんに、立ち寄ってみるのも良いと思います。
本選びに関しては、自分の勘だけでなく、書評やガイドブック、口コミなど、自分以外の人の意見もどんどん参考にしては如何でしょうか。
本との新しい素敵な出会いがあるやもしれませんよ(^^)
まあ~、そんな感じなので、考えてみれば知識がほしいと思って読んだ本でも、月日が経過する程、内容は、ほとんど忘れてしまっています(^^;
もちろん、本は、読んだときは、年齢相応に大きな影響を人に与えてくれるのだから、その後、忘れたって価値がないわけではありません。
最近は、読んでいるうちに、ふと読むのを止めて考え込んでしまうことがあります。
以前は、結構、早く読むことばかり考えていたけど、実は、読書とは、本を読みながらゆっくり考えることだったようです。
じっくり、ゆっくり、繰り返し読みながら考える。
これって、結構楽しいですよ(^^)
宮内優里「読書 (feat. 星野源)」
ということで、2023年1月に読めた本や観た映画の中から、特に面白かった本(3選)と見応えがあった映画(2本)のご紹介です。
【特に面白かった本3選】
1.「量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突―」(新潮文庫)マンジット・クマール(著)青木薫(訳)

読書メモ:
スマホから核兵器まで、現代のテクノロジーの源にある量子力学。
20世紀初頭、この新しい物理学の解釈をめぐり、アインシュタインとボーアは論争を繰り広げていました。
量子論の100年を追うノンフィクション本です。
アインシュタインとボーアを軸に、ハイゼンベルク、シュレーディンガーなど天才たちが織りなすドラマは読み応え大です。
2.「デタラメ データ社会の嘘を見抜く」カール・T・バーグストローム/ジェヴィン・D・ウエスト(著)小川敏子(訳)

読書メモ:
ソーシャルメディア上では、同じような興味や関心を持つ人たちが集約される傾向にあるため、確証バイアス(自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向のことを指す。 政治、経済、ビジネス、SNS、日々の実生活等のさまざまな場面で散見される。)が強く機能します。
そのため、ある事柄に対して、懐疑派には、例えば、危険だという情報だけが集まり、日ごろから抱く信念を肯定してくれます。
すると、それが嘘かどうかをファクトチェックしようという気持ちも薄くなります。
なにせ、自分の考えに合っているのですから。
そして、繰り返し、同じような主張を目にしていると、それが真実だと錯誤する(真理の錯誤効果)ようになります。
注意しないと^^;
3.「生命を守るしくみ オートファジー 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム」(ブルーバックス) 吉森保(著)

読書メモ:
オートファジーの研究は、長らく進展していませんでした。
その研究を切り開いたのが、酵母を用いた大隅先生です。
その結果を、著者らが哺乳類に展開したことにより、大きく発展しました。
特に、選択的オートファジーの機構解明や、ブレーキ役であるルビコン(オートファジーを抑えるブレーキ役のタンパク質で、これが老化で増えることがわかりました。)の発見・機能解析には感心させられます。
「研究の良し悪しは、役に立つか立たないかでなく、ワクワクするかどうかで決まる」の言葉は、次世代業務自動支援システムの研究開発・実証試験を経験してきたので胸に響きます。
(おまけ)
書籍を通じて科学者の生き方・考え方、科学のおもしろさ・素晴らしさを届ける事業である「科学道100冊プロジェクト」において、学者×本のプロによる選書が、以下の通り行われていますので、興味のある方は確認してみてください(^^)
【見応えがあった映画】
1.西部戦線異状なし

徹底した反戦目線で描かれた、西部戦線の長大な塹壕での独仏の戦い。
毎日、次々と仲間たちが犬死していきます。
終戦まであとわずか。
その様な状況下で、最前線で敵の塹壕に攻め込む愚かさ。
塹壕の空を見上げれば、終戦を知らせる無数のビラが舞います。
そこに勝利者はいるのか。
因みに、1914年から1918年までの間、西部戦線は、ほとんど動くことない膠着状態にあり、多くの戦死者をだしました。
この戦況は、日露戦争でいうところの203高地に近いかもしれません。
きな臭い社会情勢が続く、今の時代に、訴えかける戦争の愚かさ。
本作が訴えかける意味は大きいと感じます。
2.インターステラー

本当の物理学者が本気で考えたストーリー。
【参考記事】
【参考書籍】
「ブラックホールと時空の歪み―アインシュタインのとんでもない遺産」キップ・S. ソーン(著)林一/塚原周信(訳)

週末、予定も無いし、外に行く気力もない。
そんな方は、ぜひとも、21世紀版「2001年宇宙の旅」である今作で、ちょっとヘビー目(上映時間も2時間 49分と長い)の宇宙旅行を体験してみては?
ノーラン監督らしいスケールと難解さだけど、最後は、人情味溢れる家族映画へ。
父と娘の信頼の絆は、重力と同様に、時間の壁を超えていく、この映画からは、色んな気づき事項が有りました。
・届かないものを信じる真実と届くものを信じてしまう弱さ
・声が届かない苦しみ
・結局自己完結から脱却できない人間の思考パターンの脆弱性
・重力と愛が超えさせる(ブラックホールと愛)
・重力と時間の概念の変化
・愛は観察可能な力(愛の数値化は量ではなく行動。特にコンタクト方法がより重要。)
泣けるSF映画として、是非、覚えておきたい逸品です。
【二言三言】
「ディラン・トマス全詩集」ディラン・トマス(著)松田幸雄(訳)

映画「インターステラ―」の中で、ディラン・トマスの詩が引用されています。
ディラン・トマスの詩「穏やかな夜に身を任せるな(Do not go gentle into that good night)」の一節でしたが、とても有名な詩(死に瀕した父親を見守り、嘆願する子供の様子をうたったものです。)です。
この映画自体が、滅びゆく地球と人類。
そして、愛する家族のために宇宙へ旅立つ父親の物語。
一度は捨てていた自分の人生。
それを取り戻して、困難に立ち向かっていくという意味でもある映画です。
また、何事かを成し遂げるのにも、時に必要とされるのは、貪欲さとか、理不尽を許さない怒りだと感じます。
その様な物語だから、この詩の内容に、とても良くマッチしていて、印象に残る詩篇でしたね(^^)
こんな感じの詩です。
《和訳①》
穏やかな夜に身を任せるな
老いても怒りを燃やせ 終わりゆく日に
怒れ 怒れ 消えゆく光に
最期に闇が正しいと知る賢者も
その言葉で貫いた稲妻はなく 彼らが
穏やかな夜に身を任せることはない
叫ぶ善き人よ あれは最後の波 どんなに明るく
そのかよわい行いが 緑の湾で踊ったことか
怒れ 怒れ 消えゆく光に
軌道をゆく太陽を 捕え歌った荒くれ者よ
遅すぎて過ちを知り その道行きを弔った
穏やかな夜に身を任せるな
墓守たちよ 死を間近に 盲目の目で見る者よ
見えない眼は流星と燃え 鮮やかにもなれたはず
怒れ 怒れ 消えゆく光に
そしてあなたよ 私の父よ その悲しい高みから
呪いたまえ 祝いたまえ 烈しい涙でいま私を
穏やかな夜に身を任せるな
怒れ 怒れ 消えゆく光に
《和訳②》
あの穏やかな夜におとなしく身を任せてはいけない。
老いたならばこそ燃え上がり、暮れゆく日に荒れ狂うべきだ。
消えゆく光に向かって、怒れ、怒れ。
最期を迎える賢人たちは暗闇こそが正しいと知っているが、彼らの言葉が電光を発することはないのだから、彼らはあの穏やかな夜におとなしく身を任せることはない。
儚い行ないが緑の入り江でどれほど明るく躍動したかもしれないと最後の波を前にして叫ぶ善人たちよ、
消えゆく光に向かって、怒れ、怒れ。
荒れ狂う者たちは逃げ行く太陽を捕まえ謳歌し、そして学ぶ、遅すぎたと。
逃げ行く太陽に悲観するのだ。
あの穏やかな夜におとなしく身を任せてはいけない。
死期が近づいた威厳を持った者たちの眩い光景を見て、盲目と化した瞳が流星のように輝き煌びやかであるように、
消えゆく光に向かって、怒れ、怒れ。
そしてあなた、私の父よ、その悲しみの絶頂にいる私を荒れ狂う涙で呪い、祈ってくれと願う。
あの穏やかな夜におとなしく身を任せてはいけない。
消えゆく光に向かって、怒れ、怒れ。
【補足情報(ネタバレ注意!)】
この映画では、全世界で軍はなくなっていました。
その様な環境下に置かれた地球では、生きていくこと、つまり、食糧のことが最重要問題です。
そのため、軍事にかけられる財源も無く、争っても仕方ないと気づいた人類。
ここまでいかなければ争うことを止めることができないんでしょうね^^;
まるで、シェイクスピアのロミオとジュリエットの両家の争いのようにも感じます。
物理学者が考えた未来は、とてもクールに世界観を表しているなと、改めて、そう思いました。
【リストアップした書籍】
「「世界文学」はつくられる 1827-2020」秋草俊一郎(著)

「歴史は現代文学である―社会科学のためのマニフェスト―」イヴァン・ジャブロンカ(著)真野倫平(訳)

「システム・エラー社会 「最適化」至上主義の罠」ロブ・ライヒ/メラン・サハミ/ジェレミー・M・ワインスタイン(著)小坂恵理(訳)

「量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突―」(新潮文庫)マンジット・クマール(著)青木薫(訳)
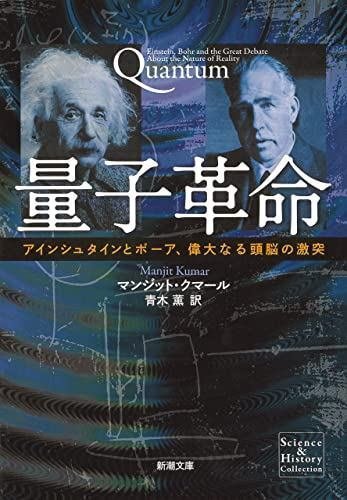
「歴史に残る外交三賢人 ビスマルク、タレーラン、ドゴール」(中公新書ラクレ) 伊藤貫(著)

「市民的抵抗 非暴力が社会を変える」エリカ・チェノウェス(著)小林綾子(訳)

「論点・日本史学」岩城卓二/上島享/河西秀哉/塩出浩之/谷川穣/告井幸男(編)
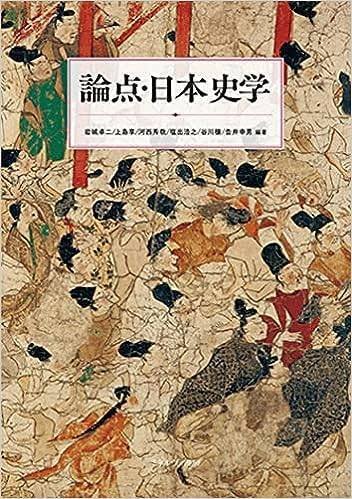
「ジャリおじさん」(日本傑作絵本シリーズ)大竹伸朗(著, イラスト)

「算数文章題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学力不振」今井むつみ/楠見孝/杉村伸一郎/中石ゆうこ/永田良太/西川一二/渡部倫子(著)
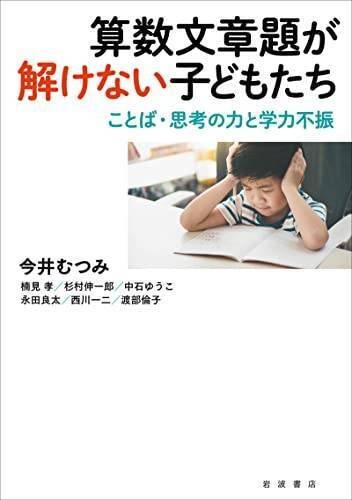
「多様性の科学」マシュー・サイド(著)

「人はなぜ物を欲しがるのか」ブルース・フッド(著)小浜杳(訳)

「東大連続講義 歴史学の思考法」東京大学教養学部歴史学部会(編)

「論点・西洋史学」金澤周作(監修)藤井崇/青谷秀紀/古谷大輔/坂本優一郎/小野沢透(編)

「論点・東洋史学 アジア・アフリカへの問い158」吉澤誠一郎(監修)石川博樹/太田 淳/太田信宏/小笠原弘幸/宮宅潔/四日市康博(編)
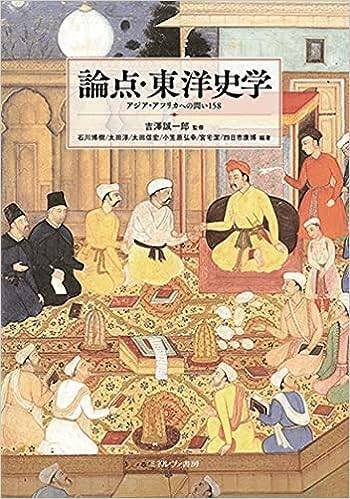
「反穀物の人類史―国家誕生のディープヒストリー」ジェームズ・C・スコット(著)立木勝(訳)

「物語創世 聖書から〈ハリー・ポッター〉まで、文学の偉大なる力」マーティン プフナー(著)塩原通緒/田沢恭子(訳)

「デタラメ データ社会の嘘を見抜く」カール・T・バーグストローム/ジェヴィン・D・ウエスト(著)小川敏子(訳)

「我が友、スミス」石田夏穂(著)

「人工知能は人間を超えるか」(角川EPUB選書)松尾豊(著)

「生命を守るしくみ オートファジー 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム」(ブルーバックス) 吉森保(著)

「プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本 交渉・タスクマネジメント・計画立案から見積り・契約・要件定義・設計・テスト・保守改善まで」橋本将功(著)

「動機づけ面接を身につける 一人でもできるエクササイズ集」デイビッド・B・ローゼングレン(著)原井宏明(監修)岡嶋 美代/山田英治/望月美智子(訳)

「小説の惑星 オーシャンラズベリー篇」(ちくま文庫)伊坂幸太郎(編)
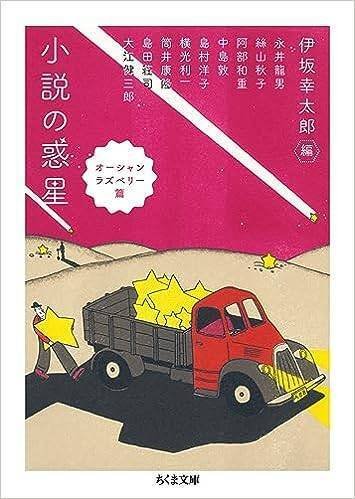
「詐欺師の楽園」(白水Uブックス) ヴォルフガング・ヒルデスハイマー(著)小島衛(翻)

「ザ・フォーミュラ 科学が解き明かした「成功の普遍的法則」」アルバート=ラズロ・バラバシ(著)江口泰子(訳)

「上流思考─「問題が起こる前」に解決する新しい問題解決の思考法」ダン・ヒース(著)櫻井祐子(訳)
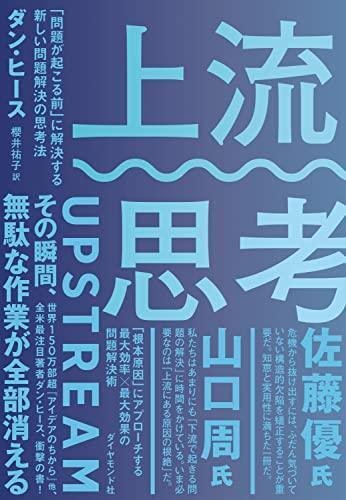
「恐怖の地政学 ―地図と地形でわかる戦争・紛争の構図」ティム・マーシャル(著)甲斐理恵子(訳)

「終りなき夜に生れつく」(クリスティー文庫) アガサ ・クリスティー(著)矢沢聖子(翻)

「セックスロボットと人造肉 テクノロジーは性、食、生、死を“征服"できるか」ジェニー・クリーマン(著)安藤貴子(訳)

「アート・オブ・プロジェクトマネジメント ―マイクロソフトで培われた実践手法」(THEORY/IN/PRACTICE)Scott Berkun(著)村上雅章(訳)

「アジャイルプラクティス 達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣」Venkat Subramaniam/Andy Hunt(著)木下史彦/角谷信太郎(監訳)

「歴史をどう語るか 近現代フランス、文学と歴史学の対話」小倉孝誠(著)

「「期待」の科学 悪い予感はなぜ当たるのか」クリス・ バーディック(著)夏目大(訳)

「誰よりも、うまく書く 心をつかむプロの文章術」ウィリアム・ジンサー(著)染田屋茂(訳)

「小説の惑星 ノーザンブルーベリー篇」(ちくま文庫) 伊坂幸太郎(編)

「ロウフィールド館の惨劇」(角川文庫) ルース・レンデル(著)小尾芙佐(訳)

【関連記事】
多読・濫読・雑読・精読・積読それとも?
https://note.com/bax36410/n/n17c08f767e73
【本棚のある生活+α】2023年2月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1e809f8ad981
【本棚のある生活+α】2023年3月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n5b9792df1aa9
【本棚のある生活+α】2023年4月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n1255ac2dcf12
【本棚のある生活+α】2023年5月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n72c887bf894a
【本棚のある生活+α】2023年6月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n81559c79dd80
【本棚のある生活+α】2023年7月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n0d1664588d07
【本棚のある生活+α】2023年8月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nefb833a75642
【本棚のある生活+α】2023年9月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nf3d7ecad89cc
【本棚のある生活+α】2023年10月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/nea4c59c8cadc
【本棚のある生活+α】2023年11月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/ndb4b28943a59
【本棚のある生活+α】2023年12月に読んで面白かった本と見応えがあった映画
https://note.com/bax36410/n/n3b772659b3e0
【参考記事】
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
