
「知ってる」と「できる」は全くの別物だね^^;
ゲーテ曰く「知るだけでは足りない。それを使わなければいけない。願うだけでは足りない。それを実行しなければいけない。」と・・・・・・
知識はあるのに、考えているだけで行動できていない。
行動できても、自分の軸がしっかりしていないので続かない。
どちらが欠けていても、能力をフルに発揮することは難しいから、頭と身体の両方を使えるように変わっていく必要があります。
特に、注意すべきは、この頭を、どう使うかってこと。
検索すれば簡単に情報が手にできる今の時代では、誰もが手にできる情報自体に、あまり大きな価値はありません。
しかし、その使い方次第では、そこに価値を生み出せるのも事実です。
情報が入ってきても、自分で何かを経験し感じなければ、気持ちは豊かにはなれないから、いろんなことを経験して、自分の気持ちを豊かにしていくことが大切です。
簡単に、たくさんの情報が入ってくるからこそ、知りすぎている一方で、感じなさすぎていないか?
この点に配慮しながら、経験と気持ちを大事にしていく。
多くの情報よりも、価値のある、または豊かな情報を入手して、それを実際に活用していくことが重要だと考えています。
堀場製作所創業者である堀場雅夫さんが言っていましたが、特に、普通の人がおもしろいヤツ、つまり、興味を持たれるおもしろいヤツになるためには、やはり、まずは、自分だけの豊かな情報を持てるように努力することがポイントです。
前述の通り、誰もが検索して入手できる情報は、目新しくもなく特別なものでもないため、自分が直接聞いたり、体験した一次情報を大事にしていく必要があります。
自分だけの経験や情報は、小さなことでも興味の対象になるため大切に扱っていきたいよね(^^)
但し、多すぎる情報は、自分の心を亡くす可能性が高いため、情報から自分を守ることに注意が必要です。
検察ツールなどで、簡単に情報が入る時代だからこそ、そこから本質を見抜く力が必要になり、多くの情報の中から、自分で取捨選択し、情報に振り回されないようにしないと^^;
情報が多ければ判断が楽というものではないから、情報判断能力を高めなければ、これからもっと情報に振り回されることになるので、いろんな情報に惑わされないように、大事な情報が何かを見極めていかなくてはなりません。
情報が多くなれば、その分間違った情報や憶測でしかない情報も増えてくるから、必要な情報が何かを見極めて、適切な判断と行動をするように要注意です^^;
その処方箋としては、すべての情報に目を通そうとしてもムダであるため、自分に関係のない情報は、はなから必要ないと考えて、情報の海で溺れてしまわないようにしないといけないので、以下の記事とか参考になります。
【関係記事】
情報が入りすぎれば、それだけ情報に惑わされ、気持ちもブレてくるから、多くの情報に振り回されないように、情報に優先順位をつけてみることをおすすめします。
知らないからというだけで、自ら範囲を限定しては、それ以上のことは期待できないので、思い切って必要ない情報を遮断することで、頭を一度整理してみる。
自分の思考範囲を広げることで、これからの可能性と期待を大きくしていく。
自分が知っている範囲だけで考えて、視野を狭くしないように気をつける。
自分にできることより、自分にできないことを知る方が大事なので、どんなことでも、まず気づくということを意識するようにしています。
気づくか気づかないかは、その後の考え方や行動に全て影響するし、気づいていなければ、どんなことをしても、その人には響かないからなあ^^;
要は、この”生”を無駄にしないで、私は自分にできることをやったとみずから言うことができるようになりたいと考えています。
いろんなことを考えて悩んだとしても、やったかやらないかで全ては決まるので、自分が納得できて、後悔しないように、今できることを実行してみる。
やらないで心に残り続けるより、思い切ってやってみて、改善しながら進んでいく方が建設的だしね(^^)
ただ、すべての事ができるわけではないから、取捨選択が大事になってくるけど・・・・・・
そう、人は、自分ができる事をするだけ、それだけでよいのだと、そう思っています。
できることをやっていないのに、考え過ぎて不安になってしまっている人も多いと思うのですが、まず、目の前にある、自分のできることを、確実に実行していく。
できることを確実に実行していくだけでも、気持ちの面では違ってくるから、「できるけどやらないだけだ」と自分に言い聞かせている間は、「できない」ということを別の表現で言っているに過ぎないので要注意です^^;
確かなことは、ただ考えているだけでは、何も起きないし、状況を変えることはできないから、考えているではなく、実際に自分でやったかどうかを判断基準にしていきたいね!
そうそう、自分への戒めでも有るのですが、どんなに金言名句をたくさん知っていても、どんなに良い気質を備えていても、機会が来るたびに具体的に行動に出なければ、人格は少しも向上しないんだよね^^;
多くの人は、大事なことや、やるべきことは既に分かっているのに、行動に移していないことって、多いと思うけど、知識を持つことではなく、それをもとに行動することに重点を置きながら、実際に自分でやってみたことは、人から聞いた多くの知識や情報よりも価値があるんだよね(^^)
百知って何もしないより、三知って、その三つを実践するほうがいいし、知識や一時的な感動を繰り返し増やしても、行動がなければ何も変わらないので、自分の知識を、行動によって成果に変えていくことを意識しています。
知っているのにできなければ、理論も知識もただの屁理屈といわざるをないし、知識や情報がある人はたくさんいるけれど、それを実際に活用し実行している人は少ないから、どれだけ知っているかではなく、どれだけ実行できたかを重視して、入ってきた知識はどんどん試して実践していこうぜ!
自分が知っている範囲だけで生きる者は、想像力を欠く者であり、自分が知っている範囲だけで考えて、視野を狭くしないように気をつけないと、ね^^;
そうそう、評論家になるのなら、どんんどん知識だけを採り入れていけば良いかもしれないけど、自分がプレーヤーになりたいのなら、入ってきたものを行動に反映させていかないといけないから^^;
確かに、ものを知らない人は、よくしゃべり、よく知っている人は、あまりしゃべらないような気がするけど、気のせいかな?
自分の思考範囲を広げることで、これからの可能性と期待を大きくしていかないと、時代の流れに乗れないし、、また、知らないからというだけで、自ら範囲を限定しては、それ以上のことは期待できないので、その点、常に、ケアしていかにといけないことだと考えています。
但し、コミュニケーションの量は大切だと思うけど、いくらたくさんしゃべっても、要点がはっきりしなければ、相手には伝わらないから、短い言葉、簡単な言葉で、どれだけのことを伝えられるかを考えて、普段から、実践していますが、書き言葉から話し言葉への変換は、別なスキルが必要で、なかなか困難です^^;
その場合、注意すべき点として、自信のなさを言葉の数で補うのではなく、一つ一つの言葉を大事にしてみること。
私は、教職についたことはありませんが、以前、公文の先生をしていたことがあって、小学生の低学年から高校生の算数・数学を教えていた時に感じたことは、先生は、すべてを知っているのではなく、むしろ知らない部分について、より多くの自覚を持っている者なのではないか?
そうであれば、そのことから導き出されるのは、自分の知らないこと、弱みが何なのかを自覚して、知らないことや弱みが何かを分かっていなければ、対処のしようがないってこと^^;
分からないことを早く対処することで、成長のスピードを早めていけるので、たくさんのことを生半可に知っているよりは、なにも知らない方がいい場合もあるってことです。
中途半端な知識や情報が自分の行動を妨げている場合も、往々にしてあることを自覚しておくことは、非常に、重要な点であると考えています。
ここまで長々と、「知ってる」と「できる」は全くの別物だってことを書いてきましたが、言い換えると、同じ状態がこの先もずっと続くことはなく、変化は必ず必要になってくるのですが、「知ってる」から「できる」への、大袈裟に言うと、パラダイムシフト的な変化って、たとえ良い方向に変わっているときでさえ、常に障害と不快がともなうため、変化を恐れて進めない、または、それさえも”気づけない”場合があると考えています。
ここで、この曲を聴いてみて下さい♪
「変化に気づかない」でのショートムービーのその後を表現した「凩(=こがらし)」のMVです。
ユアネス-yourness- 「変化に気づかない」
ユアネス「凩」
【関連情報】
多くの人達が幸福や成功を手にできない理由に、今までの自分が変化することに対する恐れがあげられるのではないかと推定しています。
成長したいと思いながらも、慣れ親しんだ自分が変わる、変化するということに勇気が持てないんだとも推量できます。
そう、自分の意思とは関係なく、いつかは変化しなければいけない時が来ます。
過去に固執して変化しないままであれば、また、変化することを躊躇して何もしなければ、いずれ衰退する時が来ることは必然です^^;
勇気を出して、今までとは違う、変化をすることに挑戦していこうぜ!
そのためにも、色んな評判やうわさに惑わされないで、情報を自分で判断できるようにしておかなくては^^;
学問を知っている人は、学問を愛する人に及ばないし、学問を愛する人は、学問を楽しむ人に、到底、及ばないんだってことを意識して、時には、情報量よりも情報の質にこだわって、頭の中を整理してみながら、知っていてできるということを、楽しめるというレベルに変えていきたいね(^^)
同じことをやっていても、どんな気持ちでやっているのかで、これから先どれだけ伸びるか、可能性が広がってくるかも違ってくるから・・・・・・
その道の専門家は、話題にできそうな最大ミスのいくつかを知っていて、その回避方法も知っている人のことなのだと指摘されていましたが、回避できるリスクは、事前にその対策を考え施すことで、回避していかないと、ね^^;
さてと、最大の障害は、自分自身の中にあることを自覚して、現在、未来のリスクについても考慮しながら、そして、リスクを冒しても挑戦するときと、リスクを回避する対策を施す時を混同しないで、リスクに対する見かたを変えていきながら、「知ってる」から「できる」への変化に対応して適応しなければ、現状は今のままいつまでも続かないから、注意していきましょう!
だって、自分が変わらなければ好転しないでしょ(^^ゞ
自分を変えるためにはどうすればいいか?
ご存じの方もいるかもしれませんが、元マッキンゼー日本支社・社長の大前研一さんによると、以下の3つの方法で人は変われるといっていましたね。
————————————————————————————————
人間が変わる方法は3つしかない。
1番目は時間配分を変える。
2番目は住む場所を変える。
3番目は付き合う人を変える。
この3つの要素でしか人間は変わらない。
最も無意味なのは「決意を新たにする」ことだ。
————————————————————————————————
早速、1番目の時間配分を変えてみて、日々の決意をnoteやブログに記するも良いよね♪
意思は行動のモトになる!!から、ね(^^)
【参考サイト】
【参考図書】
「私たちは子どもに何ができるのか――非認知能力を育み、格差に挑む」ポール・タフ(著)駒崎弘樹(その他)高山真由美(翻訳)
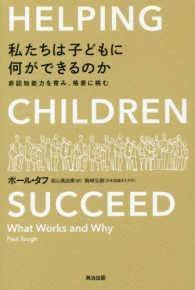
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
