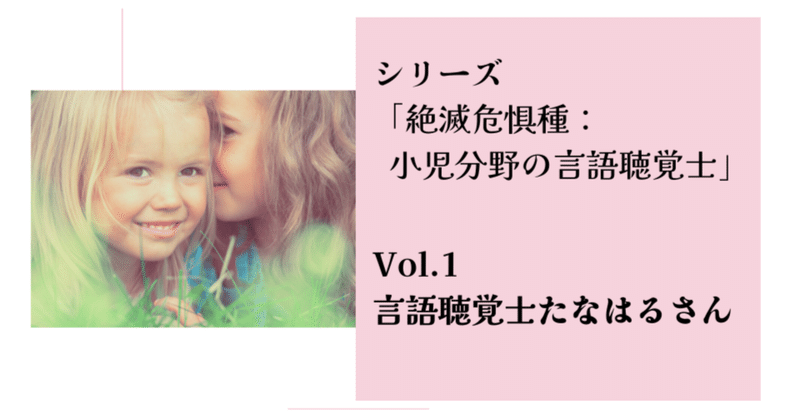
発語の有無よりもまず「生活」に目を向けて。【Vol.1】言語聴覚士たなはるさん
言語聴覚士。ことばによるコミュニケーションに難がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職である。
小さな子どもをもつ親は「子どもがなかなか言葉を話さない」「特定の発音が難しい」など、言語発達に課題や不安を感じたとき、彼らの支援を受けたくなるだろう。
しかし残念ながら、生活圏内でアクセスできる小児分野の言語聴覚士は非常に少ない。
そこでこの連載では、小児分野の言語聴覚士やその育成に関わる方に話を伺い、子どもの言語発達に関するトピックや、言語聴覚士としての活動内容などを紹介する。
子どもの言語発達に悩むすべての人に、この記事が届きますように。
* * *
今回お話を伺うのは、大学病院で8年間小児の療育を担当し、現在は子育てをしながらメールで支援を行っている、言語聴覚士のたなはるさんです。

「今日からできる!ことばを支えるかかわり」をテーマに、Instagram・ブログ・音声配信Voicyなどで発信している言語聴覚士。大学・大学院にて心理学を専攻し、2013年に国立の言語聴覚士養成校を卒業後、大学病院にて勤務。リハビリテーション部の言語聴覚士として主に小児を担当し、2021年までの8年間で延べ650人以上のお子さん及び親御さんと出会う。2021年3月に病院を退職し、現在はメールにて個別相談を受付中。プライベートでは3歳・0歳の男の子の母。
小児に関わり、研究も臨床もできるなら…言語聴覚士を志す
——はじめに、たなはるさんが言語聴覚士になった経緯や理由を教えてください。
たなはる(以下略):私は大学で社会心理学を、大学院で発達心理学を専攻していました。院生時代に、研究の世界に身を置くか、それとも手に職をつけて働くかを検討していたときに、大学院の授業で「日本赤ちゃん学会」の存在を知りました。その学会では、研究者や医者だけでなく言語聴覚士も発表を行っていました。
その話を聞いたときに「言語聴覚士なら、研究も臨床も両方できるんだ!」と知って。研究も臨床もしたかったので、そこから言語聴覚士を目指し始めました。
そして言語聴覚士の養成校へ進学して資格を取得。実習先の大学病院に就職し、8年間勤務しました。
——8年間の病院勤務はいかがでしたか。
多くのお子さんや親御さんに触れ、さまざまな経験を得ることができました。私が担当していたお子さんは2歳~中学生まででしたが、多くは2歳~就学前のお子さんです。通っていただくのは数年、長くても10年弱ですが、週1回〜月1回と定期的にお会いする間に、ことばに限らずお子さんを取り巻くさまざまな相談を受けることも多かったですね。
——特に印象的だったお子さんはいますか?
3〜4年ほど関わった自閉症スペクトラムのお子さんです。彼女は2歳から通ってくるようになったのですが、外の世界への興味が見られず表情も固め。言葉は一言も出ていませんでした。
そこから数年間、いつもと違うことで癇癪を起こしやすいため、課題を毎回ほんの少しずつ変化させながら実施しましたが、なかなか言葉は出ません。でもだんだんと関係性が構築できてきて、彼女も「ここに来ると、この人がいるんだな」と認識し、課題の流れも理解するようになりました。
そしてあるとき、絵カードを見せたら急に「パン」って言ったんです。
親御さんと「え…?話した…?!」と、顔を見合わせて。そして2人で泣きました。
彼女が通い始めて3年、就学前の出来事でした。
(※お子さんが特定できないよう、表現に配慮しています)
——それは思い出深いですね。ジーンとします……。
その親御さんからは、通い終わる際に手紙をいただいたんです。
「最初は障害のことがわからず、毎回同じ課題をやっても泣いたりわめいたりで、本当に身になっているのかと不安になるときもありました。でもある日、パズルに向き合ってピースをひとつはめたとき、そして得意げに全部完成させたとき、私の中に光が見えました。そしてトンネルから出たときに、自分がトンネルの中にいたことに気がついたんです。本気で向き合ってくださり、ありがとうございました」と。
もちろん、これを読んでまた泣きました(笑)。
でもこの方だけでなく、療育を卒業する際にお手紙やお写真などをくださる親御さんは多く、毎回嬉しかったですね。

言語発達の前に生活を整える重要性
——たなはるさんは現在、SNSで「家でできる療育」などに関して発信されています。1〜2歳の子どもの発語に不安を感じたら、まず何から取り組んだらよいのでしょうか。
最近はSNSなどで子どもに関する情報が溢れているので、焦ってしまう親御さんは多いと思います。でも1〜2歳は発達の幅が広い時期で、1歳で言葉が出るお子さんは多いけれども、まだ出ていないお子さんもいます。発達の個人差が非常にあると知ってほしいですね。
言葉を出そうと思うと、つい言葉にアプローチしがちですが、実は生活リズムや睡眠、食事など、生活面を整えることの方が重要です。
発語は口周りの筋肉を動かせるようになることであり、その筋肉は体全体の筋肉コントロールをベースとしています。よって、生活リズムなどを整えて、子どもの体を成長させる必要があるのです。それに寝不足や空腹などで不快感があると、発語にまで至れないことも多いですから。
——生活面は問題なさそうなのに言葉が出ない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
お子さんは、人と関わることを楽しんでいるでしょうか?どんなに言葉が話せても、人と会話をしないと独り言になってしまうように、言葉はツールでしかありません。まずは、お子さんが他者とどう関わっているのかに目を向けてみるとよいでしょう。
子どもは「一人遊び」から覚えていきます。そこに親御さんがさりげなく入っていき、気づいたら一緒に遊んでいるようにします。例えば、子どもがミニカーで遊んでいたら、隣で別のミニカーを走らせてみたり、「この車は赤色だよ」と話しかけてみたり。大人がグイグイ迫ると子どもは引いてしまうので、さりげなく寄り添って、一緒に遊ぶ楽しさを伝えるのがおすすめです。
——3〜4歳の子どもについて、家で取り組むとよいことは何ですか?
3〜4歳なら、外で思い切り体を動かしたり、家の中でさまざまなおもちゃを使って遊んだりと、できることの幅が広がります。
おすすめなのは、親御さんのお手伝いをしてもらうこと。料理や洗濯物たたみをすると、手首や指先をしっかり使うので、手先や指先の発達が促されます。それに、家族の一員として役割をもって「ありがとう」と感謝されることが、言葉のやりとりや自信の醸成にも繋がるんです。
レタスをちぎる、泡立て器でぐるぐると回すなどの簡単なお手伝いから頼んでみてください。
SNSを見て不安になる前に、客観視できる人に相談してほしい
——子どもの言語発達が気になるときに、意識した方がよいことを教えてください。
意識してほしいことはふたつあります。
ひとつは、SNSで他の子どもと比較しないこと。ネット上は美談が多いですし、自分の子どもにぴったりと当てはまる内容はないからです。
とは言っても、私も親なので、SNSやWEBサイトで調べたくなる気持ちは非常によくわかります(笑)。そんなときは、自分のお子さんの「過去」と比較してみてほしいです。
毎日一緒にいると、子どもの成長はあまり実感できません。でも少し期間を空けて見ると、驚くほど成長しているのがわかるんです。
おすすめは、定期的にお子さんの動画を撮っておき、1ヶ月後や半年後などに見返すこと。意識的に記録しておくと、お子さんの成長ポイントを見つけるクセがつきますよ。
もうひとつは、一人で考えて不安にならないこと。多くの場合、親御さんが「これはおかしいかも…」と思うことは、だいたい当たっていると思います。一番近くでお子さんを見ていますから。
その違和感を身近な人に相談すると「気にしすぎだよ」と言われることもありますが、違和感を放置して不安になるくらいなら、こどもの発達を客観視できる立場の人に見せてほしいと思います。
<身近な頼れる人・施設>
かかりつけの小児科医
役所の家庭児童相談員
地域の子ども家庭支援センターや児童館(子育て支援センター)
困ったときは、こうした相談先があることを知っておくと安心です。
——最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
コロナ禍での育児に加え、情報が溢れ過ぎていて、その取捨選択が難しい時期ですよね。でも今のお子さんと過ごす時間は今しかありません。スマホを見て不安になるよりも、まず客観視できる人や機関に相談して、一歩踏み出してみてほしいと思います。
言語聴覚士は約38,000人しかおらず、そのうち小児領域の専門家は約4,000人といわれており、現役で働いている方はさらに少数です。そんな「絶滅危惧種」の言語聴覚士を知って、そのノウハウに触れていただくためにも、私はこれからもさまざまな情報を発信していきます。
お子さんについて「今心配すべきこと」「まだ心配しなくていいこと」「この先ずっと心配しなくていいこと」がありますので、その内容も伝えていきたいですね。
いただいたサポートは取材代もしくは子どものおやつ代にします!そのお気持ちが嬉しいです。ありがとうございます!
