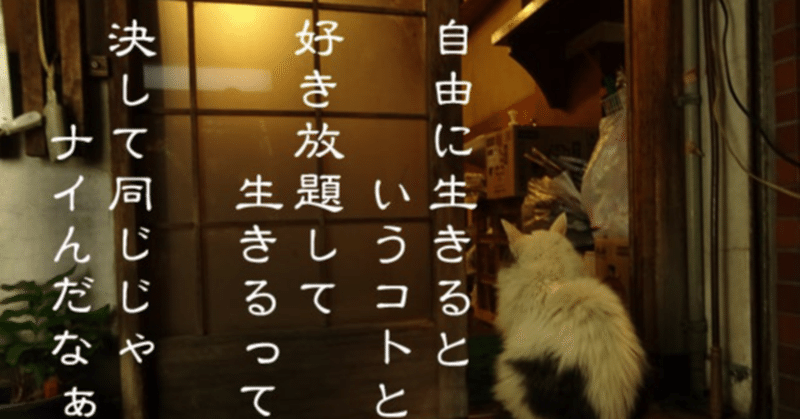
24時間営業を辞めたコンビニ〜1月の販売数値の動向〜「デイリー品」
「価値観の多様化」と「自己中」という境界線の狭間で
皆さんこんにちわ、あやすけです。
2月に入りましたね。クリスマス寒波との戦いのあとに迎えた当店の平和な日々は、その後すこし経って完全に消え去りました。1月は「2度の大雪」という敵の大攻勢がありましたが、何とか乗り越えることが出来ました。
今年の冬から除雪業務の委託を辞め全て自前で行うこととしている当店ですが、昨年と比較して降雪量が少ない印象であるとはいえ、現時点までに除雪に係る委託費はゼロです。加えて言えば、軽トラはすげぇ車だと再確認しました。子供時代に親戚の家の農業を手伝っていた時以来、長らくその偉大さを忘れていたことを想い出した私です。経験とは、いつどこで役に立つか分かりませんね。
一方で、「2度の大雪」と同様に、当店の販売数値にも敵の攻勢が始まるサインが見え隠れしてきた1月でした。今後の日販の鍵を握るであろう「客単価」と、その先行指標である「買上点数」に黄色信号が灯り始めたようです。撤退戦を継続中の当店に対し、敵の追撃がいよいよ始まるのでしょう。
当面の敵は既にコロナではなく、インフレとそれによる購買意欲の減少、その結果としてのコンビニ以外への客数の流出、となるでしょう。同時にコロナ流行以前からの敵である、日販上昇の力を上回る「経費の増」についても、未だ健在であるどころかその勢いを増しています。
上記を踏まえ、やるべきことは今月も引き続き変わりありません。
生き残ること、これが最優先です。
撤退戦ですから、まぁ当然の帰結です。そしてそのためには、他人ではなく自分だけが決定権を持っている自らの「境界線」の線引きを、「自己中」寄りに引き直して準備することにしましょう。スタンスを変えることは、わたし大得意ですから(笑)
それでは、デイリー品における当店1月の販売数値の動向です。
1.基礎数値
・日販
前年比106%(100%)
コロナ禍初年度比92%(104%)
24時間営業時比84%(89%)
・客数
前年比105%(93%) ※参考 前前年比105%
コロナ禍初年度比78%(97%)
24時間営業時比73%(76%)
・客単
前年比102%(107%)
コロナ禍初年度比117%(108%)
24時間営業時比115%(116%)
・買上点数
前年比97%(100%)
コロナ禍初年度比106%(101%)
24時間営業時比103%(105%)
※( )は前月の数値です
現時点における、当店経営陣の今後の数値の見立ては以下のとおり。
「客数」・・・コロナ禍からの回復度合いは2021年並に留まる
「客単価」・・・上昇度合いの頭打ちから今後ゆっくりと数値が低下
「日販」・・・コロナ禍初年度であった2020年並に留まる→つまりコロナ禍
以前には戻らない
1月の数値の状況と照らし合わせると、前月の状況とは反対に客数は予想以上に上ブレ、客単価は上昇の頭打ちが終わったものの予想以上に大幅低下、結果として日販は前年より6%の上ブレ&コロナ禍初年度と比較して8%の下ブレ、となりました。客数の前年比&前前年比が5%も伸びたことは嬉しい誤算でした。また、コロナ禍初年度の1月&2月のコロナによる日販への影響は未だ少なかったことも、数値に影響しているかも知れません。
現在のところ、10月の経営数値に基づき立てた上記の見立てを変更する要因は無いと視ていることから、今後の数値が見立て通りに推移する確率は高いと考えています。一方で、客単価&買上点数の数値低下が予想以上に大きかったため、日販低下という大波は想定以上に早く来る可能性も高くなりました。
以上の事から、これまでと同様に、その上昇度合いが低下すると予想される「客単価」を少しでも長い期間下支えすることを基本的な取り組みとしつつ、8月から経営方針を変更した「廃棄額」の適正化による経費のスリム化に軸足を置くウェイトを重くして取り組む、という方針は今月も変更ありません。当然のことですが、撤退戦は継続です。
2.前年比upした分類
◯米飯→前年比111%(112%)
・「おにぎり→大幅up」
・「チルド弁当→up」
・「寿司→大幅up」
・「弁当→大幅up」
・「こだわりおむすび→大幅down」
・「御飯→大幅up」
前月と同様、状況に変化はありません。「客単価」と「付加価値」を重視した取り組みが数値に表れています。地区平均と比較しても大幅に優位な数値であることも変化なしです。一方で、廃棄率の数値は依然として高めであることも変化なしです。
引き続き、前月までと同様に「販売額と廃棄額をどのスケールまで小さくするのが妥当か」という視点に基づき、取り組みを継続します。理想とするゴールまでの道のりは、この分類においてはまだまだ長い道のりとなりそうです。
◯フライヤーその他→前年比109%(97%)
・「フライヤー→大幅up」
・「中華まん→大幅down」
・「おでん→取扱い無し」
8月から経営方針を一部変更した「経費のスリム化」に基づき、従前より仕込み数を減らしている分類となりますが、直近2ヶ月の前年比割れから今月は大幅に販売数値が改善しました。地区平均と比較しても同水準です。一方で、廃棄額の数値は予算を大幅に超えました。
前月までの数値を視た上で販売額と廃棄額のバランスが妥当な水準であると結論付けた先月でしたが、1月の数値を視て分かるとおり、今後はその「妥当と見込んだ水準」を如何にして毎月コントロールするか、加えて地区内でもトップレベルの販売額を如何に維持するか、という視点が重要となるでしょう。
上記の視点から今月の数値を視た結果は、100点満点中50点となります。
◯スイーツ→前年比121%(110%)
・「チルド洋菓子→down」
・「チルド和菓子→大幅up」
・「チルド洋菓子NB→大幅up」
・「ヨーグルト→大幅up」
・「プリン、ゼリー→大幅down」
フライヤーと同様に立地的に弱い分類である「スイーツ」について、自店の強みにする取り組みを6月から開始していますが、前月に引き続き数値は上ブレであることに変更無しです。併せて地区平均の数値と比較しても大幅に優位な数値であることも同様です。
8月から経営方針を一部変更したことに伴い、「自店の強みとする取組」と「経費のスリム化」という2つのバランスを取ることを重点として取り組んでいますが、11月から3ヶ月連続で数値が上ブレした結果でした。その数値を牽引しているのは、「チルド和菓子」&「チルド洋菓子NB」です。一方で、廃棄率の数値は「洋菓子」「和菓子」ともに高く、予算額を超えてしまった1月の結果でした。加えて、スイーツ全体の販売額も、地区平均の数値と比較すると自店の強みと言える程の金額の水準には程遠い現状です。
「廃棄額をチルド洋菓子で抑えつつ、販売額前年比をチルド和菓子で稼ぐことで、立地的に弱いスイーツを自店の強みとする」という、定石とは真逆の方針に基づいて取り組みを継続している現状ですが、その方針に基づいて数値を視た結果は、100点満点中60点です。
◯調理パン→前年比107%(92%)
・「サンドイッチ→大幅up」
・「ロール→大幅down」
・「ブリトー→大幅up」
前年比の数字が割れている状況が数ヶ月続いていましたが、今月の数値は上ブレしました。地区平均の数値と比較しても大幅に優位な数値です。数値を牽引している分類を視ると、付加価値がそれ程高くないと見込んでいる「サンドイッチ」であることから、分類全体の数値が1月に上ブレした要因は、おそらく予想外であった「客数の前年比増」でしょう。
経営数値の今後の見立てについては始めに書きましたが、今後の「客数」の推移の見立てによれば、数値上昇の牽引役が「サンドイッチ」のままの状況が続くのであれば、1月の数値の上昇は「たまたま」となるでしょう。
一方で、現在の当店の状況は「撤退戦」です。たとえ客数が減少することが確定事項であり、だからこそ付加価値の高い商品分類に注力することがセオリーであったとしても、撤退戦においてはその「余力」に限りがあります。
以上のことを踏まえ、結論は単純なものとなります。限りある資源を売れている分類に集中しましょう。しかしその集中すべき分類である「サンドイッチ」には、将来性は無い&伸び代は無いということを頭に入れておくべきでしょう。またいつの日か、付加価値が付けやすい&将来性が高いと言える「ロール」の分類に注力出来る日が、きっと来ることでしょう。
3.前年比downした分類
◯ペストリー→前年比99%(89%)
・「惣菜パン→up」
・「菓子パン→大幅down」
・「NBパン→大幅down」
・「ドーナツ→大幅up」
8月から前年比の数値が改善し始めた状況が続いていまいしたが、12月の数値は再び下ブレし、1月もその傾向は継続中です。「惣菜パン」の好調は依然として継続しているものの、「菓子パン」の不調が大きく惣菜パンの好調さを打ち消しています。一方で、廃棄率はほぼ適正値です。
分類全体では、地区平均と比較してほぼ同水準をかろうじて維持できてはいるものの、今月の客数の前年比が105%であること、加えてこの分類は現状において客数依存の度合いが強いことを考慮すると、販売額と廃棄額のバランスが上手く取れていない可能性が大きいです。
今後は、「販売額と廃棄額のバランス」という視点から、販売数値が比較的に好調な「惣菜パン」に資源を集中することを方針として発注に取り組んでいきます。また、撤退戦の状況という視点に立ち、付加価値が現状において見込めないこの分類について、「地区平均と同等の販売数値で十分」という方針を継続します。
◯デリカテッセン→前年比97%(96%)
・「惣菜→大幅up」
・「サラダ→大幅down」
・「主菜→大幅down」
・「食事サラダ→大幅up」
・「副菜→up」
前年比の数値が大幅にupした状況が続いていた分類ですが、先月に引き続き今月も下ブレしました。一方で、地区平均の数値と比較して同水準です。
問題となるのは、先月は客数の前年比が下ブレでしたが、今月は上ブレであったことです。今月は客数が前年比で上向いているにも関わらず、販売額が依然として下ブレを継続している状況ですが、その要因として可能性があるのは、しばらくブームが続いていた「中食」という流行が、もしかすると下火になってきたかも知れないという事です。その原因は、恐らく「インフレ」による購買意欲の減でしょう。
以前からこの分類については、販売額の将来の伸び代は少ないという認識ではありましたが、上記の見立てが正しかった場合、そのブームの天井は予想以上に早い段階で到来してしまった可能性もあります。何故なら、お客様の現在の購買心理において、「背に腹は変えられない」という状況になっていてもおかしくない状況とも言えるからです。そしてその状況は、恐らく今後まだしばらくは続くでしょう。
今後の方針は「様子見」です。現状の品揃えと廃棄率を維持しつつ、今後の数値を注視することとします。万が一、数値低下の継続が確認された際には、「ペストリー」と同様の方針としたいと思います。
◯麺類・その他→前年比82%(93%)
・「カップ麺→大幅down」
・「スパパス→大幅down」
・「グラタンドリア→大幅up」
・「うどん焼きそば→大幅up」
地区平均と同様の水準である状況が2ヶ月続いていましたが、今月は地区平均と比較して数値が劣後しました。廃棄率が極端に低い訳では無いことから、この一進一退の状況が継続している原因は、やはり「品揃え」ではないようです。加えて、今月は客数の前年比が上向いていることを併せて考えれば、その見立ての正当性も妥当と言えます。
・・・現状、打つ手は思い付きません。当面は様子見をしつつ、「地区平均と同等の水準」まで数値を回復させることを理想として耐え忍んで行くこととします。
それでは今日はこの辺で。
このクソッタレな世界と戦う皆様と明日もともに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
