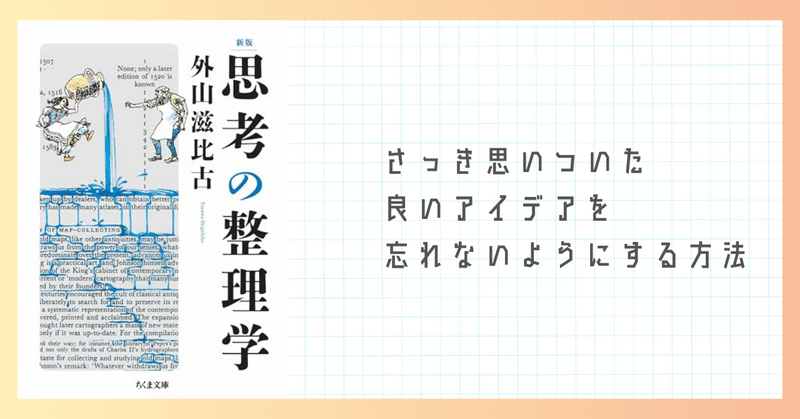
【本要約】考える力とは何なのかを考える「思考の整理学」
「よく考えろ」ってなんなのでしょうか?
よくわからないですよね。
しかし本記事を読めば、それがわかります。
そのもやもや、スッキリしますよ。
こんにちは、けいごです。
「考える力」って大事ですよね。しかし、実際には抽象的で、理解できない。そのため、考える力自体がなんなのかを知る必要があります。
本記事では、それを理解するための「思考の整理学」という本を紹介します。
スマホ社会の問題点
本書は1986年に発行されたものです。そのために、PCが世に出始めた頃の視点で描かれています。しかし、著者が見ている世界では、現代のスマホ社会でも同じように思えます。
テクノロジーの発達によって、情報の検索が安易に出来るようになり、「考える力」が衰えていくことを問題視しています。
物事には表面に出ているものと、裏面の見えない物があります。考える力のない人は、常に花にばかり着目し、枝や幹、根っこは見ない。根っこを見ることは花が出来る過程に必要であるのに、です。
「思考の整理学」では、本の中で「考えること」についてまとめています。
思考の種類
本書では、思考の種類を大きく分けて以下の3つに分類しています。
発酵
カクテル
アナロジー
それぞれ、具体的にまとめていきます。
発酵
源氏物語やシェイクスピアは、時代によって評価が変わっています。作品は変わらないのに、何故このようなことが起きるのかというと、以下が理由です。
人間は自分の解釈をつくらずにはいられない存在
2〜3年経つと解釈に解釈が加わる
解釈を作るということは、「Aのものを読んで理解したら、A'になる」ということです。つまり「別物」です。
これが「発酵」するということになります。
しかし実際には食品の発酵とは違い、思考の発酵は人それぞれのタイミングの差があります。
思考の発酵が始まれば、自然と頭の中のゴチャゴチャが動き出します。寝かせてタイミングを待つことも重要ということです。
カクテル
すぐれたバーテンダーは、カクテルに自分の主観を全面には出しません。自我を抑え、良いものと結びつきやすくして、はじめてすぐれたカクテルになります。
例えば自論Xがあったときに、他のA、B、C、Dの4つの説のうちBに近かったとしたら、AもBもCもDも、それぞれ適度に参照しながら、新しい調和を考えます。
すると独断に陥らない、手堅さを持つ論ができます。
アナロジー
ビジネス書が好きな方であれば、アナロジーという単語を聞いたことがあるのではないでしょうか?
これは、比喩表現のような物です。本書では、アナロジーを数式で表していますので、以下に記載します。
A:B=C:X
何かわからないことを「X」としたときに、何か知っている物事と比較して公式で考えると、物事が理解できたりします。
中学校の数学になりますが、この公式を求めるには以下のようにします。
X=BC/A
今まで感覚でアナロジーしてたものが、この公式でスッキリです。
情報を整理する
情報には3つの種類があります。気になる方は以下の本を読んでみてください。
本書内容で、簡単に整理すると以下のようになります。
一次情報:フィルターがかかってない情報
二次情報:一次情報に捉え方が入った情報
三次情報:二次情報に対する感想や評価
著者いわく、一次情報→三次情報に進むにつれて、「段階的抽象化」をしていく。一次情報を他の情報と関連させ、まとめることで二次情報となります。
ここで、先ほどのアナロジーや発酵などが役立ってきます。
良いアイデアを忘れない方法
良いアイデアを忘れないようにするには、メモするしかありません。
例えばトイレでnote記事のテーマを思いついたときに、紙でもスマホでもなんでも良いのですかさずメモします。
本書でお薦めしているメモの方法として、以下があります。
スクラップ
手帳とノート
それぞれ、まとめていきます。
スクラップ
新聞の切り抜きや本の大事なところを切り取って貼ったり袋に入れたりします。
ネットがある現代であれば、スクショしてアルバムに入れるような感覚でしょうか。
しかし、これも溜まり過ぎてしまわないようにしましょう。一定期間寝かせて、不要であれば捨てる。そうしないと重くて身動きが出来なくなりすぎ。脂肪を捨てれば身軽になるように。
手帳とノート
手帳には、ハッと思いついたアイデアも必ず記入します。そして、見出しをつけ、軽く要点をまとめておき、日付をつけます。
こうして発酵させておくと、アイデアが必要なときに手帳をパラパラとめくっていたら、使えそうなアイデアに辿り着く可能性があります。
ふと思いついたアイデアは無駄にしないようにしましょう。
情報は適度に捨てる
今まで記録してきた情報は、適切なタイミングで整理して捨てましょう。
整理とは、その人の持っている関心、興味、価値観によって、ふるいにかける作業です。
価値観がはっきりしていなければ、大切なものをすて、どうでもいいものを残してしまいます。
仮に価値観の物差しがあっても、ゴムで出来ていれば、時によって整理に間違いが出てきます。
そのため、価値観を把握し、都度再吟味することが重要です。
考えるとは何か?
情報は発酵させ、カクテルにして、アナロジーを使い、整理しながら新しい世界を作るために使います。
本書において、思考を整理するということは以下のことを指します。
適度に忘れて頭をスッキリさせること
物がを適度に忘れ、頭をスッキリさせることでゴチャゴチャだった頭の中が整理され、「考える」ことが出来るようになります。
それによって自論を作り出し、それもまた再吟味する。これが、考えるということです。
もっと「考えること」について具体的に知りたい読者さんは是非読んでみてください!
難しい比喩が多い本ですが、理解できれば頭がスッキリしてゴチャゴチャがなくなりますよ!
読書要約・書評リスト
Xもよろしくお願いいたします。
「趣味では年4回、妻と国内海外問わず旅行すれば幸せ」
— Keigo.log@内省ライフハック (@K84275195) May 6, 2024
「仕事では地域の人にサロンに参加してもらい、そこから地域の輪に繋がるとやりがいを感じる」
一日一行でも「日記」を書けば、
このような数値的・具体的
価値観把握が可能です#note#日記#自己分析#価値観
https://t.co/WfjQHszBsr
ご一読有難う御座いました! もし「ここがわかりやすい」「ここがわかりにくい」などありましたら、ご遠慮なくコメント欄にご投稿ください!
