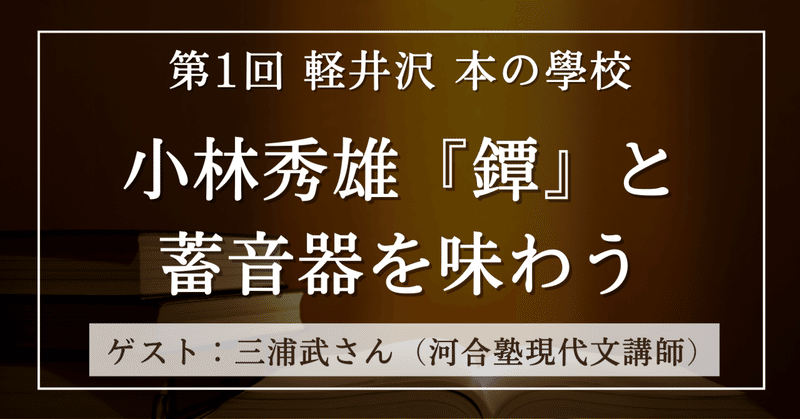
「考えるには、身を交わらせることが大事なんだ」小林秀雄が僕らに残した言葉とは?【イベントレポート】[第1回] 軽井沢 本の學校
2022年10月16日(日)、あさま社は「軽井沢 本の學校」第1回を開催しました。
◇「軽井沢 本の學校」とは
コンセプトは、”本と出会う場所”。今読むべき「名著」を選び、新たな視点で、本の読み方をナビゲートします。インターネットによる手軽で便利な情報が溢れる中、読者の深いところに共振する本の世界。川端康成、堀辰雄、室生犀星といった文豪たちが愛した軽井沢という土地で、文学の世界にトリップする体験を提供します。
詳細はこちら
記念すべき第1回のテーマは「小林秀雄」
扱ったのは、小林秀雄のエッセイ、『鐔(つば)』。意表をつく言い回しが多いといわれる小林秀雄の文章を、軽井沢という土地でじっくりと味わいました。
さらに、音楽愛好家としても知られる小林秀雄がいかに「音楽」を味わっていたか、音楽の世界も追体験。蓄音器から響く音色を堪能し、タイムトリップするかのような特別な時間を共有しました。
会場は、軽井沢・追分宿にある「信濃追分文化磁場 油や」。堀辰雄らが執筆に利用したという、文学にゆかりのある旅館です。
この記事では、当日の様子をレポートします。
◇◇◇
ゲスト:三浦武さん
大手予備校・河合塾で25年以上のキャリアを持つ現代文講師。著書に『現代文をていねいに読み解く』(KADOKAWA)、 共著に『ことばはちからダ!現代文キーワード―入試現代文最重要キーワード20』(河合出版)、『評論・小説を読むための新現代文単語 』(いいずな書店)がある。
聞き手:河野通和さん
「軽井沢 本の學校」校長。中央公論新社「婦人公論」「中央公論」編集長や、新潮社の季刊誌「考える人」の編集長を歴任。「ほぼ日の学校」を立ち上げ、学校長を務めた。
◇◇◇

2人の出会いは、小林秀雄がきっかけでした。
2013年4月。新潮社の季刊誌『考える人』の創刊10周年企画として、80ページにもわたる小林秀雄特集号が発売されました。当時、編集長を務めていたのが、他ならぬ河野通和さんです。
河野:特集号をつくっていたときに、小林秀雄作品を手がけた先輩編集者から「河合塾に、小林秀雄を熱心に教えている名物講師がいるんだよ」と紹介を受けました。それが、三浦さんとの出会いのきっかけです。
特集号発売後に会いにいったところ、三浦さんは、開口一番に僕に言いました。「あの小林特集号のおかげでエラい目に遭いましたよ」と(笑)。実は三浦さんは、特集号を20冊ほど購入し、熱心に周囲に配ってくれていたんです。頭が上がりません。
ただ、小林秀雄がきっかけで出会った私たちですが、ずっと小林秀雄の話をしてきたわけではありません。今では蓄音機が、私たちのお付き合いのメインです。
小林秀雄を熱心に読み、蓄音機の魅力にもどっぷりはまるという、共通点の多い2人。和やかな雰囲気で、トークが盛り上がります。
河野:会場の皆さんは、小林秀雄作品にどんなイメージをお持ちでしょうか?いい思い出を持っている人は、少ないのではないかなと思います。というのも小林は、試験問題で悩まされた…という作家の代表格ですから。
でも、心配ありません。この学校では、いわゆる学校がやるような「正解を出すための読み解き」ではなく、もっと自由に味わって、作品を楽しんでいきましょう。本には読み方の正解はない。いくつも読み方があって当たり前。そのことをお伝えしたくて、今日は小林秀雄作品を選んだのですから。

発売即重版という絶好調の売れ行きでした。
一同は、手元に配られた『鐔(つば)』の原稿を開きます。刀の鐔について書かれた、小林秀雄のエッセイです。
三浦:河野さんのいうように、今日は、正しいとか間違っているとかを超えて、冒険をしましょう。強いられてやる勉強って、面倒だし、すぐに忘れてしまうものです。でも強いられたところから一歩踏み出して、過剰にやりはじめると、物事は面白くなるもの。
問題を解くためだけではなく、味わおうと思って読むと、なかなか楽しいと思いますよ。
三浦さんが、音読を始めます。会場一同、軽井沢の空気を吸いながら、じっくりと小林秀雄の世界に身を委ねていきます。

実はこの『鐔』というエッセイは、2013年に「センター試験」の評論文に出典として使われました。その年の国語の平均点が例年よりも大きく落ち込んだことで、マスコミでも大きく取り上げられ、話題になりました。
三浦:このエッセイが、小林の最高傑作だとは言いません。でも、1960年代の作品の中でももっとも重要なもののひとつだと思っています。
序盤の内容を、粗雑に要約すると、鐔が美しいものになっていった前提には、応仁の乱という混沌がある。人間は戦乱の混沌に耐えられず、痛ましい中で、切実に美しいものを求めた。その結果、あくまで実用性に立ちながらそれを超えるものが鐔に求められ、ひとつの文化になっていったという話です。
三浦さんは自身の軽快なエピソードも交えながら、親しみやすい調子で読解を進めます。
三浦:この『鐔』という文章のもっとも大事なポイントは、書き出し部分に隠れています。小林は書き出し部分では、鐔について「いろいろ説があり、不明な点が多いのだが。」と曖昧さをにじませていますよね。
しかし次の段落まで読み進めていくと、小林は、実際に鐔をいじってみたことで、鐔とは応仁の乱という混沌の産物だと「はっきり気付いた」と書いています。誰かに聞いているうちは曖昧だったけれど、実際にいじって体感することで、鐔についての考察を深めた。曖昧から確信へと変化した、この対比が重要なんです。
小林秀雄は『鐔』を書いた1960年代、代表作である『本居宣長』の連載を始めています。その本居宣長の言葉から、「考える」という行為について、こんな文章を残していたそう。
三浦:「考える」は、古語だと「かむかふ」。「かむかふ」の「む」は身、「かふ」は交ふ(交わる)と指すのだというわけです。つまり、身を交わらせることこそが考えることなのだと、小林は紹介しました。これは、『鐔』を発表する少し前に書かれた文章です。
近代では、対象を自分と切り離して、距離を置きながら物事を分析することが多いですよね。でも、切り離して得られる知なんてないよ、と小林は言っているのだと思われます。考えるには、身を交わらせることが大事なんだと。
この主張を、小林秀雄自身の文章作法に落とし込んで考察することもできるといいます。
三浦:個人的に、小林は『鐔』の中で、自分の文章作法について告白しているのかなと考えています。
小林の文章は、観念で読むから難しい。でも思考のリズムだと思って、解釈しようとせずに書いてあることをたどれば、考えが深まっていくんです。それでもわからないことは疑問を一旦保存して、何年でもかけて自分の体でじっくり探していけばいいと思います。

ここから話は、『鐔』に書かれている変化の過程に及びます。
『鐔』では、鐔が素朴なものから、抜き差しならないかたちを経て、装飾に凝っただけのものへと変遷していく過程を考察しています。鐔はもともとは素朴な実用品で、刀匠や甲冑師がつくるものでした。しかし大乱が始まり「平常心、秩序、文化を捜さねば生きて行けぬ」と思った人々が、徹底的に実用性を追求していく過程で、専門の鐔工が現れるなど鐔のあり方が変わっていったのだと小林秀雄は書いています。
三浦:人間は最後の最後、生物として大事なものよりも、自分が人間であるために大事なものを求めるという話でしょう。この文章を読んで私は、幼い頃に父から聞かされた、あるエピソードを思い出しました。
1945年1月23日のベルリンの話です。1945年は、ベルリンが史上もっとも破壊されたといわれた頃。空襲が続いている中でも、なんとベルリン・フィルのコンサートは開催されていたというのです。しかも、コンサートの途中で空襲警報が鳴り、停電しても、客は帰らなかったそう。街を歩いているだけで誰何されたり、とつぜん射殺されたりといった、人が人として扱われていない極限状態でした。その中で、自分が人間であるために大事なもの、それがベルリンの市民にとっては音楽だったのでしょう。
切実な状況だからこそ、人は芸術を求める。『鐔』の話と音楽に共通性が見いだされたところで、いよいよ蓄音機のゼンマイが巻かれます。1曲目はオーストリア出身のヴァイオリニスト、クライスラーによる『ロンドンデリーの歌』です。

ここから主題は音楽に。三浦さんは、小林秀雄が体感してきた音楽の世界を紹介していきます。
小林秀雄は『モオツァルト』という評論を著作に持ち、音楽愛好家としても知られます。そんな彼がはじめて生で聴いた世界的なヴァイオリニストは、ミッシャ・エルマンだったそう。
三浦:1921年、当時浪人していた小林は、エルマンの来日コンサートを聴きに行っています。小林は、エルマンをはじめ、クライスラー、ティボーなどなど、来日した有名バイオリニストの公演をもれなく聴いていたみたいですよ。 メニューインは戦後まもなく来日し、小林はそれを聴いて翌日にはもう「あなたに感謝する」という一文を発表しています。
時が経ち、1982年の11月にもメニューインが来日し、コンサートを開催しました。その様子は年が明けた頃に、テレビで放送されています。この放送時、高齢になった小林は、病床である2階から下りてきて1階のテレビの前に座り、耳を傾けたといいます。これがおそらく、生前最後のメニューインとのふれあいでした。
音楽に魅了された小林秀雄の人生に思いを馳せながら、三浦さんは、メニューインの「ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K. 216 第2楽章」や、ナタン・ミルシテインの「アンダルシアのロマンス」を再生。小林秀雄が感じてきた世界を、参加者全員で追体験します。

三浦さん所蔵の蓄音機は1930年頃もの、針は1940年頃のものだそう。
希少なレコードや蓄音機を多数所有する、コレクターでもある三浦さん。楽しげな語り口から、音楽への愛が伝わります。その後もレコードやヴァイオリニストについて盛りだくさんの話をしながら、時間の許す限りレコードを再生。アルノルト・ロゼ、クライスラーなどの演奏が、会場を包み込みました。
小林秀雄の心に入り込むような、不思議な2時間半。終盤で、河野さんが本日の「授業」を総括します。
河野:今日、初めて蓄音機からの音を聴いたという方は、私が初めて聴いたときと同じように、体の震えを感じたのではないでしょうか。まさに、昔の演奏家がここに立っているかのような臨場感や感動があったかと思います。
前半で三浦さんから、「かむかふ」ということばの解説がありましたが、つまりは、考えるとは身を持って対象と親密な関係をつくることだと小林は考えています。蓄音機で聴く音楽体験は、この「かむかふ」というキーワードに通底するものがありますよね。
小林秀雄は物にも人にも体を交わらせ、自分が感動しているものはなんなのかをじっくり解釈し続けたのだと、河野さんは語ります。
河野:小林秀雄を読むときのコツも、体を交わらせることにあると思います。小林のリズムに合わせて詩のように読むと、伝わってくるものがあるんです。
小林の文章は、意味を論理的に説得する文章としては、お手本的ではありません。でも、対象として論じると難解な『鐔』も、「かむかふ」の姿勢で読むことで、より味わい深く受け取ることができると思います。

河野:今日は、三浦さんがこんなふうに『鐔』を読んでいるのだと知れて、私としても感動的な時間でした。たぶん私が話していたら、また違う話になるだろうなと思いながら聞いていました。
このような会を、文学者が貴重な仕事をしてきたここ「油や」で開催できたことは、大変ありがたく、また意義深いことと感じています。本当にありがとうございました。
ご参加いただいた皆さんにはぜひ、三浦さんの読みを踏まえながら、またこのエッセイを読み返してみてほしいです。
学びの中に和やかな笑い声が響く、2時間半にわたる「授業」。参加者の皆様にとって、これまでにない本との出会いを堪能する、思い出深い時間になったのではないでしょうか。
【オンライン動画で見る】
当日のイベントの様子は「見逃し配信」としてSTORESで公開しています。気になった方、2時間の小林秀雄体験に浸りたいという方は、ぜひこちらをのぞいてみてください。
◆第1回<小林秀雄を味わう-見逃し動画-> 詳細・お申し込みはこちら
【次のイベントをチェックする】
『軽井沢 本の學校』は、好評につき第3回の開催が決定しています。軽井沢ならではの、特別な読書体験を楽しみませんか。ぜひご参加ください。
概要:2023年3月19日 (日) 10:30 - 16:00 @軽井沢芸術倶楽部
第3回のテーマは世界的戯曲家・シェイクスピア。取り上げる作品は「夏の夜の夢」。 タクトを振ってくださる講師は、劇団カクシンハンの演出家、木村龍之介さんです。 「シェイクスピア」作品をまんなかに置き、その場に集う参加者のみなさんと思いっきり、五感をひらく時間をつくってみます。 作品を解釈するのではなく、参加者が演じ、体感し、自分の中に取り入れることで「シェイクスピア」の作品そのものを味わうイベントです。
◆第3回の詳細・お申し込みはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
