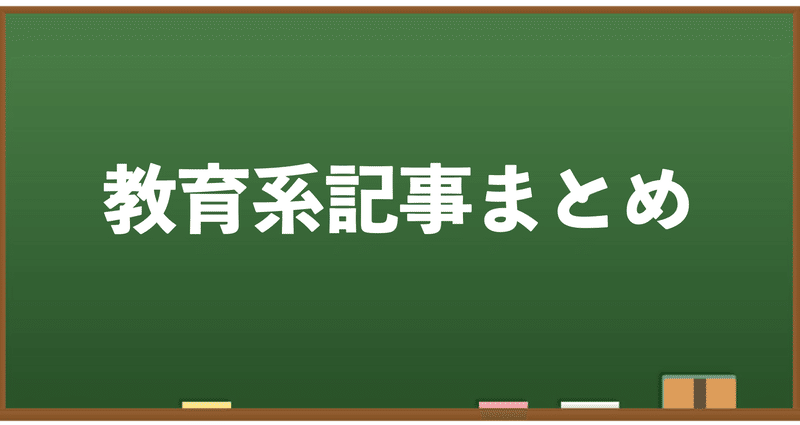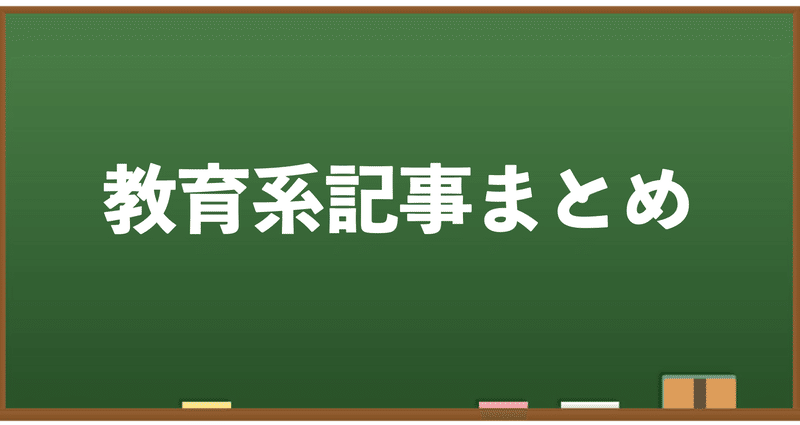学級の振り返りの質を上げるためには数値を活用しよう【Google フォーム活用】
学期ごとに自分達の成長を振り返る場面が学年で設定されていることがあります。また、そのような場面がなくとも、4月に語った ”学級担任の願いの確認” や、学級みんなで作った ”学級目標の達成状況の確認” は必要となってきます。
自分達の姿を振り返る時、課題は多く出すことができます。忘れ物が多い、挙手ができない、時間を守ることができていない、・・・。これらの課題を列挙して、実際課題を克服することができることは数少ないでしょうし、自分達の苦手とするところをずっと指摘し続けるというこ