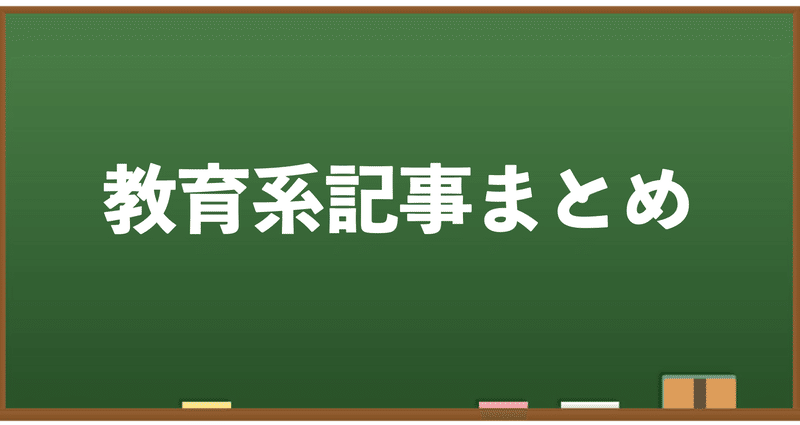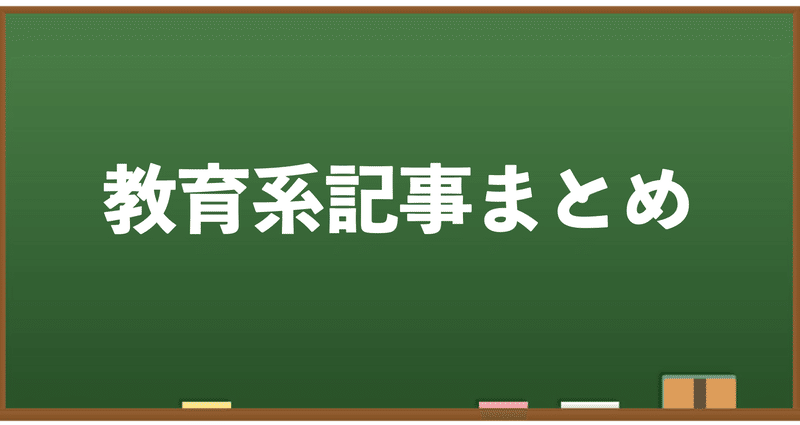自主研という名ばかりの不必要な講義
学校には“自主研”という名の研修があります。
自主研は『自主的な研修』です。必ず受けなければならない研修ではなく、その学校の実態に即して行われる研修ということです。
学校の先生、特に公立の学校の先生は法律で『研究と修養をおさめること』とされているので、1年間の中で多くの研修が準備されています。
わたし自身も研修で多くのことを学びました。実際に現場を離れてみるからこそ、見えてくる課題や、自分が行っている実践が周りからはどのようにみられるのかを知ることができる機会だからこそ、研