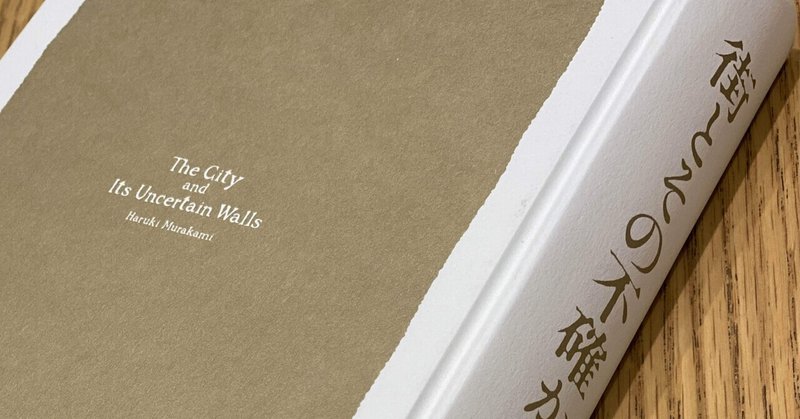
街とその不確かな壁はモネの睡蓮。村上春樹書評その2。

「街とその不確かな壁」。2巡目の感想をポツポツと。
大まかな感想は、前回のnoteに記載しました。その時に私は「モネの晩年の睡蓮のようだ」と書きました。しかし、読後のもっとも最初の印象としては、「なんとも言いようがない」でした。
世界同時販売にあたり、新宿あたりではハルキストが夜に並びごった返したそうです。彼ら彼女らはその数日後、どう思ったんでしょう。
予想としては、その半数以上がこう思ったのではないでしょうか。
「え?これで終わり?」と。
世界中で????マークが浮かんだのかもしれません(笑)。
私はそこまでディープな読者ではなく、著者の本はせいぜい10作くらいなものですが、一冊一冊、思い入れのある物語だったと思います。特に近年の「騎士団長殺し」に関しては、私が画家ということもあり、興奮して読み進めたものでした。
それでも学生時代は、逆に鼻がついて、嫌いな作家の部類でした。美大の先輩たちがこぞって陶酔しながら勧める姿がなんだか異様だったし、そのストーリーにおける主人公に全く共感できないところもありました。
しかし、改めて30代半ばにもなり、ポツポツと読み始めてみると、嫌いだった頃から変わらず、一気に読み終えてしまうほどの世界観のすごさに圧倒されつつ、村上春樹が一貫して伝える意識と無意識(地下の世界)が、絵画の制作活動とリンクするところもあり、物語としても楽しめるし、心理学としても、世界の不思議としても、私自身に大きな気づきを与える一冊になり続けました。
そして新作「街とその不確かな壁」。
な、何も起こらない??
唖然としたものでした。そして隣にいる家族に、ネタバレ辞さず、不平不満を述べたものでした(笑)。人に説明してみればわかります。
「主人公が美少女にあってね。で、その子は消えてしまって、探してる間に歳をとって、不思議な人たちに出会って、たまによくわからない壁のある街に居て、で、結局、女の子と別れて、現実に戻る話なんだ・・」。
生涯、この本を読むことのないであろう(音声朗読なら別かも)家族は、こう言いました。
ふーん。何それ。面白いの?
言葉につまりました(笑)。
前回のnoteにも述べたように、あれだけ私自身に共通点のあった物語なんです。面白くないわけがない!!と信じたい(笑)。
なので、その後にこう付け足しました。
モネの晩年の睡蓮のようなんだ。
絵描きである家族は、「へぇ」と言いました。一応の理解を示してくれて。
その後、ずっとこの物語のことを考えていて、その苦し紛れの表現は、あながち間違っていなかったなんだなと感じています。
モネは晩年、ほとんど視力を失い、気力も失せていましたが、親友の強い勧めで手術を受けて、一時的に回復し、自分の残された少ない時間を確信しながら、必死にキャンバスに向き合います。そして100mを超すオーランジェリー美術館の大睡蓮を完成させるのです。(正確には、最後の絵画の数10センチの余白だけ残して力付きます)
彼は、この作品は自分が死んでから発表してくれといいました。酷評にはもう耐えられる力がないと。彼自身の睡蓮は、神様の与える光を再現するための、生涯をかけた挑戦の集大成でした。その画風は、もはや全盛期の日本人の大好きな睡蓮とは違い、20世紀の抽象画を切り開く「曖昧さ」が描かれていました。睡蓮であり、睡蓮でない。光であり、光でない。もはや老齢の画家は、世界の鮮明さを描くことができませんでしたが、それだけに「あの世」に深く足を踏み入れて、もっと総体的な情景を描いたのです。
大きく失うものがあるからこそ、見える世界がある。それこそが、村上春樹が一貫して描いてきたきたものではないでしょうか。(初読で面白くないかも、と言った自分への恥ずかしい言い訳のように聞こえますが・・)。
そうして、モネが描ききれなかった最後の数10センチの余白のようなラストシーンも、「あえて書かなかった」と読み取れます。
物語のことを触れましょう(やっと)。印象的なシーンを1つづつ。
ラストシーン間際。主人公は、再び川の流れを歩いていきながら、45歳から17歳まで若返っていきます。そうして、再び16歳の彼女と出逢います。絵画のように美しい情景です。誰しも追体験をするに違いないでしょう。僕も17歳に戻っていきました。そこには鹿児島の片田舎の美術室で、全裸で自画像を描いている青年がいました。身体は細く、顎も鋭角で、誰も信じない眼をしていました。鏡の中(壁)の自分自身という(影)を追うことしか、世界のことを知ることができませんでした。
そうして主人公も、16歳の彼女とまどろみながら、こう言われるのです。
ねえ、わかった?わたしたちは2人とも、ただの誰かの影に過ぎないのよ。
しかし、主人公や読者にとって、心が焼き切って元に戻れない時代にこそ、戻る必要があるのかもしれません。それを描いている村上春樹本人は、71歳にもなるのです。71歳の著者からしてみると、彼の辿ってきた人生は、どう映るのでしょうか。
村上春樹の不可思議な世界は、その「会話」にヒントがある場合が多いです。今回は特にわかりやすい示唆があります。本当は物語自体に、その示唆があるほうが私の場合は好きなのです。(「沈黙」遠藤周作のように)。
会話で語られることは、ある意味安易とも取れますが、それはそれぞれの登場人物自体が、主人公の無意識の産物であり、導き手であるわけですから、物語の特性と言えるべきでしょうね。
45歳の主人公は、コーヒーショップのオーナーの女性に対してこう思います。
ーーー
そのコーヒーショップの女性に対して私が抱いている気持ちは、もっと広い範囲に及ぶものであり、より穏当で柔らかな衣に包まれ、それなりの智恵と経験によって抑制されたものだった。
ーーー
私が求めているものは、彼女が身につけた防御壁の内側にあるはずの穏やかな温かみだった。そしてその特殊な素材で作られた円形カップの奥に脈打っている心臓の確かな鼓動だった
(村上春樹・街とその不確かな壁・586ページより)
ーーー
この思いこそ、この物語を的確にまとめていると思います。そして71歳の著者の想いなのだと。
「温かみ」は表現の抽象度と曖昧さや余白なのかもしれないし、「鼓動」は今目の前にいる世界の物語(子易さんや四季や、人々の歴史など、壁には存在しない時間の流れ)かもしれない。
それらの感覚が、読後も「よくわからないけど、とても気になって仕方がない・・」という想いに繋がるのでしょう。少なくとも私自身は。
やれやれ。
たった2つのシーンを取り上げただけで、もう時間切れです。明日からは出張。いろんな出会いがあり、絵を描くのでしょう。それぞれの想いを色にして・・。
体調をしっかり整えて、呼吸をして、姿勢を保って。
きっと私の影は、早々と彼の地へ赴いているに違いありません。私は影を追いかけます。ゆっくりと、そして確実に。
(おしまい)
よろしければサポートお願いいいたします。こちらのサポートは、画家としての活動や創作の源として活用させていただきます。応援よろしくお願い致します。
