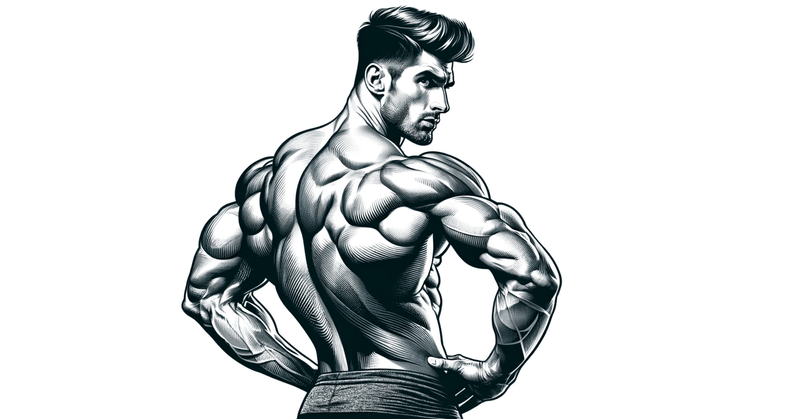
論文まとめ334回目 Nature 過去2000年で類を見ない2023年夏の暑さ!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
Plasmid targeting and destruction by the DdmDE bacterial defence system
バクテリアの防御システムDdmDEによるプラスミドのターゲティングと破壊
「バクテリアは、外来のDNAから身を守るために様々な防御システムを持っています。DdmDEシステムは、コレラ菌の中で小さなプラスミドを素早く排除することが知られていました。本研究は、クライオ電子顕微鏡や生化学的手法を駆使し、DdmDEがどのようにプラスミドを認識し、分解するのかを詳細に解明しました。DdmDタンパク質が標的DNAを捕捉すると構造変化を起こし、DdmEと協調してプラスミドを効率的に破壊することが分かりました。バクテリアの巧みな防衛戦略の仕組みに迫る発見です。」
2023 summer warmth unparalleled over the past 2,000 years
過去2000年で類を見ない2023年夏の暑さ
「2023年は観測史上最も暑い年でした。特に北半球の夏の気温は異常に高く、自然変動の範囲を大きく超えていたのです。過去2000年分の古気候データと比較したところ、2023年の夏は0.5℃以上も平均を上回り、記録的な暑さだったことが判明。536年の寒冷な夏と比べると、実に3.93℃もの差がありました。地球温暖化に加えてエルニーニョ現象も重なり、極端な高温になったと考えられます。もはや異常気象は当たり前。温暖化対策に真剣に取り組まなければならない時が来ているのかもしれません。」
Dispersion-assisted high-dimensional photodetector
分散支援型高次元光検出器
「光には強度、偏光、波長の情報が含まれています。この研究では、薄い膜の界面で光の偏光と波長の応答を波数領域で操ることで、これらの情報を一度の撮像で同時に得る新しい光検出器を開発しました。深層残差ネットワークを用いて情報を復号化する手法と組み合わせることで、従来の偏光計やスペクトロメータと同等以上の性能を持つ超小型・多機能な光検出・イメージングデバイスが実現できます。」
A renewably sourced, circular photopolymer resin for additive manufacturing
再生可能原料由来の付加製造用循環型光重合樹脂
「この研究では、再生可能な原料であるリポ酸から光硬化性樹脂を合成し、それが3Dプリント可能であることを実証しました。さらに、印刷物を簡単な操作で元のモノマーに分解し、再び樹脂として利用できることを示しました。これにより、3Dプリンティングの材料を「作る→使う→捨てる」の直線的なプロセスから、「作る→使う→分解→再利用」という循環的なプロセスに変えることに成功。持続可能な3Dプリンティング材料への道を拓く画期的な研究です。」
Dimerization and antidepressant recognition at noradrenaline transporter
ノルアドレナリン輸送体の二量体化と抗うつ薬認識
「ノルアドレナリン輸送体は脳内のノルアドレナリンを調節する重要なタンパク質です。今回、その立体構造を明らかにし、二量体(2分子が結合した状態)を形成していることを発見。さらに、抗うつ薬がどのように結合するかも解明しました。二量体の接触面にはコレステロールなどの脂質が介在し、安定化に寄与していることもわかりました。この知見は、うつ病などの治療薬開発に役立つと期待されます。」
Entanglement of nanophotonic quantum memory nodes in a telecom network
テレコムネットワークにおけるナノフォトニック量子メモリノードの量子もつれ
「量子インターネットの実現に向け、離れた2つの量子ノード間で量子もつれを生成・維持する技術が重要です。本研究では、ダイヤモンド中のシリコン空孔(SiV)を用いたナノフォトニック量子ノードを開発。35kmの都市部に敷設された光ファイバーを介して2つのノード間で核スピンの量子もつれの生成に成功しました。量子周波数変換と動的デカップリングを駆使し、現実的な量子ネットワーク環境での長距離量子もつれ配信を実証した大きな一歩です。」
要約
ショートアルゴノート型防御システムDdmDEが、いかにしてプラスミドを迅速に排除するかを構造生物学的に解明
本研究は、コレラ菌の防御システムDdmDEがいかにして効率的にプラスミドを排除するのかを構造生物学的に解明した。DdmEは触媒活性を持たないDNA標的型のショートアルゴノートで、特徴的な挿入ドメインを持つ。DdmDは一本鎖DNAの標的を捕捉すると、自己阻害型の二量体から活性型のモノマーへと構造変化する。DdmDEと標的DNAの複合体構造から、DNAの認識がどのようにプラスミドの連続的な分解を引き起こすのかが明らかになった。本研究は、ショートアルゴノートが補助因子を利用してプラスミドを排除する仕組みの理解を大きく前進させた。
事前情報
真核生物のアルゴノートはRNA干渉に重要だが、原核生物のショートアルゴノート(pAgo)の中には、外来DNAの分解に補助因子を必要とするものがある。
DdmDEシステムは、コレラ菌の中で小さなマルチコピープラスミドを迅速に排除することが知られている。
行ったこと
クライオ電子顕微鏡、生化学的手法、in vivoプラスミド排除アッセイを組み合わせてDdmDEの活性化経路を解明した。
DdmEの構造を決定し、触媒活性を持たないDNA標的型pAgoであることを示した。
DdmDが一本鎖DNA標的の捕捉に伴い、二量体からモノマーへと構造変化することを見出した。
DdmDE-ガイドDNA-標的DNA複合体の全体構造を決定した。
検証方法
クライオ電子顕微鏡による構造解析
生化学的実験によるDdmDの二量体-モノマー変換の検出
in vivoでのプラスミド排除アッセイによる機能評価
分かったこと
DdmEは触媒活性を持たないDNA標的型pAgoで、特徴的な挿入ドメインを持つ。
DdmDは自己阻害型の二量体として存在し、一本鎖DNA標的の捕捉に伴いモノマーへと構造変化する。
DdmDE-ガイドDNA-標的DNA複合体の構造から、DNAの認識がプラスミドの連続的な分解を引き起こす仕組みが明らかになった。
この研究の面白く独創的なところ
pAgoによるプラスミド排除の分子機構を構造レベルで解明した点
DdmDの二量体-モノマー変換という新しい活性化機構を発見した点
DdmDE-ガイドDNA-標的DNA複合体の全体構造を捉えることに成功した点
この研究のアプリケーション
バクテリアの防御システムの理解に貢献し、抗菌薬開発などへの応用が期待される。
pAgoを利用した外来DNA排除技術の開発に役立つ可能性がある。
著者と所属
Jack P. K. Bravo, Delisa A. Ramos, Rodrigo Fregoso Ocampo, Caiden Ingram & David W. Taylor
(Department of Molecular Biosciences, University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA)
詳しい解説
バクテリアは、ウイルスや外来のDNAから自身を守るために、様々な防御システムを進化させてきました。中でもDdmDEシステムは、コレラ菌の中で小さなマルチコピープラスミドを素早く排除することが知られており、その分子機構に注目が集まっていました。
本研究は、クライオ電子顕微鏡による構造解析と生化学的実験、さらにin vivoでのプラスミド排除アッセイを駆使することで、DdmDEシステムの全容解明に挑みました。その結果、DdmEが触媒活性を持たないDNA標的型のショートアルゴノートであること、DdmDが一本鎖DNA標的の捕捉に伴い自己阻害型二量体から活性型モノマーへと構造変化することが明らかになりました。
特に画期的だったのは、DdmDE-ガイドDNA-標的DNA複合体の全体構造を高分解能で捉えることに成功した点です。この構造から、DdmDEがDNAを認識し、プラスミドを連続的に分解していく仕組みが原子レベルで明らかになりました。標的DNAを挟み込むようにDdmDとDdmEが配置され、効率的な分解が可能になっていたのです。
本研究は、ショートアルゴノートが補助因子を利用して外来DNAを排除する分子メカニズムを解き明かした重要な成果であり、バクテリアの防御システムの理解を大きく前進させるものです。抗菌薬の開発などへの応用も期待されます。また、pAgoを利用した外来DNA排除技術の開発にもつながるかもしれません。
バクテリアの巧みな生存戦略の一端を構造生物学の力で解き明かした本研究。今後のさらなる展開から目が離せません。
2023年の北半球の夏は過去2000年で最も暑かったことが明らかに
本研究では、観測データと古気候の復元データを組み合わせ、2023年の北半球中高緯度地域の6〜8月の地上気温が過去2000年で最も高かったことを明らかにした。2023年夏の気温は、自然変動の95%信頼区間を0.5℃以上も上回っていた。536年の最も寒冷だった夏と比べると、2023年までの最大温度差は3.93℃にも達した。2023年の極端な暑さは、温室効果ガスによる地球温暖化の傾向とエルニーニョ現象の影響が重なった結果と考えられる。この異常な高温は、温暖化対策の重要性と緊急性を強調するものである。
事前情報
2023年は観測史上最も暑い年と報告されている
19世紀の気象観測データは疎らで、暖めに偏っている傾向がある
行ったこと
観測された6〜8月の地上気温データと、過去2000年分の古気候復元データを組み合わせて解析
2023年夏の北半球中高緯度地域の気温と過去の自然変動の範囲を比較
2023年と過去2000年で最も寒冷だった536年の夏の気温差を算出
検証方法
観測データと古気候復元データの統合
確率密度関数を用いた自然変動の95%信頼区間の推定
2023年と536年の気温差の計算
分かったこと
2023年6〜8月の北半球中高緯度地域の気温は過去2000年で最高だった
2023年夏の気温は自然変動の95%信頼区間を0.5℃以上超えていた
536年の最寒夏と2023年の気温差は3.93℃に達した
2023年の極端な暑さは温暖化傾向とエルニーニョ現象の影響と考えられる
この研究の面白く独創的なところ
観測データと古気候復元データを組み合わせて2000年スケールの気温変動を比較した点
単に平均値の比較だけでなく、自然変動の範囲からの逸脱度も定量化した点
過去2000年の最寒夏との気温差を算出し、極端な暑さをより印象付けた点
この研究のアプリケーション
現在の気候変動の程度を過去の長期的な文脈の中で理解するための材料を提供
異常気象の頻発化と極端化を裏付ける具体的な証拠として活用できる
地球温暖化対策の重要性と緊急性を訴える上で説得力のあるデータとなる
著者と所属
Jan Esper & Max Torbenson (Department of Geography, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany)
Ulf Büntgen (Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic)
詳しい解説
2023年は世界的に記録的な高温に見舞われ、観測史上最も暑い年となったと報告されています。しかし、現在の温暖化が過去の自然変動の範囲内なのか、それとも異常な事態なのかを判断するのは簡単ではありません。19世紀の気象観測データは疎らで、しかも暖めに偏っている傾向があるためです。
この研究では、観測データと過去2000年分の古気候復元データを組み合わせることで、2023年の北半球中高緯度地域の6〜8月の地上気温が過去2000年で最も高かったことを明らかにしました。2023年夏の気温は、自然変動の95%信頼区間を0.5℃以上も上回っていたのです。これは、現在の温暖化が自然変動の範囲を大きく超えた異常事態であることを示しています。
さらに衝撃的なのは、536年の最も寒冷だった夏と2023年の気温差が3.93℃にも達したことです。わずか1500年ほどの間に、こんなにも気温が上昇したのは驚くべきことと言えるでしょう。
2023年の極端な暑さは、人為的な温室効果ガスによる地球温暖化の傾向に、エルニーニョ現象の影響が重なった結果と考えられます。エルニーニョ現象は数年に一度発生する自然の気候変動ですが、地球温暖化によってその影響が増幅されている可能性があります。
この研究の面白いところは、観測データと古気候復元データを組み合わせて2000年スケールの気温変動を比較した点です。また、単に平均値の比較だけでなく、自然変動の範囲からの逸脱度も定量化したことで、現在の温暖化の異常さがより明確になりました。過去2000年の最寒夏との気温差を算出したのも、極端な暑さをより印象付ける効果的な手法だと言えるでしょう。
この研究の成果は、現在の気候変動の程度を過去の長期的な文脈の中で理解するための材料を提供するとともに、異常気象の頻発化と極端化を裏付ける具体的な証拠としても活用できます。さらに、地球温暖化対策の重要性と緊急性を訴える上で説得力のあるデータとなるはずです。
2023年の異常気象は、もはや異常ではなく「新たな日常」になりつつあるのかもしれません。私たちは、この危機的な状況を直視し、温暖化対策に真剣に取り組まなければならない時が来ているのです。
光の偏光とスペクトル情報を同時に得る新しい薄膜型高次元光検出器を開発
本研究では、空間分散と周波数分散を有する薄膜界面を用いて、光の偏光とスペクトル情報を波数領域で操作・符号化し、単一撮像で高次元の光情報を得る新しい光検出器を開発した。得られた情報は深層残差ネットワークを用いて復号化される。本手法により、任意の偏光状態と広帯域スペクトルを単一デバイス・単一測定で完全に特性評価できる。また、最先端の小型偏光計やスペクトロメータと同等以上の性能を示す。本アプローチは既存のイメージングプラットフォームに容易に適用でき、超小型・高次元の光検出とイメージングに新たな道を開く。
事前情報
光の強度、偏光、波長を同時に特性評価することは高い需要がある
偏光計やスペクトロメータの設計には多大な努力が払われてきた
高次元の光情報を同時に得るには、複雑な偏光・波長感応素子の時空間統合が必要とされてきた
行ったこと
空間分散と周波数分散を有する薄膜界面を設計
偏光とスペクトル応答を波数領域で操作・符号化
深層残差ネットワークを用いて高次元光情報を復号化
広帯域の任意偏光状態を単一デバイス・単一測定で特性評価
検証方法
理論計算とシミュレーションによる設計
サンプルの作製と測定による実験的検証
深層学習を用いた情報の復号化と性能評価
最先端の小型偏光計・スペクトロメータとの性能比較
分かったこと
薄膜界面の空間・周波数分散により、偏光とスペクトル応答を波数領域で操作できる
高次元光情報を単一撮像で符号化し、深層学習で復号化できる
任意偏光状態と広帯域スペクトルを単一デバイス・単一測定で完全特性評価可能
最先端の単一目的小型偏光計・スペクトロメータと同等以上の性能を示す
既存イメージングプラットフォームに容易に適用可能
この研究の面白く独創的なところ
薄膜界面の分散特性を利用して、偏光とスペクトル情報を波数領域で巧みに操作・符号化した点
深層残差ネットワークを用いて高次元光情報を効果的に復号化した点
単一デバイス・単一測定で任意偏光と広帯域スペクトルを完全特性評価できる点
最先端の単一目的デバイスと同等以上の性能を、はるかに単純なシステムで実現した点
この研究のアプリケーション
超小型・高性能な偏光イメージングとハイパースペクトルイメージングへの応用
既存の顕微鏡や望遠鏡などのイメージングプラットフォームへの容易な統合
医療診断、リモートセンシング、材料分析などの幅広い分野への応用可能性
著者と所属
Yandong Fan, Weian Huang, Fei Zhu, Chunqi Jin, Wei Li
(GPL Photonics Laboratory, State Key Laboratory of Luminescence Science and Technology, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences)
詳しい解説
この研究は、光の強度、偏光、スペクトル情報を同時に特性評価できる新しい高次元光検出器を開発した画期的な成果です。 従来、光の偏光状態とスペクトルを同時に測定するには、複数の偏光感応素子や波長感応素子を時間領域や空間領域で複雑に統合する必要がありました。しかし、本研究では空間分散と周波数分散を有する薄膜界面を用いることで、偏光とスペクトル応答を波数領域で巧みに操作・符号化し、単一撮像で高次元の光情報を取得することに成功しました。
研究チームは、理論計算とシミュレーションに基づいて薄膜界面を設計し、サンプルを作製して実験的に概念を実証しました。得られた高次元光情報は、深層残差ネットワークを用いて効果的に復号化されます。驚くべきことに、この単純なデバイスと手法により、任意の偏光状態と広帯域スペクトルを単一測定で完全に特性評価できることが示されました。しかも、その性能は最先端の小型偏光計やスペクトロメータと同等以上であったのです。
本手法の大きな利点は、既存のイメージングプラットフォームに容易に適用できる点です。顕微鏡や望遠鏡などに簡単に組み込むことができ、アライメントフリーで動作します。つまり、この革新的な光検出器は、幅広い分野で超小型・高性能な偏光イメージングとハイパースペクトルイメージングを可能にするポテンシャルを秘めているのです。
医療診断では組織の偏光特性とスペクトル特性から病変を検出したり、リモートセンシングでは地表の偏光とスペクトル情報から物質組成を分析したりといった応用が考えられます。材料科学の分野でも、材料の光学特性を多次元で評価するのに役立つでしょう。
本研究は、光の偏光とスペクトルという異なる性質を波数空間で巧みに融合し、深層学習を活用して情報を解読するという独創的なアプローチにより、光検出とイメージングに新たな地平を切り開いた点で高く評価されます。この革新的な光検出器が、様々な科学・工学分野に大きなインパクトを与えていくことが大いに期待されます。
再生可能な原料から合成した、3Dプリント可能な光硬化性樹脂の開発に成功し、印刷物を分解・再利用できる循環型材料を実現
本研究では、再生可能な原料であるリポ酸を用いて、3Dプリント可能な光硬化性樹脂を開発しました。この樹脂は、高解像度の3Dプリントが可能であり、熱的・機械的特性も市販のアクリル系樹脂と同等です。さらに、プリント物を簡単な操作で元のモノマーに分解し、再び樹脂として利用できることを示しました。これにより、3Dプリンティングの材料を循環利用する道が拓かれました。また、リポ酸由来の樹脂は、組成や架橋構造を変えることで、様々な特性を持つ材料の設計が可能であることも明らかにしています。
事前情報
現在の3Dプリント用光硬化性樹脂は、主に石油由来の(メタ)アクリレートやエポキシドを原料としている
これらの樹脂は不可逆的に硬化するため、プリント物のリサイクルが困難
再生可能な原料から3Dプリント用樹脂を開発する試みは行われているが、循環利用可能な材料は実現されていない
行ったこと
リポ酸とイソソルビド、メントールから、動的ジスルフィド結合を持つモノマーを合成
モノマーの配合比を変えて光硬化性樹脂を調製し、3Dプリントに適用
プリント物をリン塩基触媒存在下で加熱し、元のモノマーに分解
回収したモノマーを再び樹脂化し、3Dプリントに利用
検証方法
NMR、MS、IR、UV-visによるモノマー・樹脂の構造解析
サイズ排除クロマトグラフィーによる分子量測定
示差走査熱量測定、動的機械分析による熱的特性評価
引張試験による機械的特性評価
光レオロジー測定による硬化挙動解析
3Dプリンターを用いた造形性、寸法精度の検証
分かったこと
リポ酸由来のモノマーから、3Dプリント可能な光硬化性樹脂が得られる
樹脂の熱的・機械的特性は、モノマー組成や架橋構造によって制御可能
プリント物を高収率・高選択的に元のモノマーに分解できる
回収したモノマーは、再び3Dプリント可能な樹脂として利用できる
モノマーの再利用を2サイクル実証、元の樹脂とほぼ同等の特性を確認
モノマーをエステル交換により完全に再生可能な原料に戻すことも可能
この研究の面白く独創的なところ
リポ酸の動的ジスルフィド結合を3Dプリント用樹脂の設計に利用した点
モノマー組成や架橋構造を変えるだけで、多様な特性の材料が得られる点
プリント物を元のモノマーに分解し、繰り返し再利用できる点
従来の3Dプリンティングの直線的なプロセスを、循環型のプロセスに変えた点
この研究のアプリケーション
持続可能な3Dプリンティング材料の開発
熱的・機械的特性の異なる高解像度3Dプリント物の製造
3Dプリンティングにおける未反応樹脂や廃棄物の削減
動的結合を利用した自己修復性や形状記憶性材料への展開
著者と所属
Thiago O. Machado, Connor J. Stubbs, Viviane Chiaradia, Maher A. Alraddadi, Arianna Brandolese, Joshua C. Worch & Andrew P. Dove
(School of Chemistry, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, UK; Department of Chemistry, Macromolecules Innovation Institute, Blacksburg, VA, USA)
詳しい解説
本研究は、3Dプリンティング用光硬化性樹脂の新たな設計指針を提示した画期的な成果です。再生可能な原料であるリポ酸から動的ジスルフィド結合を持つモノマーを合成し、それを3Dプリント可能な樹脂に適用することで、従来の石油由来樹脂では成し得なかった循環利用が可能になりました。
リポ酸は、スポーツ栄養食品などにも使われる安全性の高い化合物です。研究チームは、このリポ酸をイソソルビドやメントールとエステル化することで、多官能モノマーや反応性希釈剤を合成しました。これらのモノマーを混合して光硬化性樹脂を調製したところ、市販のアクリル系樹脂と同等の熱的・機械的特性を示す高解像度の3Dプリント物が得られることを見出しました。
さらに驚くべきことに、プリント物をリン塩基触媒存在下で加熱するだけで、98%以上の収率で元のモノマーに分解できることを明らかにしました。回収したモノマーのNMRスペクトルは元のものとほぼ一致しており、再び高品質な3Dプリント物を与える樹脂として使えることを実証しました。樹脂からプリント物、そしてまたモノマーへというサイクルを2回繰り返すことにも成功しています。
従来の3Dプリント用樹脂は、高い架橋密度のために不可逆的に硬化してしまうため、プリント物を分解・再利用することは非常に困難でした。それを動的結合の導入によって克服した本研究のコンセプトは、他の高分子材料の設計にも大きなインパクトを与えるものです。
リポ酸由来のモノマーは、再生可能でありながら多様な構造設計が可能な点も魅力です。モノマーの種類や配合比を変えるだけで、用途に応じた最適な熱的・機械的特性を持つ材料を得ることができます。本研究で実際に、ガラス転移温度や弾性率、強度の異なる樹脂が複数合成されています。
3Dプリンティングは、少量多品種生産に適したものづくり技術として注目を集めていますが、使用後の材料の処理が大きな課題となっていました。本研究は、3Dプリンティングを持続可能な技術へと変革する大きな一歩になるでしょう。動的結合の導入により、未反応樹脂のリサイクルや、プリント物の修復・再利用が可能になることが期待されます。
これまで直線的だった3Dプリンティングのプロセスが、循環型へと移行する日が来るかもしれません。本研究は、そのための基盤となる材料の設計指針を示した点で、非常に価値のある成果だと言えます。持続可能性と高い材料特性を両立する3Dプリンティング用樹脂の開発が、今後ますます加速していくことでしょう。
ノルアドレナリン輸送体の二量体化と抗うつ薬認識機構の構造基盤解明
本研究では、ノルアドレナリン輸送体(NET)の立体構造を、基質であるノルアドレナリンや各種抗うつ薬との複合体として単粒子クライオ電子顕微鏡で解析した。その結果、NETが脂質分子を介して二量体を形成していることが明らかになった。ノルアドレナリンは中央の結合ポケットに深く結合し、その アミノ基が保存されたアスパラギン酸残基と相互作用していた。また、各種抗うつ薬の認識機構とモノアミン輸送体選択性の構造基盤も明らかになった。これらの知見は、NETの機能調節と阻害の理解を深め、神経精神疾患の治療に役立つ改良型抗うつ薬のデザインに貢献すると期待される。
事前情報
ノルアドレナリン輸送体(NET)は神経伝達物質バランスの調節に重要な役割を果たしており、正常な生理機能や神経生物学に不可欠
NETの機能不全はうつ病や注意欠如・多動性障害など多くの神経精神疾患に関与
NETの構造や機能制御、薬物による阻害メカニズムは不明な点が多かった
行ったこと
基質非結合状態、ノルアドレナリン結合状態、6種類の抗うつ薬複合体状態のNETの構造をクライオ電子顕微鏡で解析
NET変異体を用いて、基質や阻害薬の結合に関わるアミノ酸残基を同定
NET二量体の接触面を形成する脂質分子の同定と役割の解明
検証方法
単粒子クライオ電子顕微鏡による構造解析
NET変異体を発現させた細胞を用いた薬物結合実験と取り込み実験
質量分析や脂質含量分析による二量体接触面の脂質同定
分かったこと
NETは脂質分子(コレステロールやリン脂質)を介して二量体を形成していた
ノルアドレナリンは中央の結合ポケットに深く結合し、そのアミノ基がAsp75と相互作用
抗うつ薬はそれぞれ特徴的な結合様式を示し、NETとセロトニン・ドーパミン輸送体の選択性の違いに関与するアミノ酸残基が明らかに
NET二量体の接触面にはコレステロールなどの脂質が多数結合しており、二量体の安定化に寄与
研究の面白く独創的なところ
NETの構造を様々なリガンド結合状態で高分解能に解明した点
NETが二量体を形成していることを初めて明らかにした点
NET二量体の接触面が脂質分子によって形成・安定化されていることを発見した点
各種抗うつ薬の結合様式の違いから、モノアミン輸送体選択性の分子基盤を解明した点
この研究のアプリケーション
NETの機能と阻害の理解に基づく、うつ病などの神経精神疾患治療薬の開発
NET二量体を標的とした新しいタイプの薬物の探索
抗うつ薬のNET選択性の改善によるより安全で効果的な治療薬の創出
脂質によるNET機能制御の解明に基づく、新たな創薬標的の提案
著者と所属
Heng Zhang, Yu-Ling Yin, Antao Dai, Tianwei Zhang, Chao Zhang, Canrong Wu, Wen Hu, Xinheng He, Benxun Pan, Sanshan Jin, Qingning Yuan, Ming-Wei Wang, Dehua Yang, H. Eric Xu & …Yi Jiang
(State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences; Lingang Laboratory, Shanghai; State Key Laboratory of Chemical Biology, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences; 他)
詳しい解説
ノルアドレナリン輸送体(NET)は、神経終末でノルアドレナリンを再取り込みすることで、シナプス間隙のノルアドレナリン濃度を調節しており、正常な脳機能に不可欠のタンパク質です。NETの機能異常は、うつ病や注意欠如・多動性障害(ADHD)など様々な神経精神疾患の発症に関与していることが示唆されています。しかしながら、NETがどのような立体構造をとっているのか、基質や薬物をどのように認識して輸送するのか、その詳細は不明な点が多く残されていました。
今回、中国科学院上海薬物研究所のHeng Zhangらの研究グループは、NETの立体構造をクライオ電子顕微鏡で解析することに成功しました。彼らは、基質非結合状態、ノルアドレナリン結合状態、そして6種類の抗うつ薬との複合体状態のNETについて、それぞれ2.6〜3.6Åという高い分解能で構造を決定しました。
その結果、NETは脂質分子を介して二量体(2分子が結合した状態)を形成していることが明らかになりました。これは、モノアミン輸送体で初めて観察された二量体構造であり、大変興味深い発見です。二量体の接触面には、コレステロールやホスファチジルイノシトールなどの脂質分子が多数結合しており、二量体の形成と安定化に寄与していると考えられます。
また、ノルアドレナリンがNETのほぼ中央に位置する結合ポケットに深く結合し、そのアミノ基がAsp75と相互作用していることがわかりました。一方、各種抗うつ薬は、結合ポケット内の異なる位置に結合しており、薬物ごとに特徴的な結合様式を示しました。さらに、NET、セロトニン輸送体、ドーパミン輸送体のアミノ酸配列を比較することで、各輸送体への選択性の違いを生み出すアミノ酸残基を同定しました。
本研究は、NETの構造と機能の理解を大きく前進させただけでなく、NET二量体という新たな創薬標的の可能性を示唆するものです。NET二量体の形成や安定化に関わる脂質との相互作用を標的とすることで、より選択性の高い神経精神疾患治療薬の開発が期待されます。また、各種抗うつ薬の結合様式の違いに基づいて、副作用の少ない安全な薬物設計につながる可能性もあります。
うつ病をはじめとする神経精神疾患は、世界中で多くの患者さんを悩ませている深刻な問題です。本研究で得られた知見は、こうした疾患のより効果的な治療法の開発に大きく貢献するものと期待されます。今後、NETの構造と機能のさらなる解明と、それに基づく創薬研究の加速が大いに期待されるところです。
遠隔地にある2つのナノフォトニック量子メモリノードを都市部の光ファイバーネットワークで量子もつれを実現
本研究は、シリコン空孔(SiV)を埋め込んだナノフォトニックダイヤモンド共振器を量子ノードとして用いた2ノード量子ネットワークを実現しました。2つのノード間の量子もつれ生成には、時間ビン光子を介した連続的なスピン-光子ゲート操作を用いました。さらに、量子周波数変換を利用して光子を通信波長帯に変換し、最大40kmの低損失光ファイバーを介した長距離核スピンもつれの生成に成功。動的デカップリングにより最大1秒間のもつれ保存を実現しました。また、ボストン都市部に敷設された35kmの光ファイバーループを用いて、現実的な量子ネットワーク環境での量子もつれ配信を実証しました。
事前情報
量子インターネットの実現には、離れた量子ノード間の量子もつれ生成・維持技術が重要
ナノフォトニック共振器と結合したSiVは、強い光-物質相互作用による効率的なスピン-光子インターフェースを提供
29Siの核スピンは長寿命量子メモリとして機能する
行ったこと
SiVを埋め込んだナノフォトニックダイヤモンド共振器を2つの量子ノードとして使用
時間ビン光子を介した連続的なスピン-光子ゲート操作により、2つのノード間で電子スピンと核スピンの量子もつれを生成
量子周波数変換により光子を通信波長帯(1350nm)に変換し、最大40kmの低損失光ファイバーを介した長距離量子もつれ配信を実現
動的デカップリングにより核スピンもつれを最大1秒間保存
検証方法
時間遅延干渉計による光子の重ね合わせ基底での測定により量子もつれ生成を検証
ベル状態測定による生成された量子もつれ状態の忠実度評価
量子ビットの回転とその後の読み出しにより相関測定を実施
動的デカップリングのデコヒーレンス保護効果を核スピンもつれの保存時間で評価
分かったこと
時間ビン光子を用いた連続的なスピン-光子ゲート操作が、位相安定性を必要としない堅牢な量子もつれ生成手法であること
量子周波数変換と低損失光ファイバーにより、40kmまでの長距離量子もつれ配信が可能なこと
動的デカップリングが量子ノード間の古典通信に必要な時間よりも十分長い量子もつれ保存を可能にすること
開発したSiVベース量子ノードが都市部の敷設済み光ファイバーネットワークと互換性があり、現実的な量子ネットワーク環境に対応可能なこと
この研究の面白く独創的なところ
SiVベースのナノフォトニック量子ノードを用いて、長距離量子もつれ配信を初めて実証した点
時間ビン光子を用いた連続的なゲート操作という独自の量子もつれ生成手法を開発した点
量子周波数変換と低損失光ファイバーを駆使して、現実的な量子ネットワーク環境での長距離量子もつれ配信を可能にした点
動的デカップリングを利用して、量子中継に必要な古典通信時間よりも十分長い量子メモリ保存時間を達成した点
この研究のアプリケーション
量子中継器や大規模量子ネットワークの実現に向けた重要なステップ
分散量子計算、長距離秘密通信、分散量子センシング・計測など、様々な量子ネットワークアプリケーションへの応用
SiVベース量子ノードのチップ上大規模集積化による、実用的な量子ネットワークシステムの開発
著者と所属
C. M. Knaut, A. Suleymanzade, Y.-C. Wei, D. R. Assumpcao, P.-J. Stas, M. D. Lukin 他
(Department of Physics, Harvard University; John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University; AWS Center for Quantum Networking)
詳しい解説
本研究は、シリコン空孔(SiV)を埋め込んだナノフォトニック共振器を量子ノードとして用いた2ノード量子ネットワークを実現した画期的な成果です。SiVは、ダイヤモンド中の光学的に活性な欠陥の一種で、ナノフォトニック共振器と結合することで強い光-物質相互作用が得られ、効率的なスピン-光子インターフェースとして機能します。また、29SiのSiVは決定論的に長寿命の核スピン量子メモリを有しており、多数量子ビット量子ノードの構築に適しています。
著者らは、2つのSiVベース量子ノードを開発し、それらを光ファイバーネットワークで接続した2ノード量子ネットワークを実装しました。量子もつれの生成には、時間ビン符号化された光子を介した連続的なスピン-光子ゲート操作を用いるという独自の手法を採用しました。これにより、2つのノード間の位相安定性を必要とせず、光子ロスに対して堅牢な量子もつれ生成が可能になりました。
さらに、量子周波数変換技術を駆使して、SiVの発光波長(737nm)の光子を通信波長帯(1350nm)に変換し、低損失の光ファイバーを介した長距離伝送を実現しました。これにより、最大40kmの光ファイバーを介した長距離核スピンもつれの生成に成功したのです。また、動的デカップリングを適用することで、量子ノード間の古典通信に必要な時間よりも十分長い、最大1秒間の量子もつれ保存を実証しました。
本研究の特筆すべき点は、開発したSiVベース量子ノードがボストン都市部に敷設された35kmの光ファイバーループとの互換性を示したことです。量子ビット間の周波数差を補償するための能動的な偏光安定化を施すことで、現実的な量子ネットワーク環境における量子もつれ配信に成功したのです。これは、提案されている量子ネットワークアーキテクチャを既存の通信インフラで実装する上で重要なステップとなります。
本研究で実証された要素技術は、量子中継器や大規模量子ネットワークの実現に向けた重要な基盤となります。SiVベース量子ノードのチップ上大規模集積化と、量子周波数変換・動的デカップリングの最適化により、分散量子計算、長距離秘密通信、分散量子センシング・計測など、様々な量子ネットワークアプリケーションが現実のものとなるでしょう。量子情報処理におけるブレークスルーとなる可能性を秘めた研究であり、今後のさらなる発展が大いに期待されます。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
