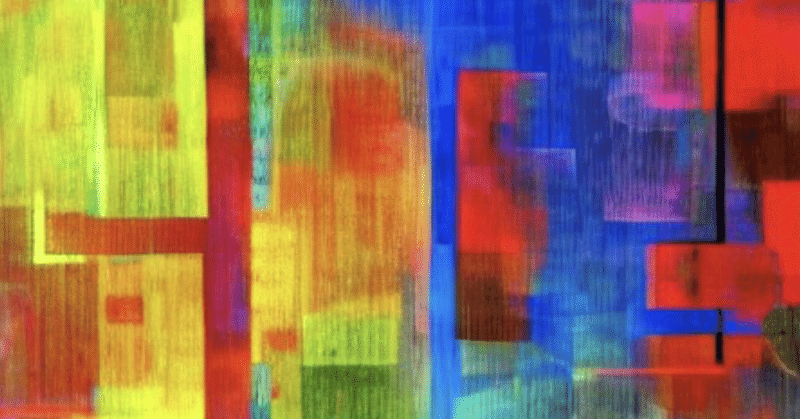
こころが疲れたサインが出たら、ちょっと休もう。
福島県の医学部で学生教育をしながら、心理カウンセラーをしたり、研究をしたり、YouTubeの運営をしたりしてるあおきしゅんたろうです。
新生活のストレスについていくつか記事を書いてきましたが、
ストレスによってこころが疲れることもあります。
ただ、こころの疲れは気づかぬうちにたまっていく場合が多く、なかなか自覚することが難しい場合もあります。
そこで今日の記事ではこころが疲れた場合に出てくるサインをご紹介しますので、もし気づいたら、休むサインかなあというように考えてもらえたら何よりです。
一番わかりやすいのは気持ちが落ち込む、お先真っ暗な感じになることです。これが抑うつ気分と呼ばれるものです。
同時にやる気が出なくなり、楽しかったことが全く楽しめなくなるということもあります。趣味や興味がなくなってしまう場合も注意が必要です。
睡眠寝付きが悪くなったり、食欲がなくなったり、食事量が増えたりする場合もサインの一つです。
また、焦りやそわそわ、仕事で忙しい時に焦ってしまうこともあります。
疲れや肩こり、疲れが取れない慢性疲労も限界のサインです。
自分を責める罪悪感や自責感が強くなる場合もあります。
集中力の低下や仕事のペースの落ち込み、頭の中が整理されていない感じも限界のサインです。
そして最強の限界のサインは、死にたくなることです。
希死念慮と呼ばれる状態で、うつ症状が高いけれどもうつ病ではない人と、うつ病の人では、うつ病のひとで希死念慮が出る確率が高いと言われています。
これらのサインが出てきたら、まずは自分を大事にして休むことが大切です。必要であれば、専門家に相談してアドバイスをもらうこともおすすめです。
出てきやすい症状を理解し、それに対処することで、健康的な心身を保ち、生産的な生活を送ることができます。
こういったサインが出てきた場合、仕事や人間関係を頑張り過ぎず、休暇を取ったり、趣味やリラックスする時間を作ることも大切です。
健康的な食生活や十分な睡眠を確保することも、過度なこころの疲れを防ぐ上で重要です。
みなさんが実践している、ストレス解消法を試してみましょう。散歩やヨガ、マッサージなど、自分に合ったストレス解消方法を見つけ、定期的に実践することも大切です。
最後にこういう場合には、自分自身に対して優しく接することが大切です。周囲の人にも、自分がどのような状態にあるのかを伝えることで、理解を得ることができるかもしれません。
必要な場合には専門機関にかかることも大切です。
過度に疲れすぎず生活できるのがいちばんですが、もし上記のサインを見つけたときには、じぶんをいたわってあげて、無理しないように過ごしてくださいね。
YouTubeチャンネルのばっちこい心理学でも同じテーマでお話ししていますのでよろしければご覧ください。
それでは最後までお付き合いいただいて、ありがとうございました!
もし記事に共感していただけたら「スキ」ボタンを押してくれたらうれしいです。サポートしていただけたらもっと嬉しいです、サポートいただいたお金は全額メンタルヘルスや心理学の普及や情報発信のための予算として使用させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筆者 あおきしゅんたろうは福島県立医科大学で大学教員をしています。大学では医療コミュニケーションについての医学教育を担当しており、臨床心理士・公認心理師として認知行動療法を専門に活動しています。この記事は、所属機関を代表する意見ではなく、あくまで僕自身の考えや研究エビデンスを基に書いています。
そのほかのあおきの発する情報はこちらから、興味がある方はぜひご覧くださいませ。
Twitter @airibugfri note以外のあおき発信情報について更新してます。
Instagram @aokishuntaro あおきのメンタルヘルスの保ち方を紹介します(福島暮らしをたまーに紹介してます)。
YouTube あおきのぼやきと見た景色を載せてます https://www.youtube.com/channel/UCIjPXbecsTqIfznCwhKGBgQ
ばっちこい心理学 心理学おたくの岩野、とあおきがみなさんにわかりやすく心理学とメンタルヘルスについてのお話をお伝えします。
YouTube
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
