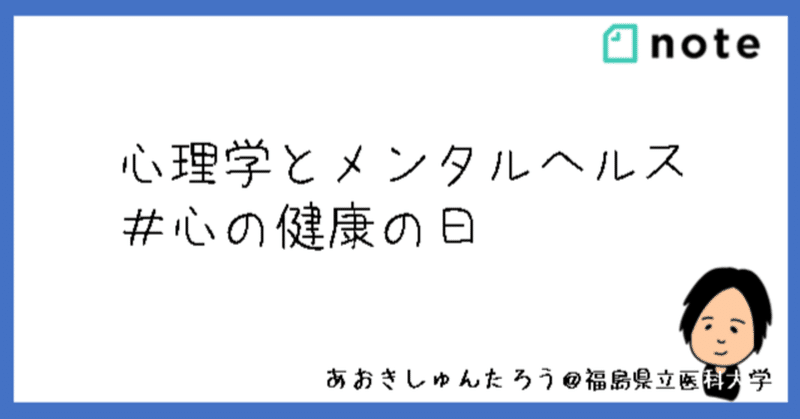
こころの健康と心理学 #心の健康の日
9月16日は「心の健康の日」です。心の健康への意識向上、心の健康に関する情報発信などを通して、国民が心健やかに過ごせる一日にしましょうと和光大学の高坂先生が発起人となり、なんかしようぜという日です。
9月16日は公認心理師法が制定された日ということで、それを記念して。わたしも公認心理師なのですが、その仕事内容の1つに「心の健康に関する情報を普及すること」があるわけなんです。
そこで本日の記事では、心理学とメンタルヘルスの基本「こころの健康と心理学はどのようにつながっているか?」を話していきたいと思います。
心の健康とは?

「メンタルヘルス」ともいいます。うつ病や不安症などの精神疾患、心身症など、さまざまな病気の原因にもなります。病気ではなくても、メンタルヘルスの悪化は不調の原因にもなります。
メンタルヘルスをひとことで言うと、「感情」と「生活満足」です。
感情というのは「ネガティブな気持ち(憂うつ、不安、怒り)」と「ポジティブな気持ち」です。
「ネガティブな気持ちが少なく、ポジティブな気持ちが多い、そして生活に満足できていることがこころの健康が良い」といわれる状態です。
心の健康はどんな原因で脅かされるか?

基本的には外的な環境によって心の健康が脅かされます。いわゆる「ストレス」と呼ばれるものです。
対人関係、仕事、生活のこと、お金など、環境によって私たちの心が動きます。心を動かす要因はすべてストレスです。
ストレスが発生すると、以下に説明する「考え方・行動・からだの不調」を通じて感情が発生します。
怒られたら「落ち込み」ますし、不当な扱いをされると「怒り」が出てきます。試験があれば「不安」になります。褒められると「嬉しい」気持ちになりますよね。
心の健康は、ストレスによって感情が発生することによって脅かされたり、逆にそれがポジティブなものであれば良くなったりもします。
心の健康をキープする心理学
(わたしのnoteのマガジンでたくさん書いてますのでよかったら↑も参照ください)
心の健康に関連する研究や議論は臨床心理学という分野で行われてきました。その中でストレス研究や認知心理学、学習心理学の知見を応用した研究がされてきました。
ストレスの後、すぐに感情が元通りになるというのはあまりないのですが、ネガティブな気持ちが続きすぎるとメンタルヘルスが脅かされます。
ネガティブな気持ちが続きすぎる要因の1つが「考え方」です。叱られた後、「よし、次は怒られないように、確認を気をつけよう」と考えるか、「また怒られちゃった、自分ぜんぜんダメだ」と考えるか。
どちらが落ち込みや不安が続く考え方でしょうか?
次に「行動」です。同じように叱られた後、反省をし、友達に話して聞いてもらおうとか、ちょっとリフレッシュしようと遊びに行く、あるいは、家にこもってなにもしないでいる。
どちらが落ち込みや不安が続く行動でしょうか?
こういったことが、臨床心理学の研究からいろいろとわかってきています。
また、「からだの不調」も感情に影響します。心身相関ともいいますが、心臓がどきどきして汗をかいてきて息が荒くなってくる・・・とこれは危険な状態だと脳が判断するので不安な気持ちになります。
こういったときには呼吸を整えたりすることでうまく心の健康を調整できる場合もあります(もちろん基礎疾患があるばあいもあるのでその場合は医療機関を受診してください)。
このように「考え方・行動・からだの不調」が「感情」に長いこと影響し続けることが、こころの健康が悪化する正体です。
ウェルビーイングに生きる

最後に、心の健康のもう1つの側面に「生活満足」があるとお知らせしました。これはネガティブな気持ちがなく、ポジティブな気持ちが多いだけではなく、「生活に満足できているか?」が心の健康に重要と言われてきました。
病気ではないけど、なんか不満があったり、生活に納得できないというのは果たして健康と言えるのか?という発想です。
ウェルビーイングとも言います。生活に満足できているかを超えて、「自分らしく人生を過ごせているか?」ということでもあります。
もちろん、ネガティブな気持ちが少なく、ポジティブな気持ちが多いということがウェルビーイングの土台です。
一方、「ウェルビーイングに生活するほうがネガティブな気持ちが少なく、ポジティブな気持ちが多い」ということも研究でわかっています。
心の健康の日ということで、みなさま自身の気持ち・感情について、今一度考えてみる機会にしていただきたいなあと思います。
それでは最後まで読んでいただいてありがとうございました!
もし記事に共感していただけたら「スキ」ボタンを押してくれたらうれしいです。サポートしていただけたらもっと嬉しいです、サポートいただいたお金は全額メンタルヘルスや心理学の普及や情報発信のための予算として使用させていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筆者 あおきしゅんたろうは福島県立医科大学で大学教員をしています。大学では医療コミュニケーションについての医学教育を担当しており、臨床心理士・公認心理師として認知行動療法を専門に活動しています。この記事は、所属機関を代表する意見ではなく、あくまで僕自身の考えや研究エビデンスを基に書いています。
そのほかのあおきの発する情報はこちらから、興味がある方はぜひご覧くださいませ。
Twitter @airibugfri note以外のあおき発信情報について更新してます。
Instagram @aokishuntaro あおきのメンタルヘルスの保ち方を紹介します(福島暮らしをたまーに紹介してます)。
YouTube ばっちこい心理学 心理学おたくの岩野、とあおきがみなさんにわかりやすく心理学とメンタルヘルスについてのお話を伝えてます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
