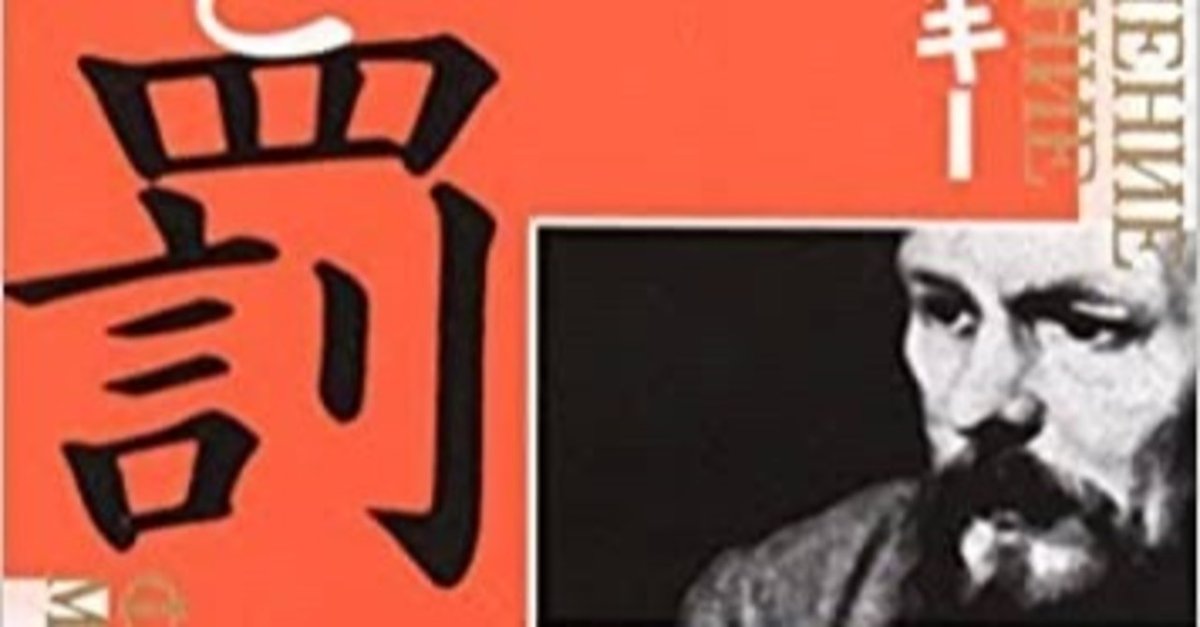
『罪と罰』第一部を読み終えて
作品自体のネタバレは一切しない。
高校生のとき、「マンガで名著を読破できるシリーズ」にハマっていた時期があって、『カラマーゾフの兄弟』も『罪と罰』もそれで読んでいた。そのため、両方ともあらすじだけは知っていた。カラマーゾフの兄弟は、マンガを読んだだけでも背筋が震えるほどゾクッとして感銘を受けた。それにくらべ、罪と罰はなんかパッとしない感じでビミョーだなと思っていた。でも、実際に本を読んでみるとやっぱり違いますね。主人公の心理描写や情景描写がえげつなくて、主人公の思考や主人公が見たもの・嗅いだ臭いまでもが直接頭の中に注入されていくような気分になる。
脇役の設定の作り込み方もはんぱない。冒頭で「マルメラードフ」っていう脇役が出てくるんだけど、この男が実際に存在してるんじゃないかって疑いたくなる。着ているものや体型、言葉の端々から透けて見える本人の性格。まるで、自分がマルメラードフと出会って喋ってるような気分になれる。
たぶんドストエフスキー自身がふだんから行っていた自己内省や他者に向ける眼差しが如実に文章に反映されている。おそらく、自分に対しても他人に対しても観察眼が鋭い人だ。
オタクって「自分の心理の変化には繊細だけど他人の心理には恐ろしいほど鈍感」っていう人が多い。それが一概に悪いことだとは言えない。そういうオタクが作った作品には良いものがたくさんある。しかし、ドストエフスキーが凄いのは、オタク的な自己内省をしつつも、他者のことを徹底的に外枠から捉えて、その内面まで観察し尽くそうという態度を持っていることだ。ドストエフスキーが描く物語の中でも依然として「主人公対対象」「私とその他」な世界観ではあるのだが、その人の顔・目つき・体格・癖・着ているもの・その人の経験した印象的な出来事などのプロフィールを徹底的に詳細に描き込み、あとは読者がその人の人となりや内面を想像できるようになっている。脇役の心理が"実際には"どのように動いているのかは、文の中で説明されていないので知ることはできない。しかし、ラスコーリニコフ(主人公)の目に映った世界や経験した出来事は、確実に読者が追体験できるようになっている。つまり、ドストエフスキーは「強化版オタク」なのである。そういう印象を受けた。
ただ、情景描写や脇役の描写が詳細すぎて(長すぎて)途中で読むのを挫折する人も多いと思う。たとえば、マルメラードフの語りは長すぎるし、青年が見た悪夢の内容(←ストーリーとは無関係)まで詳細に書いてあることに至っては「ノリが合わないな〜」と感じる人が大半だろう。しかし、そうした描写が、『罪と罰』の世界のリアリティを演出する上で重要な役割を果たしている。決して「冗長な駄文」というわけではない。
文章には書き手のリズムがあり、読者はその筆者独特のノリを掴むことで、文章を楽に読むことができる。たとえば、マルメラードフの語りシーンは、それこそ日高屋でマルメラードフっぽいジジイに絡まれたと思って、話半分にテキトーに速読するのが正解だと思う。
思うに、私(たち)は「あ、メタネタだ」「伏線だ」「伏線回収された!」「オチは?」というような通ぶった読み方で話のあらすじをたどるのに慣れすぎている。だからこそ、ドストエフスキーの文を読むと回りくどく感じてしまうのだろう。そこは反省した。
繰り返しになるが、ドストエフスキーの文章の独特のノリや一見回りくどく見える表現にさえ慣れてしまえば、「脳に直接データをインプットされたかのように」心理の変化や情景が入ってくる。こりゃあものすごいコンテンツ!ものすごいエンターテインメントや!
この情報量で、かつ1000ページもある作品を一冊のマンガに収めるのはマジで無理ゲー。むしろ、「マンガで読破シリーズ版 罪と罰」の作者はめっちゃ健闘したと思う。
ところで、物語のシリアスな場面でいきなり変なユーモア入れてくるところが狂人っぽくて好きだ。ふつうに声出してウケてしまう。人をびっくりさせるのが好きなんかな。ドストエフスキーといっしょに酒飲んだら楽しいだろうな〜。ドストエフスキーは酒場で人に会うと自分の作品のことばかり喋ってたらしいけど。
第一部しか読んでないのに長々となにを語ってるんだって感じだ。スミマセン…
引き続き読んでいく。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
