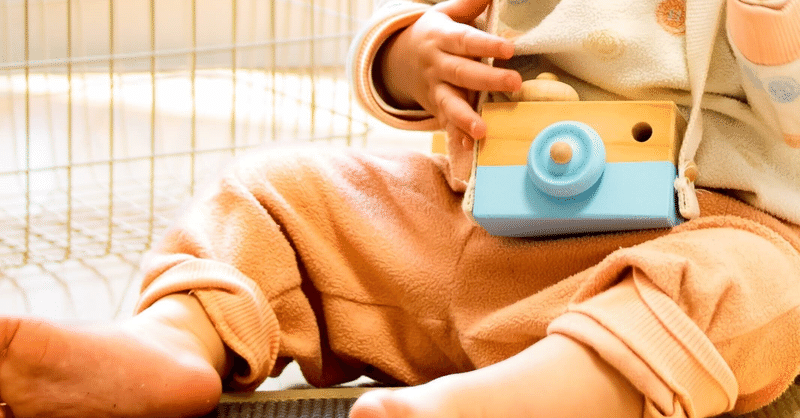
【小児科専門医が解説】赤ちゃんの発達についての悩み、疑問
こんにちは。
子育て医療のあんよ編集部です。
あんよは、複数の小児科専門医と一緒に作り上げる子育て医療のQ&Aの発信をしていきます。
この記事は、主にあんよで寄せられたQ&Aをもとに作成しております。
より多くのQ&Aを読みたい方は、アプリをインストールしてみてください。
赤ちゃんの発達についてのQ&A
1. 生後7か月です。自分から寝返りをせず、うつ伏せになりません。手で押して助ければ寝返りできますが嫌がります。うつ伏せから寝返り返りはできます。このままだとハイハイをしないのではないかと発達が心配です。
赤ちゃんの発達は、必ずしも、「寝返り→お座り→はいはい→つかまり立ち→伝い歩き→ひとり歩き」とう順番通りにすべてをクリアしないといけないわけではありません。中には、寝返りをせずにお座りできるようになる子もいれば、ハイハイせずにつかまり立ちをする子もいます。極端に言えば、最終的に歩けるようになればよいわけです。お子様は、うつ伏せの状態が嫌なだけかもしれません。ご心配であれば、母子手帳の「6〜7か月健診」として、あるいは、発達相談として小児科を受診してみてください。
2. 生後7か月です。自分が家事をしている時など、ついテレビを見せてしまいます。1日2時間以内くらいなのですが、言葉の発達や視力低下が心配になります。乳児のうちから、テレビは見せない方が良いのでしょうか。
日本小児科学会では、「2歳以下の子どもには、テレビ・ビデオを長時間見せないようにしましょう。」「授乳中や食事中はテレビをつけないようにしましょう。」などの提言が出されています。その中で、4時間以上の子どもを長時間視聴児として発達への影響を懸念しています。 乳幼児期のテレビの上手な見方は、長時間見せない(長くても2時間以内)、つけっぱなしにしない(見終わったら消す)、乳幼児に一人で見せない(親と一緒に見て、歌ったり踊ったり、子どもに話しかける)、授乳中・食事中はテレビをつけない、将来、子ども部屋にはテレビを置かない、などです。
3. 「バイバイ」はしますが、「はーい」や「どうぞ、ちょうだい」を理解しないので発達が少し不安ですがどうすれば良いですか? (1歳・男児)
子供の発達には、個人差が大きく、その日の気分でも、できることとできないことがあります。できないことにばかりに目が向いがちですが、できることを褒めて楽しく過ごしてください。 もし、テレビ・ビデオ・DVDなどの視聴時間が長すぎると思ったら、なるべく視聴時間を短くして、その時間に「ままごと遊び」などを試してみては如何でしょうか?「ままごと遊び」は、ことばや双方向のコミュニケーション能力を育む効果があります。 なお、発達に不安がある方もない方も、1歳半健診は必ず受けて、発達に関するチェックを受けましょう。
心配なことがあれば、すぐに小児科医へ相談しましょう。
あんよでは、ご自宅で気軽に専門医へビデオ相談ができる、あんよonlineを行なっています。
保険証、こども医療証をご提示いただければ、保険適用の自己負担金のみでご利用いただけます。
相談・診療枠には限りがあります。ご了承の上、ご利用ください。
ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
