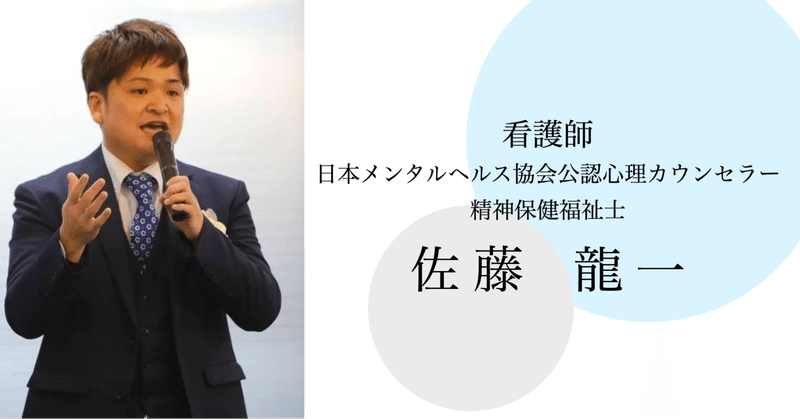
『日本の4人に1人!?僕がこころに寄り添い続ける理由』
2020年、リーマンショック後の2009年以降、10年連続減少していた全国の自殺者数が、11年ぶりに前年度を上回りました。現在、実に日本人の4人に1人が『心の病』だとも言われています。
厚生労働省も「自殺は追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題」であると警鐘を鳴らしています。
今回は、精神看護師として約10年病棟勤務後、現在は看護師兼、精神保健福祉士・心理カウンセラーとして障がい者施設勤務だけでなく、『心に寄り添うこと』をテーマに全国講演活動もされている佐藤龍一さんに取材させていただきました。勤務形態を残しながらも、自分らしい資格の活かし方をする佐藤さんの新しい働き方を紐解いていこうと思います。
佐藤 龍一
■ 経歴
看護師・日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー・精神保健福祉士
現在、大分県の障がい者支援施設勤務。
看護学校卒業後、病院奨学生のため総合病院の手術室で勤めたが半年で退職。その後、実習で魅了された精神科で約10年勤めた。
働きながら学校に通い、精神保健福祉士と心理カウンセラーを取得。
4人に1人が心の病の今、幸せな人を増やすことを目的に『心に寄り添うこと』をテーマに2018年、30歳から全国にわたり講演活動を開始。
大分県警の講師も勤め、一般講演をはじめとする企業研修、小中高校や警察署、少年院などで命の授業や教育講演など様々な場所で活動。
全国で幸せな人を増やし反響を得ている。
実は、僕は初めから精神科という領域に魅力を感じていた訳ではありませんでした。
むしろ「暗い・怖い」といった精神科に対する偏見が強く、「精神科の実習は楽だから休憩だよ」とも聞き、マイナスイメージを持つ自分がいました。
その偏見が魅力に一変したのが、精神科実習で訪れた病院初日の出来事。
患者も看護師も一歩一歩、共に歩む戦友のように輝いていたのです。指導者だった男性看護師も精神看護に対する想いが熱すぎて、実習初日のカンファレンスで僕は偏見を持っていた自分がとても申し訳なくて号泣し、実習期間であった3週間は精神看護の世界にのめり込むように勉強しました。
その結果、実習生の立場で病歴30年以上だった患者を3週間で退院支援メンバーにまでサポートでき、その後、退院することが出来たと報告を受けました。
それから手術室での勤務を経て、念願の精神科病院に転職しました。学生時代、指導者と共に出来ないを出来るに変えるサポートが出来た経験もあって、僕は患者ファーストな精神看護をすると意気込んでいました。
しかし、病棟での現状は思い描いた世界とは少し異なっていました。
精神科が他の診療科と異なる特徴のひとつに、多量処方になりやすいことと、一度入院すると長期間になりやすい現状がありました。
僕としては、患者ファーストで寄り添うことを大切にしていたので、もっとこのような看護をしたらどうだろうかという提案を上司や主治医に積極的にしてきました。
”よく眠れるようになってきたからこの薬は少し減らせるのではないか?”
”もし薬が順調に減っていけば一時的にでも外出が可能なのではないか?”
それは病棟内では「患者」ですが、入院するまでは外の世界にその方の日常が広がっていて、当たり前のように日々生活し、家族や友人と過ごしていた1人の人だったはずだという想いからなんです。
だからこそ、病院の都合ではなく、出来る限り患者の今までの日常に寄り添った形のケアを僕はしたかったんですね。
しかし、自分は患者ファーストでやりたいと思っても、看護師は医師の指示を受けざるを得ないケースも多く、病棟のルールや制約によってやりたい看護を諦めないといけないことがとても悔しかったんです。
看護師10年目を前に、僕は自分の看護師人生はこのままで良いのか、入院前だけでなく、心が疲れる前に人々に寄り添えないのかということを考えるようになっていきました。
そんな頃に、ある偶然の出会いがありました。
僕の1番の理解者である妻に相談していたことから、周り回って当時福岡県で小学校教諭をされていた女性を紹介され、心理学スクールの体験会に半ば強引に連れて行かれたんです。
自分が看護師をする中で感じていたこと、心が疲れる人を未然に救いたいと言う思いの丈を聞いてもらい、そこで言われたのが「講師として伝えていけば、全国に幸せな人が増えるよ」という言葉でした。
僕は病院の現状を変えることに必死で、自分の想いを言葉に乗せて発信していくことを考えたことがなかったので驚きました。
そして2018年、スクールの先生がご厚意で場所を提供してくださったことがきっかけで始まったのが、僕の講演『心に寄り添うこと』です。

その時全国から来てくれたカウンセラー仲間が共感してくれ、今や全国で講演させて頂けるようになりました。また、僕は高校の時に事故で父を、24歳の時に親友の突然死を経験しています。
最近では、地元の大分県警で被害者遺族を代表して心の寄り添い方を、九州内外の学校・少年院・警察署などでも講演依頼があり、地元に貢献出来ることに幸せを感じています。
現在は、精神保健福祉士・心理カウンセラーも取得し、大分県の障がい者支援施設で勤務しながら、講演活動も並行し、精神領域に携わり続けています。
■メッセージ
今の看護学生や若手看護師に伝えたいことは、「ひとつの形にこだわらなくても良い」と言うことです。
僕も最初の手術室では人間関係がうまく行かずに看護師を辞めたくなったり、精神科ではやりたい形を見出せず、もがきながら10年続けてきました。
その中で感じたことは、「看護」と言う定義は今のあなたが思うよりもとても広い意味が込められていて、想像以上に全ての世代、どのような人にも必要なものだと言うことに気付きました。
たとえ、ひとつの道が塞がれたとしても、あなたらしい看護が活かせる場所はたくさんある事を忘れないで欲しいです。
そして、同じ看護師として、1人でも多くの人の心に寄り添える仲間であり続けてくれる事を僕は願っています。
*
*
*
今回のインタビュアーは山田理早さんにお願いいたしました。
ありがとうございました。
佐藤さんとお友達の秋吉さんのインタビュー記事も大好評!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
