
介護福祉士がnote、YouTube、ブログ、電子書籍、SNSなどを頑張った結果【収入、労力、コスパ】
こんにちは、アルゴです。
介護施設で働いていたころ〜現在にかけて、いろいろなSNSを通じて、ネット社会で収入をあげられるのか頑張ってきました。
●労力をかけたのにうまくいかなかったもの・・・
●気軽にやっていたのにうまくいったもの・・・
●徐々に売上があがってきたもの
このnoteをはじめ、タイトルにもあるようにYouTube、ブログ、Twitter・・・・
その他にも、Instagram、キンドル電子書籍出版、インディーズマンガコミニティなど、いろいろなチャレンジをしてきました。
今回の記事ではこれらネット上活動で、今までやってきた努力と結果、感じたことなどをお話できればと思います。
大切なポイントは
① 介護福祉士として、介護のスキルをネット社会にどれだけ活かせるか?
② ネット活動の収入だけで食べていけるのか?
で、この2点に焦点を狭めてお話します。
ブログ
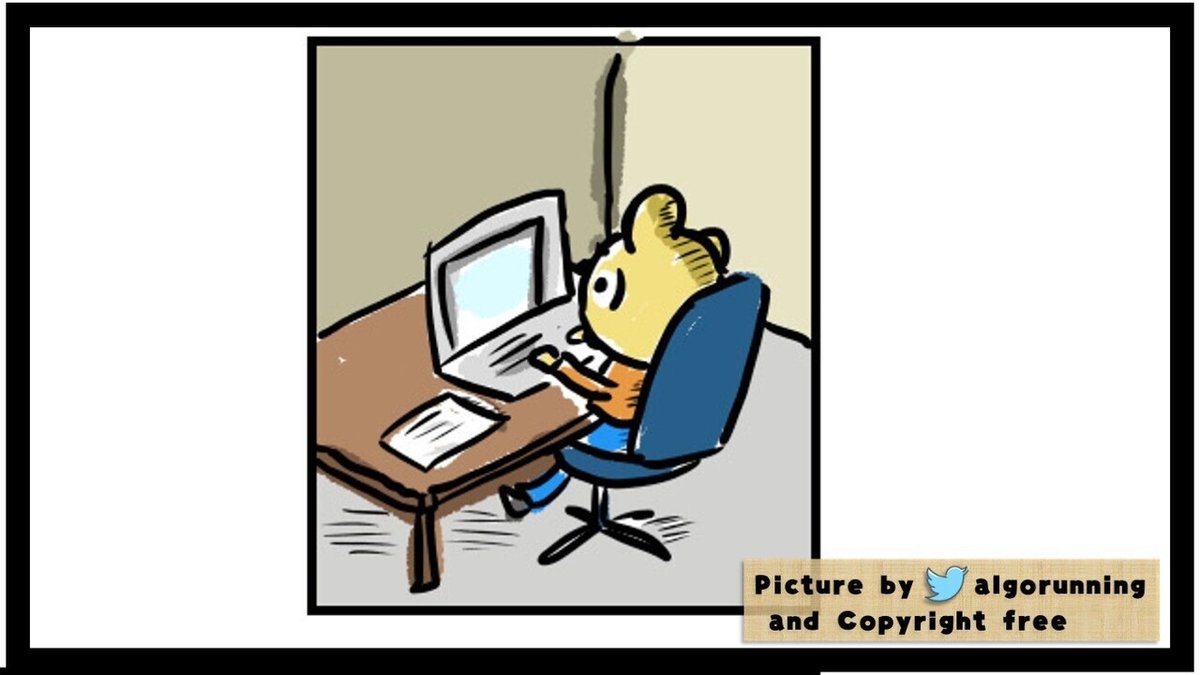
私はこのnoteを始める前に、
スローライフの歩き方 というブログサイトを運営しています。
このブログには介護のことはほとんど書いていないですが、自分自身の健康とか、独身マイホームライフとか、ありきたりなことを書いています。
しかし今までで一番アクセスがあるのは、1ヶ月間玄米を食べ続けた結果・・・について書いた記事です。
自分でも全く予期していませんでしたが、Google検索からの流入が多いです。
ブログ収入は、ブログを商品宣伝して売るアフィリエイト収入と、
広告をクリックしてもらうだけで収入が入るアドセンス収入があります。
私はどちらもかけあわせて行っていますが、かけた労力に対して収入は雀の涙です。しかも売れた月、売れなかった月で安定もしないです。
サーバーレンタル代など維持費もかかっています。それを回収してプラスになったとしても、努力の割に結果がついてきませんでした。
今は完全に、書きたいときだけ書く感じになっています。
note

ブログと併用して始めたのが、このnoteです。
上記のような個人ブログはGoogle検索のアルゴリズムが変わってしまうたびに、一気にアクセスが落ちてしまうことがあります。
そんな中でもnoteはSEOが強いので、トレンドな記事を書くとアクセスは伸びます。
ただし、Google検索からの流入は、noteにログインしていない人もアクセスするので、アクセスが多くてもフォロワーが増えるとは限りません。
それもあって、アクセス数といいね数は全く比例していないということです。
私のすべてのnote記事の中で、歴代一番アクセスの多い記事を上から順に上げると、
1位 📘『科学的介護推進に関する評価』について
2位 📘職場の介護施設に尽くしたいという考え方について
3位 📘【マンガ】今、ボクがいる世界
となっています。
このうち、1位と3位が10くらいのいいね数しかないのに対し、2位の愚痴っぽい記事だけが40以上のいいねをもらっています。
※ noteではいいねを『スキ』といいますが、ここではいいねとして統一します。
1位の科学的介護の記事は圧倒的にGoogle検索からの流入と思われます。ちょうど今年の4月に介護保険のLIFE加算がはじまった時に書いたので、トレンド的なものになったのでしょう。トップ記事なのに、いいね数は全くありません。
3位のマンガはTwitterで固定ツイートにしている関係でアクセスがあるのかもしれません。LIFE記事と同様、noteに登録していない人も見るので、やはりいいね数もないです。
2位の記事は愚痴っぽい内容なのですが、それなりに多くのいいねをもらえました。noteではこういう内容が共感をうむのかもしれない…と感じました。介護職であればこういったネタは誰もがもっていると思うので、noteはむいているかもしれませんね。私自身も、他の人のこういう記事を見ることで気持ちがラクになることがあります。
ただ、個人的にイチオシ…というか、一番労力をかけた記事が、ランキングにまったく入ってこないこちらの記事なのです。
手荒れに関する記事で、全然読まれていないですが、個人的にはめっちゃがんばって、有益な記事を書いたつもりでした。
ただ、ニーズがなかったようです(笑
(いいねしてくれた人、ありがとうございます…)
しかし、個人的にnoteは、フォロワーやいいねを集めることの他に大きく貢献してくれていることがあります。
それは電子書籍の売上です。
私はKindleで電子書籍を数冊書いていて、今も執筆中です。noteの記事を書くことに、リンクをつけたりしているのです。
ひとつひとつ、リンクをつけた記事を執筆するたびに、いいね数とは関係なく、電子書籍の購入や購読数が増えます。
あとは、みんなのフォトギャラリーで400回くらい他の方に私のイラストが使用されていますが、これはいくら使われようと一銭も入りません(笑
電子書籍出版

私はAmazonの電子書籍 Kindle(キンドル)で、電子書籍を4冊出版しています。投資の含み益とかを除けば、これが現在、一番の収入源となっていますね。月を追う毎に売上が上がっていくので、今後も伸びていきそうです。
電子書籍出版というと難しく感じそうですが、本当に誰でもできます。とはいっても、最低限パソコン1台は必要になりますが、WindowsでもMacでも何でも良いです。パソコンさえあれば、出版にお金もかかりません。(審査はあります)
電子書籍出版に関しては、私のYouTube動画で、原稿作成〜出版までの手順を24分で解説しています。
↓↓↓
先程ブログでアフィリエイト収入やアドセンス収入について述べましたが、ブログで一生懸命文章を書くくらいなら、ぜったい電子書籍にして販売したほうが良いです。
Kindle利用数は右肩上がりになっているため、市場も成長していくと見込めます。

さらに、介護関係の本を出している個人はあまりいないです。
Amazonの検索窓で「ユニットリーダー」「介護リーダー」「ユニットケア」などとありふれたワードで検索すると、すぐに私の本が出てきます。ブログのような競合相手が少ないということですね。
ライバルを増やしたくないから言いたくないけど、狙い目です。
Kindleの収入には2つあります。簡単ですが説明しますね。
1つ目は単純に販売数。値段を自分で決められます。私は売れたぶんの70%がロイヤリティとして入金されています。
2つ目は無料購読数です。KindleにはKindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)という月額980円で電子書籍読み放題のサブスクサービスがあります。(私も入ってますよ)
このサブスクに入っている人が無料で電子書籍を読んでくれても、読まれたページ数✕0.5円が私の収入となります。
詳しくは、上記の海河童さんの本を見てください(^^)
一度販売してしまえば、自分は何もしなくても売れていくものなので、まさに不労所得に適しています。
ですが上述したように、noteとかけあわせて収入を増やせると良いと思います。
YouTube

YouTubeをまじめに始めたのは半年くらい前です。(削除した動画もたくさんありますが)
本来YouTubeはほとんど趣味、遊びでやっていましたが、noteとあわせてフリーランス介護に関する動画も投稿してみました。(①〜③まであります)
文字をひたすらうって、エフェクトを調整したり、素人ながら大変です。こんな動画でも1本作るだけで5〜6時間はかかります。
ただ、こういうマニアックな動画はニーズがないのか、3本ほど出しても再生数が伸びません。
それとはうらはらに、ただ単に家の中を撮影しただけという…ほとんど手をかけていないような内容の動画の再生数が伸びることがあります。
とはいっても、再生数だけ見ても、noteやブログに遠く及びませんけどね…(悲
YouTubeは難しいな。
一生懸命、フリーランス介護の動画を作成したのが馬鹿みたいです。これから介護系の動画を作ることはないと思われます。疲れる上に誰も見ないので(笑
チャンネル登録者数も1000人を超えなければ、広告収入はゼロです。

現在私は、Twitterはほぼ、情報収入や交流のためだけに行っています。
しかし以前は自分のブログや電子書籍の宣伝に使っていました。
2,3年前にインフルエンサーの間でよく言われていたのが、Twitterを頑張ってフォロワーを1000人にすれば、それだけでそこそこ稼げるというものでした。
私もメインアカウントである @algorunning は500人近くフォロワーがいます。
でもTwitterのフォロワーって、フォローしている人がフォロー返しをしてくる、相互フォローというものがけっこうあるんですよね。相互フォロー目的にフォローしてくる人もいて、そういう人はしばらくフォローを返さないと、フォローを外されたりすることだってあります。
ちなみに私は、TwitterでもnoteでもInstagramでも、相互フォローは基本的にしません。
たまたま私をフォローしてくれた人が、自分にとって興味のある人だったら私からもフォローするということはあります。また、こちらからフォローしたらフォローを返してくれるということもあります。
だから結果的に相互フォローになってしまった…というケースが多いですね。
なので、私のフォロワー500人のうち、相互フォローになってしまった人が7〜8割かと思います。
ちなみに、YouTubeにもTwitterにもいえることですが、相互チャンネル登録・相互フォローというのはアルゴリズム的によろしくないそうです。人気がない…と判断され、おすすめなどに上がりにくくなってしまいます。
自分に興味のない相互フォロワー…つまり、フォロワーのアタマ数だけ増やしたとしても、自分の収入につながるということ難しい。フォローしてくれるのと、お金を出してくれるのは別問題です。
私の経験上、Twitterでリンクを貼ったツイートをしても、それがクリックされる確率は非常に少ないです。とりあえず『いいね』だけ押している人はいますが、その人もリンクをクリックしたり、リンク先の商品を買ったりしないでしょう。
そういう事に気づいてから、私はTwitterをまじめにやるのをやめました。
商品を売るのなら、商品を求める人が集まる場所に商品を出すべきです。
つまりAmazonという世界最大の書店で販売されるKindle電子書籍の執筆は、商品としても市場ニーズとの兼ね合いを考えてもコスパが良いです。
結論、いくら頑張っても報われないことは手放したほうがいい

本記事で述べてきたように、
●労力をかけても報われないもの
●労力をかけていないのに成果がでるもの
があり、労力に対して成果は比例しません。
どんなものでも、一生懸命取り組めば必ず自分の経験としてプラスされるのは事実ですが、それで収入を得ていくということを考えると、コスパが悪いことは切り捨てなければなりません。
エジソンの有名な言葉、『1%のひらめきと99%の努力』について。日本では誤訳…というか、間違った解釈をされてしまっているようです。
本当の意味は、『1%のひらめきがなければ、99%の努力が無駄になってしまう』…という意味なんですね。
つまり大切なのは、労力をかけることではなくて、労力を無駄にしないよう、しっかりコスパ良く行動することなんだと思います。
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
