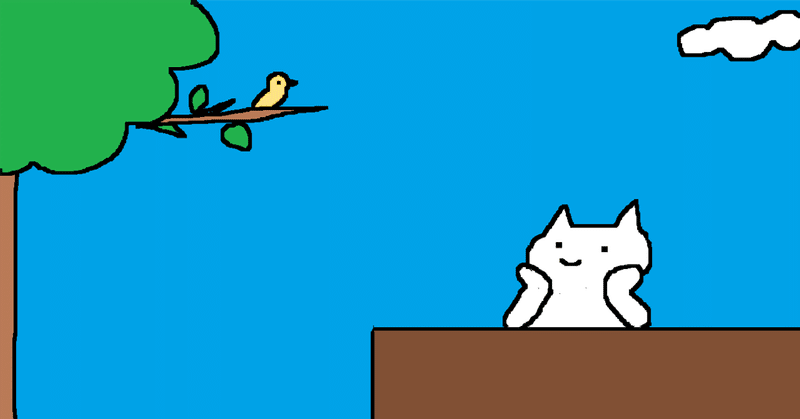
でき太くん三澤のひとりごと その67
私があまり好きではない言葉。
教育関連では、「反抗期」、「不登校」です。
これは教育に携わる大人側が作った用語で、子ども側の視点を取り入れていない用語のように感じます。
こういう用語をしっかり吟味せず、何気なく使っていると、その用語の持っているネガティブな力によって、問題でもないことが問題となっていくことがあります。
たとえば、子どもは3歳前後になると「反抗期」があると一般的には言われています。
わが子がその時期をむかえたときに、「やりたくない!遊びたい!」と癇癪を起こしたら、3歳から「反抗期」があるということを知っている親御さんは、「うちの子にも反抗期が来たのかな?どうしよう?どう対応したらよいのだろう?」と考えるようになると思います。
でもこれって、「反抗」ではなく、子どもがようやく「自分」というものを主張し始めただけのことではないでしょうか。
これまで親御さんの援助がなければ、何もできなかった状況から、ようやく自分の足で大地に立ち、「自分がしたいこと」、「自分の考え」というものを主張できるようになったという、成長の「証」なのではないかと思うのです。
同じ現象でも、「反抗」と捉えたら、それはネガティブに見えてしまいますが、成長の「証」と見れば、それはポジティブなものとなります。
同じ現象をどのような言葉、用語で認識するか。
これによって行動に大きな違いが出てきます。
「やりたくない!遊びたい!」と子どもが言ってきたとき、もしそれを「反抗」というイメージで捉えた場合は、「もう時間がないから帰るよ!いつまでも泣かないの!」、「お母さんの言うことを聞きなさい!」というような感情や力で子どもを押さえつけ、親が良しとする方向に引っ張っていこうとすると思います。
逆にその状況を「反抗」ではなく、子どもが自分を主張できるようになった成長の「証」として捉えることができたら、おそらく感情や力で押さえつけたりせず、まずは子どもの気持ちを聞いてみたり、話をしたりすると思います。
ようやく「自分」というものを主張するようになったわが子が、どういうことを感じて、どんな考えを持っているのか聞いてみようと、その状況を受け入れることができるはずです。(もし自分の考えや気持ちと違うことを主張することを「反抗期」とするなら、社会で自分と意見の合わない人は、みんな「反抗期」ということになります)
「不登校」についても同じです。
私の知人には、子どもが休みたいときに休んで、行きたいときは行く。休みのときには思いっきり自分のしたいことをしている、というご家庭もあります。
進路はすでにN校と決めているようで、自分の感じたまま、やりたいことをどんどん突き詰めているようです。
こうなると、「不登校」の「不」のイメージはありませんよね。
学校へ行かないことによる罪悪感もなく、その子は毎日を思いっきり楽しんでいます。
なぜそんなに楽しめるのかといえば、おそらくそのお子さんは自分のことを「不登校」という言葉で認識していないのだと思います。
きっと「不」というマイナスのイメージでは捉えていないのでしょう。
どのような言葉や用語で現象を認識するか。
一度自分の認識を見直してみるのもよいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
