
ちょっとだけ気になっていること
遠藤周作氏の小説『女の一生』を読んだ感想(といえるのか)は本棚のマガジンに入れている。この小説のことを教えてくれたのはKさんだった。
『女の一生』には一部と二部があり、といっても「上下巻」のようにひとつの物語がつながっている構成ではなく、長崎のとくに大浦周辺を中心として、当時のキリシタンを取り巻く舞台設定という点で共通してあることと、一部と二部では時代が進んでいて、かつ登場人物のなかには血のつながりをもたせるなどして、分けてある。続けて読むといいし、それぞれの巻を、それぞれの物語として読むこともできるような小説となっている。
大浦天主堂の保護者は日本二十六聖人としてあり、建物はその日本二十六聖人が処刑され殉教地となっている西坂を向いて建てられている。正式名称は「日本二十六聖殉教者聖堂」という。
西坂の刑場を向いて建てられている、というこれはいくつもの文献や観光案内の情報などでみられる表現である。
この本の話を聞いたときに、Kさんがこの件について、現在西坂の丘として整地されている場所と、実際の処刑場との位置関係について疑問点があるということを言った。それがなんだか印象に残った。
日常業務のなかで、大浦地区を歩くこともわりとある。この物語を読んだあとに、この位置関係に関することが気になって大浦天主堂の正面入り口に立ってみた。その場所から西坂の方向を眺めたりしたが、視界を遮る建物が多すぎてよくわからなかった。
その場所に立ってみたときというのは第一部を読み終えた直後で、物語にも出てくる信徒発見のマリア像の前に座るなどして、いろいろとおもいを馳せたりもした。マリア像の背後、祭壇に向かって右手側にはプティジャン神父の墓碑があることもあって、物語に寄り添いながらしばらく静かな時間を過ごしてみたいとおもってのことだったのだけれど、いまや観光施設ともなってしまった大浦天主堂の御堂の中では、案内を録音したアナウンスが繰り返し流れていて、静かに過ごすことは叶わない。サービスのひとつなのはわかるけど、こういうのって、どうなんだろうか、ぶつぶつ。
こんどは西坂周辺を訪ねようとおもいつつ、まだ果たせていない。
西坂周辺にはまだ足を運んではいないのだけれど、先日県庁舎に行く用事があった。現在の庁舎は尾上町というところにあって、そこから長崎港や反対側の山手が見渡せる。この日はあいにくの雨だったけれど、傘を手にそれぞれの方向に目を向けた(下の地図上の青い丸印)。



そのあと、事務所に戻る途中の長崎港からもう一度、大浦の方向を眺めたりした(地図上の緑の丸印)。昔の景観はどんなふうだったんだろうか。
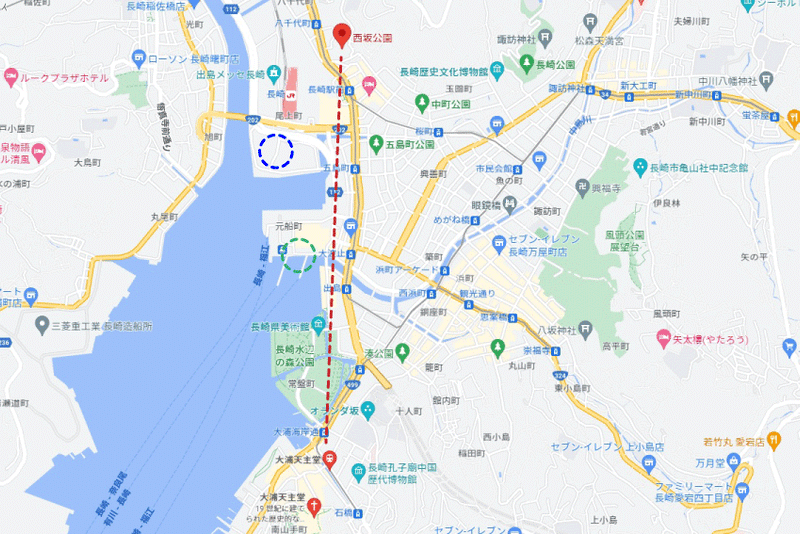
地図で見ると、ピンがあるそれぞれの位置は確かに直線でむすべるようになっている。でもそもそもこの「西坂の丘(西坂公園)」というのと、当時の処刑場があった場所について疑問が残るらしい。ちなみに当時はここが岬になっていたというから、つまり現在の国道や長崎駅周辺はすべて埋め立て地ということになる。


1863年の1月にパリ外国宣教会のフューレ神父が来日、開国はされたもののまだ日本人に対するキリシタン禁教は解かれていなかった。外国人居留地に暮らす外国人のための教会建設が許可され、フューレ神父はその候補地として南山手町乙1番地(現在地)を購入した。
先に司祭館が落成された1864年の8月初旬、同宣教会のプティジャン神父が来日している。翌年1月請負師に熊本県天草出身の小山秀之進(のちに秀と改名)を迎え、建設に着手する運びとなった(ちなみにこの小山秀という人物は放送作家の小山薫堂氏の高祖父にあたるらしい)。
パリ外国宣教会日本総責任者のジラール神父、フューレ神父の設計による教会建設はプティジャン神父を加え進められ、献堂式を迎えたのは1865年2月19日となっている。
プチジャン神父は当時の教区長あての書簡にこう書いている。
将来の天主堂の位置は、聖地の真向いで、直線になおしたら半里か4分の3里ばかりの所に位置して居り、司祭館の北窓から此の祝せられた丘を見る事が出来る。
司祭館の北窓ということは、聖堂の正面から西坂を眺めたのと少し位置がずれるようにおもう。当時居留地であった南山手の一帯は、土地の余裕がなかったようだし、西坂の方向が見られるように建てられたということで、きっちり正確に刑場に向けたという意味ではないのかもしれない。
大浦天主堂の増改築や変遷について少し書いておく。
第1期工事は上に書いたとおり1865年の創建時にあたる。これは大小3基の塔をもつ90坪ほどのものだったのではないかとされている。まもなく左右の小塔は取り除かれ、1879年にポアリエ師よって第2期工事に着手される。外壁を煉瓦造りとし、左右に一間ずつと奥行きも深くされ当初の2倍の大きさに拡張され、現在のゴシック建築の大浦天主堂となっている。
この増改築の際の大工棟梁は小山秀と同じく天草出身の丸山佐吉ということだが、この人物は実際には彫刻師であり、設計と工事監督とをつとめたが、建築工事に関しては浦上の信者である溝口一造が中心となって行われたとある。
1933年1月23日に国宝に指定となり、1945年には原爆投下によって損傷を受けたため復旧のための第3期工事がおこなわれた。これは1947年から52年にかけて5か年以上を要し、費用もかなりのものだったらしい。1962年には司教座が大浦天主堂から浦上天主堂に移された。
プティジャン神父の墓碑(祭壇向かって右手)の上には大額が掲げられていて、これは日本二十六聖人殉教の油絵だ。1868年にプティジャン神父がローマを訪問した際にフィレンツェの女流画家に依頼したものといわれ、「C,THOREL 1869」の署名がある。
御堂のなかは撮影禁止であるため、興味のある方は現地に足を運んでいただくといいとおもう。
*
生まれた町が好きかどうかとか、興味があるかないかとか、そういうのは人によって様々だろう。私自身はとくに故郷が好きとかいうおもいとしては薄いほうだとおもうけれど、ここ数年はそういう、好きかどうかということを超えて、興味を持って眺めてみるおもしろさみたいなものを感じている。
今回は読書が好きなことや、私がこういった歴史に関わる仕事をしているということから、『女の一生』を勧めてもらい、読んでみて、興味が広がっていく体験をした。ふだん何気なく歩いている土地や、触れている文化というのが、どういう道筋を辿ってきたかというのは知ってみるとわくわくすることが多いとおもった。
人と出会って、そんなふうに興味や世界がひろがるというのもおもしろくていい。
西坂は近い。じりじり汗をかく季節がやってくる前には訪ねよう。そうおもった。
サポートを頂戴しましたら、チョコレートか機材か旅の資金にさせていただきます。
