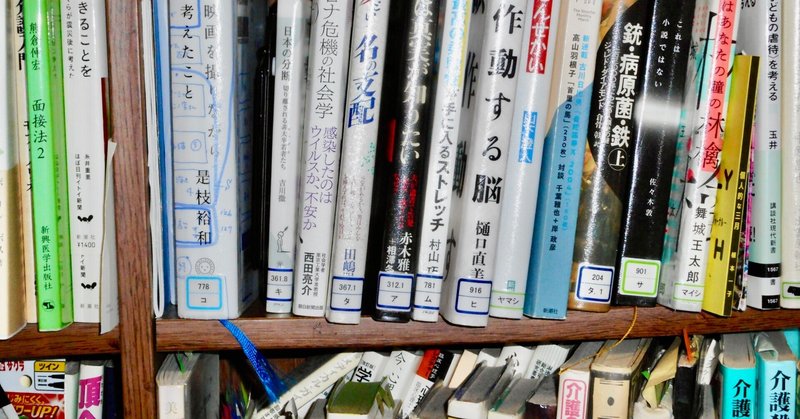
読書感想 『みんなの「わがまま」入門』 富永京子 「とても親切な社会運動ガイドブック」。
「わがまま」という言葉は、もっとそれぞれの人が自由に生きられるようになれば、使われなくなるのだと思っていた。
同時に「人に迷惑をかけるな」というような内面化しやすいルールの強制力も、弱くなっていくと思っていたのだけど、時代は進んでいるはずなのに、「自己責任」という言葉の使われ方が、やたらと広く強くなってきたために、「わがまま」は「迷惑をかけること」として嫌がられる度合いが、また強くなってきているようにさえ思う。
そのことによって規律正しい社会になって安全性が増して安心して暮らせるようになればいいのだけど、今の印象は、より抑圧の強い社会になってしまい、だから、コロナ禍のような非日常になっている現在は、そのことのマイナス面が強く出ているようにも思う。
個人の意識の持ち方を変える。それによって、社会で生き残る方法は、数多く語られてきたのだけど、それも限界がある。かといって社会を変える、というのはさらにハードルが高いから、その発想自体を考えられない年月が続いている。
どうしたらいいのだろう。
みんなの「わがまま」入門
失礼ながら、著者のことを知らず、ラジオで話し方を聞いて、人に伝えることを諦めずに続けている繊細さを感じ(勘違いの可能性はあります)、それでその著書を読んでみたくなり、その中でも、中高生の講義を元にした、この本が読みやすそうだと思って読んだのは、著者の専門が社会運動ということを知り、自分の中で無駄にハードルが高くなっていたせいもある。
「わがまま」ということに対しては、個人的な印象に過ぎないけれど、主に2つのアプローチがあったように思う。
一つは、否定的なアプローチ。
今でも、「あの子はわがままだから」などと言われるのは、相当のダメージがあるようで、それは「人に迷惑をかけない」や、ここ10年での「自己責任」の使われ方と相性がいいこともあって、今でも広く使われていて、そして、そのラベリングをされることは、一般的には避けたいことのままのようだ。
「わがまま」は、自分のことばかりで、みんなの調和を乱す、といった言い方をされ、だから、「わがまま」であることは、「よくない」ことで、教育(もしくは、しつけ)は、その「わがまま」な子どもを、「わがまま」を言わない子どもにすること、といった見方も、まだ少なくない人たちに共有されていると思う。
もう一つは、肯定的なアプローチ。
「わがまま」というのは、「自分の意志」でもあるのだから、「わがまま」であることは、人間として素晴らしいことで、だから、ある人が「わがまま」と感じられるのであれば、それは、そう思わせる「社会が悪い」という見方。
それは、「わがまま!」という言葉で、人の気持ちを無理に抑え込むよりは健全だと思う。
現代の「わがまま」
これまでは、こうして、肯定的と否定的なアプローチがあったように感じてきたけれど、どちらも、誰かが「わがまま」であることを前提にしていて、それに対しての評価であることは共通している。だけど、その前提がもう通用しないのではないだろうか。というよりも「わがまま」がどういう状態なのかが、決定的に変わってきている可能性もある。
誰かに対して「わがまま」と感じることはあるけど、それが、どうしてそんなに不快に感じるのかが分からない。
実は、今は、(特に若い層ほど)そこに一番大勢の人がいるのではないか。現代の「わがまま」って何だろう?というところから地道に考えて、伝えていかないと、「わがまま」から、さらに考えを発展させることもできない。
現代の「わがまま」は、以前と比べると、少し複雑な現状になっているのではないか、とこの本を読んで、気がつくことができた。
現状の正確な把握
時おり、メディアなどで見かける「大学の先生」の中で、自分が苦手とするのは、「今の大学生は」と、日常的に接していることをアドバンテージとして、現代の若者論を語る。それも否定的に論じる人に対して、だった。
自分が若い大学生の頃は、学問に対して徹底的にサボっていたこともあるのだけど、教授と言われるような人たちの多くは気難しい印象で、気持ちを率直に伝えることなどなかったように記憶しているから、そもそも、そういう「今の大学生は」という把握が正確なのだろうか、と疑問に思っている。
その上、もし「今の大学生」が至らないところがあるのだとすれば(10代から20代だったら、その方が自然だけど)、そこを何とかしていくのが仕事のはずなのに、だから、自分の教育者としての至らなさ、という恥ずかしさも少しはあって当然なのに、そうした気配がない、妙に堂々とした「大学の先生」が苦手だった。
だけど、この本を読んで、この著者は、「知らない」ことに対して、下に見る感じがないから、もしかしたら、私が勝手に苦手と思っている「大学の先生」のような人たちは、すでに過去の遺物になりかかっているのかもしれない、とまで思った。
著者の富永京子氏の、この姿勢を可能にしているのは、まずは「今の大学生」も含めて、現状を正確に把握しようとする力なのではないだろうか。
例えば「多様性」という言葉自体は、誰もがすぐに言うようになった。だけど、それがどういうことなのか「具体性」という実感を持って把握しないと、実は「多様性」と「自己責任」が結びついて、寛容性ではなく、ほったらかし、という切り捨てにつながりやすいと思う。
著者は、「多様性」を公的なデータを中心として、具体的に取り上げている。
恥ずかしながら、私は、これ↓を読んで、すでに半分の人たちが、過去の「ふつう」ではないことに初めて実感として気がつかされた。
日本が30人の教室だとしたら
ひとり親世帯の人は2人。
発達障害の可能性がある人は2人。
LGBTの人は3人。
貧困状態にある人は5人。
世帯年収1000万円以上の人は3人。
外国籍の人は1人。
だから、こうした現代の「わがまま」に対しての分析まで、読者としても、真っ直ぐにつながって考えられるようになる。
みんな違って当たり前で、それぞれにそれぞれの生きづらさを感じている。一見同じに見えるけれど、本当は違う人々のなかで、みなさんがイメージする「ふつう」は相当無理して維持されていることを、最初にわかってもらえればと思います。
「ふつう幻想」に沿っていない人の行動を、私たちは個人的で自己中心的な「わがまま」だと思ってしまいがちです。
社会運動への見られ方
「わがまま」というパワーワードからスタートして、その「わがまま」という自分の思いを、まずは伝えようとすること自体が、すでに社会運動ではないか、という気持ちになれるし、この本を読み進めると、社会運動へのハードルが下がっていく感じにもなれるのは、素朴すぎる言い方だけど、書き方のベースが親切だからではないだろうか。
「社会運動って、迷惑じゃないですか?」
例えば、公道などを使うデモなどに対して、今は、特に若い層は、「迷惑」と捉える人たちが、多いらしい。そんな疑問に対して、それは権利だから、という言い方ではなく、こんな言葉の差し出し方をしている。
まず「公共の場だからみんながまんする」んじゃなくて、「公共の場だからみんなが使っていい」という考えにシフトしてみましょう。
社会運動への、とても親切なガイドブック
こうした親切さは、あちこちにあって、例えば、自分を変えてみよう、色々な人に会ってみよう。という提案をする時にも、かなり様々な方法の具体例を次々と、徐々にハードルを下げつつ出している。
色々な場所に行ってみよう。それが無理なら、本を読む。ラジオを聞く。また、隣に住んでいる人を知ることも、自分を変えることにつながる、と書かれているから、少しでも興味がある人間だったら、やってみようと思えるまで、誘導されているように感じる。
しかも、もしも「社会運動」に関わったとしても、自分が消耗するほど無理をすることはないし、途中でやめても構わないし、あまりにも真剣に考えるあまり就職活動などの時に必要以上に視野を狭めないためのアドバイスまでされている。
こんなに親切な「社会運動」のガイドブックは、他にないように思えた。
この本を読んだ後は、人間が生まれて、今ある社会に属していくために、自分が変わっていく必要性は無くなるとは思えないけれど、新しいメンバーが加わるときに、その新しさに合わせて、社会の方が、わずかでも形を変えることも必要ではないか、と以前よりも自信を持って思えるようになった。
外からの視点
この著者の中で、何度か語られているのが、社会運動の研究者であるけれど、社会運動に参加したことはない、と本人の立場が明らかにされていることだ。
そのことで、微妙な後ろめたさと、だからこそ考えられることがある、という揺れる思いもありそうだけど、そうした両方に対して開き直っていないこと。あとは、邪推だけど、元々コミュニケーションが得意でなく、伝わることへの疑いや、正確に伝わらないことの怖さを十分以上に味わってきたからこそ、人に無闇に踏み込まないような、慎重で親切な伝え方を身につけているようにも思う。
それに、これは語るのが難しく、どう取り上げても失礼になりがちなのだけど、特定の宗教を信じている宗教学者もいるはずだけど、同時にどの宗教も信じていない宗教学者もいると思うし、どちらも必要な視点のはずだ。対象からの距離の取り方の難しさで言えば、比べることではないにしても、社会運動も似た印象もあるので、こうした社会運動に参加しない「社会運動の研究者」という「外からの視点」は、これからも必要だと思う。
と言っても、もしも、著者が社会運動に参加した場合は、そのことも含めて、今までにないような社会運動への視点を、新たに提供してくれるのではないか。社会運動に対して、ほぼ無知なまま気持ちの距離を勝手にとってきた人間が言う資格はないとも思うけれど、そんな期待をしてしまうほど、著書が新鮮で有意義な本だった。
学生だけでなく、社会人にも、ベテランの大人にも、混乱している時代だからこそ、おすすめしたい本でした。
(他の記事↓も読んでいただければ、うれしく思います)。
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
