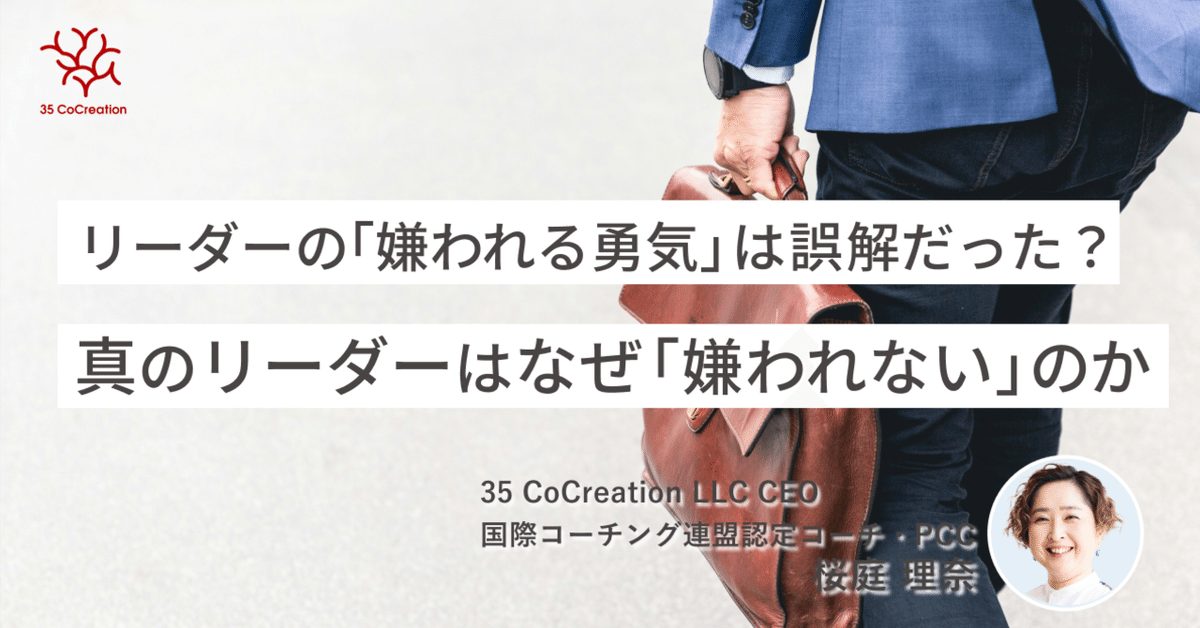
リーダーの「嫌われる勇気」は誤解だった? 真のリーダーはなぜ「嫌われない」のか
コーチングを通して次世代リーダー育成を支援する、35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)CEOの桜庭です。
アドラー心理学をわかりやすく解説した書籍「嫌われる勇気」は、多くの人に読まれ、大きな影響を与えています。本で解かれている「人からどう思われるかを気にしなくていい」「嫌われることを恐れず、自分の人生を生きればいい」という考え方に共感し、勇気をもらったという人も多いのではないでしょうか。しかし、書籍で語られる『嫌われる勇気』には、誤解されやすい側面も存在します。
実は『嫌われる勇気』が持つ意味は、立場によって大きく異なることをご存じでしょうか。私はこれまで1,000名を超えるエグゼクティブ・コーチングを行ってきました。その中で『嫌われる勇気』を「嫌われることを恐れない」ことだと履き違え、部下を威圧するような言動を取ってしまうリーダーにも、多く出会ってきました。このような誤解に基づくリーダーシップが原因で、部下の成長を阻害し、組織運営に支障をきたしている例は、残念ながら少なくありません。
本記事では、『嫌われる勇気』にまつわる誤解をテーマに、真のリーダーシップについてお話します。
✍️著者プロフィール
桜庭理奈(さくらば りな)
35CoCreation合同会社CEO (元GEヘルスケアジャパン人事本部長)
GEヘルスケア・ジャパンへ入社後、人事本部長、執行役員を歴任。2020年に35 CoCreation合同会社を設立し、CEOに就任。経営・組織・リーダーシップ開発コーチングを伴走型で支援。一般社団法人日本オントロジカル・コーチング協会代表理事。2023年に株式会社メドレー社外取締役に就任。国際コーチング連盟認定PCCコーチ。
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/rinasakuraba/
誤解された「嫌われる勇気」が招く落とし穴
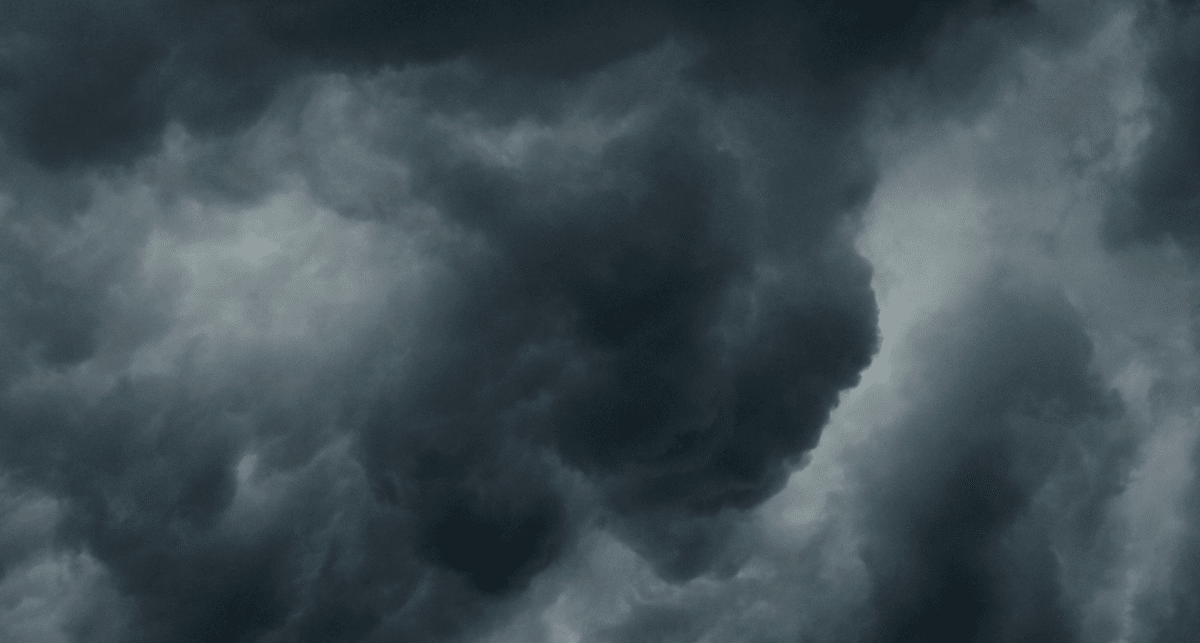
35 CoCreationのコーチングセッションには、部下から嫌われてしまっているリーダーが頻繁に訪れます。中には、嫌われていることを気にしていない様子の人も少なくありません。
その一例が、鈴木さん(仮名)です。
鈴木さんはとあるIT企業で重職を務めており、過去は海外出向を任されるなど、一見順風満帆なキャリアを歩んでいるように見えました。しかし、ある時、絶望的な出来事に見舞われます。
海外出向から帰任した鈴木さんは、閑職に追いやられてしまうのです。実は、鈴木さんはこれまで一緒に働いてきた同僚や部下から嫌われてしまったために、希望していた仕事から外されてしまったのでした。
その原因は、『嫌われる勇気』を誤解した鈴木さんのコミュニケーションにありました。
従来の鈴木さんの仕事の進め方は、強引そのものでした。
自分が「正しい」と思ったら、「やるぞ」と指示を出し、部下に意見を求めることはありません。有無を言わさず、物事を進めていくのです。常に命令口調で、部下がミスをすれば、容赦なく詰めました。
鈴木さんは「嫌われることを恐れない」という考えに基づき、部下に対して以下のような言動を取っていました。
・「部下に嫌われようが、どうでもいい」と、歩み寄る努力をしない
・自分の基準で部下を一方的に評価
・部下が自分と異なる意見をぶつけてこようものなら、「自分の信頼を勝ち取ってから言ってくれる?」と言わんばかりの態度で相手を突き放し、「言うことを聞け」と圧をかける
このようなコミュニケーションを取っていた鈴木さんは、部下から次第に距離を置かれ、孤立。ついには閑職に追いやられるに至ったのです。
客観的に見れば、絵に描いたような「パワハラ上司」に映るかもしれません。しかし私の経験では、鈴木さんのようなケースは決して珍しくないのです。
彼らは人間関係を縦で捉え、「自分より下」の人から嫌われることを厭いません。一方で、「自分より上」と認識した人からの「嫌われることへの恐怖感」は大きく、「『嫌われる勇気』が持てない」と悩みながら、鬱屈した気持ちを抱えていることもしばしば。
そうして抑圧した感情が周囲への重圧となって表れ、組織全体に悪循環を生み出した挙句、自分自身も苦しみを感じるようになってしまうのです。
自分を愛することができないリーダーは、本当に嫌われる
当然ですが、本当に周囲から嫌われてしまったリーダーは、円滑に仕事を進めることも健全な組織を築くこともできません。リーダーがこうした窮地に陥る背景には、『嫌われる勇気』に対する大きな誤解があるのです。
実は『嫌われる勇気』は、立場によってその意味合いが大きく異なります。
若手や部下の立場であれば「嫌われることを恐れない」ことが、上司に対して意見を言いやすい環境を作ったり、生き生きと働くための後押しになったりするでしょう。
しかしリーダーが同じように解釈した場合はどうでしょうか。「嫌われてもいい」と突き進んだ結果、鈴木さんのようなパワハラまがいの言動や部下の信頼を失うことに繋がりかねません。
リーダーにとっての『嫌われる勇気』とは、単に周囲から嫌われることを恐れないことではありません。部下を尊重し、一人ひとりの成長を真摯にサポートする意識を向けながら、時には嫌われる覚悟で相手のために厳しい意見を伝えることが、リーダーに求められる『嫌われる勇気』なのです。
しかしコーチングをしていると、そのことを誤解したリーダーが、実に多いことに気が付きます。そんな彼らの共通点は『嫌われる勇気』の前に持っておくべき『自分を愛する勇気』を持てていないということです。
自己肯定感が高く、評価の軸を自分の中に持っていれば、たとえ一時的に嫌われても、揺るぎない自信で行動できます。他人の意見に怯えることなく、時には厳しい指摘も受け入れ、「貴重なフィードバック」として成長の糧にすることができるのです。
しかし常に自信がなく自己評価も低い彼らは、他人からの評価に依存し、周囲の意見で「自分の持つ正解」が揺らぐことを極端に恐れています。
会社組織においては「上司の評価」に固執するあまり自分を追い込み、時には自分の感情を押し殺してストイックに仕事に向き合います。そうして部下に対しても同じように、必要以上に高い基準をクリアすることを求め、厳しく接してしまうのです。
『自分を愛する勇気』が育っていない理由は人によってさまざまですが、その多くはこれまで生きてきた環境にあります。
特にチームワークや調和を重んじる企業や組織では、周囲に順応することが正とされることも多く、他人に合わせるあまり自分をないがしろにしたり、自分を見失ってしまうケースも見かけます。
鈴木さんの場合は、中学生時代の風紀委員の経験がきっかけで、厳格なルール意識を持つようになっていました。「委員として役割を全うする自分」を先生や周囲に認められたことに快感を覚え、「ルール」を守ることを徹底し、破った者には厳しく処罰するべきだと考えるようになったのです。しかし、その「ルール」へのこだわりは、社会人になり部下を持った今、部下への過剰な要求につながり、パワハラとみなされる言動を生み出していました。
コーチングセッションを通して、鈴木さんはこだわっていた「根っこの感情」に気付き、自分と向き合い始めました。対話の中でポツリ、ポツリと出てきた言葉は、「こんな自分になりたいわけではなかった」「これまで我慢してきた」「閑職に追いやられて悲しかった」というありのままの素直な気持ち。
それは「愛を感じないことへの怒り」にも感じられました。
自分を愛し、自分自身を認めることが「嫌われない勇気」の出発点
リーダーが正しく『嫌われる勇気』を持つためには、まず自分自身を軸に生きるための土台を築くことが不可欠です。
しかし、長年自己肯定感を育む機会に恵まれなかった大人にとって、自分自身を認めることは容易ではありません。そこでコーチングでは、無自覚に設けている「自分と他人への評価基準」を丁寧に自覚していくことから始めます。
初めに行うのは「信条」の棚卸し。これまでの人生の中で培ってきた自分の「信条」を、対話の中から見出す作業です。無意識に繰り返されるキーワードから、「怒りの感情に繋がっている言動は何か」を丁寧にひも解き、「大切にしていることは何か」を探り当てていきます。
そして露わになった「信条」の見直しを、一緒に行います。時代や環境、自分の立場や年齢は、常に変化しています。大切に守ってきた信条が、本当に今の自分にとって重要なのか、合っているのかを、一度立ち止まって考えてみるのです。
例えばあるリーダーは「人の10倍働かないと信頼されない」という信条を掲げていました。
信条を厳格に守り、部下にも同じように守ることを求めていたため、本人も周りも、次第に苦しさを感じ始めていたのです。そんな彼に「本当に人の10倍働かないと信頼されないのか?その根拠はどこにあるのか?」と自問自答を促してみたのです。
対話を重ねる中で導き出されたのは「まずは相手の話をよく聞くことが信頼につながるのではないか」という「新たな信条」でした。そこで少しずつ職場で実践してもらうと、徐々に「これまでの信条は手放しても大丈夫」だという確信を持てるようになっていったのです。
成長の中で不要になった信条を手放し、今の自分に合った新しい信条を構築することは、自分自身に正当な評価を与えるためにも不可欠な作業です。季節に応じて衣替えをするように、置かれた環境や立場が変わったときには、自分自身がどうありたいかを見つめ直すことを心がけてほしいと思います。
「嫌われる勇気」を持つリーダーは、真のリーダーシップの本質を知る

『嫌われる勇気』を正しく理解したリーダーが最終的に目指すべきは、『他者を愛する勇気』を持つことです。これは「嫌われるか嫌われないか」という自分中心の思考から、「相手のために嫌われる覚悟を持つ」という相手中心の思考へと意識をシフトさせることを意味します。
真のリーダーは、チームの中で「自分がどう存在すればいいのか」を常に考え、自分のためではなくチームのために行動します。時に自分が間違っていることを認め、チーム一丸となって取り組むことも、真のリーダーシップに必要な勇気です。
リーダーにとって『嫌われる勇気』とは、自分の意見を一方的に押し通すことではありません。むしろ、異なる意見を持つ人にも耳を傾け、対話を通して互いを理解し、共に成長していくことを重視します。共通のゴールを掲げ、互いに尊重し合い、プロセスを共有することで、メンバー同士がより自律的に行動するようになり、高い生産性と創造性を発揮するチームが築かれていくのです。
つまり、真のリーダーは『嫌われる勇気』を持ちながらも、同時に「嫌われない」存在でもあります。相手を尊重し、信頼関係を築くことが、真のリーダーシップの本質であることを理解し、チームを成功へと導くのです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。真のリーダーが持つべき本当の『嫌われる勇気」の考え方が少しでも皆さんのチームビルディングのお役に立つことができれば、とても嬉しいです。
今後も私のコーチングセッションの体験談やコーチングのテクニックをお伝えすることで、みなさんが組織のリーダーとして活躍するための参考になればと思っています。不定期にはなりますが、次回の投稿もぜひお楽しみに。
【35 CoCreation合同会社】
35 Co Creation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社は、「ヒトの心・身・信の3つの領域の真を統合することを通して、リーダーシップの進化を大胆に促進し、地球を次世代へ手渡していくリーダー人材を開発する」をミッションに掲げ、日本初上陸オントロジカル・コーチングのアプローチに基づいた組織開発、次世代のリーダーシップ開発、人材育成、組織風土改善を支援するコーチング事業を運営しています。
オントロジカル・コーチングは、自分自身の価値観・信条・倫理観、思考傾向など自身の在り方を理解することで行動習慣を本質的に変える、ヒト起点の改革を支援します。この改革を通じて、組織における価値創造、人材育成、組織改革を実現します。
公式HP:https://35cocreation.com/
【桜庭 理奈(さくらば りな)】
35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社 CEO
元GEヘルスケア・ジャパン株式会社アジアパシフィック地域統括のHRビジネスパートナーとしてGEヘルスケア・ジャパンへ入社後、人事本部長、執行役員を歴任。2020年に35CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社を設立し、多様な業態や成長ステージにある企業で人事部長不在の企業間で、シェアドCHROサービスを開発提供し、経営・組織・リーダーシップ開発コーチング、アドバイザリー活動を伴走型で支援。経営者や人事担当者向けの執筆コラムも多数出版。国際コーチング連盟認定PCCコーチ。一般社団法人日本オントロジカル・コーチング協会 代表理事。1on1コーチ、チーム・コーチ、ヘルス・ウェルネスコーチとして活躍中。愛知県出身。
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/rinasakuraba/
