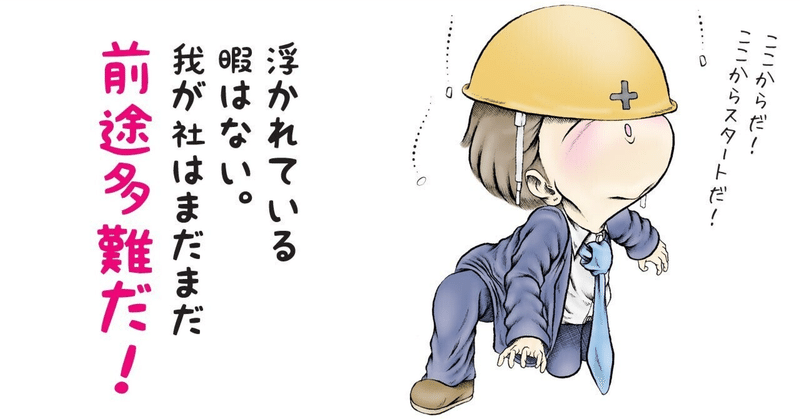
キャリアコンサルタントの選び方 ーその2・社内キャリアコンサルタントー キャリアの銀行 r
キャリアの銀行 rが考える、キャリアコンサルタントの選び方 ーその1ー の続編です。キャリアの相談先として、会社の上司先輩・知人友人ではなく、キャリアコンサルタントを選ぶ方が多くなってきています。
普段は馴染みのない職種なので、キャリアコンサルタントといってもよくわからない方が多いのが事実です。適切なキャリアコンサルタントの選び方を知らなかったために、せっかく費やしたお金と時間が無駄になってしまうケースが少なくありません。
お客様だけはなく、キャリアコンサルタントにとってもイメージが悪くなり、お互い不幸になります。
そこで、「キャリアコンサルタントの選び方」と題し、国家資格キャリアコンサルタントである私が、何回かに分けて解説しています。できるだけ客観的に書きます。皆さんのお役に立つことと、キャリアコンサルタントが思う存分実力を発揮できる世の中になることを願っています。
5つのパターンごとに補足する、それぞれのキャリアコンサルタントが抱える事情
前回の記事では、キャリアコンサルタントが働いている場所ごとに特徴を述べました。キャリアコンサルタントの選び方の参考情報となります。
1.企業の人事で働いているキャリアコンサルタント
2.大学で働いているキャリアコンサルタント
3.公共機関で働いているキャリアコンサルタント
4.人材紹介会社で働いているキャリアコンサルタント
5.独立して個人で働いているキャリアコンサルタント
https://note.com/10da/n/nbac9adb24c54
今回は、それぞれのパターンごとにそれぞれのキャリアコンサルタントが抱える事情を補足します。これらを知ることで、同じ「国家資格キャリアコンサルタント」でも、働いている場所や立場によって、まったく違う角度からのキャリア支援、相談業務になることを感じてもらえると嬉しいです。
企業の人事で働いているキャリアコンサルタント
企業の人事担当部署で働いているキャリアコンサルタントが、国家資格を取得した経緯は、大きく分けて2つあります。キャリアコンサルタントの選び方の参考情報になります。今後、社内で無料で相談するか、外部で相談するかなどの検討時に役立ちます。
①会社の方針で国家資格キャリアコンサルタントを取得した人
従業員が自分らしく生き生きと働ける環境を整備するために、社内キャリアコンサルタントを養成する会社は少なくはありません。大きな会社ですと、すでに上司や先輩が取得していて、自分は国家資格を取得したら、既に形ができているフローでキャリアコンサルティングに取り組むことができるといったケースが多いです。
一方で、小さな会社や、社内キャリアコンサルティングの導入を決定したばかりの会社だと、「初めの1人」となるので、国家資格取得後に、実務経験もないまま、カウンセリング業務だけではなく、業務設計や制度設計から取り組むことことが多々あります。
前者のケースでは、安定したキャリアコンサルティングを受けられる確率は高まりますし、同僚からも情報や感想を得ることができますので、自分に合うか否かは判断しやすいかと思います。
後者のケースでは、社内キャリアコンサルタントの頑張り次第になるので、なんとも言えないと思います。
キャリアコンサルティングやカウンセリングを受けられる環境整備は、従業員にとってはメリットになることなので、ぜひ応援して欲しいものです。
②自らの意思で国家資格キャリアコンサルタントを取得し、キャリアコンサルタント業務を人事担当部署に導入した人
社員想いの強い方、責任感の強い方が多いように思います。資格取得後には、会社に働きかけ、キャリア・カウンセリングの仕組みを社内に取り入れる活動をします。この場合もまた、実務経験もないまま、会社へのカウンセリング業務だけではなく、業務設計や制度設計から取り組むことになります。
企業の人事で働いているキャリアコンサルタントが直面する様々な悩みや課題の例
参考までに、社内キャリアコンサルタントが直面している課題などを挙げておきます。キャリアコンサルタントの選び方の参考情報になります。今後、社内で無料で相談するか、外部で相談するかなどの検討時に役立ちます。
社員のニーズと組織の要求のバランス
企業の人事部門で働くキャリアコンサルタントは、従業員のキャリアのニーズや希望と、組織の要求やビジネス戦略をうまくバランスさせることが求められます。これは、個々の従業員の成長と組織の利益の両立を目指すため、難しい課題となることがあります。
社員のモチベーション向上
従業員が仕事に対するモチベーションを持続的に向上させることが重要ですが、これは容易なことではありません。キャリアコンサルタントは、従業員のスキルや適性に合ったキャリアパスを見つけ、適切なキャリア開発プログラムや研修を提供することで、社員のモチベーションを向上させることが求められます。
多様な働き方への対応
近年、働き方の多様化が進んでおり、企業の人事部門もこれに対応しなければなりません。テレワークやフレックスタイム、パートタイムや契約社員など、多様な働き方に対応したキャリア開発や評価制度の構築が求められることがあります。
人材不足や高い離職率への対策
労働人口の減少やスキル不足による人材不足が深刻化している中、人事部門では優秀な人材の確保や定着に苦労することがあります。キャリアコンサルタントは、社員のキャリアサポートや離職防止策を考えるだけでなく、新たな人材の獲得や育成にも取り組む必要があります。
以上のような課題に取り組みながらなので、純粋に個人のキャリア支援のことだけを考えた内容にはなりにくいことを感じていただければよろしいかと思います。
次回からは、補足の続きをしていきたいと思います。そして、キャリアコンサルタントの選び方を知りたい方にとって、最もわかりにくいであろう、「5.独立して個人で働いているキャリアコンサルタント」について展開していければと思っています。
*キャリアコンサルタント全てに調査して得た情報ではないことを、予めご了承ください。私が、国家資格を取得するための養成講座、国家資格を更新するための更新講座、キャリアコンサルタントが集まるコミュニティー(複数)で、この3年間実際に話を伺ってきた内容を元にしています。
キャリアの銀行Ⓡでは、キャリア支援/相談にナラティブ・アプローチだけでなく自分史制作の支援も取り入れることが可能です。また、キャリアコンサルティングを広めるために、キャリアコンサルタントの選び方についての相談も承っています。
詳細はお問い合わせください。
キャリアの銀行Ⓡ https://gincco.net/
お問い合わせフォーム https://gincco.net/contact/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
