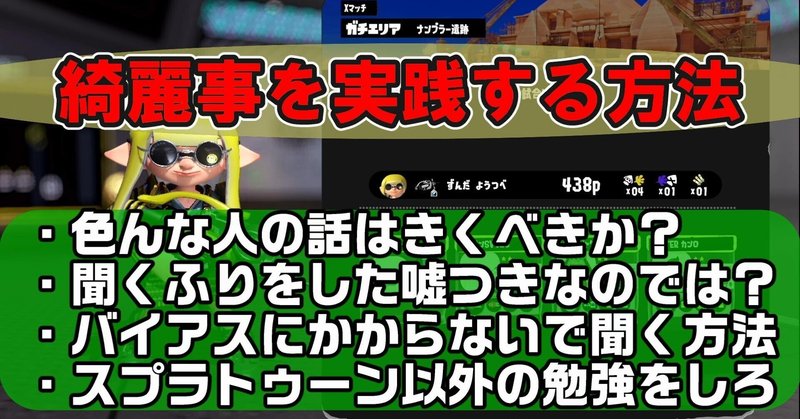
ブロックしないで自分とは違う意見をみてみる、とはどういうことか?ーTwitter、本、趣味(スプラトゥーン)などー
種々の意見を見聞きして客観的な自分がつくられる?
一つにこだわるとこだわりができて狭隘な人間が誕生する説
一定の分野の本を読んでいると、―政治学とか経済学とか文学とか―いつのまにか自分の好みの本ばかり読んでしまうと言うことがある。
この好みというのは本人が納得しやすい意見、つまり自分と同意見の本ばかりをよんでしまうという意味である。
同意見の本を読むときは理解するための苦労がいらない。自分が思っていることや考えていることが書いてあるので平坦な道を歩き続けているのと変わらないのである。
ここに落とし穴があることはいうまでもない。
所謂、エコーチェンバーというやつがネットでなくとも起こる瞬間である。
まあ、ここまでは誰もが一度はきいたことのある話だと思う。
こんなことにならないように色んな人の話をきいてみましょう。
という小学校でも習ってそうな忠告や訓戒の類いである。
色んな人の考え、をきいたところで何か変わりますか?
だが、私はこの《色んな人の考え》に触れるというのはだいぶ難しい事だと思っている。
特に自分がそれに通じれば通じるほど、全く別の見解を受け入れることは容易ではなくなる。
人はその分野に没入し、時間が経つと定見を得る。
その定見があるから、むしろその分野に詳しいとまでいえる。
定見がないというのは不勉強ということだ。
この定見が固定観念(ステレオタイプ)の謂いになることはいうまでもない。
定見=勉強している=固定観念(ステレオタイプ)
むろん、べんきょうしている以上、それは観念というよりも概念(客観的な知識)なのではないかと思われるかもしれない。
しかし、どの本を読んでいても筆者毎に細かく考えは違っている。
どこを強調するか、それについて良いと思っているか悪いと思っているか。
その人本人の好みが反映され、そしてその人の癖や偏見につながっていく。
様々なる意匠ー分野内で我々が知らない対立が存在するー
上の記事でかかれているように同じ趣味であっても、ミクロな違いがある。
【鉱物】 鉱物マニアにも購入派×採集派、観賞派×研究派、原石派×研磨派など、いくつかの系統があるらしい。 「私は原石派。自然のままの美しさに神秘を感じるし、悠久の時間にロマンを感じる。研磨したのは美しいと思いますが、鉱物じゃなくアクセサリーに見えてしまう」と言うAさん(34歳・看護師)によれば、一番大きな対立軸は現実派×スピリチュアル派とか。「『この石を肌身離さず身に着けて良縁に恵まれました』みたいなことを言うのがスピリチュアル派。本人が信じるのはいいけど、少しでも否定的なことを言われると激しく反論したりするのがね……」
こんなのどうでもいいではないかと思ってしまうが、鉱物オタクの当人等にとっては至って真面目な見解の相違である。
話をきくふりをしているだけで、真に聞く気がない人間は、お為ごかしの欺瞞家である
巷間でいわれるような「色んな人の話をききましょう」を私があまり好きでない理由は、
結局、お前、本当にそう思ってるのか?、と疑っているからである。
たとえば、Twitter上で気にくわない情報や意見を発している人間がいたとする。
あなたは考える。
「こうした人の意見も貴重だし、大事だし、何かにつながる」
だが、ほんとうにそうか?
その人のことをミュートやブロックしなければ、あなたはその人の意見を何ら先入観なく、受け入れるのだろうか。
その準備を本当にしているのか?
自分の正しさのために相手を受け入れているふりをしているだけでは?
私はそんなことはないとおもう。
むしろ、からかうための材料としてその人をみるだけではないだろうか。
人間は嫌いだからといってその人をみないわけではない。からかう対象や侮蔑する対象としてその人をフォローし、観察する。
こんなことをやっている人などいくらでもいるだろう。
あるいは自分の正しさを確認するために嫌いな人間をみているというのもある。
そいつが書き込む度に「また、間違えたこといってる。そして、それに気づいた自分は正しいし、賢い」というわけだ。
全く別のことを勉強しろー固定観念から離れる方法ー
これがずっと続くだけであり、何をどうやっていても自分の固定観念はかわりそうにない。
じゃあ、どうすればいいか?
私は全く知らない分野の話や本から栄養摂取することをお勧めしたい。
先の記事中にかいてある様々な対立をみてみる。
採集派と育成派 購入派×採集派、観賞派×研究派、原石派×研磨派 日本機派、ドイツ機派、ジェット機派、プロペラ機派
こういった対立から何がわかるだろうか?
私は殆ど分からない。
ここにどんな意味が含まれており、どんな違いがあるのか。
しかし分からないから、相手の話をすなおにきけるのである。
何ら固定観念がないからこそ。
どっちかの派閥は嘘をつきやすいとか、スピリチュアルだから宗教っぽくてイヤだとか、そういうのは何もない。
そしてこれらの他分野における対立を学んで、自分の分野にかえってきたとき、初めて「あいつの意見、嫌いだったけどなんとなくわかるかも」ということになりやすい。
おそらく抽象的なパターンが人の認識で決まっていて、他分野を通過することで客観的に冷静に把握しやすくなるのだろう。
また他分野へいっている間に、自身の分野への強熱が冷めるということもあって、諸々の対立がバカたらしくみえるのもあるかもしれない。
畢竟、適度に自分の専門から離れた方がいいということだ。
陰謀論にハマりやすい人、マンハイムのいう人間の限界
秦 正樹『陰謀論』によると、陰謀にハマりやすい人間は実は
「勉強している人間」だという。
知識欲がへたにあるとインターネットなで一人でひたすら調べ続ける。そして同士をみつけ、彼らと一緒の場で情報を得、それを発信する。
そうこうしているうちに陰謀論者になってしまう。
そういう筋書きである。
これはハンガリー出身の社会学者、カール・マンハイムも「イデオロギーに染まりやすいのは知識人」といっていた記憶がある。
人には限界がある。その時代のその環境ごとの、これを
「存在の被拘束性」という。
※水野邦彦「縹渺たる存在被拘束性」でこの概念のあやふやさが問題視されているといわれている。
ただし、マンハイムは自由に勉強することで自身の制約から解放され、全体を見渡せるような人間になるという。
つまり、執着しないで離れろ、という一事に尽きる。
まとめ・欺瞞的にならないための勉強法
私ズンダの考えとしては、同分野の、たとえば経済学であれば経済学の中で色んな人の考えをきくよりも、全く別分野の話を勉強することで固定観念から解放されると思っている。
私はスプラトゥーンというゲームをいつもやったり、あるいはそれについて語ることが多いので名前を出すが、
スプラトゥーンにおける様々の対立を俯瞰するためには、スプラ以外の分野、昆虫でも鉱物でも服飾でもいいが、そういったものを学んだ方が存外、「色んな意見を斟酌できる人」になれるのではないだろうかと思っていたりする。
スプラについて語るには、実はスプラ以外の分野を学んだ方が豊かにはなせるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
