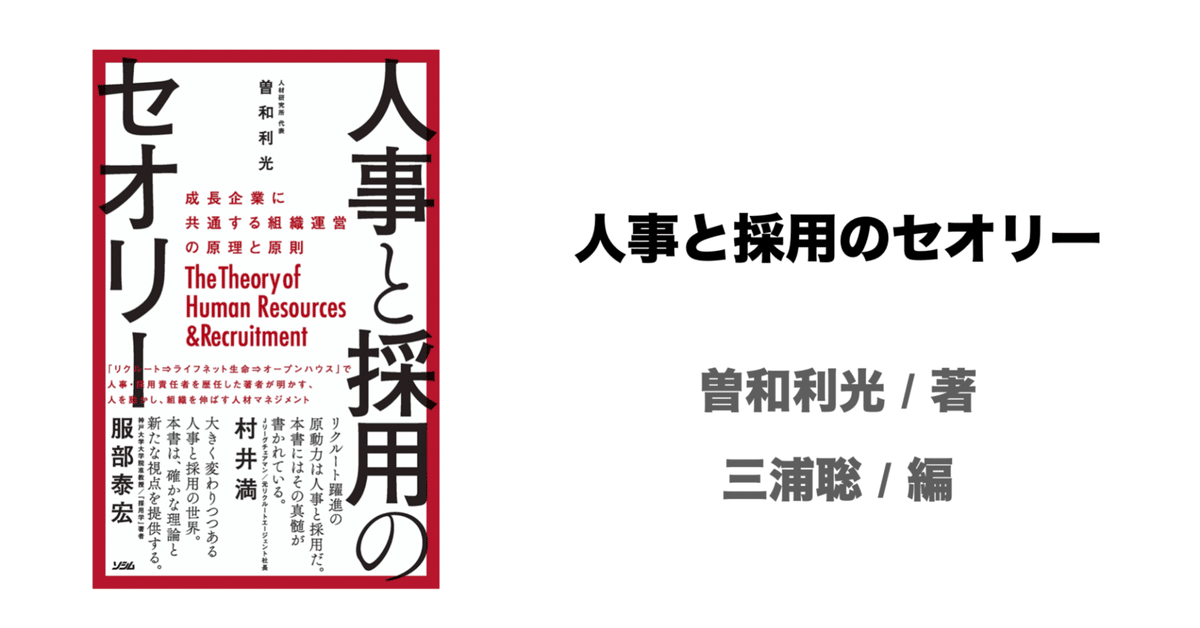
『人事と採用のセオリー』を読んで学んだこと①
はじめに
ご覧いただきありがとうございます!
株式会社M&Aクラウドで人事をしている仙波です。
本記事は私の読書感想文的な、学びをシェアする記事であり、網羅的な本の要約記事ではありませんので、その点あらかじめご了承下さい。
本書は「part1 人事のセオリー」と「part2 採用のセオリー」という二部構成となっているため、本記事では「part1 人事のセオリー」の第1~5章の内容を記載いたします。「part2 採用のセオリー」は後日別の記事で投稿します。
今後も定期的に本の感想や日々の学びをシェアしていく予定ですので、もしよろしければ「スキ」と「フォロー」をしていただければ嬉しいです!
第1章:そもそも人事の役割とは?

人事の機能は一般に、「採用」「育成」「配置」「評価」「報酬」「代謝」の6つに分けられます。このうち、企業外部に必要な人材を求めて社内に採り入れる採用と、企業内部の人材を業務で必要な特性を持つ人材に変える育成は、まとめて「調達」と呼ばれることもあります。
人事がこれら6つの機能を担う上で重要になるのが「人事の一貫性」です。人事に一貫性がないと、各機能がバラバラに最適化してしまい、全体として効果を打ち消しあって、パフォーマンスが上がらないからです。
では、どこに一貫性の「軸」を置けばいいでしょうか?
理想は、もちろん「事業」です。「組織は戦略に従う」の言葉通り、事業戦略が最もうまく遂行できるように一貫性の軸を置くのです。
図1-3に、人事の一貫性の軸を決める上で考慮するべきポイントを、企業のタイプごとに示しました。ここでは、企業のタイプを「安定・成熟事業型」と「変革・新規事業型」の2つに分けています。

上記のように、人事の一貫性は重要ですが、その実現は容易ではありません。その一つの原因が、近年の事業環境、すなわち経済状況などのマクロ環境、競合企業や消費者動向などのミクロ環境の激しい変化です。
しばしば「Volatility=変動」「Uncertainty=不確実」「Complexity=複雑」「Ambiguity=曖昧」の頭文字をつなぎ合わせた「VUCA」という言葉で表現されます。現在の事業環境はきわめてVUCAであり、当たり前のように急激に変化するのです。
事業環境が変われば、求められる事業戦略も変わります。そして、事業戦略に合わせて組織のあり方も変化させなくてはなりません。しかし難しいのは、組織には「慣性」が存在するため、変化が容易ではないことです。
では、一貫性の軸をどこに置くべきでしょう。一概には言えませんが、筆者は、自社の「容易に変わらないもの」を軸にすることを勧めています。
ある会社では、カリスマ経営トップの価値観や考え方かもしれません。あるいは、価値観や企業風土や事業モデルなども考えられます。こうした変わらないものに合わせて人事の方針を立てて、その一貫性を損なわないように事業戦略に合わせるのです。
逆に言えば、人事方針を立てるにあたっては、「容易に変わらないものは何か?」を徹底的に考える必要があります。それを認識することで、はじめて人事の一貫性を継続的に実現でき、最終的には強い組織を構築できるのです。
人材ポートフォリオと人材フロー
ここまで述べてきた人事の一貫性を実現する手段であり、人事と採用のコアとなるのが、「人材ポートフォリオ」と「人材フロー」です。
人材ポートフォリオとは、組織に必要となる人のタイプ・レベルと構成比。
人材フローとは、人材ポートフォリオの実現方針。
人事は通常、会社の状況やステージ、企業風土や事業モデルなどに応じて、必要な人材を検討し、人材ポートフォリオを決めます。人材ポートフォリオを決める軸は「事業」「職種」「階層」など人材の特性を左右する軸であれば何でも構いません。ただし、人材ポートフォリオの軸を何にするかは、人事の一貫性を実現する上で極めて重要です。
下記の「チーム↔︎個人」「新しい価値↔︎既存の手法」という2つのセグメント軸はかなり普遍性が高いようです。(参考程度に)

自社に合った人材ポートフォリオを作成し、セグメントごとの理想とする構成比を決めたら、次に自社内に各セグメントの人材がどのくらい在籍しているかを概算します。「現実」と「理想」のギャップを把握した上で、それを埋める施策を練るのです。この理想と現実を埋める施策が「人材フロー=組織における人の流れ」です。人材フローでは、新しい人をどのチャネルからどのくらい入れ(採用)、どのように組織内で動かし(配置)、どのようにどのくらい出すのか(代謝)を決めます。


以上のように、人材ポートフォリオと人材フローは、人事の一貫性を実現する上で最も重要な考え方となります。逆に言えば、人材ポートフォリオと人材フローを意識することなく、「採用」「育成」「配置」「評価」「報酬」「代謝」の方針をそれぞれ別々に立てれば、人事の一貫性は失われてしまいます。すべての人事担当者は、自社の人材ポートフォリオと人材フローをきちんと認識した上で、業務にあたる必要があるのです。
第2章:組織の成長に応じて、人事の考え方は変わる
企業が成長することで、売上だけでなく、組織の構成員が増えます。そして人数の増加に伴って、企業は人事の方針を変えることが求められます。その理由は、人の「認知限界」に由来します。認知限界とは、人の認知能力や情報処理能力の限界です。
人間はこの認知限界ゆえに、世界の複雑性を縮減する必要がある。そのための社会的装置が「組織」である。組織という階層構造を形成することで、意思決定の複雑さをいくつかのサブアセンブリに分解(≒モジュール化)することができる。それによって、個々人では実現できない高度な意思決定を行う。
世の中には様々な研究がありますが、イギリスの経営学者アーウィックによれば、一般的な事務職では1人の上司が直接管理できる人数は5~7人程度と言われています。他の様々な研究でも5~7人が最も効率的なチームであると結論付けています。つまり、一般的な人がマネジメントできる人数は6人前後と言ってよいでしょう。そのため、組織の構成員の増加に伴い、組織は階層化し、マネジメントの質が変化していきます。
経営学者グライナーが提唱する「組織のライフサイクル」によれば、組織の成長段階は5つに分けられます。グライナーモデルを解釈して、組織の成長段階をまとめたのが、図2-1です。

本書では、各Stepごとにどのような問題が発生し、それに対応するために人事の方針をどのように変えるべきか解説されていますが、本記事では割愛します。組織の成長に伴う課題というものは多くの企業で共通するものがあるため、非常に有効なモデルとなると思います。
一方で、グライナーモデルはあくまでも一つの理論であり、様々な制約条件のある現実の人事マネジメントにそのまま適用することはできません。多くの場合、一つの企業内にStep2~4の組織が混在しているためです。
特に、「ステップアップしないままでも成長できる」点には、注意が必要です。業種によっては、Step2~4のまま巨大企業になることもあります。また、「文化でマネジメント」ですぐに思いつくGoogleも、確かに中核部門はStep5ですが、末端部門はStep2~4です。これは、その組織の業務がその段階に適していて、そこに止まる方がマネジメントしやすいからです。
つまり、グライナーモデルは、あくまでも組織の成長に応じて人事の方針を変えていく上でのヒントなのです。その限界を理解した上で、グライナーモデルを活用すれば、人事の方針を変えていくときに役立つでしょう。
第3章:採用と代謝は一つの流れで考える
人材ポートフォリオを実現するには、採用と代謝をセットで考える必要があります。なぜでしょうか。
ある企業の理想的な人材フローが「毎年5%が入社し、5%が退職する」であるとしましょう。では、その企業の構成員が「定年まで居続ける」人ばかりならどうなるでしょうか。退職率が5%に満たない水準で推移し続けた結果、どこかのタイミングでリストラが必要になるのです。
組織に残りたいと思っている人たちを無理やり切れば、当然ながら組織は疲弊し、残った人たちのモチベーションも落ちます。つまり、ビジネス活動に対峙するエネルギーが失われるのです。「組織は戦略に従う」と言われる通り、そもそも人事は事業戦略を実現させるための手段であるにも関わらず、これでは本末転倒となります。
一方で、採用と退職をセットで考えるとどうでしょう。
例えば、「キャリア自律」した人々を採用すれば、社員の一部はキャリアの節目で「自然に」会社を退出していきます。それでも「5%」という目標退出率を実現できなければ、退職率をアップさせる施策を実施してもよいでしょう。自然な形で社員の退職を促すのです。
(例)人材輩出企業と呼ばれるリクルートの人事制度や人事施策
優秀なスター社員が退職することは、短期的には損失です。しかし、中にいる次世代のスター社員には「良いポジションが空く」という願ってもみないチャンスとなり、持てる力を発揮する機会が与えられます。
退職をネガティブに捉えすぎずに、組織の新陳代謝をきちんと計画的に行っていくことで、会社にとっても社員にとっても良い循環が生まれるのです。
退職率のマネジメントでは、退職率を常にモニタリングしながら、目標よりも上振れすれば退職率を下げる施策(=「求心力」施策)を、下振れすれば退職率を上げる施策(=「遠心力」施策)を実施します。

日本の企業には「退職率を管理する」という表現に嫌悪感を抱く方も少なくありません。しかし、ピラミッドは上に行くほど必要人数が減るのは定めです。退職率を管理できなければ、「船頭多くして、船、山に登る」で全員沈没することにもなりかねません。
人事担当者は、社員全員が定年まで残れないという事実から目を背けることなく、彼らの出口に対しても配慮するべきです。すなわち、ある程度自然な遠心力をつねに利かせて、活躍できる場を社外に求めやすい風土を作ることこそが、本当の優しさなのではないでしょうか。そしてこれこそは退職率のマネジメントなのです。
第4章:配置によって人を育成する
組織にとって、短期的に最も成果を上げやすいのは「今のまま=現状維持」です。しかし、中長期で見ると、新しい環境に適応し、新しい能力や考え方を身につける人が増えると、社員が成長し、ひいては組織全体の成長につながります。
また、組織は「淀めば濁るもの」です。川の流れと同様に、組織にも流れ(=人材フロー)が重要です。では、なぜ、濁った組織は死ぬのでしょうか。
一番大きな理由は、構成員の「やる気」を奪うからです。どんなに優秀な人でも長年同じ仕事をすれば、マンネリ化して成長が止まります。創造性が失われ、最高のパフォーマンスを発揮することは難しくなり、成果を出せなくなります。
また、こうした状況は、その下で席が空くのを待っている人のやる気も奪います。彼らは、仕事に飽きてマンネリ化した上司を見上げて、「そんなことなら、自分にやらせてほしい」と努力が報われない状況を嘆きます。
そんな状態が長く続けば、彼らは「学習性無力感」に陥ります。このように「組織が濁る=人材フローが停滞する」ことは、成長の停滞と組織の不活性化につながるのです。
組織が濁らないようにするには、まず「人材の内部流動性を高める」必要があります。つまり、人材を異動させたり、昇格/降格させたりするのです。
そして、その異動・配置の際に最も重要なのは、「配置される人と配置先の構成員・チームとの相性」です。
プログラミングの生産性に関する、ある研究によれば、パーソナリティの相性を考慮しないチームは、理論生産値を大きく下回る業績しか出せませんでした。一方、パーソナリティの相性をきちんと考慮したチームは、いわゆる「シナジー効果=相乗効果」を起こして、理論生産値を超える成果を上げました。
では、人間関係における「相性がいい」とはどういうことでしょうか。
実は相性の良さには、2種類あります。一つは「同質関係」、もう一つは「補完関係」です。簡単にまとめると、同質関係はコミュニケーションコストが低く、友好関係が築きやすい一方で、慣れるとマンネリ化して生産性低下を招きやすいです。補完関係は互いに異質なため、理解し合うまで少し時間がかかりますが、その段階を乗り越えられれば、互いに刺激を感じてチームの生産性が高まると言われています。
もちろんどちらにもメリット・デメリットがあるため、どちらを選ぶかは、解決すべき組織の課題などに応じて判断すると良いでしょう。
また、こうした異動・配置を機能させ、社員を育成していくためには、現場だけ、人事だけでは上手くいきません。「現場での育成を組織全体で担う」という意識が重要になってきます。
現場の上司は育成以外にも成果への責任、多岐にわたる業務を持っているため、よほどのスーパーマンでない限り、部下育成に十分なパワーを割くことはできません。人事担当者は上司一人に育成を任せ切ることなく、「会社全体で育成する」という考え方を浸透させなくてはなりません。
(例)メンター制度
第5章:評価と報酬では納得感を担保する
なぜ企業は評価と報酬に関する緻密なルールを決めるのでしょうか?
理由は簡単です。企業が儲けた利益を皆で分けなければならないからです。つまり企業は、社員からなるべく不満が出ないように、評価・報酬に関するルールを決めなくてはなりません。そしてそれは、当然、人事の仕事となります。
ところが、社員を納得させられる評価や報酬の設計は簡単ではありません。その理由は、評価や報酬とはいわゆる「外発的動機付け」であることに起因します。
内発的動機付けは一般に、効果が長期的に渡る一方、外発的動機付けは短期的には大きな効果があっても、徐々に効果が薄れます。しかも、外発的動機付けは内発的動機付けを阻害します。
このように、外発的動機付けである評価と報酬を全面に出せば、効果が長続きしないだけでなく、社員の内発的動機付けを阻害しかねないのです。
そのため、評価と報酬とは、「あ、そう言えば、うちの評価や報酬のルールはこんなだったな」と社員がたまに気付く「空気」のような存在であるくらいがちょうどいいいのではないでしょうか。「不満を持たれないくらいの納得度を担保する」ことを目標にしてもいいでしょう。それくらい評価・報酬制度の設計は難しいのです。
評価と報酬のルールを決めるのは、理想を実現する行為ではなく、不完全であることを承知の上で、最大多数の最大幸福を探る行為なのです。
本書では、評価・報酬制度の設計で何に注意すべきか、様々な制度のメリットデメリットなどを具体的に説明されています。本記事では割愛させていただきますが、制度設計に関わる仕事をされている方には一読の価値があるかと思います。
まとめ
今回は、『人事と採用のセオリー』の「part1 人事のセオリー」についてまとめさせていただきましたが、各章の内容がとても充実しており、全くまとまっていない分量になってしまいました。
しかし、筆者の主張は「人事・採用には原理原則がある」と一貫しており、小手先のテクニックや、他社の成功事例を部分的に取り入れても意味がないということを学びました。
また、自分自身もこのように原理原則を学び、人事に関する勉強をするだけでなく、きちんと自社に向き合い、自社の事業と組織をより良くしていくために行動していく必要性を感じました。頑張ります!
「part2 採用のセオリー」は後日別の記事で投稿しますので、是非また読んでいただけますと幸いです!
今後も定期的に本の感想や日々の学びをシェアしていく予定ですので、もしよろしければ「スキ」と「フォロー」をしていただければ嬉しいです!!
よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
