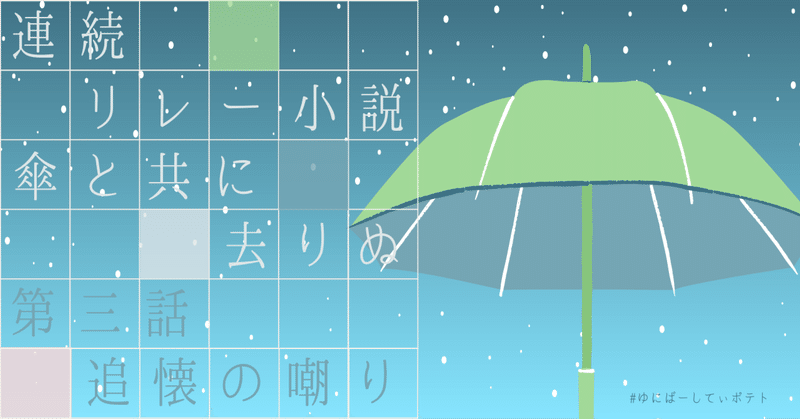
【小説】傘と共に去りぬ 第3話 追懐の嘲り【毎月20日更新!】
第2話はこちらから▼
この家には、後悔の断片が落ちている。
持ち主はわからないけれど、たぶん、もう顔も思い出せない彼ではないのだろう。それだけは確かだ。残念なことに。
「これ、誰の傘?」
答えが欲しかったわけではなかった。
しかし、律儀な母が「蒼のよ」と何でもないふうに、俺の呼吸を会話へとすり替える。
弟の名前が耳に届いたのが不快で、同時に、それを恥じない自分をしんどく感じた。喉の奥がふるふると揺れて、何だか哀れに思えてくる。もちろん、俺が、ではなく、「何でもないふう」な母にだ。
「先月、一瞬だけ通り雨が来た時に買ったって」
「へえ」
「あの子、しょっちゅう傘を持ってくの忘れるから。……この傘がどうかした?」
「いや、こんな……こんなんついてたっけ」
「どれ?」
「青いやつ。星の」
「付いてたんじゃない?」
何の変哲もないビニール傘には、青い丸と星のイラストがプリントされたチャームが付いている。「いや、」ありえんでしょ、と突っ込みを入れるのはあまりに可哀そうで、結局は会話を「いってきます」という呼吸にすり替えた。
可哀そうなのは俺、ではなく。
母と、不登校中の弟だ。もちろん。
4月/藤倉湊
自分の名前が好きな人間は、果たして多数派だろうか。
世間には、「名前は親から貰う最初のプレゼント」「人から贈り物を貰ったら感謝しなさい」だなんて迷惑な法律がはびこっていて、過半数は圧倒的勝者で、ともすれば俺たち兄弟は有無を言わさず負け組に分類されるのだった。義務教育の現場では、もう少し「ありがた迷惑」という言葉の意味を重点的に学ばせるべきだ。
「みなと」と「あおい」という、対になってるんだかなってないんだかよくわからない俺たち兄弟は、繊細で美しいこの名前と、それを命じられたこの平々凡々な顔と、三人四脚で生きていく責任がある。ありがた迷惑で涙が出るね。
こういう場合はどっちかがイケメンで、片方がもう一人に劣等感を抱いていたりするものだが、俺たち兄弟は顔から感性までよく似ていた。本当に泣ける。
そんなことを考えては息を吐き、背筋を伸ばしたり、イスに座りなおしたり、としているうちに再び同じことを考えはじめ、としているうちに講義は終わっていた。「自分の考え事に集中する」という切り口から鑑みると、非常に有意義な講義であったと言えるだろう。
「この講義落としたわ」
「まだ一回目なんだけど」
「単位は死んだ」
「フリードリヒに謝れよ君は」
「ファーストネームで呼ぶくらい親しいなら代わりに謝っといてくれ」
「フリードリヒ・ニーチェによろしく」とぼやきながら机に突っ伏す。
隣で真面目にノートをとっていたらしい篠崎が、参考書を片付けているのが音だけでわかる。彼はいつも、資料のふちを執拗なまでに整えてからバッグにしまうのだ。神経質なのだろう。メガネだからかな。どうせしまったらバラけるということは小学校で習わなかったに違いない。日本は義務教育のカリキュラムを見直すべきだ。
「『ジャクしく』か。懐かしい」
「そこで略すやつ初めて会ったんだけど、お前さては『ナルド』とか『ゼリヤ』とか言うタイプだな?」
「は……?」
「俺がおかしいみたいにすんのやめえや」
「すんませんノブさん」
「ちょっと待てえ!」
は、と笑うと、机に反射した温かい空気が鼻先を包んだ。朝ごはんのみそ汁の匂いがした気がした。
「ほら、昼いこ」と妙に切れの良い声で肩を叩いた彼に、「いてえ、折れたわ」と返しながら立ち上がる。「詫びナルドを要求する」と背中に指を突き付けてやれば、篠崎は「いや、お前が言うんかい」と猫背気味に歯を見せた。
篠崎は面白いやつだ。
たぶん、彼も俺のことをそう思ってくれている。波長が合う、楽しいやつ。だから一緒にいる。俺ら二人の間でだけは、それが事実だ。周りにどんなレッテルを貼られていても関係ない。大学に入って出会ってから、俺たちはそういう生き物になった。
では、蒼は?
蒼は、俺の弟は、俺の中では、今、「不登校の可哀そうなやつ」だ。母からしてもそう。厳格な父は「可哀そう」ではなく「情けない」と思っているに違いないだろうけれど。
そうしたのは誰だろう。
俺は、その相手のことをよく知らない。
少なくとも、もう顔も思い出せない彼ではないはずだった。
***
母は、明確に「高校まで行って、蒼に傘を届けてほしい」とは言わなかった。「また傘忘れて。あれだけ言ったのに」とため息を吐いただけだ。それを察して動いた自分が親切だなどと主張するつもりはないが、少しは減刑されてもいいのではないか、とは考えた。こんなことを考えた時点で、刑期は伸びているような気がした。
蒼の学校生活は、去年の秋、夏休み終わりを機に止まっている。
クラスの気になる女子と同じだという美術部の活動も、植え替えが面倒だとぼやいていた園芸委員の仕事も、最近順位が上がったと喜んでいた数学のテストも、そこで止まった。
厳密に言えば「教室に行かなくなった」が正解で、”登校”の定義が「週三回、保健室に通う」に変わったのだ。それから約半年、外に出るときは何かから隠れるように全身黒い服で身を包み、誰かから逃げるように速足で街並みを通り過ぎるようになった。
弟が普通の登校をしない理由は、俺には知らされていない。
いないけど、わからないほど鈍くはないつもりだ。俺たちは不思議なくらいによく似ている。ああ、いや、ある意味では鈍いのかも。だって、彼にどんな言葉をかければいいのかわからない。何かを言うべきなのは知っている。
同級生がすっかりいなくなった通学路を一人で歩き、同級生が押し寄せる前に同じ道を一人で帰る。その姿を想像するだけで、「お前はえらいんだよ」と言ってやりたい気持ちにはなる。でも、それがよろしいことなのかどうか、俺にはわからない。
かつての自分が「お前はえらいよ」と言われている姿を想像する。うまくいかない。まあ、そうだ、俺はべつにえらくなかったもんな、と思い直す。
「あっ」
バシャン、と大きめの水たまりに片足を突っ込んだせいで、思わず声がこぼれた。
周りに誰もいないことを視線で確認して、少しだけ安心する。雨音が騒がしいことが、今だけはありがたかった。
それが一瞬でありがた迷惑になったのは、母校の裏門に近づくまで、弟の姿に気づけなかったからだ。
蒼は、二人の男子生徒に挟まれるような形で立っていた。
いや、立たされていた。俺にはそう見えた。だって、弟はもうずっと前から、自分の足で立てないままだ。行かなきゃいけないから学校へ行き、相手が攻撃してくるからそれを甘んじて受け、解決しないから半年も”登校”を続けている。
三人のところへ向かって走りながら、ふと、「人は、どうして他人の嫌がることをするのか」を考えたことがあるのを思い出した。暴力とか、盗みとか、陰口とか、そういうものについて。たぶん、蒼と同じく高校生くらいの頃のことだ。
足元で水しぶきが盛大に跳ねる。
膝まで海中に浸かったように冷たい。
振りかぶった拳は、右側に立っているやつの背中にクリーンヒットした。黒い学生服の影が、スローモーションでぐちゃぐちゃの土に沈んでいく。
「人の弟に何してんだ。腹立つんだよ」
顔も思い出せないなんて大嘘だ。
一生かかっても忘れられない、吐き気のする顔と、右側のやつの眉毛の形が似ていたから。理由なんてそれだけでいいだろう。俺はえらくなかったし、もっと情けなかったけど。蒼はえらいから。それだけでいいはずだ。
そうでなければ、俺はとっくに、あんなやつの顔なんて忘れられたはずなのだ。
「みなと、」
蒼の声はかすれている。
頬まで伸びた前髪を見たときに、隙間から覗いた瞳と視線が絡んだ瞬間に、後悔の所在を理解できた気がした。
濡れた地面に倒れたやつと、そこへ駆け寄るやつをよそに「コンビニ寄るか」とだけ残して傘を拾う。くるくると回して泥を払ってから、そのまま蒼の手に握らせた。
あの、チャームの付いた傘がないことに気づいたのはそのときだった。
夢中になっているうちに放り投げてしまったか、風に飛ばされたのかもしれない。しかし、すぐに「まあいいか」と思い直した。どこで手に入れたかは知らないが、あの傘は蒼のものではないだろう。いや、そう考えると「まあよく」はないけれど。
蒼は家に傘を忘れがちだが、自分でもそれをよくわかっている。
だから傘を買って帰ったりしないし、近所なら走って濡れて帰ってくることが多い。ただ、目立ちたくないときは、あまりいい帰宅手段だとは言えないだろうから。
「いや、この歳の兄弟で相合傘ってのも目立つか」
「え、あ、どう、かな」
「セブンでビニ傘買うわ」
蒼が「なあ湊」と囁くように呼び、「なに」と不愛想に返した俺に対して、「……俺、『セブイレ』って略す派」と何でもないふうに言った。いや、そこは似てないのかよ。
(つづく)
第三話担当 前条透
次回の更新は5月20日です!
「記事を保存」を押していただくと、より続きが楽しめます!
ぜひよろしくお願いします!
▼続きはこちらから
過去のリレー小説
▼2022年「そして誰もいなくならなかった」
▼2021年「すべてがIMOになる」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
