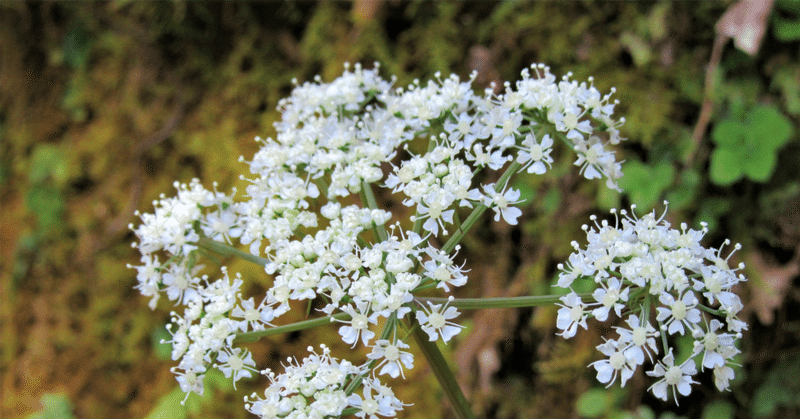
紫がたり 令和源氏物語 第二百三十九話 螢(七)
螢(七)
「とかく正史と言われるものは大まかな筋によって記されており、歴史の流れを後世に伝えるものです。そこには秘されるべきことなどはもちろん記されないわけで、そうしたものを手掛けた文官の私的なものにこそ真実が記されているわけですね。正史にある神代のような人の世は今の我々を鑑みてもただの理想のようです。実際には善も悪もあり、朝廷などにあっては陰謀や争いなどもあるでしょうから。そうしたことを物語の中に作り事のように織り交ぜて書かれることも多いので、確かに“嘘ごと”と切って捨てるわけにもいきますまい」
玉鬘は政治のことなどは今まで考えたこともなく、そこに大臣たる人の知らない顔を見たような思いです。
源氏は真剣に耳を傾ける玉鬘の聡明な様子を見て、やはりこの姫が可愛く思えてなりません。
「仏の御法(みのり)を記したものでも、同じようなことが言えます。例えば“方便”というもの。これは実に曖昧な概念です。そこには矛盾などもあり、通り一遍の学びの者はここで惑うことでしょう。突き詰めて言うと、悟りを開くにもその過程が重要ということになりましょうか。悟りを開く道はその人それぞれ、人の数ほどの道があるのです。そこに御仏の法の遊びがあるところで導かれるというようなものですかね」
玉鬘は源氏の言葉を噛みしめるように理解を深めようとしています。
源氏はくすりと笑うと姫の側に寄り添い手を取りました。
「まったくあなたのつれない態度というのは御仏の示すところの“孝行”にかなっていませんよ」
玉鬘はまた困ったことと即座に返しました。
「親が子に懸想するなどそれこそ御仏の示す“不義”にさわりましょう」
源氏はこれはしてやられた、とたじたじになりました。
まったく玉鬘とのやりとりというものが源氏には愉快でなりません。
この姫を男と対等に渡り合える女人に育てたいものだ、と源氏は密かに考えております。そこには幼い紫の君を手元に引き取り、それは長い時間愛情をかけて非の打ちどころのない立派な女性に育て上げた自負があるからでしょうか。邸内をしっかりと守り、過ぎたることもない。紫の上はまこと源氏の理想の北の方へと生い立ちました。
しかして玉鬘姫はすでに確固とした自我を持ち、最近ではその才覚も磨き上げられたように思われます。もしや宮仕えなどのほうが向いているのかもしれない、という考えも浮かぶもの。何よりそうなれば特定の男性に嫁ぐこともなく手元に置いておけるという源氏の下心も垣間見られます。
一方で真の御子である明石の姫君には違う思いを持っておりました。
ご多分に漏れず春の御殿でも絵物語が集められており、紫の上は教育に良さそうなものを選って姫に与えていたのでした。
紫の上の手元にはたくさんの絵物語が広げられており、それを精査しているのを見た源氏は言いました。
「恋のことなどを書いてあるものはおよしなさいよ。変に色気づいてもらっては困る。姫は後に中宮になろうという人だから、純真無垢なままであってほしいものだよ」
「わかっておりますわ。でも、いろいろと考えさせる物語は自我を育てるにはいいと思いますの。ただのお人形のようでは国母は務まりませんもの」
なるほど紫の上の言うことももっともであります。
源氏は明石の姫を疵無き玉のように育て上げたいと願っています。
持って生まれた美しさと慈悲深い心を育て、紫の上のように内面から美しさが滲み出るような女人にしたいのです。
それを思うと、この人は本当に素晴らしいと紫の上を見つめずにはいられません。
近頃玉鬘のことばかりが気に懸かっていたものの、この人を見ればこれ以上に優れた人はいないと思われる。
それでも自分の心の厄介なこと、と源氏は深く自嘲の溜息をつきました。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
