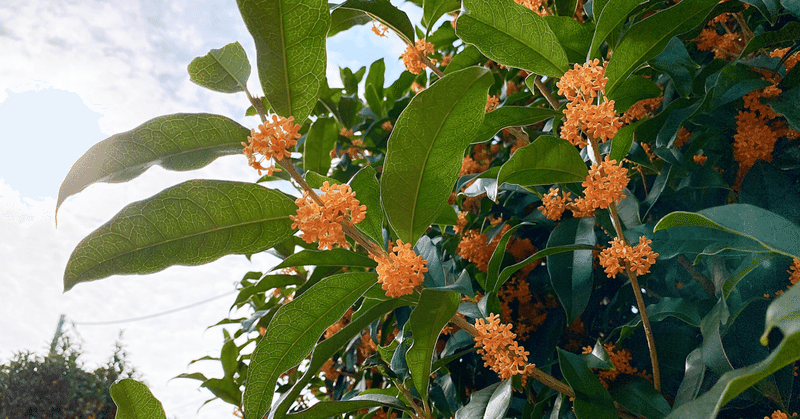
令和源氏物語 宇治の恋華 第百三十七話
第百三十七話 浮舟(一)
弁の尼は宮の姫が二条院にて恙なくお過ごしで時期を見て薫君に嫁がれるのであろうと、これでようやく薫君も心の平安を得られるのではあるまいか、と穏やかに亡き方々を弔う日々を送っておりました。
そんな矢先に常陸の守の北の方からもたらされた文に衝撃を受けたのは言うまでもありません。
まさか匂宮が姫を見つけて我が物にしようとしたとは。
世間では褒めそやされる匂宮ではありますが、こと女人に関することには我を忘れるほどの放埓ぶり、『玉に疵』という程度であればよろしいのですが、いずれ足元を掬われるのではないかと思われるほど。
それにつけても中君も此度のことでどれほど御心を痛められているでありましょうか。宿縁とはいえあの方が夫であるのは気苦労も多かろうと年老いた尼には姉妹ともども気の毒に感じられます。
常陸の守の北の方の意向としてはやはり姫を薫君に嫁がせたく、仕方なしに三条辺りに姫を匿っているものの、先行きが不安であると切に訴えてありました。
京に姫を置く限り匂宮がいつ居所を突き止めてしまうやも、と危惧するのも無理からぬこと。しかしてあの姫を宇治へ呼び寄せるのが得策と思われるも、北の方は常陸の守との折り合いも悪くなり、なかなか邸を抜け出せずにいるようなのでした。何より宇治への道行きは遠く険しいのです。
なんとも怪しからぬ御仁のおかげで話が抉れてしまったものよ、と弁の尼は深い溜息を吐きました。
晩秋の頃に薫君が宇治を訪れるのは変わらずに続けられていることでありますし、御堂も出来上がったこととて近々お越しになるであろう。この事を伝えるにはよい機会ですが、姫と匂宮とのことは伏せておくべきである、と尼君は考えました。
薫君は匂宮のように恨み言などをあからさまに口にするタイプではありませんが、いつまでも心裡にしこりとして抱え続ける性質なので、晴れて結婚という門出には相応しくなく、伝えてもよいことはひとつもないというわけです。あまつさえ所詮は下賤の身と見下されれば姫にとっては気の毒なことになりかねません。
なんともうまく運ばぬ様子が先行きの不安を感じさせますが、心ひとつで明るい未来も拓けよう、不遇の姫には幸せになってもらいたいと願う尼なのでした。
三条の鄙びた邸に身を寄せる宮の姫はこれまで長く母君と別れたことがなかったもので、心細い思いをしておりました。
庭も整っていないので気晴らしに眺める花もありません。しかしながら新たにやってきた右近の君には慰められております。
右近の君は際立って美しくはありませんでしたが、さすがは京生まれ京育ちですので物腰も洗練されて、垢抜けた在り様が新鮮なのです。
加えて世情に通じているので、退屈を凌ぐにはよい話し相手でした。
田舎びた女房たちに囲まれてきた年頃の姫には上流社会へ仕える者でさえこれほどならば、と仄かな憧れを抱かずにはいられません。
姉の中君が貴婦人らしくあったのを自分もあのようになれたら、と内心では夢見ているのです。
姫の傍らには常に乳母とその娘である侍従の君という乳姉妹、そして右近の君が侍り、姫の寂しさを埋めてくれております。
宮の姫のように身の置き所なく過ごしてきた人はなかなか自分の心を表そうとはしないものです。
たとい寂しくはあってもそれを訴えて母君や周りの人たちを困らせるようなことをしてはならないと自然に心得るものなのでしょうか。
姫は詫びる母君の手紙に暢気に過ごしております、などとさりげない気遣いをみせるので、北の方はまた涙ぐまずにはいられないのでした。
次のお話はこちら・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
