
続・ツッコミテクニック7選
ツッコミテクニック7選と題し、ツッコミの様々な技術を書いた以前の記事。
これはツッコミテクニックの代表的なものを7つに絞って書いたものだが、ツッコミの種類と発明はまだまだある…と思い立ったので今回はツッコミテクニックの続編を書きます。
まず…
ツッコミが主役となり始めた現代漫才は多種多様なツッコミパターンをたくさん生み出し、細分化すると共にレベルも向上している。
新しさと普遍性…
そのどちらも大切であり、どちらも並行しながら進化を繰り返していく。
今は特にM-1の影響もあり、何をすれば斬新に見えるのか?何をすれば驚いてくれるのか?
お笑い人口の増加と共に、ツッコミ1つを取っても発明が加点ポイントなのは間違いない。
何もかもが出尽くしたであろう今の時代に笑いと向き合う上で、新しさを求める姿勢は大切。
だが、ここが笑いの難しさ…
新しければ必ずしも面白いわけではない。
目的は笑わせることであり、手法や策ばかりが前面に出てしまっては、お笑いとしては不正解となる。
『面白い』『笑える』が先にあって、なおかつ新しく見える…これが理想の形。
新しいから面白いのではなく、面白いものが結果として新しい。それが正解。
ツッコミにおいて新しさを追求するのは非常に難しく、想像以上に奥が深い。
そして、新しさだけが全てではない。普遍的かつ王道のツッコミを踏襲しながら笑いは歴史を紡いできた。
新しいものだって歴史の上に成り立つからこそ新しく見えるのだ。
新しさと普遍性。
その2つの角度を念頭に置きつつ、私の尺度ではありますが、現時点において正解を導き出した新しいツッコミや普遍的なツッコミもふくめ、今回はツッコミの名手から紐解いた7つのツッコミ技術を紹介していこうと思います。
①受け入れツッコミ
【ぺこぱ 松蔭寺太勇】

M-1グランプリ2019で第3位に輝いたぺこぱの受け入れツッコミ。
新しさの一点において群を抜きながら、さらに驚くほど面白い。本当に何も考えずに笑える。
松本人志氏がこのツッコミを称したのは『ノリツッコまないボケ』
たしかに、ノってツッコむと思わせ裏切ってくるので、そのネーミングは抜群だ。
だが、私はあえて受け入れツッコミと呼ばせていただく。
ツッコミというのは基本が否定である。
「誰が言うてんねん!」「どこがや!」「違うだろ!」など、「ツッコミはボケが言ったことを否定するもの」という常識がある。
そのオーソドックスな手法の共有があってこそ、受け入れツッコミは光る。
ツッコミ=否定だったはずなのに、その逆の肯定を笑いにつなげる新技。
漫才の歴史の全てがフリになっている。
ボケに対しツッコミを入れかけて「とは言い切れない…」
ボケに対しツッコミを入れかけて「いや、俺のせいかもしれない…」
相手のボケや言動を批判すると見せかけて肯定する。これはツッコミテクニック7選のパート1の④で紹介した、ノリツッコミのアップデート版である。
ノリツッコミで否定する相手を相方ではなく自分自身へと変えて、それらを受け入れる。
これは人の個性や多様性、自分の間違い、全てを受け入れていることと同義語に当たる。
大袈裟かもしれないが、これがなぜ笑えるのか?という思考回路の見直しにもなる。
ボケが変なことを言う。その変なことを言っているところにアンダーラインを引くのが本来のツッコミの仕事。そのワンセットで、おかしなことを言っている共有が成立して笑いが起きる。このメカニズムが従来の笑いの方程式。
ぺこぱの漫才は全くそのメカニズムに沿っていないがバンバン爆笑を取る。
おそらく、既存の漫才の型をキャラに乗せて崩す…という良い意味でのバカバカしさ。その上で決めにかかるツッコミワードのセンスと言い方の面白さ。
そして、2人の絶妙すぎるキャラの融合。
おそらく、このツッコミ成立の背景にはキャラが乗っかっている部分も大きい。
様々な要素が複合的に重なった上で出来上がった奇跡のバランス。
ぺこぱを一夜で売れっ子に押し上げた受け入れツッコミこそツッコミ全盛時代における最終地点…だと思います。現時点で。
②時間差ツッコミ
【カミナリ 石田たくみ】

カミナリたくみくんのツッコミと言えば、どちらかと言えば頭をおもいっきり叩く、どつきツッコミのイメージが強いだろう。
しかし、肝は頭をどつくところではなく、時間差で泳がせてからキラーフレーズを入れ込む漫才の構成だ。
ボケは基本的にフリとなっており、普通に話は進んでいく…と思わせておいてから頭をどついてフレーズを大声で入れ込む。
漫才の山場はツッコミにあり、そこへ向かうまでの「来るぞ来るぞ…」という期待感を楽しめる構成となっている。
頭をどつくことは1つのサインになっており、「ここがサビですよ」と知らせる役割を果たしている。笑わせるポイントを明確化し、そのリズムを観ている側と共有できた瞬間に爆発が起こる。
ツッコミポイントをサビとした、音楽のような漫才である。
カミナリは2人共ヒップホップが好きだが、何となくヒップホップ文化を踏襲している空気もある。
ヴァース(AメロBメロ)があって、フック(サビ)に繋がる構成。
どつき漫才という漫才クラシックを踏襲したサンプリング(引用)、さらには地元茨城をレペゼン(代表)する姿勢…などなど
この2人からはヒップホップを感じざるを得ない。
そして、ツッコミにおいて意外と効果的になっているのが茨城訛りの言葉である。
もしも、ツッコミが関西弁だったり、標準語だったりしたら…頭をおもいっきり叩いて大声で激しくツッこむことが、もっと尖った印象に見えてしまうかもしれない。
茨城弁の絶妙な訛りとの相性もふくめ、本当によく練られたツッコミの形である。
③キレ気味江戸っ子風ツッコミ
【アンタッチャブル 柴田英嗣】
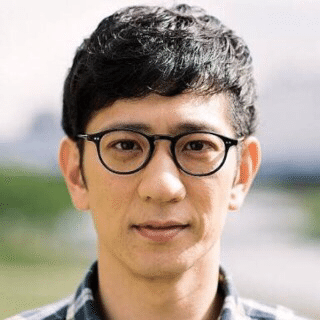
サポートも嬉しいですが、記事やマガジンを購入していただけたほうが嬉しいです。読んでくれた人が記事の内容を覚えている文章を心がけております。

