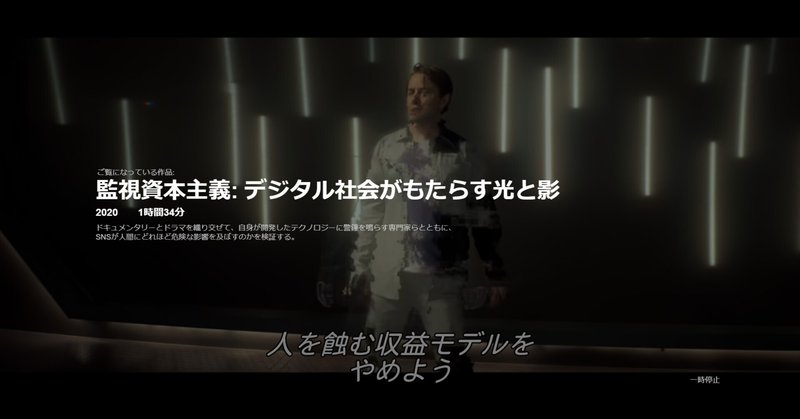
『監視資本主義 デジタル社会がもたらす光と影』
ネットフリックスオリジナル作品『監視資本主義 デジタル社会がもたらす光と影(2020)』を観た。
この作品はドラマとドキュメンタリー部分があるが、ドキュメンタリーに登場するのは元ビッグテックの社員で、重要なセクションで開発を行っていた人などもいる。
そんな彼らがあるとき「これはまずいだろ」と気づき、退社して啓蒙活動をしている。
”中の人”だから分かることがあり、そんな彼らが警鐘を鳴らすことが意味するものは何か。
しかし、彼らはこれらを全否定しているわけではない。
テクノロジーの進化には賛美を送る彼らは、現在の社会におけるデジタルコンテンツに関する仕組みを変えるべきだと訴える。
つまり法を作り、規制をかける、ということだ。
これらの問題は常に提起されてきたし、何よりスティーブ・ジョブズが自分の子供にはiPadを持たせない、と言ったというくらいだから、それが意味することは容易に想像がつくと思われる。
この作品で興味深いのは、常々私も感じていたことだが、日本で起こっていることがアメリカでも現実に起こっていることだ。
若者、とりわけデジタルネイティブは、かつての共同体の枠組みにおける(宗教的)価値観は共有しておらず、日本と同じような現象が起きている。
デジタル依存の何が問題なのかというと、この作品でも取り上げている、ビッグテックにおける『情報の個人化』であると思われる。
かつてのWebは「個」よりも「公」的な要素が大きいかったと思う。
SNSの浸透により、情報は一人ひとりにカスタマイズされて提供されるようになった。
先日、笑い話のネタにこんなものがあった。
「禿の薬の広告ばっかり出るけど、こんなの若いやつ見たくないだろう」
そう、この人はスマホに表示されるWeb広告が、みな等しく同じだと思っている。
かつてはWebの広告もそうだった。
どのサイトのどのページに何を出すかが決まっていた。
しかし、グーグルアドセンスなどからそれはWeb上の個人の動作(検索やクリック)によってカスタマイズされるようになった。
これはいわゆるフィルターバブルを発生させ、どんな情報も存在するWebという大海を、どこかの限定された砂浜にしてしまうことになった。
少数意見だと思っていたものが、それに関する肯定的な情報にアクセスすることで、彼の見るWebはそういった情報で埋め尽くされることになる。
そしてそれが広告ビジネスに結びつく。
こういったアルゴリズムによって表示されるWeb広告やSNSの仕組みは、若者の倫理形成において重大な問題があると考えられている。
ビッグテックの元社員は、子供にスマホを与えるのは高校生になってから、と口をそろえて述べていた。
ちょっとした興味がフィルターバブルによって、彼にとってはフェイクニュースが真実になってしまう。
今、統一教会問題が話題だが、インターネットなどがない時代から、そういったことをテクニカルに行ってきた。
つまり、必ずしもインターネットが悪いわけではない。
技術には功罪があり、その特徴によって法を整備していく必要があると、この作品は訴えている。
しかし、現実的にとても難しいことであるのは、これらの規制を行うには、世界を牛耳るビッグテックを説得しなければならない。
この肥大化したIT企業のモンスターは、資本主義におけるリヴァイアサンであると思う。
国家ではなく企業もまたリヴァイアサンとなってしまう。
むしろ国家よりも企業が力を持っている時代でもある。
かつては国家と教会の勢力争いがあったが、今は国家と企業であり、神の尊さは金融という欲望に置き換わった。
私はよく現代を『お金に収束する世界線』という言葉を皮肉を込めて言うことがある。
資本主義が悪いのではなく、先物投機や金融派生商品よってお金を増やすことが主となってしまった資本主義が辿る方向性について悲観的なだけだ。
これも、本当は都度法整備を行いながら社会を守る必要がある。
それを守るための政府もまた金に塗れてしまうのは世の常で、だから市民は権力を監視しなければならないし、その情報をジャーナリズムが担保してくれないといけない。
そこにどれだけ根深くお金至上主義が蔓延しているかで、報道の自由度ランキングは変わってくるだろう。
私も仕事がWebなので、その仕組み等はある程度知っている。
いろいろよろしくないなと思って、元ビッグテック社員の彼らが実践していることを、すでに私もやっていることがある。
何よりもスマホの通知を切ること。
通知はリアルな人とのコミュニケーションツールであるLINEとGmail、そしてSMSのみにしている。
Twitterはフォローをすべて外し、見たいアカウントをリスト化し、能動的に見るようにしている。
Facebookは公開をすべて友人のみにし、通知も切っている。
駅の階段でも、電車のドアから出るときもスマホから目を離さない若い人を見ているとなんだか悲しくなってくる。
この作品では、アメリカでも若者がリアルな異性との関係を持つ比率が顕著に落ちてきていると言っていた。
日本ではすでに周知の事実だが、あのアメリカでさえも、と驚いた。
彼氏彼女を持つことよりもスマホをいじっている方が楽で楽しい、と思っているのだろうか。
サブスクを始め、無理に気を遣うコミュニケーションを取るよりもSNSの方が楽で楽しいのだろう。
”デジタルおしゃぶり”という言葉が出てきて笑ってしまったが、常に通知を気にし、スマホをいじることを指している。
スマホが悪いのではなく、情報の個人化アルゴリズムが寛容性を失わせ、思考を極化させる。
中庸が減り、社会の寛容さも低下している。
アメリカの銃乱射事件はかなり顕著に増えてきている。
現SNSは人間を表面的には満足させるツールが山ほどあるが、根本的な楽しさを提示できない。
驚くことに、現ネット世界には多様性に触れる機会が著しく消失しているからだ。
どれだけそのことに早く気づけるのかが重要だ。
デジタル断捨離はするべきだろう。
私も一時期デジタル書籍を買っていたが、今は基本的には紙の本を買うことにしている。
デジタルとの付き合い方だが、全部やめる、とかではなくその現状を理解したうえで活用することができれば最高だ。
私自身、デジタル大好きだし、ネットは欠かせない情報源だ。
かつての自由な検索結果が懐かしい。
今はそのようなわくわくする検索結果はほとんど表示されない。
ブラウザの設定である程度は可能かもしれないが、情報自体の質が変容しているし、かつてのような野良サイト的な自由さが減っている。
ブログもSNSもお金に結びついた記事が多すぎてつまらない。
長くなりました。
ネトフリ入っている人はぜひ。
そんなネトフリも同じアルゴリズムだけどね笑
