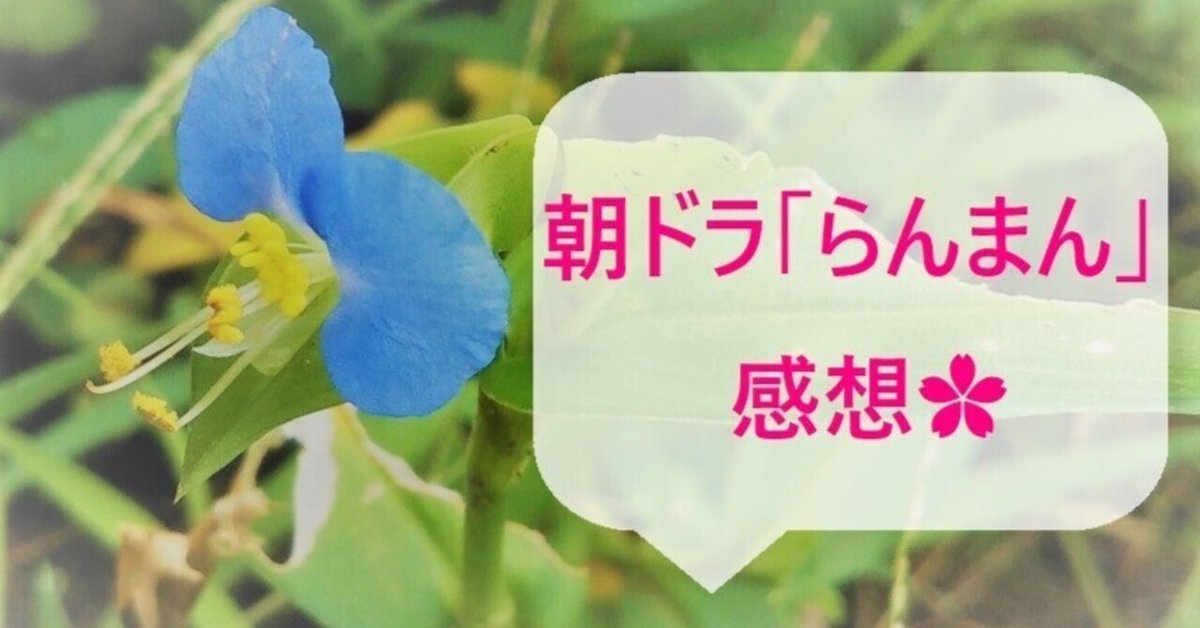
【らんまん】日本「初」の新種とは?【第15週・ヤマトグサ】
「らんまん」第75回感想です。
今日は牧野富太郎博士の有名な業績である、「ヤマトグサ」命名の瞬間が描かれていました。
昨日の放送で、土佐の植物が新種だと明らかになりました(ドラマでは、似た植物と、植物図を見ながら形態を比較して、花弁の数や毛の有無などから、新種だと判断していました。今はDNA解析によるAPG分類が主流となっているので、きっと研究方法も違ってくるのだと思います)。
万太郎はこの植物の和名を「ヤマトグサ」と名付けました。「日本人が初めて日本の雑誌に発表する植物だから、ちなんだ名にしたい」と、その由来を語っていました。
それ以前に日本人が新種を発表したことはありましたが(後述)、外国の雑誌での発表だったので、「日本人が初めて日本の雑誌に…」という説明になったのでしょう。
日本人が日本の雑誌で初めて発表した新種、そして日本を意味する「ヤマト」の名を与えられた植物が、意外とマイナーな植物だったのは、やはり日本の植物学が、海外と比べてずいぶん遅れていたから、ということのようです。そのことについては、何回かご紹介した『牧野富太郎の植物学』(田中伸幸著)に詳しく書かれていました。
日本人が古くから慣れ親しんでいたり、名前が付けられていたりした植物でも、学名がなかったものについては、外国の学者が学名を付けて「新種」として発表してしまったのですね。
1784年にスウェーデンの植物学者ツュンベルクが発表した『日本植物誌』には約800種もの日本の植物が掲載されており、その半数ほどが「新種」だったとか。アジサイ、サザンカ、キリなどの身近な植物に、ツュンベルクが学名を付けて発表しているそうです。
ドラマの話に戻ります。『植物学雑誌』の新刊で、ヤマトグサを新種として発表することになりました。Theligonum japonica Okubo et Makino と、オオクボ、マキノという名前が刻まれたことに、大窪と万太郎、そして植物学教室のみんなは大興奮。
※ドラマではイラクサ科セリゴナム属と説明されていましたが、その後ヤマトグサ科→アカネ科と変わったようです。
一方、万太郎と寿恵子が協力して作業していた『日本植物学図譜』も完成! (実際は『日本植物志図篇』)
一方、田邊教授の身にも事件が起こっていました。かねてから田邊教授が研究していたトガクシソウを、ケンブリッジ大学に留学していた伊藤孝光が新属Ranzania T.Itô として発表したため、トガクシソウにタナベの名を付けることはできなくなってしまったのです。
これが「破門草事件」と呼ばれるエピソードで、実際の命名者である伊藤篤太郎は、イギリスの雑誌にトガクシソウの論文を掲載したため、日本人が初めて付けた学名ではあるものの、「日本の雑誌に」という点では、牧野富太郎が一番だったということになるのですね。
伊藤篤太郎は東大の植物学教室に出入りしていましたが、このことに激怒した矢田部教授が伊藤を東大に出入り禁止にしたため、トガクシソウが「破門草」と呼ばれるようになった…ということで、ドラマとは少し事情が違っているようです。
今日は自分の勉強&頭を整理するため、何だか堅苦しい内容になってしまいました…
最後、寿恵子から万太郎に、うれしい知らせが…。来週からは、槙野家が少しにぎやかになりそうです。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

