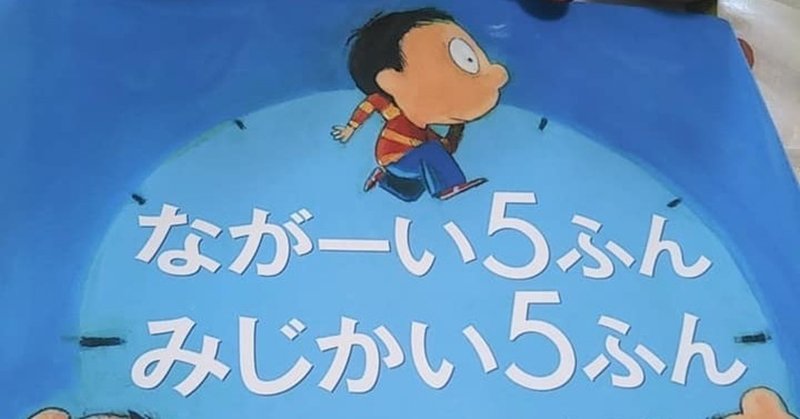
小学1年の課題図書で東大院卒が読書感想文を書いたらどうなるのか
※しょうがっこう1ねんせいのみんな、
このどくしょかんそうぶんをそのまままねると、「おとながかいた」とばれるからぜったいやめようね!
きみたちがかいたもののゆうれつをきめるなんてそもそもおかしいはなしなんだ。
きみたちがかんじるものをそのままかいてよいんだよ。
【ほんのしょうかい】
オリヴィエ タレック (イラスト), Liz Garton Scanlon (原著), Audrey Vernick (原著), Olivier Tallec (原著), リズ・ガートン スキャンロン (著), オードリー ヴァーニック (著), 木坂 涼 (翻訳) (2019). ながーい5ふん みじかい5ふん 光村教育図書
れつにならんでいるときは5ふんなんてまてなーい!
ジェットコースターにのっているときは5ふんってあっというま!おなじ5ふんでも、こんなにちがう。
5ふんはながい? 5ふんはみじかい?

時間知覚の認知的処理モデルに伴う「自己超克」の変容-「ながーい5ふん みじかい5ふん」を読んで-
よしだ あや
時計で計測される時間は同じ間隔を保ち、同じく進行するものなのにも拘わらず、感じられる時間はさまざまな要因によって長くなったり短くもなる。
感じられる時間の長さに影響を及ぼす要因には複数あると考えられている。これまでの研究によれば、時間経過に対する注意、身体的代謝、体験される出来事の数、感情の状態などを挙げられる。
「時間知覚」とは「物理的経過時間に対する知覚作用」のこと
「時間知覚」とは「物理的経過時間に対する知覚作用」のことであり、時間的に離れた事象間の間隔を評価及び判断する基礎となる過程のことである。
時間知覚の心理学的モデルは大きく2つに分類される。「感覚的処理モデル」と「認知的処理モデル」の2つである。
感覚的処理モデルは何らかの内的な振動子やペースメーカーのような時間情報の基礎となるシステムを生体が持っていると仮定している(e.g., Treisman, 1963)。※1
これらのモデルでは連続的な時間の流れを離散量としてパルス(短時間に急峻な変化をする信号の総称)や単位時間に置き換える変換過程により時間知覚を捉えようとしている。
一方で認知的処理モデルは、時間とは無関係な情報の処理によって時間が知覚されると仮定している(e.g., Ornstein, 1969)※2
時間が長ければ、その中に含まれる情報も多くなる。従い、処理された情報量が多ければ、それに応じて時間が長いと「知覚」される。

「死の恐怖と生の虚無」への処方箋
時間が無限であるならば、結果として、すべての人生は虚しくなり、やがて来る死は恐怖以外の何物でもなくなる。この死の恐怖を克服するために人間はいろいろなことを考えてきた。
一つは不死の薬の探求やミイラ保存の技法のような「技術的解決」。第二は幻想的に征服する試みとしての、肉体は有限であるが魂は永遠であるといった「宗教的解決」。第三はそれを論理的に征服しようとする時間の非実在性の論証といった「哲学的な解決」である。
真木※3は、このいずれもを『われわれはこの精神の病にたいして、文明の数千年間、誤った処方を下してきたように思われる』と断言する。
「自己超克」とは自己との付き合い方
自己超克(じこちょうこく)とはフリードリヒ・ニーチェによって提唱された言葉である。
自己が置かれている現状を超えるような価値を創造したり道徳を形成することから、人間としての本来あるべき自己を形成していくということである。
「自己超克」とは「自己」から完全な離脱、あるいは乗り超えを意味するのではなく、それとの付き合い方を意味している。※4
「自己」において忘却は存在しないため、「自己」に根付いた衝動はなかったことにはできないが、後からそれに対応することはできる。
魂を衝動の複合体として捉え、衝動を受け止めたうえで乗り超え、利用することが「自己超克」の意味するところである。
例えば、何か腹立たしい出来事に直面しても感情的に振舞うことをしない場合、我々は精神によって、「確かに憤りを覚えるが、ここは抑えよう」などと、衝動を一度受け止めたうえで制御し、別の見方を提示している。
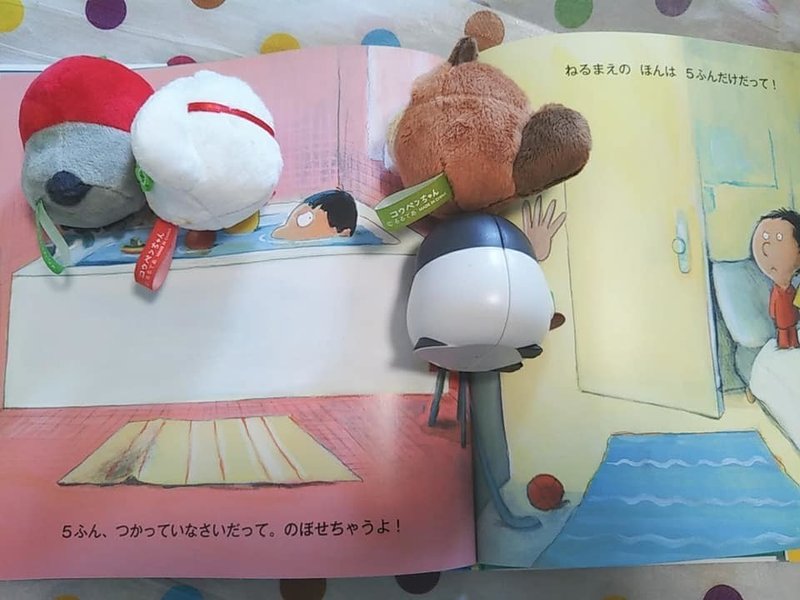
時間知覚の認知的処理モデルに伴う「自己超克」の変容
我々は将来のより良さを求めて前へ前へと自分を鼓舞する。
そうすると、いつの間にか目指す将来像を実現することだけが心の頼りになり、そのために今現在が犠牲となって虚無を感じざるを得なくなることがある。
さらには何かを達成したと思ったらそれはそれでこれまで依存していた将来像がどこかへ消えて無くなり、さらに深く虚無に襲いかかられてしまう。
終いには、その恐怖感から逃れるために再び無理やり将来像を作り出していく。
本書「ながーい5ふん みじかい5ふん」を貫くのは、そのような「時間のニヒリズム」(死の恐怖と生の虚無)に対する問いである。
時間感覚における「認知的処理モデル」に伴う人間の「自己超克」は、価値の固定化を引き起こし、自由な価値創造ができなくなっている「自己」を、「自我」を道具として活かしてその固定化した「自己」から解放することで可能となるのである。
時間感覚における「認知的処理モデル」に伴う「自己超克」は、私たちが日頃抱えている「死の恐怖と生の虚無」を紐解く手がかりとなるのではないか。
※1 Citation. Treisman, M. (1963). Temporal discrimination and the indifference interval: Implications for a model of the "internal clock". Psychological Monographs: General and Applied, 77(13), 1–31.
※2 Ornstein, R. E. (1969). On the experience of time. Penguin.
※3 真木悠介 (2003). 時間の比較社会学 岩波文庫
※4 村田 将太郎 (2012). ニーチェにおける自我と自己―自己超克について― 学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅠ
※本稿はQuizKnock「小1の課題図書で東大生が読書感想文!どのくらいすごい?」をリスペクト&オマージュでお届けしております。

サポートいつでも有り難いです。 本執筆の為の本を買います!
