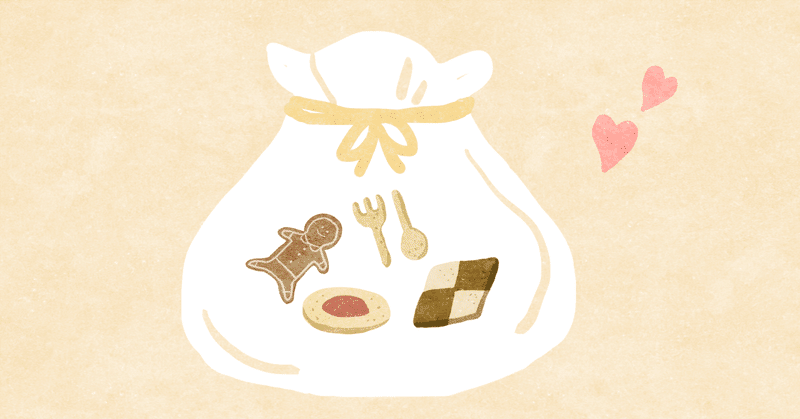
事あるときは幽霊の足をいただく!【長編小説】第3章 第6話(2) ジンジャークッキーはいかが?
前話までのおさらいはマガジンで読めます。
第1章第1話はこちらから読めます。
【真之助視点】
「守護霊だよ」と抑揚なく真実を伝える真に、友人A君は「あ、そ」と軽く聞き流し、真の隣で焼きそばパンに大口でかじりついた。
「で、昨日は聖子ちゃんと何があったんだ?」
「別に何も」
「それは嘘だ。今朝のホームルームで聖子ちゃんが怪我の話をしたとき、クラスの中で顔色を変えずに聞いていたのは真だけだったんだぞ」
本日、何度目のやりとりだろうか。その都度、真は冷や汗を額に浮かべながら、忙しく目を泳がせる。まるで取り調べ室の犯人と刑事のようだ。
「話したくないんだったら、無理にとは言わない。でも、オレは真実を知っているんだぞ」
「し、真実って?」
「昨日起こったことのすべてだよ」
「聞いたのか?」
「おう、聞いた。確かにな」
友人A君が自信ありげに大きく頷いた。
真は友人A君のタレ目の奥に隠された真実を注意深く探っていたけれど、やがてすっと目を逸らして、観念したかのように小さく息を洩らした。
「聖子先生も案外お喋りだな」
「ほら、やっぱり何かあったんだろう!」
「図ったな」
友人A君の力強い腕が真の細い首に絡みつき、蛇が獲物を締め上げるように技をかけた。
真は友人A君の腕をすかさずタップするが、力が緩む気配はない。
「おい、助けろ!」
助けて欲しいわりには偉く横柄な真に、私は笑みを返した。
「安心してよ。友人A君は手加減しているし、真が本気で苦しんでいないのも知っているから、私は子犬のじゃれあいを微笑ましく眺める飼い主の気分だ」
「ふざけんな!」
友人A君は真の抗議が自分に向けられたものだと思い違いをしたまま、嬉しそうに新たな技をかけ始める。
「いい加減、吐いた方が楽になるぞ」
「やめろ!」と真が悪態をつく傍で、私は平和なお昼休みの一コマに安堵の息を洩らしたとき、背中に刃物を突き付けられるような視線を感じ、咄嗟に振り返った。
聖子先生が腰に手を当て、美人が台無しになるような鋭い眼力で、真と友人A君を睨めつけていた。
怒りで長い髪が逆立ち、今にも地鳴りが聞こえてきそうだ。
「二人とも仲がよくて何よりね」
「聖子ちゃん」
友人A君が真から手を離す。
「オレに本当のことを話してくれ。昨日、真と何かあったんだろう?」
「何かとは何ですか! 芦屋君が何を疑っているか知りませんが、邪推するようなことは何もありません」
「でもよ――」
「でも、じゃありません。これ以上、無用な勘繰りをするのなら、これはいらないってことでいいわよね?」
「それ、何ですか?」
消極的だった真まで身を乗り出し、釘付けになっている。
聖子先生の左手には可愛らしいラッピングの小袋が二つ。
もったいつける口ぶりで聖子先生は言う。
「昨日、お見舞いに来てくれた二人へのお礼の気持ちでジンジャークッキーを焼きました。私の手作りです」
「マジかよ!」
二人は歓喜の声を上げながら、おやつを前にはしゃぐ子犬のようにまっしぐらに駆け寄った。それぞれクッキーの入った包みを受け取る。
苦手な聖子先生からクッキーをもらった。手作りのお菓子はもちろん、バレンタインデーとも無縁の真は嬉しさもひとしおのはずで、感動のためにどんぐり眼が潤んでいる。
「仲良く食べるのよ」
「はい!」
聖子先生の前で優等生のような返事をした友人A君だったが、聖子先生が立ち去ると、真のクッキーをひょいと取り上げた。
そして、包みを広げたかと思うと手作りクッキーをパクパクと食べ始めたのだ。
独り占めして美味しそうにというより、工場のロボットのように効率よく迅速に作業的にクッキーを口に詰め込んでいく。
「今、聖子ちゃんと目配せしただろう。オレにはわかるぞ。お前たちの間には何やらエロい空気が流れている」
「流れてねえよ! 返せよ」
「これは愛の味だ、聖子ちゃんの愛だ。クッキーはオレだけのものだ、聖子ちゃんの愛はオレだけのものだ」
「オレのクッキー!」
友人A君の嫉妬は案外根が深い。
昨日の警察署での出来事はこのまま隠し通した方が賢明かもしれない。
のどかな昼下がりの中庭に真の叫び声が響き渡り、私は笑った。
次話『第7話 (1) ナイフの芦屋』はこちらから読めます。
サポートありがとうございます。応援していただいたサポートは今後の創作活動やワンコのご飯になります!より良い作品を生み出す力を分けていただけると嬉しいです。
