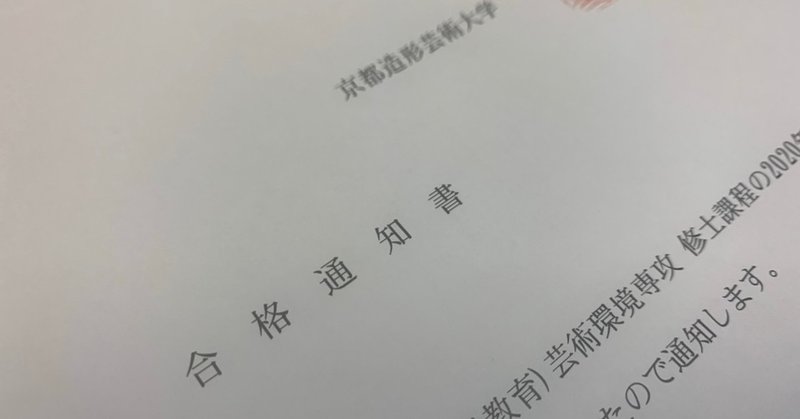
京都造形芸術大修士課程に合格しました&志望理由
今日は、ご報告を。このほど、京都造形芸術大芸術研究科(通信制)芸術環境専攻学際デザイン研究領域に合格し、合格通知を頂戴しました。シンプルに言えば芸術大の大学院生になります。と言っても、通信課程ですので、仕事や子育てをしながら家庭で学びを進めます。
『発酵』×『デザイン・芸術』というキャリアだと、発酵デザイナー小倉ヒラク君に、なかじ君、醤油ソムリエの黒島慶子さんなど、たくさんいらっしゃいます。『発酵』を突き詰めていくとどこかで『デザイン』にぶち当たるのかなと思ったりするところです。
さて、私自身の動機ですが。山口周さんの『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」』を始め、多数の書籍があり、近年、ビジネスにアートの視点を取り入れる必要性が叫ばれています。特にまとまっているのは以下の記事でしょう。
つまるところ、多くは、少なくとも先進国においては、『定義された問題に対して、スキル的に解決を図っていく』というアプローチが成熟社会で限界に来ています。これから人口が減っていく一方、ものやサービスが成熟し、あらかたの不便が解決してくると、これからは、『問題を解決するための技術やスキル』が急速に陳腐化、デフレ化していきます。
現実、私が15年前にMBAをとったときに「10年前のMBAの授業でやってるようなことは、結局書店に並んでる」みたいなことを言う人がいましたが、15年たつと、やっぱり、そうでした。
その中で重要なのは『問題』を定義する力。これを学ぶのに、アートやデザインのアプローチや思考が必要になると考えました。
この問題意識は、種麹という食品素材を扱うメーカーの経営者として、日頃の問題意識にとてもマッチする物でした。率直に、味噌や醤油など一般調味料は、今、どんな商品も、おいしいし、流通物流技術も発達して、よほど変な物はそもそも市場に流れていません。清酒も焼酎も、みんな、美味しいです。先人から受け継がれてきた努力に大変感謝するところです。
逆に言えば、『技術』で解決する余地が非常に小さくなった。テストで言うと、0点から90点を取る努力と90点を99点にする努力、99点を100点にする努力の総量は同じと言います。高度になればなるほど、1点を伸ばす努力が必要になります。そして、今の日本の製造業はほぼ全てがこのレベルに突入したのではないでしょうか。もちろん、それは、高度成長以降の日本の技術発展の証左でもあります。
携帯電話が肩掛け鞄ぐらいあった40年前には、携帯を軽くするというのは、必要性も高かったし、数キロが数百グラムになれば、それは革命に近かったでしょう。そして幾多もの技術革新を経て、今、スマフォを1g軽くするのは、本当に細やかな改善の凌ぎ合いになっているでしょう。しかし、その1gぐらいの差は、おしゃれなカバーケースやアクセサリーをつければ、簡単に埋まってしまいます。これと同じことが、あちこちで起きています。
この状況で、『技術を良くする』ことが解決アプローチで、さらに『課題を他社に先駆けて如何に早く解決するか』が勝負を分けるルールでやっていると、閉塞感しか生まれません。『正解』を提供する技術やスキルが過剰になっているのです。
もっといえば、『便利さ』はもう臨界点を超えたということではないでしょうか。現実、むしろ、少々不便な物の方が高い値段で売れています。先に紹介した記事でも触れられていましたが、部屋をボタン一つで暖めるエアコンが数万円なのに、わざわざ薪を割って火をくべる暖炉が数十万円で売れています。それは、そこに『暖炉』を買う意味やロマンがあるから。ブランディングの言葉を使えば『機能的価値=便利さ』から『情緒的価値=意味』にシフトしてきました。
もちろん、一方で、『発酵』には大きな可能性があります。地域おこしにつながったり、日本の文化発信に繋がったり、もちろん『発酵』の考え方、精神性は組織マネジメントや社会設計にも応用出来る可能性も指摘されます。でも、それはまだ『可能性』、その『可能性』を引き出すには『発酵』に、どういう意味付けをしていくか、そこには、徹底して『意味』の価値を追求する営みであるデザインやアートの力が必要だと思うのです。
もう一つ、昔から課題に感じていたことがあります。それは、発酵食品はとかく、健康食品などの売り文句にされ、科学的には間違った解説が広まりすぎていることです。科学的な正しさより、感情的な議論が優先されてしまう。それはここ数週間のコロナウイルス関連の社会状況を見れば、一目瞭然です。今日は3.11、放射能に対する議論もそうでした。
あるいは、医療においても、普通の医学での治療をすれば回復したと思われる患者さんが、医療を信用出来ず、怪しげな民間療法に走り、結果、命を失うことになったりします。
正直、この国では、科学とマスメディアの相性は圧倒的に悪い。科学者とメディアはなぜコミュニケーションに失敗しがちなのでしょうか。なぜ、正しい情報が伝わらないのか。科学とメディアがコミュニケーションに失敗していることで、相当な社会的損失が起きているのではないでしょうか。そんなことを普段から考えていました。
結局、科学者は「客観的な機能」の議論をし、メディアは「主観的な意味」の議論をします。だから、その橋渡しが必要。今日本にはここが必要な人材です。これまで、技術系企業の経営者として「サイエンス」や「問題解決スキル」を中心に歩んでいたからこそ、そこに自分のキャリアが活かせるのではないか、そんなことも考えています。
そして、それが、「発酵」の未来に繋がると思っています。
今日の話はここまで。
最後までご覧いただきありがとうございました。 私のプロフィールについては、詳しくはこちらをご覧ください。 https://note.com/ymurai_koji/n/nc5a926632683
